古代の弥生時代の性意識は、家制度、ムラの集団性と、信仰心がよくみえる。
当時から、信仰=祭り=性の機会であったと考えられる。
・・・石の森章太郎「まんが日本の歴史」より
この頃の祭りは『神遊び』と呼ばれる。
神を仲立ちにして、男女が契ることで、神の霊能の獲得でもあった。
弥生人は、日常的な性を禁じ、神前でのみ、それを許した。
その際、ムラを2つの族に分け、違う族の異性を選ぶという掟があった。
近親交配を避ける仕組みである。


もう一つの契りの形は、幾つかのムラに住む男女が、"村境い"に集まって、
違うムラ同士の男女で契りを交わすものである。

近親相姦防止の為、同じムラ同士から、もっと範囲を広げる必要があった為とみられる。
後に『歌垣』とよばれる風習である。
この同族同士の契りに反した者は、身分を『』に落とされた。
今でも、村境の『道祖神』が、男女の契りを司る神であるのは、
古代人の愛の形の、名残りなのである。

人口がそう多くなく、隣村までの距離があったであろう時代、
掟なく放置すると、近親相姦が繰り返されることは、予想できます。
恐らく、経験上、近親相姦で出来た子供に異常が現れることを知り、
そこに神の怒りを感じたのではなかろうか、と思います。
だから、種の保存の為に、神を仲介として、男女の契りの場を作った。
人間が、狭い範囲で集まって暮らすには、必要不可欠なシステムで
あったのかもしれません。
当時から、信仰=祭り=性の機会であったと考えられる。
・・・石の森章太郎「まんが日本の歴史」より
この頃の祭りは『神遊び』と呼ばれる。
神を仲立ちにして、男女が契ることで、神の霊能の獲得でもあった。
弥生人は、日常的な性を禁じ、神前でのみ、それを許した。
その際、ムラを2つの族に分け、違う族の異性を選ぶという掟があった。
近親交配を避ける仕組みである。


もう一つの契りの形は、幾つかのムラに住む男女が、"村境い"に集まって、
違うムラ同士の男女で契りを交わすものである。

近親相姦防止の為、同じムラ同士から、もっと範囲を広げる必要があった為とみられる。
後に『歌垣』とよばれる風習である。
この同族同士の契りに反した者は、身分を『』に落とされた。
今でも、村境の『道祖神』が、男女の契りを司る神であるのは、
古代人の愛の形の、名残りなのである。

人口がそう多くなく、隣村までの距離があったであろう時代、
掟なく放置すると、近親相姦が繰り返されることは、予想できます。
恐らく、経験上、近親相姦で出来た子供に異常が現れることを知り、
そこに神の怒りを感じたのではなかろうか、と思います。
だから、種の保存の為に、神を仲介として、男女の契りの場を作った。
人間が、狭い範囲で集まって暮らすには、必要不可欠なシステムで
あったのかもしれません。










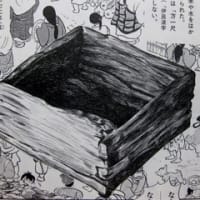









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます