このブログに時々コメントしていただいているsolo_pinさんという方のブログに、こんな記事があった。
なんでかよくわからないんだけど、とっても胸に沁みた。
正直、儂はアイヌのことはほとんど知らない。
北海道の先住民族で、言葉を始め固有の文化を持つこと、他の先住民族と同様に偏見や差別にさらされてきた歴史をもつこと、すぐに思いつくのはこのくらいか。
だから、アイヌのことについてどうのこうのと言うことはとてもできないんだけど、このブログの「気付かぬ差別」というタイトルには、何か感じるところがあったので、ちょっとだけ何か書いてみようと思った次第。
この番組、「仕事のBGMがアイヌの音楽じゃないのか」とか「アイヌのご飯じゃないのか」とか「アイヌ語は話さないのか」とか、まあ、テレビ番組の演出ということもあるんだろうけど、よくこういう言葉が出てくるな〜というのが最初の率直な感想。
確かに悪気なんか微塵もないんだろうけど、こういうのって、「私達とあなた達は違う存在」という無意識の意識から生まれてくるんだろうなと思った。
昔の差別は開拓のためとか直接利害に絡むことも多かったんだと思うけど、今の差別は、客観的な理由はなくて、ほとんどが感情的?生理的?といったことから生まれてるんじゃないかな。そしてそれには意識的なものと無意識なものがある。
もちろん、アイヌ以外のことでも同じだと思う。
例えば今回のコロナ。医療従事者とかその家族への差別、これは意識しての差別だろうけど、明らかに感情的あるいは生理的なことが原因だよね。
人種差別だってそうでしょ? 実は合理的な理由なんかないのに、自分と違うものは嫌だ、許せないっていう、そういう感情的なところから起きる。
もちろん人間誰しもそういう一面があると思う。でも、それを実際にあからさまに表に出してしまうのは、「相手がどう思うか」とか「自分がやられたらどう思うかとか」とか、要するに「相手の立場に立つ」ことができないからだと思う。
仏教の四摂法、特に「同時 」ということがこれを言っている。ただ、「同事」というのは「相手の立場に立つこと」と言われていることが多いけど、儂はこれにはなんとなく違和感がある。「相手の立場」があるのであればそこには「自分の立場」もあるので、結局は対立の芽がある?と思ってしまう。(リクツッポインデス
本当の意味での相手の立場に立つというのは、相手に共感すること、自分が相手と一つになることでしょ。
以前に、「お母さんが赤ちゃんをあやす時に、赤ちゃんの顔を見ながら赤ちゃんと一緒に口を開けて『バー』とやる。あれはお母さんが赤ちゃんに共感して無意識でやっていることであり、あれこそが同時ということ。」という話を、仏教の本で読んだかお坊様に聞いたかした。(どっちだったか思い出せないw)
こういうことができれば、差別なんてなくなるはずだと思うんだけどね。
あと、差別の話っていうのは往々にして政治的な意味合いを絡めて議論されることも多いと思うんだけど、儂、これはちょっと違うと思う。
差別は政治なんかとは全く関係がない、人間そのものとしての問題と思うんだけどね。
solo_pinさんのこの記事を読んだ時に、実はもう一つ頭に浮かんだものがある。
それは、湯山昭という作曲家が作曲した「混声合唱とピアノのためのバラード『コタンの歌』」という合唱曲のこと。
この曲、今から50年も前に作られた曲で、アイヌの民族音楽のメロディやリズムを取り入れ、詩にもアイヌの言葉が使われている。構成的にも、混声7部だったり複雑な和声やリズムだったり(当時としてはw)するし、おまけに長い。
儂がそろそろ本格的に合唱に目覚め始めた頃wに出てきた曲でもあり、初めて聞いた時は結構な衝撃だった。
だから、アイヌという言葉を聞くと、いつも反射的にこの曲が頭に浮かんでくる。
これが儂が初めて触れたアイヌの文化の一端かもしれない。
儂が好きなのは、3曲目の「熊の坐歌」と4曲目の「アツシの歌」かな。
Ⅰ.船漕ぎ歌
Ⅱ.マリモの歌
Ⅲ.熊の坐歌(ウポポ)
Ⅳ.アツシの歌
Ⅴ.臼搗き歌
Ⅵ.ムックリの歌
Ⅶ.パナンペ・ペナンペのリムセ
Ⅷ.カエルの子守歌
文化というものは、変化はすれど滅びてしまってはいけないものだと思う。












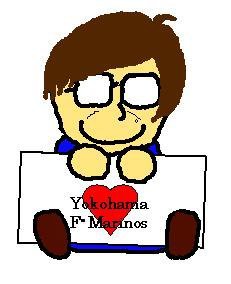






早速記事にしてくださったのですね~。
有難うございます!
恐縮です💦
そして、こんなにたくさんの楽曲を
ご存知なのですね~💖
てか、合唱バージョンなるものが
あるのにビックリしました。
知ってる歌が、知らない側面見せてきた!って感じでした。
教えて下さって
有難うございました(*´▽`*)
今日は男のくせにっていう言葉が耳にはいり、これは差別なのかセクハラなのかを考えました(・∀・)
実は、ちょっと前から差別とか同事のことを書こうかなと漠然と思っていたところに、solo_pinさんのあの記事が出たので、いろいろ考えることができました。
m(_ _)m
「コタンの歌」は我々の世代で合唱をやっていた人間にはかなり有名な曲だと思います。(最近はほとんど歌われてないと思いますがw)
逆に、これってやっぱり原曲のようなものがあるのでしょうか?
詩は「パナンペ・ペナンペ物語」を元に構成して、曲はアイヌの旋律やリズムを素材としたと楽譜には書いてあるので、そういうものがあるのであれば是非一度聞いてみたいです。
>差別をするほうの必死さが醜く見えます
まさにこの通りですよね。
記事にも書きましたけど、人間て自分と違うものを受け入れ難くできているんだと思いますが、これって、生物が自分を守るためにはある程度仕方がないことじゃないかとも思うんですよね。
でも、それをあからさまに出してしまうのは、高等な(と思われるw)知恵を持っている人間がやることじゃないと思うんです。
コロナのことで医療関係者を差別するのは、あきらかに行き過ぎた自己防衛で、自分もしくは自分のテリトリーのことしか考えていないということだと思います。こういうのが愚の骨頂だと思います。
「男のくせに」も差別だと思いますよ。確かに性差ってあると思います。でもそれは単に生物学的な違いであって、男はこうあるべき女はこうあるべきなんていうことはナンセンスだと思います。昔はそういうことがあったと思うんですが、否応なしに時代が変化してきていて、今はもうそんな価値観は古いんですよ。
この世の中のもので変化しないものはないし、変化しないもの、変化できないもの、変化を拒否するものは滅びる、というのが私の基本的な考えです。