
日本の伝統:節分の日は「恵方巻」・分厚い巻き寿司を食べる!

「節分」は日本の毎年恒例の伝統行事です。厄を祓い、「みんなが健康で幸せになれますように」という願いを込めた「行事」が行われる日。「鬼は外、福はうち」と言いながら豆まきをするイベントです。インドネシア語で「悪魔は去れ!幸せは家の中にある」という意味です。それとは別に、この節分の日には「恵方巻き」という食べ物を食べる習慣があり、恵方の方角を向いて恵方巻きを食べると願いが叶うと言われています(※説明は一番下にあります)記事の)。以前にも豆まきや豆まきについての記事をご紹介しましたが、今回は節分の日に特別な食べ物を食べることや「恵方巻」の由来について解説します!
節分の概要

節分とは本来「春夏秋冬」の季節が始まる前日のことを指します。かつては4人制限の前日を「節分」と呼んでいました。江戸時代以降、立春の前日が「節分の日」と定められました。
恵方巻きのひと目

恵方(恵方)とは、その年の幸福をつかさどる歳徳神(としとくじん)という神様がいらっしゃる方位のことです。毎年方角が変わるため、毎年決まった恵方の方角に沿って恵方巻き・巻き寿司を切らずに食べることで、その幸せが尽きることなく続くといわれています。それとは別に、おしゃべりしながら食べると運気を下げると言われているので、恵方巻を食べるときは静かに落ち着いて食べるのが良いでしょう。
恵方巻の中身には様々な意味がある

恵方巻の餡にはさまざまな具材が入っており、基本的には7種類の具材が入っています。「7」という数字には七つの宝という意味もあり、七福神の七神は縁起物として扱われています。7種類の具材を海苔で巻くことで、人生の幸せに関わるという願いが込められているそうです。
- 椎茸:古来より神への捧げ物として親しまれてきました。また、傘の形が守りを意味する陣笠に似ていることからも。
- 鰻(うなぎ):進歩や覚醒などの意味を持ちます。長い数字は長寿の象徴とも言われています。
- かんぴょう:細長い形から「長生きしてほしい」という意味が込められています。
- エビ:健康長寿の象徴とされています。
- 伊達巻:その黄色から富と幸運の源として使われています。
- 桜でんぷ:淡水魚のような白身魚をすりつぶしてピンク色に着色したもの。淡水魚は「幸せ」という言葉を持つ縁起物で、ピンク色がその美しさを表しています。
- きゅうり(きゅうり):「九つの利」という言葉から、九つの利益の意味が込められています。
2021年の節分の日は2月2日!?
現在の日本では節分は2月3日ですが、上で説明したように節分の日は固定ではなく「立春の前日」という決まりがあります。2021年の立春は2月3日なので、2021年の節分の日は2月2日となります。なんと、124年ぶりにまたこんなことが起こってしまったのです!
日本の伝統のひとつである「恵方巻き」を恵方の方角(2021年は南南東)に向かって静かに食べてみませんか!












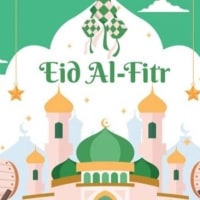








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます