
新年の始まりにふさわしい日本の伝統その2
1月8日
年賀状/年賀状/年賀状から寒中見舞い/寒中見舞い/寒中見舞いまで
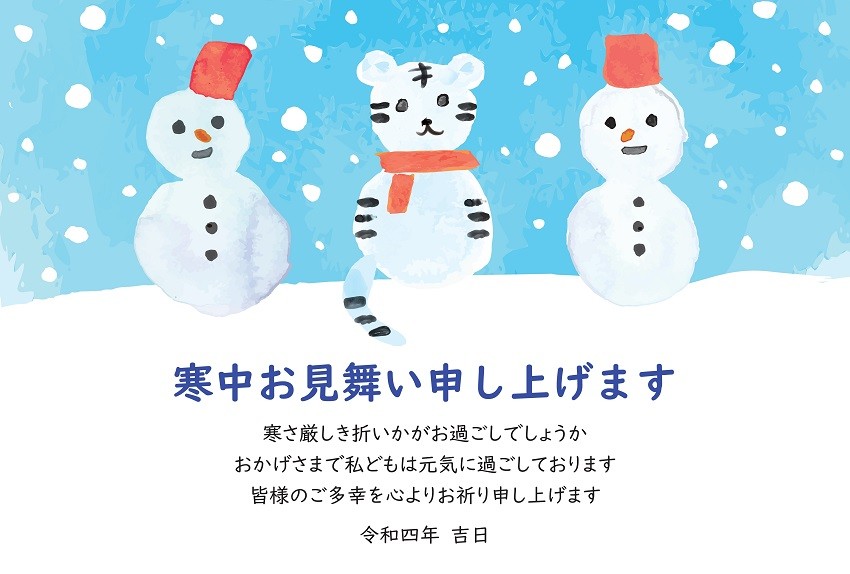
年賀状や年賀状を受け取ったら、送った人に送り返す義務があるという風習があります。1月7日までに返送する時間がない場合は、「年賀状」の代わりに「冬をお過ごしください」というカードを送りましょう。
日本では、その年に家族が亡くなった人にはバースデーカードを送らないのが慣例となっている。そのため、家族が亡くなったというはがきを受け取った場合や、前年に家族が亡くなった人にすでに年賀状を出している場合には、寒中見舞いを出しましょう。
1月11日
①鏡開き・鏡開き

1月7日(松の内)までは「鏡餅」が歳神のご先祖様の姿でした。「松の内」の松の展示を終えた1月11日は、もち米餅を使った「鏡開き」が行われ、餅を炊いてお雑煮 やおしるこを作ります。「割る・飾る」(鏡開き)ことで、病気や災害など縁起の悪いものを「断つ」と信じられています。
「鏡開き」は、包丁で「切る」ことや金づちで「割る」ことは縁起が悪いことから「鏡餅を開ける=鏡開き」と呼ばれるようになったと言われています。病気にならずに健康でいられることを願っています。
②ぜんざい・ぜんざい

「ぜんざい」は、年神様が住む鏡餅の餅を使った小豆粥のようなおやつで、魔除けの効果があるとされる小豆も縁起の良い料理とされています。鏡餅はお雑煮にも使えます。
小豆は煮るのに時間がかかるので、小豆缶を使っても大丈夫です。
1月15日(ミニ正月・小正月・小正月)
もち花 / 餅花

「餅花とは、五穀豊穣を願い、柳の枝に紅白の餅を付ける飾りです。関東では「繭玉」の形に付けられます。この日は「小正月」とも呼ばれます。 」、または小正月。正月に忙しい女性のための日として「女子正月」とも呼ばれます。
米粒を吊るした「稲の花」や正月飾りの「花餅」などの餅花は、地域によって飾られる時期や場所が異なります。
左義長、「どんど焼き」または「さいと焼き」。

「左義長」は、正月飾りや書き初めを燃やす行事です。3本の竹を組み合わせた「三毬杖」という漢字に由来するといわれています。「どんど焼き」「さいとう焼き」とも呼ばれます。
左義長の火で体を温めたり、左義長の火で焼いた餅を食べると長生きでき、丈夫になると言われています。
小豆粥 / 小豆粥

新年の無病息災を願って1月15日に食べる「小豆粥」は、土鍋でお粥を炊き、最後に煮小豆を加えたほんのり甘い小豆粥です。
1月1日から15日までに日本に滞在する方は、この日本の伝統を体験するユニークな体験をしてみてください。











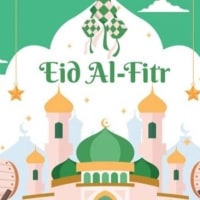








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます