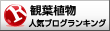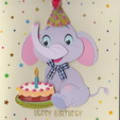2013年8月19日(月)、一関市東山町松川字台の親せきの家に行きました。家の門口に植えられているハナガサギク(花笠菊)が、八重咲きで黄色い花を沢山咲かせていました。また、やかましいほどにセミの鳴き声がするので近づいて行ったら、5~6匹もセミがいました。
(下)庭に植えられている桜の木の幹にミンミンゼミとアブラゼミが、すぐ傍にいました。

(下2つ)ミンミンゼミ:セミ科 Robust Cicada:体長3.3㎝。日本全土で見られる。7月の終わりから9月にかけて見られる。特に8月に多い。ケヤキなどの木にとまってミーンミンミンと鳴く。[講談社発行「日本の生きもの図鑑(石戸忠、今泉忠明:監修)」より]


(下2つ)アブラゼミ: セミ科 Large Brown Cicsada:体長 3.7㎝。7月半ばから9月にかけて 全国で見られる。ナシやリンゴなどの木に集まるが、電信柱や家の壁にもとまる。ジージリジリジリと鳴く。







キク科 ルドベキア(オオハンゴンソウ)属 Rudbeckia spp.
ルドベキア(大反魂草の仲間)は、北米に約15種が知られている多年草で、ごく一部が一、二年草である。花心が盛り上がっているのが特徴で、広く流通しているR.ヒルタ(和名・荒毛反魂草)は一、二年草。草丈が30㎝ほどの矮性品種から90㎝のものまであるが、黄色の花の基部が褐色の’グロリオサ・デージー’が有名である。また、一重咲きで花心が褐色のものは牧場などに野生化している。花期は7~9月。オオハンゴンソウ(R.ラシニアタ)は宿根草で、花心は初め黄緑色、草丈は60~300㎝。切花用に栽培もされるが、各地の川沿いなどに野生化している。本種の八重咲き品種に<strog></strog>ハナガサギク(花笠菊)がある。いずれも丈夫で栽培が容易。[講談社発行「野の花・街の花(監修:長岡 求)」より]