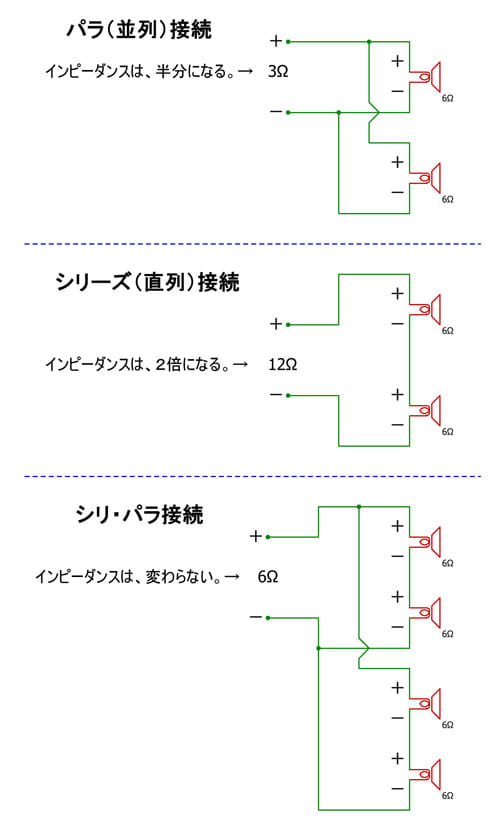こんばんは。前回マグネットの最終回がちょっとあっさり過ぎたとのコメントがありましたので、今日はおまけ編として今までの経験での私の各マグネットについての印象をちょっと書いてみようと思います。今日の話はかなり個人的な思い入れや私見ですので、その辺はお許しを。
マグネットについての印象と言えば、私が一番強烈な印象を持っているのはやはりアルニコマグネットです。今まで設計した中で、何回かアルニコとフェライトとの音質差について検討を行いましたが、一番分かりやすい例としてはSONYのプロ用ユニットのSUP-T11とSUP-T12でしょう。

この2モデルは、全く同じ振動系を採用しており、違いはフェイズプラグとスロートの材質差(これの影響ももちろんありますが)とマグネットの差(T11はアルニコ、T12はフェライト)だけなのです。当然特性などは全く差が無く、特性だけで言えば同じ音が出てもいいはずなのですが、まぁそんな甘い話にはならないのがスピーカーの奥深いところです。両モデルの音質の違いを一言で言えば、私は音の柔らかさの差だと感じています。音が柔らかいというと、なんか音が甘いというような印象を持たれる方もいらっしゃるかも知れませんが、むしろ逆でアルニコのT11の方がはるかに解像度は高いのです。別の表現で言えば、音が自然な感じということになりますね。フェライトのT12の方は音の細部にちょっと余計なヒゲがつくような感じで、これをシャープな音と好意的に感じる方もいるかも知れませんが、私自身はこの手の音は苦手で、歪みの多い音という印象が強く、音量を上げていくとその差はさらに大きくなっていきます。前にも書いたかも知れませんが、解像度や音の分解能を上げながら、聴きやすい柔らかい音を出すということは技術的に本当に難しいものです。単に柔らかい音を作るのは簡単なんですけどね。
ではその音質差はどうして出るのか? これもいろいろなメーカーが研究していたことかと思いますが、私の知る限りこれが決定的な要因だというレポートは見たことがありません。私が若い頃(随分昔です)、某大手マグネットメーカーがアルニコの導電率の低さに着目して、導電率をかなり改善したフェライトマグネットを開発していましたが、確かに若干ではありますが音質は良くなった記憶があります。ただそれでアルニコと同等のものができたかと言えばそんなことはなく、結局その開発品も量産にはなりませんでした。
それ以外の要素として、前にも説明したように内磁型と外磁型の差がありますが、私自身はこれも結構大きい要素ではないかと感じています。量産化はボツとなりましたが、T11を開発している時にネオジムの外磁型と内磁型の試作品を検討したことがありました。同じ材質で内磁と外磁を検討するにはネオジムは最適なのです。マグネットは同じネオジムでしたので、正に外磁と内磁の差を確認することが出来たのです。その時の音の印象としては、同じネオジムでも内磁型の方が音が自然で少しではありますがアルニコ的な方向になるなぁというものでした。ちなみに、JBLではプロ用の4インチドライバーはネオジムの外磁型を使い、ホーム用のK2などではあえてネオジムの内磁型を使っているのを見ても、彼らも同じような印象を持っているのではと勝手に思っています。
ネオジムに関して世間ではかなり好印象を持たれているようですが、私の印象では少なくとも音質に関してはアルニコとの差はかなり大きいと感じています。音の自然さ(これが一番重要です)で言えば、アルニコ内磁>ネオジム内磁>ネオジム外磁>フェライト外磁 といった感じでしょうか。
さてそんなアルニコですが、最大の欠点はパワー減磁です。まぁPARCのような通常のホーム用ではそんな簡単にパワー減磁するということはないのですが、私が開発を担当したプロ用モデルでは実際にスタジオで減磁が発生して問題になっており、開発をスタートする時点で現行モデルよりも耐パワー減磁特性を上げることが重要なテーマの一つでもありました。下の図は当時の生データです。もう15年以上も前のものですので、時効ということでお許しを。
これらのデータは、単体のユニット(BOX無し)に150Hz、2kWの入力をほんの3秒間だけ印加し、前後の特性差を測定したものです。38cmウーファーなのに低域が全く出ていないのは、測定を簡単にするためにユニット単体でやっているためなので無視してください。要はその変化率が大事なのです。正直なことを言えば、こんなテストで減磁が簡単に測定できるのかと最初は半信半疑でしたが、やってみると見事にデータに差が出て、本当にあらためて驚きました。理屈では分かっているものの、パワー減磁はほんの数秒で起こります。まぁ実際のスタジオで2kWが入力されるかは微妙ですが、間違ってケーブルにタッチしたりして瞬間ブーンとノイズが発生したりすることもあるので、安心は禁物です。
一番上から、A社のモデル1、A社のモデル2、SONYのSUP-L11となりますが、モデル1に関しては実際にスタジオで減磁が問題となり、その対策品としてモデル2が発売されたという経緯があります。でそのモデル2もやはり改善はされたものの完璧ではないとのことで、何とか内製で完全なものをということになったのです。下記のデータを見れば一目瞭然ですが、その差ははっきりとしていますね。ちなみにL11のマグネットはパーミアンスを目いっぱい上げるために、モデル2のマグネットの2倍のサイズ(同じマグネットを2段積み)にしていますが、検討段階では1.5倍のもので十分OKという結果になりました。では何故2倍まで大きくしたのか? 実はそれは音質差だったのです。もちろん、1.5倍から2倍にしたと言ってもそれはパーミアンスを上げるためにやっていることで磁束的には殆ど誤差の範囲だったのですが、その音の差は一言で言うと非常に安定しているという感じだったのです。まぁパワー減磁に強いということはそれだけ磁束が外部磁界に対して安定しているということで、スピーカーの基本動作原理として磁束は安定して動かないという前提があるので、後から考えれば音がいいのは当然かも知れません。ちょうどアンプの電源部をしっかりしたものにしていくと、音も良くなっていくということと似ているのかも知れません。ただ経済原理で言えば、やはりその設計はちょっとやり過ぎで、当時のソニーだからこそ出来たことではあります。他社のエンジニアから見れば、何と効率の悪い不経済な設計をしているんだろうと思われたかも知れませんね。



以上マグネットに関して今までで印象の強かったものについて書いてみましたが、今回でマグネットは本当に終了ということにしたいと思います。次回は、あと1ヶ月となった真空管オーディオフェアに関連した内容をお話したいと思います。では今日はこの辺で。