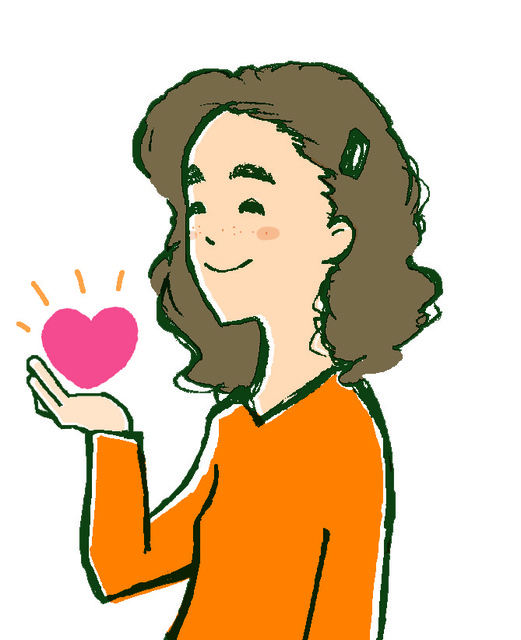自分がしゃべる勉強会と、
自分はそんなにしゃべらない勉強会がある。
たとえば、自分がリーダー的な立場の時、
以前は、自分が完璧に理解して話をしなきゃ、
って感じで、一人で背負って、緊張してた。
背伸びしてでも、無理してでも、
ちゃんとこの場を進めていかなきゃ、って。
でも、苦手なんだよね。人前で理路整然と話をするの。
前もってわかってることを話すのは、あんまりおもしろくない。
自分の心の中を見 . . . 本文を読む
哲学って、難しい。
高校生の頃、世の真理とかが書いてありそうで、
憧れて哲学書を手に取ってみたけど、
日本語で書いてあるのに
何一つ意味がわからなくて、ビックリした。
それからン十年。
ちょっとずつわかってきた。
哲学が難しいのは、抽象的だからだ。
万人に共通する考えの結晶だから、
抽象的にならざるを得ないのだ。
だから、テツガクする時には、
一人ずつが自分の現場に照らし合わせて
具体的なこと . . . 本文を読む
読み終わるまでに7年もかかった
シュタイナーの『自由の哲学』。
最後の文を読み終えてから3年が経ちました。
その本を仲間と一緒に読む機会をいただき、
最近、また最初から読み直しています。
10年前には文字通り一文ずつ、
どの一文のおいしさも逃すまいと思って
スルメを噛むみたいにしつこく格闘したんだけど(^^;)、
(このコメントの応酬を見よ!41件だって!!)
今回は、ちょっと読み方を変えて、 . . . 本文を読む
最近、というか、ここ10年あまり、
「自由」について改めて考え、それなりに挑戦していますが、
今日は「自由」って何に役立つの? について考えます。
言葉としての「自由」の定義じゃなくて、
「自由」は、生きるのにどう使えるか、です。
自由とは、柔道の型
パソコンのOS(基本ソフト)のように
計算する時の公式のように、
ピアノを弾く時の鍵盤のように、
柔道をする時の型のように、
自分が生きる . . . 本文を読む
神戸横尾忠則現代美術館で開かれている
「横尾忠則 自我自損展」に行ってきました。
この展覧会は、
「自画自賛」じゃなくて
自我自「損」というところがミソで、
「エゴに執着すると損をする」がテーマだそうです。
自分の前作や過去のポスターに思い切り手を加えて、
全然違う絵になってたりするものが、
あれこれあったのですが、
中でも「おおっ」と思ったのが、この絵。
小さくて見えないでしょうが、
. . . 本文を読む
自由の哲学に一元論と二元論についての話があります。
たしか、
「二元論でとらえてる限り、いつまでも自由になられへんで~」
というようなことが。
ずっと前に読んだことを、今日、散歩中にふと思い出しました。
昔から、おしゃれすぎる人は苦手でした。
なんとなく、気後れするというか、
興味の対象があの人と私じゃ違うだろうな、
って決めつけて。
でもそれは二元論的に見ていたから。
オシャレに無頓着 . . . 本文を読む
10年ほど前に、スーパーマイペースな困ったちゃんと
自由な人の違いについて考えてたことがありました。
ココ
最近、自由とワガママの違いについて、
当時よりシンプルな言葉にできた気がします。
「ワガママな人」と、「自由な人」は違います。
「人」っていうと、固定してしまいますが、
誰でも成長していくし、その時々の状態で変わるので、
「わがままな時」と「自由な時」にしておきましょうか。
「自由 . . . 本文を読む
言い換えるなら、きっと人は
自分を起こさずに世に流されて生きるか、
自分で自由に自分を動かすか、
他人に従うか、の3つのどれかで動いている。
人はカラダが求めるものを満たして生きるだけとか、
他人の言うことに従うだけじゃイヤだ、と思う時、
その人自身によって、その人が決まる。
他の何からも、その人を決められはしない、
自分の中から来る以外のどんなものも、
その人を左右したりはしない。
※
まる . . . 本文を読む
人が「私は何をすべきか」と、
自分にわからないあちらの神などの世界に求めても無駄だ。
人は、自分が何をすべきかを、
その人自身が描く理想のうちに探し、見つける。
それは、生物としての欲求を、
その人自身が自分で越え出て、
かつ、他の人が描く理想に乗っかる
というイージーさを求めない、
という条件の時に、見つける。
※
前半、わかります。
自分が何をすべきなのか、
カウンセラーやシンクタンクの . . . 本文を読む
同じく、一元論の主張するところからして、
私たちの行為の無期先も、
人をどこかよそに置いた世界を指針にする
ようなことはできない。
私たちの行為の目的は、考えられた目的である限り、
きっと悟りからkている。
人は自分では見通せない神や造物主の目的を
自分の目的にすることではんく、
自分の目的であり、自分の理想から来る目的を
追い求める。
人は行為することで自分のものになる考えを、
その人 . . . 本文を読む
だから、一元論には、
私たちの経験できないような世界を指すような考えも、
ただの仮説でしかない形而上の内容を示す考えも、
共に、考える必要がない。
多くの人が考え出してきた、
神や死語の世界やカルマや何やかやの考えのすべてが、
一元論にとっては不具象だ。
その不具象な考えを生み出した人は、
もともとは経験できること(=具象)から
その考えを借りてきた。
それを、忘れているだけだ。
※
もとも . . . 本文を読む
一元論の見るところ、科学でも
覚えを記録して説明するだけが客観的で
正しい現実なんだ、と制限し、
感和えでそれを補わないのは、中途半端だ。
しかし、また考えだけでそれに見合う覚えを探さず、
覚えることができる世と考えをつなげる
あらゆる網の目のどこにも当てはまらないもの、
それも中途半端だ。
※
前の文では、考えはただの思い設けじゃなく、
リアルな物理の世と精神の世をつなぐものだ
という話で . . . 本文を読む
私たちにわからない世界によって満たされる考えが、
「不具象」の考えだ。
その場合、私たちにわかる世界の現実は伴わない。
私たちがしみじみ思うことができるのは、
現実を伴う考えのみだ。
そして、現実を伴う考えの中から
現実そのものを見つけ出すには、
「覚える」力が必要だ。
世の誰であれ、何であれ、
「考え出されただけの存在」というのは、
本当に「考える」ということをわかっている人にとっては、
あ . . . 本文を読む
ほんとに、人の精神は私たちが生きている現実の中にある。
また、現実を抜け出して高いところに探しに行く意味もない。
そもそも、この世を解き明かすのに必要なすべてが、
この世にあるからだ。
哲学者が「きっとあっちにあるはず」と言って、
それでヨシとするものがあるなら、
それをあっちじゃなくてこっちに置いても、
同じようにヨシとすることができるはずだ。
そのあっちやこっちに置く内容は、
私たちの生き . . . 本文を読む
人は誰でも、それぞれで考える。
その考えは、まるごと全体の考えの世の一部だ。
考えの世、全体を見通して考えることはできないから、
そういう意味では、一人ひとりの考えは別々で、
異なったものにしか見えない。
しかし、その一人ひとりの考えの内容は、
まるごと一つの考えの世の中の一部なのだ。
だから、一人ひとりが考えることで、
すべての人の中にいる神のような高い存在を
一人一人、自分の中に認めること . . . 本文を読む