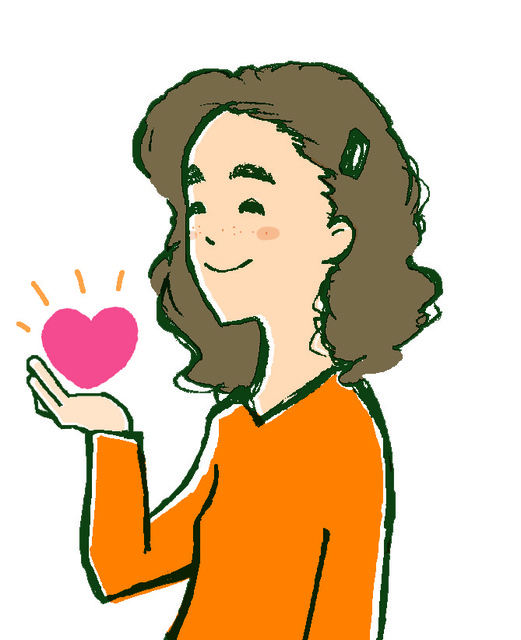考えることは、一人ひとりバラバラな覚えを
ひとつの同じものに近づけ、導いていく。
考えの世はひとつ。だけど、
覚える人ごとに違う覚えを、いろいろなあり方で与える。
人は、自分だけの覚えに執着している限り、
自分を一人きりの人にしか見えない。
だけど人は、自分の中にうっすら感づいている
一人ひとり違うみんなに共通する世に注目すると、
自分の中に丸ごとの世界が
生き生きと見えてくるのを感じる。
. . . 本文を読む
代わりに一元論は、人が現実に生きることは、
人が覚えられない神や精神世界などを設定しなくても、
確かにそこに意味がある、と告げる。
一元論は、現実の意味を、
人が経験できないものに求めない。
なぜなら、
経験の中身そのものが現実だと知っているからだ。
そして、一元論は、その現実だけで完結している。
なぜなら、考えるという働きそのものに、
現実を現実として立証する力があることを
知っているからだ . . . 本文を読む
私たちが現実に、この世で生きていることは、
いかにピュアな主観想念論者でも否定しないだろう。
ただ、私たちが「考えることに意味がある」と言った時、
それには反対するだろう。
それに対して、一元論では、
「考える」のは、主観の働きでも客観の働きでもなく、
現実のふたつの面に及ぶ原理だ、と言う。
私たちが、考えつつ見る働きそのものだって、
現実に存在するもののひとつだ。
私たちは考えることで、経 . . . 本文を読む
覚えは、客観的に与えられる現実の半分で、
考えは、主観的に与えられる現実の半分だ。
私たちの精神の作りは、その二つの現実を半分に引き裂く。
ひとつは、覚える。もうひとつは、悟る。
その二つを両方合わせて、
現実の法則に、考えを重ね合わせることで、
まるごとひとつの現実に至る。
私たちは、ただの覚えをそれだけ見て(考えないで)、
意味のないカオスに向き合い、
覚えについての法則(誰かの考え)だけ . . . 本文を読む
(考えなんて主観的なものでしょ、という人は、)
しかし、考えることは主観にも客観にもまたがることも、
覚えと考えを合わせてまるごとの現実に至ることも、
知らなかった。
覚えから見て取れる法則を、
単に、自分の頭の中だけで理解するなら、
なるほど、それは主観的だ。
だけど、自分の覚えと絡めて考えること、つまり
覚えたことについて、考えに助けてもらって得る内容は、
主観的ではない。
その内容は、 . . . 本文を読む
私たちが自分で考えることで、
現実の本当の姿を、まとまりのある全体像として
私たちに見せる。
一方、覚えが一人ひとりバラバラなのは、
私たちが一人ひとり違うから、
それに左右される見かけにすぎない。
覚えが一見カオスなのを越えて本当のことを知ることは、
いつの時代にも考えることの目標だった。
科学は客観的な覚えだけを現実だと決め、
その覚えに法則を見いだした。
しかし、人が考えて結びつける . . . 本文を読む
人の存在は、ただの一人も世から孤立していない。
一人ひとりの人は、まるごと世の一部であり、
宇宙全体のまるごとと実際につながって存在している。
ただ、そのつながりが、
私たちの覚えにとって、別々に見えるだけだ。
私たちは最初、自分が宇宙の中で一人きりで、
誰ともつながっていないように見る。
なぜなら、自分の人生を動かす歯車に、
宇宙の基の力を伝えるベルトや綱を見ないからだ。
そのつながりを見よ . . . 本文を読む
ついに、講座が終わってしまいましたが、
こっちもついに第3部。
と言っても、第3部は1章だけですが、読んでいきます。
残りページの少ないのが惜しいこと!
最終章のテーマは「つまりの問い」。
…問い?
最後まで、答えを教えてくれないらしい(^^)。
でも、読んでいくこと自体が、自由を教えてくれる。
自分が自由を考えること自体で、自由になっていけるという、
何とも謎の本です。
「どうやったら自由に . . . 本文を読む
類的なものから自由になれない時、
つまり、不自由な時、人は、
自然界や、精神界のひとかけらになる。
そこにいて、その中の一員でいる時は、
誰かの真似をするか
他人が命令する通りに生きることになる。
本当の意味で、その人の倫理が値打ちを持つのは、
その人が自分の内側からの悟りでしたいことを決め、
損得を越えて「その行為を愛してする」時だ。
また、所属するグループの伝統や、価値観が
構成員一人ひ . . . 本文を読む
人は「類」的なもの(女・会社員・日本人などのくくり)から
自由になりゆくほどに、
社会の中でも、自分らしさを失わず、
自由な精神で生きていけるようになる。
誰ひとり、まるっきり類そのままではないし、
誰ひとり、まるっきり類の影響がない人もない。
誰もが、自分なりの所を
多かれ少なかれ、生物としての類らしさから、また
権威のある人に命令されて縛られるところから、
少しずつ自由にしていく。
※
. . . 本文を読む
前半は、認識の自由。
今度は、実行の自由についてのいくつかの文です。
一人の人が、具体的に何をしたいと思うのか。
そのことも、「類」の見方からは導けない。
一人の人をわかろうとするなら、
類ではなく、その人自身に迫らなければならない。
セオリー通りの見方では見えない。
そういう意味では、一人ひとりが、ひとつの謎だ。
そして、抽象的な考えや、類という考えに関わるすべての学問は、
1,一人が世をど . . . 本文を読む
■自由の哲学14章06段落_1
人を「類」で見ようとする人は、すぐ限界に突き当たる。
人は「類」の限界を越えて、
自由に自分のことを決める者にもなる。
「類」で判断するなら、科学的に見ることもできる。
人種、種族、民族、性別は、科学になり得る。
「私は」ではなく「私たちは」と言う時は、
「類」として科学的に判断される対象でしかなく、
何かのステレオタイプにピタリと当てはまるだろう。
しかし、 . . . 本文を読む
一人の人をわかろうとする時、
類型的な見方をしていては、その人がわかるはずがない。
特に、やりがちな間違いは、性別を巡っての理解だ。
男と女は互いに「男らしさ」「女らしさ」を見て、
相手の人を一人として見ていない。
その弊害は、女の方がより多く被っている。
男は一人ひとりの力に沿って社会での地位が決まるのに、
女は、女らしくありさえすればいい、とされる。
女がこういう仕事もできる、というよう . . . 本文を読む
人はしかし、その「類」らしさから自由になる。
そもそも、人の「類」らしさは、
むしろ「類」としてしっかり生きることで、
人の自由を妨げるものではなくなる。
それが、意図的に強制したりしなくても、だ。
人は自分の中からの求めによってのみ、
自分の性質と働きを作り出す。
そこにあって、「類」らしさは、
人が自分の個性を表す土台としてあるだけだ。
人は自然から与えられる性質を元として、
その上で自 . . . 本文を読む
何かに帰属する人の一人ひとりは、
性質や働き方は母集団によって決まる。
民族はひとつの「類」であり、
その民族に帰属する人は、みんな
その民族の性質を帯びる。
そのうちの一人の性質も働き方も、
民族の質で決まる。
だから、一人の立ち居振る舞いも、
どことなく、その民族らしさを帯びる。
その中の一人を取り上げて、
なぜこの人はこうなんだろう、と考え、
その元を探れば、答えは、
その人一人じ . . . 本文を読む