
長良川水系ででコクチバスを確認した。
ボクが今年の6月1日にアップした記事を再録する。
こんな事態が来なければいいなと思って書いた記事だった。
輸入動植物規制の外来生物法スタート 監視態勢強化 (朝日新聞) - goo ニュース
外来生物法がスタートした。
この画像は、コクチバス、魚類の中では同法の目玉となっている魚でもある。
このバスは、栃木県の友人が送ってきたもの、今は、不法放流の証拠物件として、とある博物館の収蔵庫にある。
ボクは、一昨年、琵琶湖博物館の特別展の撮影のために、全国の外来生物の現場を訪ねた。
コクチバスとは産卵行動を撮影に行った長野県の青木湖で初めてであった。
通称、ブラックバスとは、コクチバスとオオクチバスを指すが、青木湖には両方のバスがいる。他の湖でオオクチバスをみると、さすがに捕食者とその活力に驚かされるが、コクチバスと比較したら、オオクチバスなどおとなしいものだ。
潜って撮影していると、大抵の魚は用心して逃げ出すものだが、コクチバスは猛然とビデオカメラめがけて突進してくる。ハウジングの前面レンズが割れるのではという勢いで突進してきた。
そして、コクチバスがオオクチバスと異なるのは、流水の中でも生息すると言うことだ。
オオクチバスは湖、ダム湖のバスだ。そしてコクチバスは川のバスと言えるかも知れない。
こんなものが、日本の川に入ったら、その時の不安は今現実のものとなりつつある。
このコクチバスは、関東の名河川、那珂川で採られたものだ。自然豊かな川であればあるほど、異人達もまたその数を増やすことだろう。
個人的には、現在バス擁護派(?)の水口憲哉さんとは仲がいいのだが、あの論法であの行動というのが、理解できない。
たぶん、琵琶湖総合開発にしろ長良川河口堰にしろ、魚類学者・生態学者が本気で反対しなかったということで、彼をしてもの狂いに走らせているのかもしれない。
在来の生き物たちを脅かしてしているもの、その第一は人間の開発行為である。環境の改変(破壊工作)こそがすべての元凶であるということは、ボクも同じ考えに立っている。
ただし、自然破壊という行為が、たとえて言えば、全てを燃やし尽くす放火された火事とするならば、ブラックバスの放流とそれを容認する釣りという行為は、火事場泥棒に類する所業だ。
長良川でもバス達は着実にその数を増やしている。内水面漁業がすさまじい勢いで衰退し、長良川ダム湖での漁業を諦めてしまったことから、その影響は顕在化してはいない面がある。しかし、火事と火事場泥棒、それは、セットになって、ボクたちの川を蹂躙している。
にいむら
ボクが今年の6月1日にアップした記事を再録する。
こんな事態が来なければいいなと思って書いた記事だった。
輸入動植物規制の外来生物法スタート 監視態勢強化 (朝日新聞) - goo ニュース
外来生物法がスタートした。
この画像は、コクチバス、魚類の中では同法の目玉となっている魚でもある。
このバスは、栃木県の友人が送ってきたもの、今は、不法放流の証拠物件として、とある博物館の収蔵庫にある。
ボクは、一昨年、琵琶湖博物館の特別展の撮影のために、全国の外来生物の現場を訪ねた。
コクチバスとは産卵行動を撮影に行った長野県の青木湖で初めてであった。
通称、ブラックバスとは、コクチバスとオオクチバスを指すが、青木湖には両方のバスがいる。他の湖でオオクチバスをみると、さすがに捕食者とその活力に驚かされるが、コクチバスと比較したら、オオクチバスなどおとなしいものだ。
潜って撮影していると、大抵の魚は用心して逃げ出すものだが、コクチバスは猛然とビデオカメラめがけて突進してくる。ハウジングの前面レンズが割れるのではという勢いで突進してきた。
そして、コクチバスがオオクチバスと異なるのは、流水の中でも生息すると言うことだ。
オオクチバスは湖、ダム湖のバスだ。そしてコクチバスは川のバスと言えるかも知れない。
こんなものが、日本の川に入ったら、その時の不安は今現実のものとなりつつある。
このコクチバスは、関東の名河川、那珂川で採られたものだ。自然豊かな川であればあるほど、異人達もまたその数を増やすことだろう。
個人的には、現在バス擁護派(?)の水口憲哉さんとは仲がいいのだが、あの論法であの行動というのが、理解できない。
たぶん、琵琶湖総合開発にしろ長良川河口堰にしろ、魚類学者・生態学者が本気で反対しなかったということで、彼をしてもの狂いに走らせているのかもしれない。
在来の生き物たちを脅かしてしているもの、その第一は人間の開発行為である。環境の改変(破壊工作)こそがすべての元凶であるということは、ボクも同じ考えに立っている。
ただし、自然破壊という行為が、たとえて言えば、全てを燃やし尽くす放火された火事とするならば、ブラックバスの放流とそれを容認する釣りという行為は、火事場泥棒に類する所業だ。
長良川でもバス達は着実にその数を増やしている。内水面漁業がすさまじい勢いで衰退し、長良川ダム湖での漁業を諦めてしまったことから、その影響は顕在化してはいない面がある。しかし、火事と火事場泥棒、それは、セットになって、ボクたちの川を蹂躙している。
にいむら











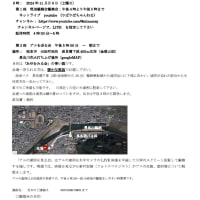














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます