
霊柩車に、一度だけ棺とともに乗ったことがある。
1970年、岐阜の祖父が亡くなったときに
バスのような形の霊柩車に、祖父の棺と一緒に
棺を真ん中に、対面するように4,5人で火葬場まで行った。
目の前にある、白い布が被せられた箱の中に
死んじゃった、おじいちゃんが居るんだって思うと不思議だったとか、
思い出させてくれたのが、井上章一さんの「霊柩車の誕生」
バス型霊柩車が出てきて思い出した。
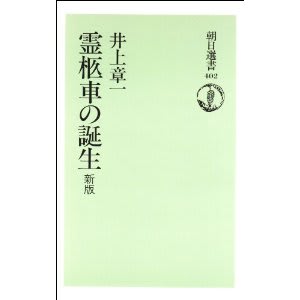
各都道府県の、霊柩車の種類と所有台数が載っていて(昭和56年)
それによると、バス型は北海道が144台と圧倒的に多い。
岐阜は7台。
そうか、7台のウチの1台だったのか。
祖母のお葬式のとき(1980年代)は、宮型霊柩車だったような気がする。
2008年、母の時は黒塗りの、業界用語で「洋型霊柩車」で、見送った。
もう、デコラッティブなアラブの王様が欲しがるような霊柩車は
最近、見かけなくなったなぁ。
んで、そうそう、曾祖母のときは、霊柩車じゃなかった。
寝棺でもなかった。
まだ、小さかったから記憶が曖昧だけど、
お寺の本堂で、お葬式が終わった後、木の樽のような棺、座棺?
これを、隣の墓地、歩いて1分もないところに、運んでいくのが
重くて重くて、大人達が大騒ぎしていたような。
とか、つらつら思い出しながら読んでいく。
自動車が、まだ無かったとき、もちろん人力で棺を運んだのだけど
江戸時代と明治になってからでは
ひょう~、こんなに変わったのか。人の暮らしも。
井上章一さんは、一度、講演を聴いたことがあって、
そのときの、口調のまんま、そのままで
学術的に「霊柩車の考察」がなされている文章。不思議。
つらつら読めて、ビックリな出来事がいっぱい。
アラブの王様が霊柩車をお買い上げした話は載ってなかったけれど
どうなんだろう?
気になるなぁ。
1970年、岐阜の祖父が亡くなったときに
バスのような形の霊柩車に、祖父の棺と一緒に
棺を真ん中に、対面するように4,5人で火葬場まで行った。
目の前にある、白い布が被せられた箱の中に
死んじゃった、おじいちゃんが居るんだって思うと不思議だったとか、
思い出させてくれたのが、井上章一さんの「霊柩車の誕生」
バス型霊柩車が出てきて思い出した。
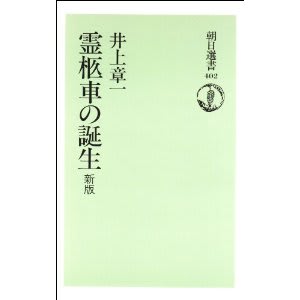
各都道府県の、霊柩車の種類と所有台数が載っていて(昭和56年)
それによると、バス型は北海道が144台と圧倒的に多い。
岐阜は7台。
そうか、7台のウチの1台だったのか。
祖母のお葬式のとき(1980年代)は、宮型霊柩車だったような気がする。
2008年、母の時は黒塗りの、業界用語で「洋型霊柩車」で、見送った。
もう、デコラッティブなアラブの王様が欲しがるような霊柩車は
最近、見かけなくなったなぁ。
んで、そうそう、曾祖母のときは、霊柩車じゃなかった。
寝棺でもなかった。
まだ、小さかったから記憶が曖昧だけど、
お寺の本堂で、お葬式が終わった後、木の樽のような棺、座棺?
これを、隣の墓地、歩いて1分もないところに、運んでいくのが
重くて重くて、大人達が大騒ぎしていたような。
とか、つらつら思い出しながら読んでいく。
自動車が、まだ無かったとき、もちろん人力で棺を運んだのだけど
江戸時代と明治になってからでは
ひょう~、こんなに変わったのか。人の暮らしも。
井上章一さんは、一度、講演を聴いたことがあって、
そのときの、口調のまんま、そのままで
学術的に「霊柩車の考察」がなされている文章。不思議。
つらつら読めて、ビックリな出来事がいっぱい。
アラブの王様が霊柩車をお買い上げした話は載ってなかったけれど
どうなんだろう?
気になるなぁ。









