戦争責任を受け止める主体位置-「超国家主義の論理と心理」と「中国の近代と日本の近代」(中野敏男、「前夜」3、P180)
前回まで、中野敏男は「戦後を問う」という営みの概略的な意義とともに「戦前」と「戦後」という言葉の中に含まれる「断絶」に注目し、そこで語られる「主体」が実は目的意識的に追及されその過程で、植民地主義あるいは戦争における日本人の責任が免罪されていったことを明らかにした。
第三回からは、このような視点でもって「戦後思想」を読み込んでみると新たに出てくる問題は何なのか、とりわけ「代表的テキストに基づく一貫してまとまりある『思想史』の語り」が「一貫してまとまりある排除をもって成立している」事実に着目し、代表的著作を取り上げつつそこに認められる差異と落差の中に「抗する」営みの実質を捉える努力をしている。
1.「戦後思想史」を割り割く読み
「…代表的なテクストをいくつか選んで読み、それによりもうひとつの『思想史』を語ろうとするなら、それはかなり危うくきわどい作業になってしまう…。小熊英二が文字どおり再演したことだが、たとえば時々の言説状況を支配した(マジョリティで男性の)知識人たちのテクストばかりを並べて取り上げ、このメインストリームを代表にして一貫した『戦後思想史』を語ってしまうと、どれほど多くのことがそれにより見えなくなってしまうだろうか(180)」。
- 「一貫した思想史」としての「物語」を語るうえで出てくる暴力性/排他性
・テクストを「選んで」読み取ること(たとえそれが同時代の多くの人々に読まれ同型的な思想の形が繰り返し現れてくると分かった場合でさえ)は、そのようなテクストを一連の系譜に整序したりするのは、それ自体が一つの解釈作業に他ならない。
・そのような言説は支配的な言語の文法に強く拘束され方向づけられている、ということから、その解釈に沿って語られる「思想史」も支配的な言説であるということから免れえない。
・すなわち、別様な意味理解の可能性についての抑圧や排除を必然的に含んでいる
→ まとまりある「思想史」の語りは、一貫してまとまりある排除をもって成立しているのである。
- そのような暴力性に抗する試みとして
①「思想史」の伝統的な語りに抗して、それが排除してきたテクストの存在に関心を寄せ、そのテクストのほかなる声に耳を傾けようとする努力(女性/民衆など)
→在日朝鮮人などのマイノリティ、労働者、学生、民衆が自ら声を発し、そこからの精神生活への影響など、また貧困や差別の極北におかれた人々の行動や声
→排除され埋没してきたそのような経験や声に光をあて、そこから「戦後」の思想的意味を考え直す
※しかし、「問題」はある。
・「資(史)料」の問題
:手に入れるのが難しいなか、手に入るいくつかのテクストを「代表」とするとまた「排除」が?
→「サバルタンは語れるのか(スピヴァク)」、「忘却の穴(アレント)」などを想定しているだろう。
② そのような「問題点」を鑑みるとき、一つの方法として以下のような方法論を提起できる。
「テクストとテクストの間、そこに現われている差異に意味を認め、その落差の中に『抗する』営みの実質を捉えて、それらの批判する潜在力を図ろうとする試み」
→間=「差異」と「落差」:このようなものがなぜ生まれ出る必要があったのか、というところに焦点をあて、想像力を働かせ、そのような言説に抗した『サバルタン』を逆照射すること。
→このような営みは、「一貫してまとまりのある思想物語」を不能とし、その裂け目から萌芽としてありえたさまざまな思想的可能性を精査することによって、それらが場合によって閉塞してしまった理由を考える。
- このような方法論にしたがった第一歩として
丸山真男「超国家主義の論理と心理」(1946年6月5日)、竹内好「中国の近代と日本の近代」(1948年11月)という著作に挑戦しなければ
これらは、「敗戦直後」、大きな影響力を持ったと認めうるテキストであり、また最初の時期に、民衆の加害責任を明確に意識して戦争責任の問題を提起した数少ないものであるからである。
→前回まで見てきた「ナショナリズム不在現象」と言われるこの時期、この二つのテキストはナショナルな枠組みで加害としての戦争責任を考える二つの起点として機能している。
「民族主義者」としての竹内好、「近代主義者」としての丸山真男は、ナショナル・アイデンティティを照射しようとする思想努力の契機において一致しているのである。
→このような二つの「起点」における差異に注目し、その亀裂から「まとまりのある戦後思想史」を割り割く可能性を示すのが、本稿の射程である。
2.「東洋の抵抗」という契機
-構成概念として駆使された「ヨーロッパ」(丸山真男)と「東洋」(竹内好)
・「ヨーロッパ」=「ヨーロッパ近代国家」VS「日本の超国家主義」という認識図式は戦後日本において日本を主題化するため丸山によって意図的に選択された「装置」
・「東洋が存在するかしないかという議論」:無意味、無内容、後ろ向きの議論
→現実の「ヨーロッパ」「東洋」がなにかではなく、構成概念として駆使されている
-「超国家主義の論理と心理」と「中国の近代と日本の近代」というクリアーな対照性
・竹内:「自分流に近代化の一般理論を目指した」
→丸山の著書が敗戦直後、日本の近代化を論ずる「一般理論」として定着、それに対する批判から生まれる
・竹内の目指したものは「東洋」への視野であった(「近代」という認識における対照性)
「東洋の近代は、ヨーロッパの強制の結果である、あるいは結果から導き出されたもの」
:「東洋に視野をおく」ということは、「東洋の抵抗」に注目する、ということ。すなわち「抵抗を通じて、東洋は自己を近代化した」
→この意味で竹内は、「近代化」という意味は、植民地主義・帝国主義として理解している。
※丸山は著作において「ヨーロッパ近代」を基本型として語っているが、その近代化論と著しい対照をなしているのである。
・植民地主義と侵略戦争に加担することで加害責任を負った日本の近代を考えるうえでの対照(日本認識における対照性)
丸山 日本の近代を遅れたもしくは歪んだ近代化として理解
→日本の加害責任に対して認識してはいるものの、その責任は、近代化を徹底することで引き受けられる:近代化が徹底されなかった「日本の至らなさ」にたいする「悔恨」、戦後に邁進すべき進歩という「目標」を示唆し、戦後日本において「啓蒙」の役割を果たす
竹内 正反対の方向に理論を展開(そもそも抵抗する側から見ると日本の近代とは何だったのか)
→日本は、「ある意味」では「進歩」していたが、その内実は「ドレイの進歩」であり、「ドレイの勤勉」であった:これが、日本をヨーロッパと肩を並べる植民地主義と侵略戦争へと駆り立てたのである
このように、竹内は「日本全体が『進歩』に照準を合わせて戦後復興に乗り出そうとするとき(プロジェクト Xが回顧するその時!)」、「日本は西欧的進歩を踏襲してアジアにおける反動となった」と指摘し、西欧的な近代化と進歩そのものに対する批判を展開した。このような意味で丸山とは対照をなすのである。そのような竹内の議論の中心にある概念が「ドレイ」である
3.自由なる主体とドレイ
※魯迅「賢者とバカとドレイ」(1925年12月26日、竹内好訳)
竹内は、この寓話の主語はドレイであり、魯迅自身である、という。
「魯迅においてある、そして魯迅そのものを成立せしめる、絶望」の意味から、魯迅を「ドレイ」と呼ぶ。
-竹内は、賢人がドレイを救う論理について言及する。「救う」ということは、結局ドレイの主観における「解放」でしかない。賢人はそのようなドレイたいして「ドレイという自覚を呼びさまさない」(夢を見させる、救わない)選択をする。ドレイが最も過酷な状況は、「ドレイという自覚」なのである。
→このような状況におかれたドレイ、すなわち「自己であることを拒否し、同時に自己以外のものであることを拒否する」ような「絶望」の状況におかれたドレイは「道のない道を行く抵抗」を選択せざるを得ないのである。これが、竹内の魯迅解釈
-このような竹内の主張を、上述した日本の「ドレイの進歩」とそれに対する「東洋の抵抗」という文脈で理解する
すなわち、魯迅と同じように、「絶望の基底部」から反転していく抵抗の形をとったのが、「東洋の抵抗」であったのである。
- 丸山と竹内の交差
・では、丸山はどのように「主体(=自由なる主体)」を語っているか?
「これだけの大戦争を起こしながら、我こそ戦争を起こしたという意識がこれまでのところ、どこにも見当たらない」という認識
→敗戦後における「自由なる主体意識」欠如に対して、丸山は批判している。
これは、竹内流の言葉でいうと「ドレイ根性」への批判として捉えられがちである。
・しかし、竹内の「魯迅観」を捉えなおしてみると、「ドレイ根性」に対する批判を媒介として重なって見えたはずの丸山と竹内は実は対極にいるという事実が浮かび上がってくる。
→竹内は、植民地主義と侵略戦争を生みなお圧倒的な支配力をもって継続している近代という時代そのものに向けて、「抵抗」しているのである。
すなわち、近代的「進歩」が孕む支配性と暴力性の避けがたさに対する明確な認識、それに抗する、「道のない道」を行くという意味での「抵抗」だけが「血にまみれた民族」の加害責任を受け止める道、ということを主張しているのである
・これに対して丸山は、「近代における主体」を語っている=近代としてなお「行く道がある」ということを前提としている。(竹内流に言えば、「賢人の救い」)
すなわち「よりよくヨーロッパになろうとすること」で脱却の道を探っていっている。「ドレイはかれみずからがドレイの主人になったときに十全のドレイ性を発揮」するのだが、それが日本の植民地主義であった。しかし、丸山はあらためて「近代における主体」を提唱し、そこに行く道を示している。
→この道は、結局日本が「自分がドレイであるという自覚さえ失わなければならない」道である。
戦後に「復興」「経済成長」へと進む日本が「奇跡の復興」に酔いそれを実現した「勤勉=(ドレイの勤勉!)」を自己賛美するようになったのは、そのような帰趨を示している。
まとめとして
竹内は、丸山が「超国家主義の論理と心理」において提起した「自由なる主体」という理念的核心をこのように「割り割いている」。
→このように、思想的に問題を詰めて再出発する一つの可能性、「戦後」に抗して進む道があったにもかかわらず、この可能性がどこに向かって開かれていったのか?またどんな問題があったのだろうか? 次回からまた提出されるであろう。
********************************************************
魯迅「賢者とバカとドレイ」
奴隷はとかく人に向って不平をこぼしたがるものであります。何かにつけてそうですし、またそうしかできないのです。ある日、彼はひとりの賢人に行きあいました。
「先生」と、彼は悲しそうに言いました。涙が糸のようにつながって、眼のふちから流れ落ちました。「あなたはそ存じでしょう。私の暮らしは、まるで人間の生活ではありません。食べるものといったら、一日に高粱のカスばかり、犬や豚だって食べたがりません。おまけに、小さな椀にたった一杯.....」
「まったくお気の毒だね」賢人も、痛ましげに言いました。
「そうですとも」彼は、愉快になってきました。「そのくせ、仕事は昼も夜も休みなしなんです。朝は水汲み、晩は飯たき、昼は使い走り、夜は粉ひき、晴れれば洗濯、雨降りゃ傘さし、冬は火燃やしで、夏は扇ぎ、夜中の御馳走つくり、御主人は麻雀、おこぼれどころか、貰うものは鞭だけ......」
「まあまあ.....」賢人は、ためいきをつきました。眼のふちが少し赤くなって、いまにも涙がこぼれそうです。
「先生、これではとてもつづきそうにありません。ほかに何とかやり方を考えないことには。でも、どんなやり方がありましょう....」
「そうでしょうか。そう願いたいものです。でも、私は、先生に悩みを打ち明けて、同情して頂いたり、慰めて頂いたりしましたので、すっかり気が楽になりました。まったく、お天道様は見殺しにはなさらないものですね.....」
けれども二、三日たつと、彼には不平が起こってきました。そこで例のように、不平を訴える相手を探しに出かけてゆきました。
「先生」と、彼は涙を流して言いました。「あなたはご存じでしょう。私の住んでいるところは、豚小屋よりももっとひどいのです。主人は私を、人間あつかいしてくれません。私より狆ころの方を何万倍もかわいがっています......」
「唐変木!」と、その人は、いきなり大声でどなったので、彼はびっくりしました。その人は馬鹿でありました。
「先生、私の住んでいるところは、ちっぽけなぼろ小屋です。じめじめして、まっくらで、南京虫だらけで、眠ったかと思うとたかってきて、やたらに食いまわります。むっと鼻をつくように臭いのです。四方に窓一つあいていません.....」
「おまえの主人に言って、窓を開けてもらうことができんのか」
「めっそうもない」
「それじゃ、おれを連れて行って見せろ」
馬鹿は、奴隷のあとについて、彼の家へ行きました。そしてさっそく、家の外から泥の壁をこわしにかかりました。
「先生、何をなさるのです」彼はびっくり仰天して、言いました。
「おまえに窓を開けてやるのさ」
「いけません。主人に叱られます」
「構うものか」相変わらずこわしつづけます。
「誰か来てくれ。強盗がわしらの家をこわしているぞ。早く来てくれ。早く来ないとぶっこ抜いてしまうぞ.....」泣きわめきながら、彼は地面をのたうちまわりました。
奴隷たちがみんな来ました。そして馬鹿を追い払いました。
叫び声をききつけて、ゆっくり最後に出てきたのが、主人でありました。
「強盗が、わたくしどもの家を毀そうといたしました。わたくしが、一番はじめにどなりました。みんなで力を合わせて、追っ払いました」彼は、うやうやしく、勝ち誇って言いました。
「よくやった」主人は、そう言ってほめてくれました。
その日、大勢の人が、見舞いにやって来ました。賢人もそのなかにまじっていました。
「先生、今回は私に手柄があって、主人がほめてくれました。このまえ、先生が、きっといまによくなると言ってくださったのは、ほんとうに、先見の明で.....」
希望に満ちたように、彼は朗らかにそう言いました。
「なるほどね.....」賢人も、お陰で愉快だといわんばかりに、そう答えました。
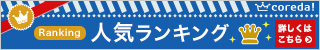

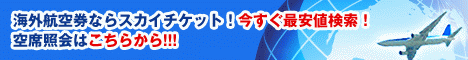

前回まで、中野敏男は「戦後を問う」という営みの概略的な意義とともに「戦前」と「戦後」という言葉の中に含まれる「断絶」に注目し、そこで語られる「主体」が実は目的意識的に追及されその過程で、植民地主義あるいは戦争における日本人の責任が免罪されていったことを明らかにした。
第三回からは、このような視点でもって「戦後思想」を読み込んでみると新たに出てくる問題は何なのか、とりわけ「代表的テキストに基づく一貫してまとまりある『思想史』の語り」が「一貫してまとまりある排除をもって成立している」事実に着目し、代表的著作を取り上げつつそこに認められる差異と落差の中に「抗する」営みの実質を捉える努力をしている。
1.「戦後思想史」を割り割く読み
「…代表的なテクストをいくつか選んで読み、それによりもうひとつの『思想史』を語ろうとするなら、それはかなり危うくきわどい作業になってしまう…。小熊英二が文字どおり再演したことだが、たとえば時々の言説状況を支配した(マジョリティで男性の)知識人たちのテクストばかりを並べて取り上げ、このメインストリームを代表にして一貫した『戦後思想史』を語ってしまうと、どれほど多くのことがそれにより見えなくなってしまうだろうか(180)」。
- 「一貫した思想史」としての「物語」を語るうえで出てくる暴力性/排他性
・テクストを「選んで」読み取ること(たとえそれが同時代の多くの人々に読まれ同型的な思想の形が繰り返し現れてくると分かった場合でさえ)は、そのようなテクストを一連の系譜に整序したりするのは、それ自体が一つの解釈作業に他ならない。
・そのような言説は支配的な言語の文法に強く拘束され方向づけられている、ということから、その解釈に沿って語られる「思想史」も支配的な言説であるということから免れえない。
・すなわち、別様な意味理解の可能性についての抑圧や排除を必然的に含んでいる
→ まとまりある「思想史」の語りは、一貫してまとまりある排除をもって成立しているのである。
- そのような暴力性に抗する試みとして
①「思想史」の伝統的な語りに抗して、それが排除してきたテクストの存在に関心を寄せ、そのテクストのほかなる声に耳を傾けようとする努力(女性/民衆など)
→在日朝鮮人などのマイノリティ、労働者、学生、民衆が自ら声を発し、そこからの精神生活への影響など、また貧困や差別の極北におかれた人々の行動や声
→排除され埋没してきたそのような経験や声に光をあて、そこから「戦後」の思想的意味を考え直す
※しかし、「問題」はある。
・「資(史)料」の問題
:手に入れるのが難しいなか、手に入るいくつかのテクストを「代表」とするとまた「排除」が?
→「サバルタンは語れるのか(スピヴァク)」、「忘却の穴(アレント)」などを想定しているだろう。
② そのような「問題点」を鑑みるとき、一つの方法として以下のような方法論を提起できる。
「テクストとテクストの間、そこに現われている差異に意味を認め、その落差の中に『抗する』営みの実質を捉えて、それらの批判する潜在力を図ろうとする試み」
→間=「差異」と「落差」:このようなものがなぜ生まれ出る必要があったのか、というところに焦点をあて、想像力を働かせ、そのような言説に抗した『サバルタン』を逆照射すること。
→このような営みは、「一貫してまとまりのある思想物語」を不能とし、その裂け目から萌芽としてありえたさまざまな思想的可能性を精査することによって、それらが場合によって閉塞してしまった理由を考える。
- このような方法論にしたがった第一歩として
丸山真男「超国家主義の論理と心理」(1946年6月5日)、竹内好「中国の近代と日本の近代」(1948年11月)という著作に挑戦しなければ
これらは、「敗戦直後」、大きな影響力を持ったと認めうるテキストであり、また最初の時期に、民衆の加害責任を明確に意識して戦争責任の問題を提起した数少ないものであるからである。
→前回まで見てきた「ナショナリズム不在現象」と言われるこの時期、この二つのテキストはナショナルな枠組みで加害としての戦争責任を考える二つの起点として機能している。
「民族主義者」としての竹内好、「近代主義者」としての丸山真男は、ナショナル・アイデンティティを照射しようとする思想努力の契機において一致しているのである。
→このような二つの「起点」における差異に注目し、その亀裂から「まとまりのある戦後思想史」を割り割く可能性を示すのが、本稿の射程である。
2.「東洋の抵抗」という契機
-構成概念として駆使された「ヨーロッパ」(丸山真男)と「東洋」(竹内好)
・「ヨーロッパ」=「ヨーロッパ近代国家」VS「日本の超国家主義」という認識図式は戦後日本において日本を主題化するため丸山によって意図的に選択された「装置」
・「東洋が存在するかしないかという議論」:無意味、無内容、後ろ向きの議論
→現実の「ヨーロッパ」「東洋」がなにかではなく、構成概念として駆使されている
-「超国家主義の論理と心理」と「中国の近代と日本の近代」というクリアーな対照性
・竹内:「自分流に近代化の一般理論を目指した」
→丸山の著書が敗戦直後、日本の近代化を論ずる「一般理論」として定着、それに対する批判から生まれる
・竹内の目指したものは「東洋」への視野であった(「近代」という認識における対照性)
「東洋の近代は、ヨーロッパの強制の結果である、あるいは結果から導き出されたもの」
:「東洋に視野をおく」ということは、「東洋の抵抗」に注目する、ということ。すなわち「抵抗を通じて、東洋は自己を近代化した」
→この意味で竹内は、「近代化」という意味は、植民地主義・帝国主義として理解している。
※丸山は著作において「ヨーロッパ近代」を基本型として語っているが、その近代化論と著しい対照をなしているのである。
・植民地主義と侵略戦争に加担することで加害責任を負った日本の近代を考えるうえでの対照(日本認識における対照性)
丸山 日本の近代を遅れたもしくは歪んだ近代化として理解
→日本の加害責任に対して認識してはいるものの、その責任は、近代化を徹底することで引き受けられる:近代化が徹底されなかった「日本の至らなさ」にたいする「悔恨」、戦後に邁進すべき進歩という「目標」を示唆し、戦後日本において「啓蒙」の役割を果たす
竹内 正反対の方向に理論を展開(そもそも抵抗する側から見ると日本の近代とは何だったのか)
→日本は、「ある意味」では「進歩」していたが、その内実は「ドレイの進歩」であり、「ドレイの勤勉」であった:これが、日本をヨーロッパと肩を並べる植民地主義と侵略戦争へと駆り立てたのである
このように、竹内は「日本全体が『進歩』に照準を合わせて戦後復興に乗り出そうとするとき(プロジェクト Xが回顧するその時!)」、「日本は西欧的進歩を踏襲してアジアにおける反動となった」と指摘し、西欧的な近代化と進歩そのものに対する批判を展開した。このような意味で丸山とは対照をなすのである。そのような竹内の議論の中心にある概念が「ドレイ」である
3.自由なる主体とドレイ
※魯迅「賢者とバカとドレイ」(1925年12月26日、竹内好訳)
竹内は、この寓話の主語はドレイであり、魯迅自身である、という。
「魯迅においてある、そして魯迅そのものを成立せしめる、絶望」の意味から、魯迅を「ドレイ」と呼ぶ。
-竹内は、賢人がドレイを救う論理について言及する。「救う」ということは、結局ドレイの主観における「解放」でしかない。賢人はそのようなドレイたいして「ドレイという自覚を呼びさまさない」(夢を見させる、救わない)選択をする。ドレイが最も過酷な状況は、「ドレイという自覚」なのである。
→このような状況におかれたドレイ、すなわち「自己であることを拒否し、同時に自己以外のものであることを拒否する」ような「絶望」の状況におかれたドレイは「道のない道を行く抵抗」を選択せざるを得ないのである。これが、竹内の魯迅解釈
-このような竹内の主張を、上述した日本の「ドレイの進歩」とそれに対する「東洋の抵抗」という文脈で理解する
すなわち、魯迅と同じように、「絶望の基底部」から反転していく抵抗の形をとったのが、「東洋の抵抗」であったのである。
- 丸山と竹内の交差
・では、丸山はどのように「主体(=自由なる主体)」を語っているか?
「これだけの大戦争を起こしながら、我こそ戦争を起こしたという意識がこれまでのところ、どこにも見当たらない」という認識
→敗戦後における「自由なる主体意識」欠如に対して、丸山は批判している。
これは、竹内流の言葉でいうと「ドレイ根性」への批判として捉えられがちである。
・しかし、竹内の「魯迅観」を捉えなおしてみると、「ドレイ根性」に対する批判を媒介として重なって見えたはずの丸山と竹内は実は対極にいるという事実が浮かび上がってくる。
→竹内は、植民地主義と侵略戦争を生みなお圧倒的な支配力をもって継続している近代という時代そのものに向けて、「抵抗」しているのである。
すなわち、近代的「進歩」が孕む支配性と暴力性の避けがたさに対する明確な認識、それに抗する、「道のない道」を行くという意味での「抵抗」だけが「血にまみれた民族」の加害責任を受け止める道、ということを主張しているのである
・これに対して丸山は、「近代における主体」を語っている=近代としてなお「行く道がある」ということを前提としている。(竹内流に言えば、「賢人の救い」)
すなわち「よりよくヨーロッパになろうとすること」で脱却の道を探っていっている。「ドレイはかれみずからがドレイの主人になったときに十全のドレイ性を発揮」するのだが、それが日本の植民地主義であった。しかし、丸山はあらためて「近代における主体」を提唱し、そこに行く道を示している。
→この道は、結局日本が「自分がドレイであるという自覚さえ失わなければならない」道である。
戦後に「復興」「経済成長」へと進む日本が「奇跡の復興」に酔いそれを実現した「勤勉=(ドレイの勤勉!)」を自己賛美するようになったのは、そのような帰趨を示している。
まとめとして
竹内は、丸山が「超国家主義の論理と心理」において提起した「自由なる主体」という理念的核心をこのように「割り割いている」。
→このように、思想的に問題を詰めて再出発する一つの可能性、「戦後」に抗して進む道があったにもかかわらず、この可能性がどこに向かって開かれていったのか?またどんな問題があったのだろうか? 次回からまた提出されるであろう。
********************************************************
魯迅「賢者とバカとドレイ」
奴隷はとかく人に向って不平をこぼしたがるものであります。何かにつけてそうですし、またそうしかできないのです。ある日、彼はひとりの賢人に行きあいました。
「先生」と、彼は悲しそうに言いました。涙が糸のようにつながって、眼のふちから流れ落ちました。「あなたはそ存じでしょう。私の暮らしは、まるで人間の生活ではありません。食べるものといったら、一日に高粱のカスばかり、犬や豚だって食べたがりません。おまけに、小さな椀にたった一杯.....」
「まったくお気の毒だね」賢人も、痛ましげに言いました。
「そうですとも」彼は、愉快になってきました。「そのくせ、仕事は昼も夜も休みなしなんです。朝は水汲み、晩は飯たき、昼は使い走り、夜は粉ひき、晴れれば洗濯、雨降りゃ傘さし、冬は火燃やしで、夏は扇ぎ、夜中の御馳走つくり、御主人は麻雀、おこぼれどころか、貰うものは鞭だけ......」
「まあまあ.....」賢人は、ためいきをつきました。眼のふちが少し赤くなって、いまにも涙がこぼれそうです。
「先生、これではとてもつづきそうにありません。ほかに何とかやり方を考えないことには。でも、どんなやり方がありましょう....」
「そうでしょうか。そう願いたいものです。でも、私は、先生に悩みを打ち明けて、同情して頂いたり、慰めて頂いたりしましたので、すっかり気が楽になりました。まったく、お天道様は見殺しにはなさらないものですね.....」
けれども二、三日たつと、彼には不平が起こってきました。そこで例のように、不平を訴える相手を探しに出かけてゆきました。
「先生」と、彼は涙を流して言いました。「あなたはご存じでしょう。私の住んでいるところは、豚小屋よりももっとひどいのです。主人は私を、人間あつかいしてくれません。私より狆ころの方を何万倍もかわいがっています......」
「唐変木!」と、その人は、いきなり大声でどなったので、彼はびっくりしました。その人は馬鹿でありました。
「先生、私の住んでいるところは、ちっぽけなぼろ小屋です。じめじめして、まっくらで、南京虫だらけで、眠ったかと思うとたかってきて、やたらに食いまわります。むっと鼻をつくように臭いのです。四方に窓一つあいていません.....」
「おまえの主人に言って、窓を開けてもらうことができんのか」
「めっそうもない」
「それじゃ、おれを連れて行って見せろ」
馬鹿は、奴隷のあとについて、彼の家へ行きました。そしてさっそく、家の外から泥の壁をこわしにかかりました。
「先生、何をなさるのです」彼はびっくり仰天して、言いました。
「おまえに窓を開けてやるのさ」
「いけません。主人に叱られます」
「構うものか」相変わらずこわしつづけます。
「誰か来てくれ。強盗がわしらの家をこわしているぞ。早く来てくれ。早く来ないとぶっこ抜いてしまうぞ.....」泣きわめきながら、彼は地面をのたうちまわりました。
奴隷たちがみんな来ました。そして馬鹿を追い払いました。
叫び声をききつけて、ゆっくり最後に出てきたのが、主人でありました。
「強盗が、わたくしどもの家を毀そうといたしました。わたくしが、一番はじめにどなりました。みんなで力を合わせて、追っ払いました」彼は、うやうやしく、勝ち誇って言いました。
「よくやった」主人は、そう言ってほめてくれました。
その日、大勢の人が、見舞いにやって来ました。賢人もそのなかにまじっていました。
「先生、今回は私に手柄があって、主人がほめてくれました。このまえ、先生が、きっといまによくなると言ってくださったのは、ほんとうに、先見の明で.....」
希望に満ちたように、彼は朗らかにそう言いました。
「なるほどね.....」賢人も、お陰で愉快だといわんばかりに、そう答えました。











