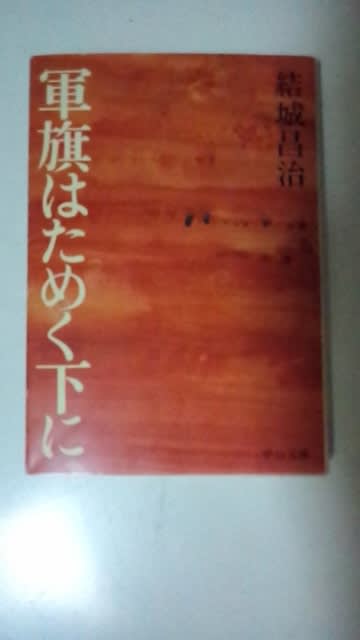『軍旗はためく下に』(結城昌治 中公文庫)
古い映画を専門に上映しているシアターでポスターを目にし、原作が直木賞とあって興味を抱いた。著者の名は知らなかった。主として推理小説を書いた人らしい。アマゾンで見つけて注文した。
五つの短編によって構成されている。だいぶ昔の古本で、以前の持ち主のメモには昭和48年と書き添えられていた。『面白くていっきに読んだ』とある。
『フーコン戦記』を読んでいるので、読了後にすべきだったのだが、ぱらぱらとめくっているうちに止まらなくなり、五つの物語を立て続けに読んでしまった。
陸軍刑法によって処刑された者たちにクローズアップした短編集である。それぞれ罪状毎に短編となっている。
『敵前逃亡・奔敵』
『従軍免脱』
『司令官逃避』
『敵前党与逃亡』
『上官殺害』
そして冒頭には、刑法が抜粋され、それがエピグラフのように掲げられる。
<陸軍刑法>
第七十六条 党与シテ故ナク職役ヲ離レ又ハ職役二就カサル者ハ左ノ区別二従テ処断ス。
一 敵前ナルトキハ首魁ハ死刑又ハ無期ノ懲役若ハ禁錮二処シ其ノ他ノ者ハ死刑、無期若ハ七年以上ノ懲役又ハ禁錮二処ス。
日本軍の蒙昧は、神がかりのような“必勝の信念”や、国際法を無視した“戦陣訓”、『失敗の本質』で取り上げられた空気を読む組織内文化だけでないということを、本書で痛感した。
陸軍刑法という抑圧の装置をも駆使して、兵らを支配し、自己保身をすら図っていたのである。多くの処刑、しかも軍法会議さえ経ない処刑が横行したことを本書は匂わしている。戦死でなく、身内に殺されるとはやり切れないだけでなく、処刑は戦病死とは扱いが異なり、遺族は恩給ももらえなかったというから二重苦だ。
と、こんなやり切れない話を、ここまで読ませるものにしてみせる著者の筆力は驚異だ。
元兵士らに聞き取りをし、事件の輪郭が解明する展開は、推理作家の得意とする描き方なのだろうが、緊張感が保たれ、緊迫感を持って読了していた。関係者が多く存命であった時代、こういうものを書くのは、一筋縄ではなかったろう。
著者は戦後、東京地検に勤務し、軍における処刑の数々を知って、このテーマを自身の使命のように抱え続けていたらしい。あとがきでそのことに触れている。
私は昭和二十七年のいわゆる講和恩赦の際、恩赦事務にたずさわる機会があって膨大な件数にのぼる軍法会議の記録を読み、そのとき初めて知った軍隊の暗い部分が脳裏に焼きついていた。それと、私自身戦争の末期に海軍を志願してほんの短期間ながら軍隊生活を経験したことが執筆の動機になっている。
純文学ではないために、文学史の年表に載らなかったりして、手にとる機会を得ないこういう本がまだまだたくさんあるのかもしれないと思う。
アンテナは拡げておかねば。また、今回は映画館でのふとした出会いだった。足で稼ぐ情報も、やはり必要である。
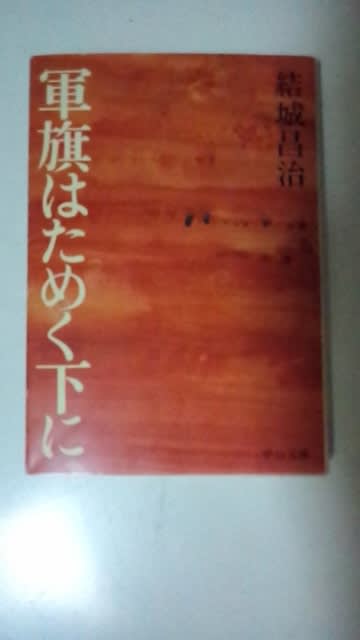
古い映画を専門に上映しているシアターでポスターを目にし、原作が直木賞とあって興味を抱いた。著者の名は知らなかった。主として推理小説を書いた人らしい。アマゾンで見つけて注文した。
五つの短編によって構成されている。だいぶ昔の古本で、以前の持ち主のメモには昭和48年と書き添えられていた。『面白くていっきに読んだ』とある。
『フーコン戦記』を読んでいるので、読了後にすべきだったのだが、ぱらぱらとめくっているうちに止まらなくなり、五つの物語を立て続けに読んでしまった。
陸軍刑法によって処刑された者たちにクローズアップした短編集である。それぞれ罪状毎に短編となっている。
『敵前逃亡・奔敵』
『従軍免脱』
『司令官逃避』
『敵前党与逃亡』
『上官殺害』
そして冒頭には、刑法が抜粋され、それがエピグラフのように掲げられる。
<陸軍刑法>
第七十六条 党与シテ故ナク職役ヲ離レ又ハ職役二就カサル者ハ左ノ区別二従テ処断ス。
一 敵前ナルトキハ首魁ハ死刑又ハ無期ノ懲役若ハ禁錮二処シ其ノ他ノ者ハ死刑、無期若ハ七年以上ノ懲役又ハ禁錮二処ス。
日本軍の蒙昧は、神がかりのような“必勝の信念”や、国際法を無視した“戦陣訓”、『失敗の本質』で取り上げられた空気を読む組織内文化だけでないということを、本書で痛感した。
陸軍刑法という抑圧の装置をも駆使して、兵らを支配し、自己保身をすら図っていたのである。多くの処刑、しかも軍法会議さえ経ない処刑が横行したことを本書は匂わしている。戦死でなく、身内に殺されるとはやり切れないだけでなく、処刑は戦病死とは扱いが異なり、遺族は恩給ももらえなかったというから二重苦だ。
と、こんなやり切れない話を、ここまで読ませるものにしてみせる著者の筆力は驚異だ。
元兵士らに聞き取りをし、事件の輪郭が解明する展開は、推理作家の得意とする描き方なのだろうが、緊張感が保たれ、緊迫感を持って読了していた。関係者が多く存命であった時代、こういうものを書くのは、一筋縄ではなかったろう。
著者は戦後、東京地検に勤務し、軍における処刑の数々を知って、このテーマを自身の使命のように抱え続けていたらしい。あとがきでそのことに触れている。
私は昭和二十七年のいわゆる講和恩赦の際、恩赦事務にたずさわる機会があって膨大な件数にのぼる軍法会議の記録を読み、そのとき初めて知った軍隊の暗い部分が脳裏に焼きついていた。それと、私自身戦争の末期に海軍を志願してほんの短期間ながら軍隊生活を経験したことが執筆の動機になっている。
純文学ではないために、文学史の年表に載らなかったりして、手にとる機会を得ないこういう本がまだまだたくさんあるのかもしれないと思う。
アンテナは拡げておかねば。また、今回は映画館でのふとした出会いだった。足で稼ぐ情報も、やはり必要である。