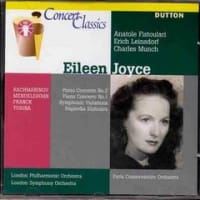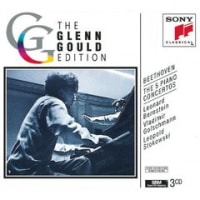京都にも、もう桜が咲いた。花冷え、とはこういうことなのかと思う、寒い日がまた戻ってきたというのに。
私は、毎日二条城の前を往復して駅へ向かうのだけれど、夜間ライトアップが始まっていて、今日の帰路は、たくさんの人で賑わっていた。確かに、夜の闇のなかに照らし出された桜の花が、一種独特の妖艶さを持っていることは、いまさら私が言うまでも無く、広く知られたことだ。
国語学の大家、山田孝雄博士の「櫻史」という名著がある。昭和16年刊行であるから、とても古い本だけれども、国語学の門外漢である私にも親しめる、浩瀚博識の書である。「櫻史まさに公にせられむとす。時正に櫻花爛漫たり。」という書き出しで始まるこの論文は、桜の花同様の、実に美しい文体を持っている。ここで博士は、古今の膨大な例を引きながら、日本人と桜の密接な関わり合いを説く。
そういう言わば「桜党」とでも言うべき氏の名著を引きながら、私自身は桜の花にかかる愛着を持たないことを、告白しなければならない。何も、あの美しさに感動しないような荒んだ心を持っているのではないけれど、散ったあと、いかにも惨めに路傍に吹き曝されている様が、何とも心苦しいのである。
「桜の木の下には死体が埋まっている!」と書いたのは梶井基次郎であったが、寧ろその感覚に、私は与し得る気が、している。
そう、散るといえば、私は椿が好きではなかった。あの「ぼとっ」と地面に落ちるのが、私はあまり好きではない。到底、潔いなどとは、言えはしない。
私は、いろ・かたち・におい、今も昔も変わらず、梅の花が好きだ。殊に、蝋梅が。
けれどもこのところ、茶の道に入るに及んで、茶花に些かの関心を持つようになって、次第に印象が改まった。晩秋以降、冬の訪れを感じると共に、茶会の折にも椿が生けられることが多くなる。私は元来甚だ不精な人間で、およそ植物も動物も、ひとりで世話をしきった記憶が無く、よって乏しい知識しか持ち合わせていない。私が今まで脳裡に描いてきた「椿」が、一体何という名を持つものかさえ分かりはしないが、初釜の折に知った、「西王母」という故事に由来した名を持つ、つつましやかな桃色の花に、すっかり心惹かれてしまったのであった。
爾来、いろいろと調べてみると、日本産の椿だけで2000種以上があって、いずれも実に美しい名前を持っている。
茶道では、莟の花しか用いないが、開けばまた、別の美しさを見せてくれるのだろうと、このところ思っては楽しんでいる。
閑話休題。「びいでびいで」と呼ばれる桜を、御存知であろうか。これは南国の方言で、正式な名を、ムニンデイゴ、あるいは南洋桜というそうだ。私は、「桜」というコトバを使ったけれども、どうやらこれは桜ではないらしい。桜が自生しない小笠原では、春の訪れを告げる花として、よく似たこのムニンデイゴを桜と擬えているとの由。花は真紅ということだが、私はまだ、見たことが無い。
関西楽壇の重鎮であった平井康三郎氏に、「びいでびいで」という歌曲がある。歌曲集「日本の笛」の一篇。詩は、北原白秋。
びいでびいでの
今 花盛り
紅いかんざし
暁(あけ)の霧
びいでびいでの
あの花かげで
何とお仰(しゃ)った
末(すえ)かけた
南国の暖かい春、島の娘の屈託のない笑顔が浮かんでくるよう―と言うとあまりに陳腐であろうが、そういう表現をつい口にしたくなるような、明るい、弾んだ佳曲。
「平城山」「スキー」など、誰もが馴染んだ童謡の作者である平井氏であるが、この曲を私は、つい最近まで不覚にして知らずにいた。北新地に、同名のクラブがあって、そこで初めて知り、また聴いたのである。
いつのまにか、随分と色々なことに詳しくなったものだ。
ところで、あすこのマダムは、南国出身なのだろうか。次に行く折の楽しみが、できた。
私は、毎日二条城の前を往復して駅へ向かうのだけれど、夜間ライトアップが始まっていて、今日の帰路は、たくさんの人で賑わっていた。確かに、夜の闇のなかに照らし出された桜の花が、一種独特の妖艶さを持っていることは、いまさら私が言うまでも無く、広く知られたことだ。
国語学の大家、山田孝雄博士の「櫻史」という名著がある。昭和16年刊行であるから、とても古い本だけれども、国語学の門外漢である私にも親しめる、浩瀚博識の書である。「櫻史まさに公にせられむとす。時正に櫻花爛漫たり。」という書き出しで始まるこの論文は、桜の花同様の、実に美しい文体を持っている。ここで博士は、古今の膨大な例を引きながら、日本人と桜の密接な関わり合いを説く。
そういう言わば「桜党」とでも言うべき氏の名著を引きながら、私自身は桜の花にかかる愛着を持たないことを、告白しなければならない。何も、あの美しさに感動しないような荒んだ心を持っているのではないけれど、散ったあと、いかにも惨めに路傍に吹き曝されている様が、何とも心苦しいのである。
「桜の木の下には死体が埋まっている!」と書いたのは梶井基次郎であったが、寧ろその感覚に、私は与し得る気が、している。
そう、散るといえば、私は椿が好きではなかった。あの「ぼとっ」と地面に落ちるのが、私はあまり好きではない。到底、潔いなどとは、言えはしない。
私は、いろ・かたち・におい、今も昔も変わらず、梅の花が好きだ。殊に、蝋梅が。
けれどもこのところ、茶の道に入るに及んで、茶花に些かの関心を持つようになって、次第に印象が改まった。晩秋以降、冬の訪れを感じると共に、茶会の折にも椿が生けられることが多くなる。私は元来甚だ不精な人間で、およそ植物も動物も、ひとりで世話をしきった記憶が無く、よって乏しい知識しか持ち合わせていない。私が今まで脳裡に描いてきた「椿」が、一体何という名を持つものかさえ分かりはしないが、初釜の折に知った、「西王母」という故事に由来した名を持つ、つつましやかな桃色の花に、すっかり心惹かれてしまったのであった。
爾来、いろいろと調べてみると、日本産の椿だけで2000種以上があって、いずれも実に美しい名前を持っている。
茶道では、莟の花しか用いないが、開けばまた、別の美しさを見せてくれるのだろうと、このところ思っては楽しんでいる。
閑話休題。「びいでびいで」と呼ばれる桜を、御存知であろうか。これは南国の方言で、正式な名を、ムニンデイゴ、あるいは南洋桜というそうだ。私は、「桜」というコトバを使ったけれども、どうやらこれは桜ではないらしい。桜が自生しない小笠原では、春の訪れを告げる花として、よく似たこのムニンデイゴを桜と擬えているとの由。花は真紅ということだが、私はまだ、見たことが無い。
関西楽壇の重鎮であった平井康三郎氏に、「びいでびいで」という歌曲がある。歌曲集「日本の笛」の一篇。詩は、北原白秋。
びいでびいでの
今 花盛り
紅いかんざし
暁(あけ)の霧
びいでびいでの
あの花かげで
何とお仰(しゃ)った
末(すえ)かけた
南国の暖かい春、島の娘の屈託のない笑顔が浮かんでくるよう―と言うとあまりに陳腐であろうが、そういう表現をつい口にしたくなるような、明るい、弾んだ佳曲。
「平城山」「スキー」など、誰もが馴染んだ童謡の作者である平井氏であるが、この曲を私は、つい最近まで不覚にして知らずにいた。北新地に、同名のクラブがあって、そこで初めて知り、また聴いたのである。
いつのまにか、随分と色々なことに詳しくなったものだ。
ところで、あすこのマダムは、南国出身なのだろうか。次に行く折の楽しみが、できた。