さて、二月堂の須弥壇には、「造花の椿」が華やかに飾られ邪気を払います。
京都伏見の紅花で染めた和紙を使用で、二月堂の下に建つ「開山堂」の境内に咲く
奈良三銘椿の1つ「糊零し(良弁椿)」を模して、
練行衆によって2月23日「花ごしらえ」で作られます。
赤と白染めの仙花紙を5枚花弁に、黄染めの傘紙を芯にして、
5cm程に切られたタロに貼り付けて400個作られるとのことです。
その椿の造花をもとに作られた和菓子「開山良弁椿」ってのが、
猿沢の池からJR奈良方面にすこし歩いたところにある「鶴屋徳満」さんで売られていましたので、
買ってきました。


三個1500円くらいと、ちょっとびっくりする値段でした。
値段に見合うおいしさかというと・・・微妙。
ただ、季節のものですからね。
(写真うまく取れなかったので、ちょっとHPから拝借しました)

家に帰る頃はすっかり夜になっていて、
「青によし 平城山の上に 満月」
まさに、その言葉のような風景でした。













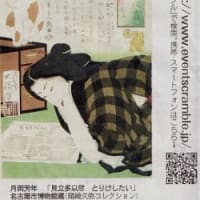
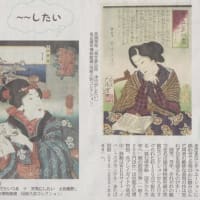





元宵の元は1月、宵は夜の意味で、旧暦1月15日は新年最初の満月の夜になります。
この日、皆は新しい春の到来を祝って、提灯に火を灯し、月を眺めます。
昔は、花提灯を観賞するという口実で若い男女は遊びに出かけ、相手を探すことができました。だから恋人に出会うための「恋人節」という名前もあります。
芋あんなんでしょうか?こういうものはそんなにどれも変わらないでしょうけど、食べるのが勿体無い感じがします。数年間和菓子は食べてないな~
中国ではまだ旧暦が生活の中心なのでしょうか。
満月を眺めるなんて、いいですね~。
最近こちらでは季節を愛でることが減ってきているように思えます。
業者の仕掛けたバレンタインデーのチョコレートとか、節分の恵方丸かじりとかばかりがクローズアップされて…
三個1500円という価格を考えると
まあ、季節の料金も入っているかという味です。
見て楽しむおかしかもしれません。
花びらは羊羹っぽくって、
黄色いところが餡でした。