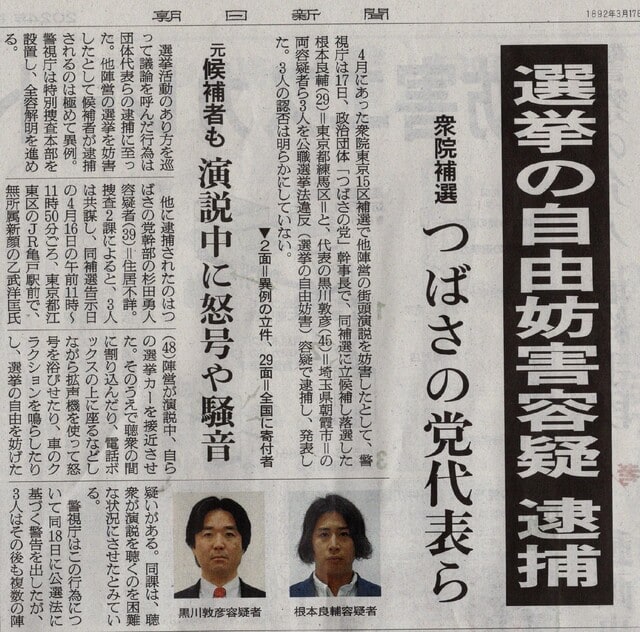前から不思議に思っていたこの謎が知りたくて読んでみた。21人の経済学者がそれぞれの分析を試みているが、まさに「群盲象を撫でる」である。曰く
① 非正規雇用が増えたから
② 労働分配率が下がったから
③ 労働生産性が落ちたから
④ 賃金の下方硬直性が上方硬直性をもたらしているから
⑤ 医療・福祉・介護業界ではサービス価格が政府によって規制されているので、需要があっても価格を上げることができないから。
⑥ 原材料の値上がりを価格転嫁できないので、労働コストを下げているから
⑦ 成果主義に原因があるから
⑧ 就職氷河期の人口サイズが大きく、彼らの賃金が低く抑えられているから
⑨ 労働者側の交渉力が弱体化しているから
⑩ 外国人労働者を導入したから
そうした中で、ちょっと有力だと思ったのは①に関連した、非正規労働市場の供給曲線を用いた説明である。

現在、30歳代の既婚女性や60歳を超える高齢者の就業率が確実に上昇している。低成長が続くなかで、彼らは生活の足しにしようと、わずかな賃金上昇でも労働市場に参入しようとする。その結果、労働供給曲線は水平に近い形(=弾力的)になる。これはちょうど、農業国が工業化を推し進めるうえで農村部に過剰労働力が存在する状況と似ている。
したがって、賃金が上昇しなかった根本的な理由は「非正規労働市場における弾力的な労働曲線にあった」と執筆者は結論付ける。
うーん、なるほど。このことをわが身に照らし合わせれば、非常勤講師という月6万円程度にしかならない低賃金で授業を行っている私も、賃金の上方硬直性の犯人の一人ということか。納得・・・
ただ、全体を読み終えて分析の仕方が経済学に偏りすぎていると感じた。もうすこし、労働組合の弱体化や政治的な側面も取り上げないと、根本原因はつかめない気がする。