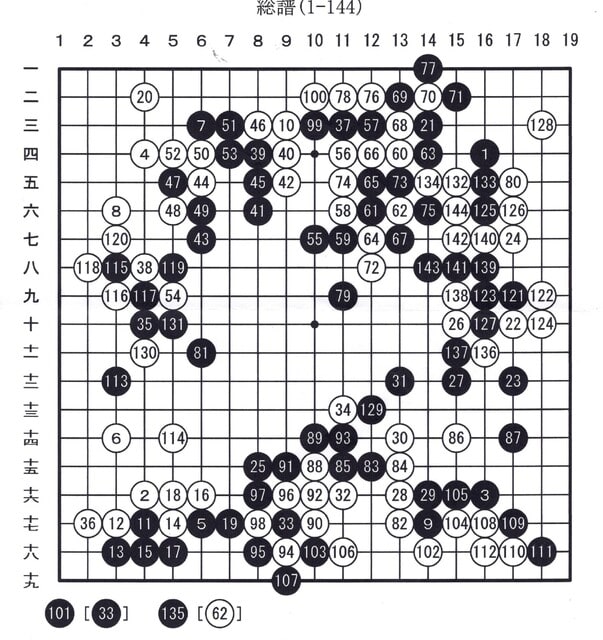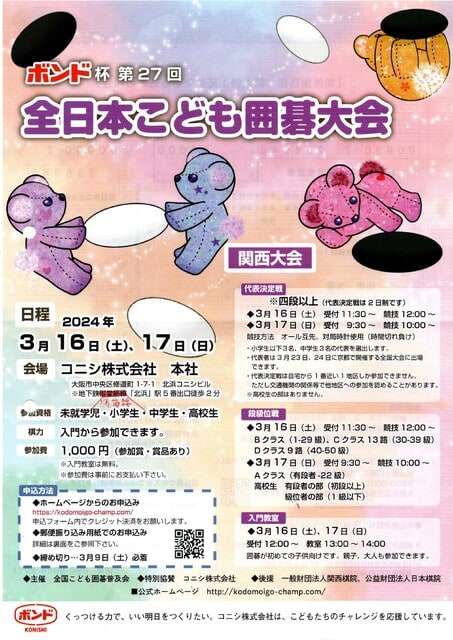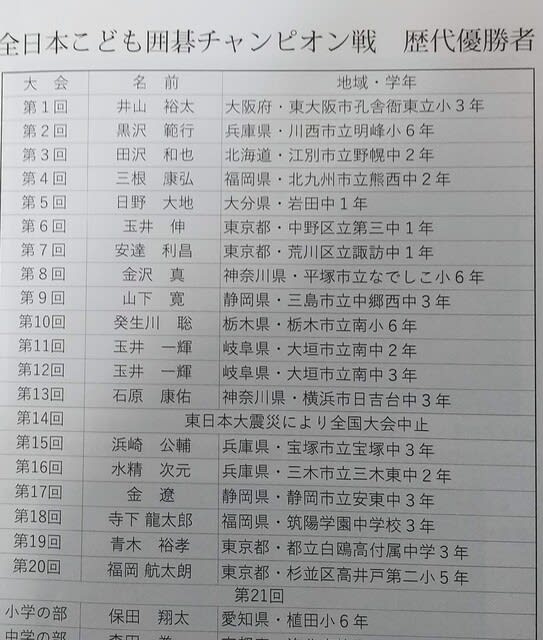本来の仏教は、釈迦が「生老病死」の苦しみから人々を救済するために説いた宗教であり、葬式とは何の関係もなかった。それが日本に伝わっていつの間にか葬式仏教になった。また釈迦は「平等」の重要性を説いた。しかし、日本の仏教界は寺院、僧侶、戒名などあらゆるものに「格差」を設け、平等とはほど遠い。
どうしてこんなことになってしまったのか。まるで悪い伝言ゲームのようだ。この疑問を解き明かすため何冊かの本を読んでみた。
(1)奈良仏教と平安仏教
日本に仏教が伝わったのは538年といわれる。当時日本には、神道と呼ばれる民族宗教があった。海、山、木、田んぼなどありとあらゆるものに神が宿るとされ、その信仰は今でも各地のお祭りや伝統行事に受け継がれている。
そこへ金ぴかの仏像をともなった仏教が入り込んできた。両者の間でバトルが展開され、政治的に勝利した仏教は奈良時代に国家の保護を受けるようになり日本に定着した。ただし、仏教の役割は国家の平安を守ることであり、葬式をすることではなかった。だから、東大寺、薬師寺、唐招提寺、清水寺など奈良時代からのお寺(奈良仏教)は今でも葬式をやらない。仏教は庶民にとって無縁の存在でしかなかった。
平安時代になって天台宗や真言宗が広まった。しかし、これらも貴族を中心とする富裕層の宗教であり庶民には無縁のものであった。
(2)庶民の宗教となった鎌倉仏教
仏教が庶民の間に広がったのは鎌倉時代になってからである。それまで貴族を中心としてきた仏教に対抗して、念仏さえ唱えれば誰でも救われると説いた浄土宗、浄土真宗などが急速に人々の信仰を集めるようになった。

(親鸞 井上雄彦画 東本願寺所有)
(3)江戸時代に現在の菩提寺システム確立
さらに江戸時代になると仏教は新たな役割を担わされるようになる。1637年に島原の乱がおきると、幕府は鎖国を行ない、さらにはキリスト教徒をあぶりだすために寺請け制度を実施した。そしてすべての家を檀家としてどこかの寺に帰属させ、寺には役所に宗旨人別帳を提出することを義務付けた。
寺は檀家の葬式を通じて葬儀、戒名などをお布施として受け取る。その一部は上納金として上位の寺に納められる。やがて本山を中心とする強大なピラミッド構造の利権集団が形成され、「お葬式は寺が引き受けます。その代わり寺の生活を檀家がみてください」という菩提寺システムが確立された。
現在の寺はこの江戸時代に確立された菩提寺システムがそのまま残っている。本山と末寺の関係もそのままであり、両者は二重構造をなしている。すなわち、全国に何万とある末寺には独立性が認められているが、その一方で本山に上納金を納める義務も課せられている。上納金は寺の格や檀家の数によって決められる。もし末寺が上納金を拒否して本山の末寺リストから外されると、末寺は檀家もすべて失う。だから末寺は本山には逆らえない。
このことは、本山はその権力を利用して末寺に過酷な上納金を安心して要求できることを意味する。本山は末寺のことを何も知らないし、知ろうともしない。本山にとって末寺は上納金を収めてくれればそれでよい存在でしかない。たとえ末寺の僧侶が不良行為を行なってもその懲戒規定は極めて緩く、審事院はほとんど機能していない。末寺が減れば上納金が減るのだから当然のことかもしれない。
江戸時代は一部の宗派を除いて僧侶の妻帯は認められていなかった。だから、末寺は現在のような世襲ではなく、弟子が跡を継いだ。ところが明治5年「肉食、妻帯、蓄髪、平服着用、勝手たるべし」という政府のお触れが出た。これ以降、僧侶も家庭を持つようになり、息子が副住職となって跡を継ぐことが一般化した。
しかし、いったん寺の世襲が認められると、寺の利権確保、利益への欲望は世俗と変わらなくなる。かくして末寺は独立した企業体となり、住職は家業となった。
(4)寺院は生き残れるか
現在日本には7万6千の寺院がある。コンビニの5万7千店より多い。上位5寺院をを宗派別にみると次のようになっている(カッコ内は本山)。
1.曹洞宗(永平寺、総持寺)
14604寺院
2.浄土真宗本願寺派(西本願寺)
10473寺院
3.浄土真宗大谷派(東本願寺)
8860寺院
4.浄土宗(知恩院)
7125寺院
5.日蓮宗(身延山久遠寺)
5011寺院
これら7万6千の寺院のうち、すでに住職がいない寺が地方を中心に1万5千あると言われ、寺院の将来が危ぶまれている。なぜ寺院の存続が危機にさらされているのか。その主な原因は次の3つである。
(原因)
① 高度経済成長後の都市化によって地方の檀家数が激減し、葬祭収入に依存する寺院経営が困難になった。
② 昭和30年代から葬祭業者が台頭し、葬式を収益源としてきた寺の収入が落ち込んだ。
③ 寺院が心の栄養を送り込む役目を果たせず、人々の仏教離れが進んだ。
一般に、寺院経営の損益分岐点となる檀家数は400軒といわれる。寺の収入の8割は葬祭関係である。400軒の檀家数があれば年間30件程度の葬式が見込まれ、寺院の経営に余裕が生まれる。ちなみに現在の平均的な葬儀費用は237万円とされ、その内訳は次のようになっている。
葬儀社 142万円
寺 55万円(戒名料を含む)
飲食費 40万円
江戸時代には「坊主丸儲け」などと陰口をたたかれたが、現在は寺よりも葬儀社の力のほうが上である。そのため葬儀費用の大半は葬儀社がもっていってしまう。以前「おくりびと」という映画が話題になったが、葬儀社はたいへんおいしいビジネスなのである。お棺、霊柩車、葬儀会場、仕出し屋、花屋、お坊さんなどはすべて外注に出すことも可能で、その気になれば葬祭業は電話1本で一人でもできる。最近小さなお葬式をうたい文句にしたそうした業者が増えている。

現在、寺の主要な収益源となっているのは「戒名料」である。戒名とは「死後出家」のことであり、死んだ後に僧侶になることを意味する。しかし、一般には「あの世へ行くためのパスポート」として理解されており、「院」「居士」「信士」などとランク付けされ、それぞれ異なる料金が設定されている。
よく世間では戒名料が高すぎると批判される。最高ランクの「院」の戒名を得るには100万円以上することも珍しくない。しかし、寺を経営するためには、住職の給料、所得税、寺の改築・修理、年間100万円単位と言われる本山への上納金や臨時負担金などのほか、僧侶として出世(?)するためにも相応のお金がかかる。そのため末寺は稼ぎ頭の戒名料で儲けざる得ないのである。
一方、寺の建物(固定資産)は住職の所有物ではない。だから固定資産税は免除されている。また本山にも寺の所有権はない。本山にあるのは任命権だけである。本山は末寺の住職の任命に際しては1000万円~2000万円のお金を受け取るといわれる。こうした本山を頂点とする仏教界の収奪構造を底辺で支えているのが檀家である。
ところが、その檀家が今減少している。それにもかかわらず本山は末寺の経営には無関心である。末寺の住職は寺を維持するため、教員や公務員などと兼業をしたり、霊園・駐車場・マンション・保育園や幼稚園を経営をしたりして、何とかやりくりしている。
しかし、家業としての住職が成り立たなくなれば、子どもは寺の後を継ぎたがらなくなる。特に子どもが優秀であればあるほど、寺の世襲は困難になる。そうした問題を本山は全く顧みない。いくらインスタントに僧侶を養成したところで、減少する檀家と葬式に依存する現在の体質が変わらない限り、今後、寺の維持が困難となって廃寺が増えるのは間違いない。

(島根県の廃寺 毎日新聞より)



(5)法然院を訪ねる
以前、京都の法然院を訪ねたことがある。貫主の梶田真章さんのお話を聞いたが、上部組織を持たない単立寺院で実に様々な試みを自由にやっておられた。「他力本願の他力とは仏力のことです」「仏教は人生をいかに楽に生きるかを教えてくれる知恵なのです」。心から尊敬できるお坊さんだと思った。
人付き合いや仕事、人生への不安、そうした悩みにこたえるのが宗教だとすれば、宗教が地球から消えてなくなることはないだろう。今の日本に必要なのは江戸時代につくられた利権構造をぶち壊して、本当の信者を獲得することである。
僧侶の資格を取得した後ろくろく修行もしない家業としてのサラリーマン住職と、プロの宗教家として一生を修行にささげる僧侶は全く別物である。日本の仏教界はこれからどこへ向かうつもりであろうか。

(法然院 山門)

法然院 梶田真章貫主