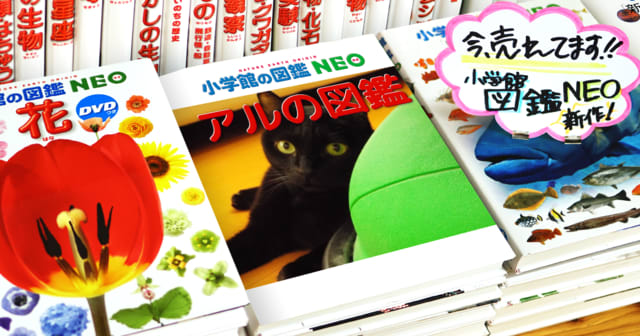金価格の高騰が続いている。1キログラム900万円を超えてきた。金価格は世界情勢が不安定になると高騰する。今回は次のような要因が影響していると考えられる。
・世界中を襲った新型コロナウイルス
・ロシアによるウクライナ侵攻
・アメリカと中国の不仲
・3月にアメリカの大きな銀行が相次いで経営破綻
・スイスで2位の規模を誇る金融機関の経営危機
資産運用は分散投資が基本である。アベノミクスが始まった2013年以来、マンション、株式、金、外貨などに分散投資をして、なるべく現金は持たないようにしてきた。今から5年前に、欲をかいて株式投資で失敗をしたことがある。そのことは以前ブログで書いた。
欲に目がくらむ - 南英世の 「くろねこ日記」 (goo.ne.jp)
あれ以来、株式投資は一切やっていない。しかし、それでもこの10年間に限ってみれば株式を含めすべてプラスで推移している。
新型コロナウィルスが世界をパニックにした2020年2月、株式が暴落した。この時よほど買おうかと迷ったが、世界恐慌になるのではないかと思い結局見送った。後から思えば絶好の仕込み時期であった。
考えてみれば、株式を大量に保有しているのは金持ちであり、その金持ちが政治家を操り政治を動かしている。だから、長期的に見れば株は下がるはずがない。単純な話である。日経新聞に出てくる細かな会社情報などクソに過ぎない。もっと大所高所から政治経済をにらむ必要がある。
次のグラフは戦後日本経済の成長率をグラフにしたものである。赤い線が実質経済成長率である。

こうやって見てくると、日本経済はほぼ10年を周期に大きな変動に見舞われている。
1965年 40年不況(東京オリンピック直後)
1974年 石油ショック直後
1986年 円高不況
1993年 バブル崩壊後
1997年 山一証券倒産
2008年 リーマンショック
2020年 コロナショック
リーマンショックから15年、コロナショックから3年がたった。たとえ世界恐慌並みのショックがあっても、金持ちは自分の資産を守るために必ず株式投資へのテコ入れを行う。このことを最近の15年の経験でようやく理解した。
さて、次の暴落はいつか? 株を所有している人には申し訳ないが、次の暴落を虎視眈々と待っている。4~5パーセントの配当を狙って獲物はすでに2~3社に絞り込んでいる。