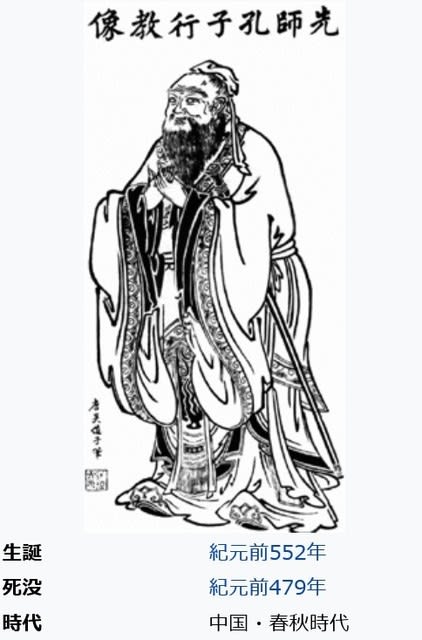今まで雑多に並んでいた本を分野ごとに並べ替えた。4日間かかった。これで仕事がしやすくなる。気分はすっかり新規の仕事モード。
今のところは何とか治まっているが、学校にある本を持ち帰ったらまた再整理する必要がある。ずいぶん捨てたはずなのに、まだ捨て足りないか。
ちなみに、この本棚は今から10年ほど前に自分で作ったものである。
https://blog.goo.ne.jp/minami-h_1951/e/c127ac9ecbe589f645568a22d3b05bf5
一方、家具職人に依頼して作ってもらったもう一つの書架は、最近買い始めたDVDで占領され始めている。

今のところは何とか治まっているが、学校にある本を持ち帰ったらまた再整理する必要がある。ずいぶん捨てたはずなのに、まだ捨て足りないか。
ちなみに、この本棚は今から10年ほど前に自分で作ったものである。
https://blog.goo.ne.jp/minami-h_1951/e/c127ac9ecbe589f645568a22d3b05bf5
一方、家具職人に依頼して作ってもらったもう一つの書架は、最近買い始めたDVDで占領され始めている。