今日は「京北の文化財を守る会」の総会に出席し、総会の後は、旧京北町元教育長の西山隆史さんの講演を聴きました。
この会は会員120人強で、名の通り地元に残る文化財を守る為の活動や会員の研修などの活動をされてます。私は2年程前から参加させて頂いていて、総会の後の講演などを楽しみにしています。
その活動のなかで面白いのは「ふるさと歴史漫歩」である。地元の人達に呼びかけ、地元の文化財を訪ね歩こうとい企画です。私は18年の弓削編、八幡宮社、その傍の弥生(縄文?)遺跡、中道寺を訪ねるのに参加したことがありますが、その時は日頃は見ることが出来ない寺社の文化財を見せて貰えます。この時は山村安郎さんの京北の地名についてのお話しを聞くことも出来ました。しかしその後は我が勤務の都合で参加できていないのが残念です。今年度は周山が当番年、果たしてどんな企画になるのか楽しみです。
総会は、何処も同じ、昨年度の事業報告、決算と監査報告、今年度の事業計画と予算案、会則の変更などが議題に上がり、粛々と議事が進行しました。最後に山村安郎さんが、何年も前に始められた「民族信仰建造物調査」がまだ完結していないことを指摘され、協議が行われたのには興味をもちました。身近に残る文化財を発掘しようという活動で、各地区ではそれぞれ調査が行われ記録に残されているそうですが、それがまとまった報告に出来上がっていない状態だそうです。これには、文化財をどの基準で採り上げるかや所有者の公開されることに対する態度や心配などの問題が横たわっている様です。また調査時から時間が経過していてその後変化が生じている事例もあるそうです。
地元の普門院には貴重な書き込みがあり、歴史を知る上で貴重な大般若経典が京都市歴史資料館に移されたことも知りました。保存状態による財の損傷や盗難の危険性という要素があるそうです。
なお、大般若経についてですが、お隣南丹市美山町では、同じ文化財を守る会で、美山に残る大般若経の基礎調査をされその発表をされました。こんどこのことは我が職場の友の会だよりに載せる予定です。大般若経はそこに残された書き込みなどは地元の歴史資料としても貴重です。
こういったことは全国共通の問題点であり、ここ京北に限ったことではないでしょう。ただ京北は京都市に合併し、京北独自の動きが出来にくくなったという問題もあります。私は京北の図書館の貧弱さや資料館がないというのは情けなさを日々感じています。
総会の後の講演は、旧京北町の元教育委員長、西山隆史さんの「京北ってこんなまち―歴史・文化・産業―」と題する2時間を越える講演を楽しく聴かせて貰いました。ご本人は、これは去る3月に開催された京都市の学校歴史博物館で話されたのと同内容のものです。京北を知らない人へ話した内容なので、いやだと断ったがどうしてもとのことだったので引き受けたが、京北を知っている京北の人を前に話をするのはやりにくいから皆さん寝てて下さいなどと冗談を言っておられました。
私としては、地元をどの様に紹介されるのかという観点からや、私の知らないことを聞くことを楽しませて頂きました。先生をされていたのでさすが勉強することが多く2時間という比較的長いお話しもお隣のIさんやH先生と時々ひそひそ話をしながらも楽しく聴かせて貰いましたし、勉強させて貰いました。
この会の会報誌は年一回の発行で地元の全戸に配布されます。この広報誌は昭和53年創刊で、当初は年2回、現在は年1回の発行になっていますが、私は幸いにも手元に全誌持っています。このファイルを覗いては先人の研究発表などを参考にしていまして、我が貴重な資料になっています。
これが再び年2回の発行出来る程の発表があれば良いなあと利用者視点から希望していますが、希望するだけでなく自分としてどう貢献できるかも考えないととも思っています。一つの視点として、近隣の同じ活動をされている団体との交流も活性化のアイディアの一つかもしれない。また歴史的な文化財にとどまらず民俗資料も保存すべきではという視点も持ち始めています。この両者の違いは何じゃいなと言われると難しいものですが、まあ広い視野を持とうということであります(^_・) 保存ばかりを叫ぶのではなく、そこに先人の気概を見いだすことはこれからを切り開くヒントが宿っているのではないかと思わないでもないからです。わがふるさとは明治維新前後には、これからは教育だ、というキーワードをきちんと察知したリーダーにより私塾が開かれ、全国でも引けを取らない位歴史ある小学校の歴史の礎を築かれています。
これに関して言えば、このComunication IT技術の進歩に伴う社会革命時代のインフラに関して京北は全くの後塵を拝している状況にいらいらしていますからでもあります。日本全体の大きな社会の大変革時に頑張られた指導者が今生きておられたら、今の様な故郷でないもっと先進的な故郷建設に邁進されていたのではとも思っています。
このブログをお読み頂いた、京北出身で今は都市部にお住まいの方々、故郷を思う気持ちをこの守る会の会員になって故郷を応援して下さいという我が希望お願いも書き添えておきたく思います。京北出身以外の方も大歓迎なのはいうまでもありませぬ(^_・)
もうひとつ付け足しですが、11日には地元の郷土史家、山村安郎さんに我が職場で、京北からの献上鮎の背景についてのお話しを聞きます。また地元ふるさと京北鉾杉塾で、献上鮎を再現しようという企画を準備しています。これも楽しみな企画です。
こんなことを考える半日でした。










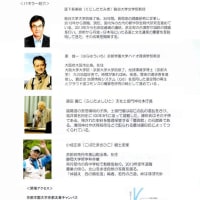
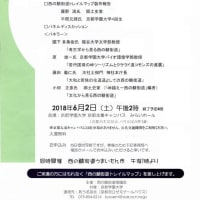
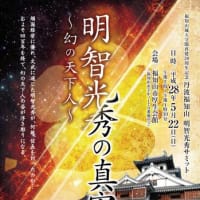


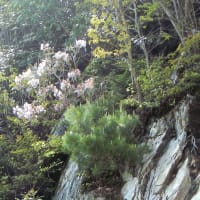


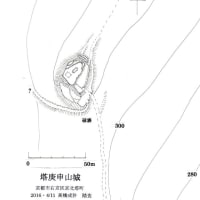


氏の父上は私達の頃の、確か職業の先生だったと思います。授業は受けておりませんが、朴訥なお人柄の人間味のある先生でした。その節に、杉鉾塾のK氏に始めてご面識を得た次第です。今回、その活動が京都市に認められたとの由。何よりと存じます。ビオトープも是非とも成功させてほしいものです。
京北の文化財は、誇るべき長い歴史を持ちながら、未だに体系的発掘・整備されていないのが、不思議な思いです。かつての私の狭い居住範囲の旧宇津村だけでも、掘り起こせば貴重な資料や遺跡などが眠っていることと思います。
振り返れば、当時は小中(高は存じませんが)を通じて、地元の歴史や文化に感心しました。向ける指導・教育は皆無でした。遅まきながら(?)とは申せ、そんな機運が高まりつつあることには快哉を叫びたくなります。
「ふるさと歴史漫歩」は面白そうですネ。私も、今後はこうした機会に可能な限り参加させて頂きたく思います。古里には本家の親族達も居住しておりますし、離れて暮らして居ても地元への関心度は薄れるものではありません。また、情報など宜しくお願い申し上げます。野次馬根性的では敬遠されるやも存じませんが、枯れ木も山の何とかと申しますし・・・。
それにしましても、mfujinoさんが指摘されています様に、地元に史料館が無いのは不思議としか言いようがありません。また、図書館の貧弱さと申しますか、その姿勢の熱意の欠如には驚くばかりです。以前、魚ケ渕の旧家のK氏宅の蔵書に対する対応で痛感しております。
これからは、mfujinoさん達意識の高い方々の熱意ある取り組みにより、古里の文化財の発掘と保存とその後の進展に、大きな動きのあることを願っております。離れて暮らす私達にも、出来る範囲での貢献に努力させて頂くのは吝かではありません。
小生はmfujino様のおかげで、京北・美山の歴史・地理、伝承の面白さを知ることが出来ました。どの集落にも、興味深い話が眠っているものだと改めて知ることが出来ました。一つ一つの峠にも色々な物語が伝わっていることを知ると、夏の暑いときでも峠を越える山行が、本当に楽しいものになりました。
様々な学問を糾合した「京北大全」、例えば全50巻とかができれば素晴らしいと思いますし、自分自身は微力でも、ゆくゆくは何かそのような会のお手伝いが出来ればうれしいと思っております。
文化財の盗難、近年は火の見櫓の半鐘にまで及んでいます。美山の大野でも確か被害があったのでは(スカタンを覚えているかも知れません[笑])、となると湖北地域で行われているように散らばる仏像を一箇所に集めて…ということもやむを得ないのかも知れませんが、やはり、あるべきところにあらしめたいとも思います。だから後を継いでいく若い人が住めるようにしていかねばなりませんね。ただ、これは国全体の有り様にもかかわりますから、本当に難しいと思います。
ご苦労さまです。文化財には有形と無形の二種類があります。今般の東日本大災害で、被災された無形文化財が22件、無形文化財が1214件と多大な被害を出しています。午前中、文化庁OBの高橋さんと同伴して、役所に報告に行って参りました。具体的な資料で、私たちグループで仕上げたものです。恩師・本田安次の席がまだ空白であるために、この際役所で一汗かいてくれないかと言われてしまって、即答を避けながら、一つの仕事を果たして参りました。
今テレビの影響で、長浜にハイライトが当たっています。浅井家や、安土城や、長浜城などが脚光を浴びているのでしょうけれど、あの辺りから湖北に掛けては民俗行事の宝庫でして、十一面観音菩薩が何故ここに多く集まったか、「オコナイ」という由々しき行事もあるのですが、戦国の世より遥かに遠い記憶の中に、今も厳然と存在し続けています。
有形から推し量る無形の精神文化は、山国もまた宝庫のはずです。去年、山形に家族で行きました折、偶々寒河江の慈恩寺というお寺に伺った際、舞踏帖と言われる江戸時代中期まで書かれた日記がありましたので、早速お借りして参りまして、調査・研究の最中ですが、面白い
発見がいっぱいあります。この日記と言っても、祭事の際の献立表に過ぎないのですが、殆ど変わりなく献立が並んでいるのですけれど、時々変更されたりしています。その時、日照りや、冷害や、干ばつなどがあった様子がありありで、こうした有形の文化がその時人々はどう振舞ったかがはっきりと分かって参ります。
但しこうした事例から、民俗学は飽くまで現在の祭事として捉えなければなりません。幾ら鎌倉時代からの祭事だと言われても、私たちは現在のモノとしか判断致しません。但し過去の貴重な文化であるに違いなく、その時代考証の一つの手立てとなるのです。
愛宕神社山領としても京北はあったに違いありません。つまり神仏混交の歴史が色濃くあったはずです。春日社にしても、何故あるのか、だったら信仰の対象となる岩座(いわくら=ばんざ)が何処に当たるのか。八幡権現さまでしたら、愈々神仏混交ですから、誰がいつ勧進されたのか、興味は尽きません。
有形・無形に限らず、どれが歴史的価値を有する一級品であるか、どれが歴史的傍証がとれるものであるのか、整理整頓してみると、多大な発見があるでしょう。学問の初歩は先ず分類から始まります。藤野さまには、きっと多くの宿題があるはずです。郷土の先人・先哲を習って、是非最初からの見直しをされては如何でしょうか。長い文章で失礼しました。有難う御座いました!
22件は有形文化財です。
それと慈恩寺の舞踏帖は凡そ600年間、毎年書かれたものです。ですから祭事の詰まらない記録ではないかと思われるものが意外に一級品の資料になりえるのです。上記訂正です!済みません!
京北の文化財はそれなりに研究されていると思っています。合併を機に京都市の教育委員会も指定文化財を調査し直したりしていますし。ただそういった調査や研究の成果が地元の図書館などで網羅されていないというのが現状なのだと思います。それなりの図書館や資料館にいけば見ることは出来るのですが、身近でこういった資料が閲覧できるのとは大きな違いがあると思います。
また文化財を守る会の活動は以前から活発になされてきました。ただその広報という面で行き渡っていたかどうかという面はあると思いますが、私は大きな差はないと読んでいます。
私自身が地元の文化財や歴史の再発見に興味を持ちだしたら、我が人生はその方向に向いた動きになり、こういった会の会員にもなり、講演会も聞きに行くようになりました。それをここで書いたりしているのですが、これが地元の動きと解釈されますとちょっと違うかなと釘をさしたくなります。道草さまが我がブログを通じてこういった話に触れられる機会が以前より増えたからではないでしょうか?一度ふるさとのお知り合いを調査してみて下さい。あ、それと守る会の会員登録よろしくお願いします。花降るさと運動や、もっともっと、そうだ、ふるさと大使として活動していただけませんかしらなんていうと、乗りすぎじゃ~!と叱られますかね(^_・)
私めなどは知識にしても意識にしても熱心な先輩方のそれに比べれば赤子の様な段階です。ただ素人なりに先輩方から学ぶ態度は大切にして行きたいと思っています。ただ色々な先輩と知り合いになれ気軽に質問できる環境が膨らんできているのは楽しいことです。
また水口民次郎さんの「丹波山國隊史」ですが、この1,000ページを越える大作も、コツコツと資料を集め、断片的に書き上げられていたのを、仲村研さんという現役の先生がその整理のお手伝いをされて出版されたと聞いています。
我が同級生のお父さんは美山町誌の編纂に加わり、ご自身は美山仏教史という著作を残されていますが、彼女、書斎に籠もってその研究に没頭している時の父親が一番幸せだったのだろう言っていました。
こういった事は学者さまの世界では当たり前の事でしょうし特に取り立てて指摘することではないでしょう。でも地元のことを、足許のことを勉強された先人の労作が身近にあり、その雰囲気を感じ取れる様な環境があれば、それに触発される人間も増えるという善循環が起きやすいのではと考えるものとして、今の京北の図書館は何たることかと寂しい気持ちになってしまいます。
仰る様な企画には興味があります。ある友人は「京北学」という表現を使っていました。そういえば我が大阪時代に、入院中友人がくれた「大阪学」というのを思い出しました。京都大学の人文科学研究所の桑原先生たちの共同研究などにも頭が行っています。
今度美山へ行けば、石川さんの「知井村史」を買って徘徊堂さまにプレゼントしましょう。面白いですよ。
文化財の盗難のことを忘れていました。建仁寺の様なところでも盗難事件がありましたが、田舎では彼らにとっては漁り場かもしれませんね。以前名田庄で改築中の薬師堂を見せて頂きましたが、そこでも仏像の盗難にあったそうです。今回の会議でも、中途半端に情報を公開すると盗難の危険を感じられる所有者に対してどうするかという問題も指摘されていました。
今回の災害が東北の文化財にとっても大変な被害を及ぼして貴重な財産を失ったことでしょう。無形文化財においてもお祭りの開催が危ぶまれていることも報道されていますね。そして無形文化財がどう保存されているかということも関心ありますが、形は変わってもどう生きているかという観点も大切だということでしょうか。
私は今まで民俗学に心が言っていた訳ではなく、硯水亭さまから色々な事を教えて貰って最近になって興味が行き始めたという全くの門外漢です。ただ物事をどういった切り口から紐解くかという、仮説の建て方によっては素人にとっても、動機付けとしては非常に大切だとおもいますし、その検証過程でこそ基礎からの勉強にも励めるのではとも思います。
今は昔の街道を探してみたりする事も多くなりましたが、こういった事を楽しみながら、そこから派生することを調べたりして見たいなあという気持ちです。色々な視点のヒントをいただければ嬉しく思います。この歳になって位置から勉強を始めて、という気になりますが、かの伊能忠敬さんの様な例もありますし…。ちょっと真似事らしきことをしてみたい気もなくはないなんて