
今日仕事で「わち山野草の森」を訪れたとき、駐車場前でどんどの準備がされていました。キャンプファイヤーの時のように木を組んでその真ん中に立派な門松が堂々と立ててありました。どんどは竹でするもの、と思いこんでいた私には新鮮な風景でしたのでポケットに入れていたカメラに納めて帰りました。トップの写真です。
皆さんにとってはこの形は珍しいですか?それとも見慣れたものでしょうか?
私が小さい頃のどんどの思い出は、川原に竹を組み、の人が集まってしめ縄などの正月の飾りなどを燃やします。その時書き初めの紙が炎と共に高く舞い上がれば字が上手くなる、と言われて激しい煙にうまく乗って高く上がるように燃やしたり、竹の先を割ってそこに菱餅つけて残り火で焼いたこと、この日ばかりはそう何回も食べれないぜんざいが食べられるのが嬉しかったことなどを思い出します。炎の勢いが増すと青竹ポーンと大きい音を出して割れ、勢いある炎と煙がもうもうと高く上がっていた風景が脳裏に焼き付いています。
参考までに、「わち山野草の森」のホームページは、ここです。
皆さんにとってはこの形は珍しいですか?それとも見慣れたものでしょうか?
私が小さい頃のどんどの思い出は、川原に竹を組み、の人が集まってしめ縄などの正月の飾りなどを燃やします。その時書き初めの紙が炎と共に高く舞い上がれば字が上手くなる、と言われて激しい煙にうまく乗って高く上がるように燃やしたり、竹の先を割ってそこに菱餅つけて残り火で焼いたこと、この日ばかりはそう何回も食べれないぜんざいが食べられるのが嬉しかったことなどを思い出します。炎の勢いが増すと青竹ポーンと大きい音を出して割れ、勢いある炎と煙がもうもうと高く上がっていた風景が脳裏に焼き付いています。
参考までに、「わち山野草の森」のホームページは、ここです。










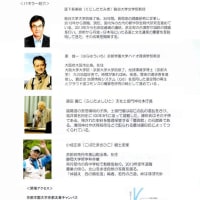
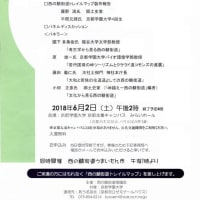
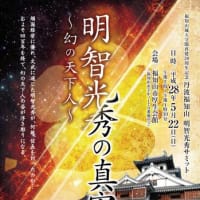


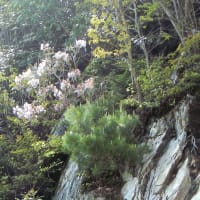


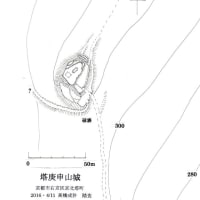


あの頃は、誰もが真面目に書き初めをしたのですねぇ。学校の書道の時間では、終わり頃になると飽きてきて墨で髭などを書き合い、先生に叱られたりしていました。
同級生に字の上手な女の子が居て、墨の摺り方からして丁寧で関心したものです。そう云えば、奈良の遠足で、お土産の代わりに書道の筆を買った女生徒も居ました。我々悪餓鬼は、元々勝負にならなかったのです。今は書道の授業があるのかどうか・・・。「どんど焼きどんどと雪の降りにけり」一茶。
この京北の正月行事体験ツアーに参加された皆さん12日の夜はゼミナールハウスで、何年ぶりかしら、などと言いながら半紙に筆を走らせておられました。また駒回しやお手玉を童心に帰って楽しんでおられる姿にはほのぼのとしたものがありました。