
これまた「京北の昔がたり」のはなしです.「丹波の赤海」という話が載せられていて、「八津良神社」の由来が描かれています.まずその中心部を引用しますと;
---------------------------------------------------------------------------------
(前略)
日本の国をつくられた神々の子孫のかたが、「日本の国はどんなに立派になっただろう」と思って、手わけして見てまわられることになりました.
丹波にこられた神様は、山へあがってごらんになって、「あっ」と驚かれました.昔から赤い波の国といわれた丹波は、今なお濁った水が見渡す限り続いています.
「これでは天下の大本である農業ができないし、人も沢山住めない.豊かな国にするにはまず水を流しだすことだ」
とお考えになり、保津峡を切り開き、亀山・園部の平野をお造りになりました.
久波田(桑田)の方面にも、水があふれて、赤い波が立っていましたので、あちこちの船つき場、八ヶ所(八津)をお回りになり、神々に、稲を作る土地ができるようご相談になりました.八津の神さまもよろこんでご協力を約束なさいました.
さっそく、若狭の国から人夫を集められ、山の尾を切りくずし、掘りさげて水を流しました.下流では、大洪水となって渦をまいて流れたので「有頭(うず)(宇津)」というようになり、水も次第にひいて、山国・弓削の方面も奥からだんだん土地ができてきました.
(後略)
---------------------------------------------------------------------------------
こうして長い歳月の後、田畑が出来、住民も増え、豊かな国となり、住民が縄野(周山)に祠を建て、大祖神の「伊邪那岐命」(イザナギノミコト)「伊邪那美命」(イザナミノミコト)を祭神として八ヶ所の神様をお祀りしたのが「八津良(ヤツラ)神社」だと言い伝えられているとのことです.
ここには地名についての素材を提供してくれています.京北の地名について調べてみたい気にさせてくれました.これについては項をあらためて書きます.
余談ですが、京北へ居を移して間もない秋、田貫のお祭りで御輿を担ぎその打ち上げの席で昔話をしていたら、幼い頃近所の遊び仲間だった公平ちゃんがこの八津良神社の神主をしているとの情報を得ました.え~、神主さん?彼の兄「清臣」ちゃんが山国神社の神主をしてられることからさもありなん、と納得.早速その翌日お祭りの準備をしている公平ちゃんに会いに行き、うん十年ぶりの再会を果せたことを思い出します.びっくりさせてやれと社務所で準備に忙しい彼の姿を見つけ、「だれか分かるか?」と声をかけると、一瞬?てな顔をした後、「お~、みっちゃんか!」と思い出してくれました.その後しばらくして区役所で再び彼とばったり遭った時、「あの後、俺(幼い頃の)夢を見たよ」と懐かしがってくれました.もういい中年のおっさんになってしまっていますが、その姿から浮かぶのは小学生時代の幼い「こんぺちゃん」のみであった.まあこんな回顧談を書くようでは僕も歳をとってしまったのでしょう.
あ、そうそう、八津良神社は<ここ>にあります.
写真は少し前、11月4日に撮影したものです.
---------------------------------------------------------------------------------
(前略)
日本の国をつくられた神々の子孫のかたが、「日本の国はどんなに立派になっただろう」と思って、手わけして見てまわられることになりました.
丹波にこられた神様は、山へあがってごらんになって、「あっ」と驚かれました.昔から赤い波の国といわれた丹波は、今なお濁った水が見渡す限り続いています.
「これでは天下の大本である農業ができないし、人も沢山住めない.豊かな国にするにはまず水を流しだすことだ」
とお考えになり、保津峡を切り開き、亀山・園部の平野をお造りになりました.
久波田(桑田)の方面にも、水があふれて、赤い波が立っていましたので、あちこちの船つき場、八ヶ所(八津)をお回りになり、神々に、稲を作る土地ができるようご相談になりました.八津の神さまもよろこんでご協力を約束なさいました.
さっそく、若狭の国から人夫を集められ、山の尾を切りくずし、掘りさげて水を流しました.下流では、大洪水となって渦をまいて流れたので「有頭(うず)(宇津)」というようになり、水も次第にひいて、山国・弓削の方面も奥からだんだん土地ができてきました.
(後略)
---------------------------------------------------------------------------------
こうして長い歳月の後、田畑が出来、住民も増え、豊かな国となり、住民が縄野(周山)に祠を建て、大祖神の「伊邪那岐命」(イザナギノミコト)「伊邪那美命」(イザナミノミコト)を祭神として八ヶ所の神様をお祀りしたのが「八津良(ヤツラ)神社」だと言い伝えられているとのことです.
ここには地名についての素材を提供してくれています.京北の地名について調べてみたい気にさせてくれました.これについては項をあらためて書きます.
余談ですが、京北へ居を移して間もない秋、田貫のお祭りで御輿を担ぎその打ち上げの席で昔話をしていたら、幼い頃近所の遊び仲間だった公平ちゃんがこの八津良神社の神主をしているとの情報を得ました.え~、神主さん?彼の兄「清臣」ちゃんが山国神社の神主をしてられることからさもありなん、と納得.早速その翌日お祭りの準備をしている公平ちゃんに会いに行き、うん十年ぶりの再会を果せたことを思い出します.びっくりさせてやれと社務所で準備に忙しい彼の姿を見つけ、「だれか分かるか?」と声をかけると、一瞬?てな顔をした後、「お~、みっちゃんか!」と思い出してくれました.その後しばらくして区役所で再び彼とばったり遭った時、「あの後、俺(幼い頃の)夢を見たよ」と懐かしがってくれました.もういい中年のおっさんになってしまっていますが、その姿から浮かぶのは小学生時代の幼い「こんぺちゃん」のみであった.まあこんな回顧談を書くようでは僕も歳をとってしまったのでしょう.
あ、そうそう、八津良神社は<ここ>にあります.
写真は少し前、11月4日に撮影したものです.










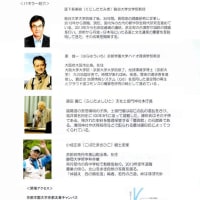
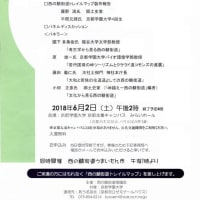
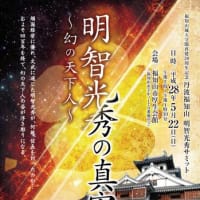


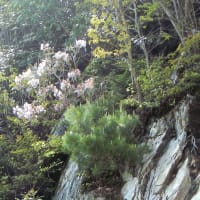


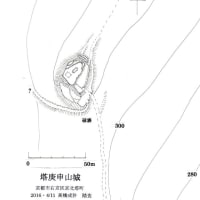


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます