どもども。
今回は今年の京大入試理系数学の第6問をやります
問題はこちら
http://www.yozemi.ac.jp/nyushi/sokuho/recent/kyoto/zenki/sugaku_ri/mon6.html
いよいよ京大の問題もこれでラストです
しかしながら,最後に立ち塞がるのはなかなかの強敵です。
確率と連分数をコラボさせるという,凄まじいことをやってくれてます
難易度は高いので,解けなくてもまぁ仕方ないかなって感じの問題です
誘導もないので,どのようなアプローチで攻略しようか悩みますね。
問題文で与えられている確率p_kの他にもう1個か2個別の確率を定義して
漸化式を立てれば良いのですが,果たしてそのような発想に辿り着けたかどうか…そこが勝負の分かれ目です
さて,上で連分数なんていう単語がちょこっと顔を出しましたが,
このY_nって一体何なんでしょう。ちょっと式変形してみます。

何やら凄いのが出てきましたね。幾重にも重なる分数の階層
こういうのを連分数といいますです
特に各階層の分数の分子が全て1であるものを正則連分数なんていいます。
今回の問題は,サイコロを振ってX_nを順次定めていく時に,
この連分数が (1+√3)/2 以上 (1+√3) 以下になる確率を求めよ
という厄介極まりない問題なわけですね~
とりあえずY_nは有理数なんで (1+√3)/2≦Y_n≦(1+√3) の不等号はイコール抜きで考えても差し支えは無いです。
あとY_n>X_n≧1 より Y_n>1です。起こり得る状況は
(1+√3)/2≦Y_n≦(1+√3),1<Y_n<(1+√3)/2,(1+√3)<Y_n
の3つなので, 1<Y_n<(1+√3)/2 となる確率も定義しておきましょう

(1+√3)<Y_k となる確率は1-p_k-q_kで与えられます。
(1+√3)/2≦Y_k≦(1+√3) すなわち (1+√3)/2≦X_k+(1/Y_{k-1})≦(1+√3) となる確率を
求めたいのですが,この条件を満たすのは X_k=1,2 の場合に限られます

X_k=1,2 のそれぞれの場合について,Y_{k-1}が取っていい値の範囲を求めてみます。
まずはX_k=1のとき。すると,なんと都合の良いことに 1<Y_{k-1}≦(1+√3) が出てきます。
これは 1<Y_{k-1}<(1+√3)/2 と (1+√3)/2≦Y_{k-1}≦(1+√3) の合併になってます

X_k=2の場合も同様に考えます。

従って,(1+√3)/2≦Y_k≦(1+√3) となるのは,
X_k=1 かつ 1<Y_{k-1}≦(1+√3) の場合
X_k=2 かつ (1+√3)/2≦Y_{k-1} の場合
の2つのパターンに限られることが分かりました
これを元に,確率漸化式を立てて解きます。

またまた運の良いことに,漸化式を立てる際に,q_kの方が消えてくれました
これで漸化式を解くのも楽チンになりますよね♪
かくて,答えのp_nを求めることが出来た,ということでした
別解法を考えてみましょう。
p_k,q_kの定義をY_kではなく (1/Y_k) の不等式を用いて言い換えてみます。

今度は(1/Y_{k-1})がどのような値を取っているかによって場合分けしてみたいと思います
(1/Y_{k-1})=aのとき,条件を満たせるX_kはいくつあるかを考えます。

あとは漸化式を立てるだけであります~

ところで,この漸化式ではq_kが見事に消えちゃってくれますが,
このq_kはどんな確率になるんでしょう?
1-p_k-q_k=r_kとおいて,q_kとr_kを最初の解法と同様の手法で求めてみます~
余事象の確率が求まればp_kも求められますね


あとはこの連立漸化式を解くだけです




q_n,r_nの方はnの偶奇によって確率が変わってしまうんですね,面白いです
とはいっても,r_kだけの漸化式にしたときに出てきた式を偶奇で分けて
2項間漸化式とみなして解いたから違う値になっただけで,
3項間漸化式だと思って解けば偶奇によらない表現も得ることが出来ますよ
(ちなみに r_k=24/35+(1/10)(1/6)^k+(3/14)(-1/6)^k になりました )
)
次回もこの問題の別解について考えてみます
今回は今年の京大入試理系数学の第6問をやります

問題はこちら
http://www.yozemi.ac.jp/nyushi/sokuho/recent/kyoto/zenki/sugaku_ri/mon6.html
いよいよ京大の問題もこれでラストです

しかしながら,最後に立ち塞がるのはなかなかの強敵です。
確率と連分数をコラボさせるという,凄まじいことをやってくれてます

難易度は高いので,解けなくてもまぁ仕方ないかなって感じの問題です

誘導もないので,どのようなアプローチで攻略しようか悩みますね。
問題文で与えられている確率p_kの他にもう1個か2個別の確率を定義して
漸化式を立てれば良いのですが,果たしてそのような発想に辿り着けたかどうか…そこが勝負の分かれ目です

さて,上で連分数なんていう単語がちょこっと顔を出しましたが,
このY_nって一体何なんでしょう。ちょっと式変形してみます。

何やら凄いのが出てきましたね。幾重にも重なる分数の階層

こういうのを連分数といいますです

特に各階層の分数の分子が全て1であるものを正則連分数なんていいます。
今回の問題は,サイコロを振ってX_nを順次定めていく時に,
この連分数が (1+√3)/2 以上 (1+√3) 以下になる確率を求めよ

という厄介極まりない問題なわけですね~
とりあえずY_nは有理数なんで (1+√3)/2≦Y_n≦(1+√3) の不等号はイコール抜きで考えても差し支えは無いです。
あとY_n>X_n≧1 より Y_n>1です。起こり得る状況は
(1+√3)/2≦Y_n≦(1+√3),1<Y_n<(1+√3)/2,(1+√3)<Y_n
の3つなので, 1<Y_n<(1+√3)/2 となる確率も定義しておきましょう


(1+√3)<Y_k となる確率は1-p_k-q_kで与えられます。
(1+√3)/2≦Y_k≦(1+√3) すなわち (1+√3)/2≦X_k+(1/Y_{k-1})≦(1+√3) となる確率を
求めたいのですが,この条件を満たすのは X_k=1,2 の場合に限られます


X_k=1,2 のそれぞれの場合について,Y_{k-1}が取っていい値の範囲を求めてみます。
まずはX_k=1のとき。すると,なんと都合の良いことに 1<Y_{k-1}≦(1+√3) が出てきます。
これは 1<Y_{k-1}<(1+√3)/2 と (1+√3)/2≦Y_{k-1}≦(1+√3) の合併になってます


X_k=2の場合も同様に考えます。

従って,(1+√3)/2≦Y_k≦(1+√3) となるのは,
X_k=1 かつ 1<Y_{k-1}≦(1+√3) の場合
X_k=2 かつ (1+√3)/2≦Y_{k-1} の場合
の2つのパターンに限られることが分かりました

これを元に,確率漸化式を立てて解きます。

またまた運の良いことに,漸化式を立てる際に,q_kの方が消えてくれました

これで漸化式を解くのも楽チンになりますよね♪
かくて,答えのp_nを求めることが出来た,ということでした

別解法を考えてみましょう。
p_k,q_kの定義をY_kではなく (1/Y_k) の不等式を用いて言い換えてみます。

今度は(1/Y_{k-1})がどのような値を取っているかによって場合分けしてみたいと思います

(1/Y_{k-1})=aのとき,条件を満たせるX_kはいくつあるかを考えます。

あとは漸化式を立てるだけであります~


ところで,この漸化式ではq_kが見事に消えちゃってくれますが,
このq_kはどんな確率になるんでしょう?

1-p_k-q_k=r_kとおいて,q_kとr_kを最初の解法と同様の手法で求めてみます~
余事象の確率が求まればp_kも求められますね



あとはこの連立漸化式を解くだけです





q_n,r_nの方はnの偶奇によって確率が変わってしまうんですね,面白いです

とはいっても,r_kだけの漸化式にしたときに出てきた式を偶奇で分けて
2項間漸化式とみなして解いたから違う値になっただけで,
3項間漸化式だと思って解けば偶奇によらない表現も得ることが出来ますよ

(ちなみに r_k=24/35+(1/10)(1/6)^k+(3/14)(-1/6)^k になりました
 )
)次回もこの問題の別解について考えてみます














 (p)について
(p)について

 そこでその外接円を考えその中心をOとします。
そこでその外接円を考えその中心をOとします。


























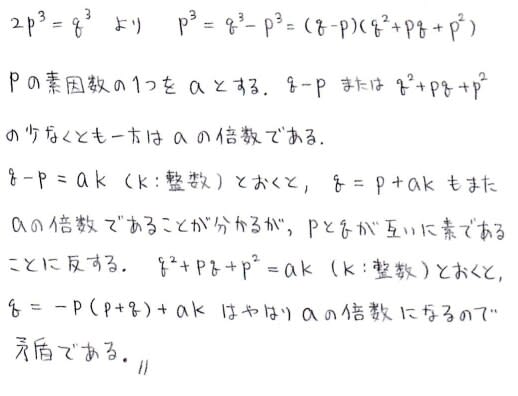






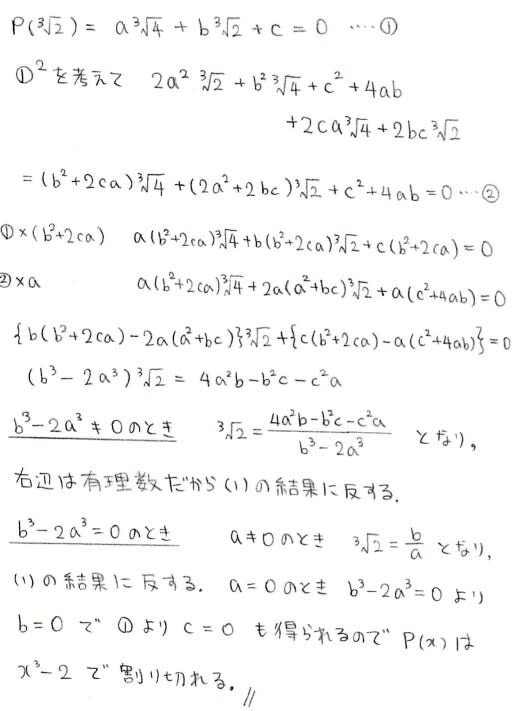




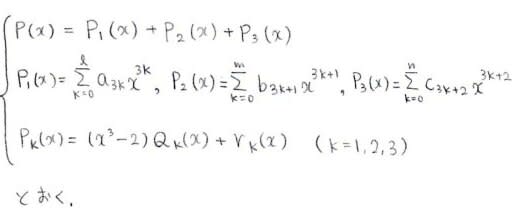






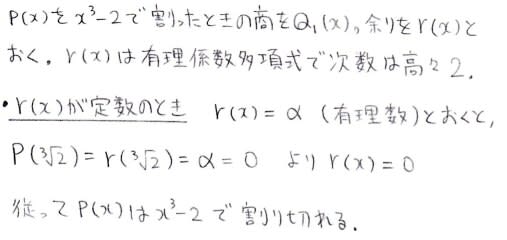
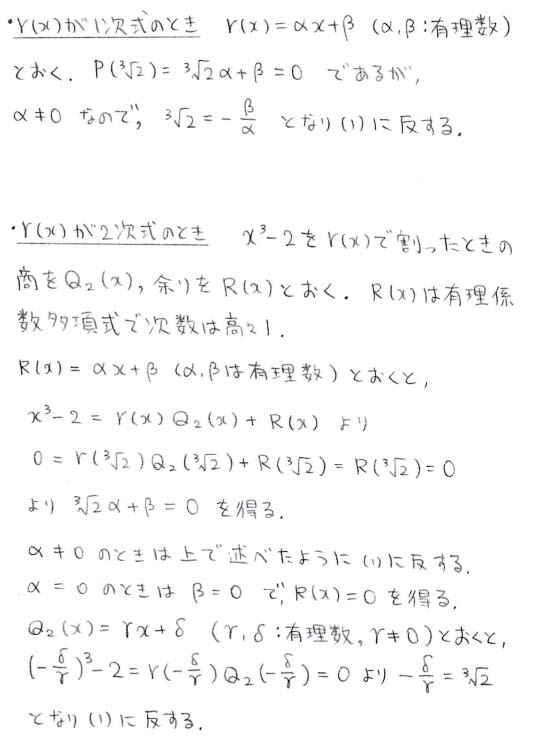





















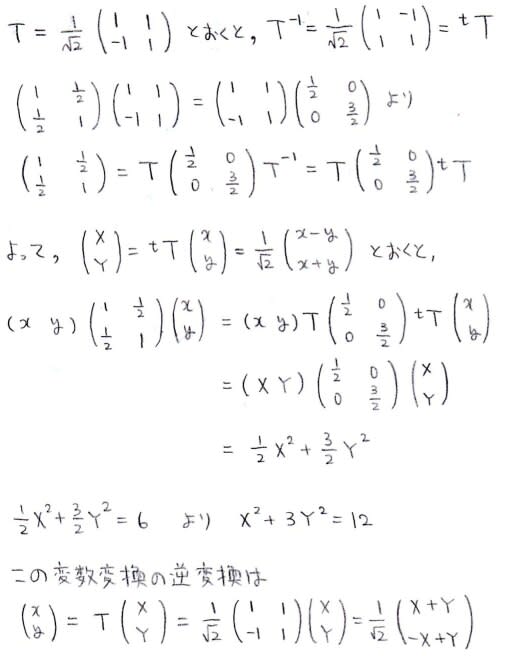

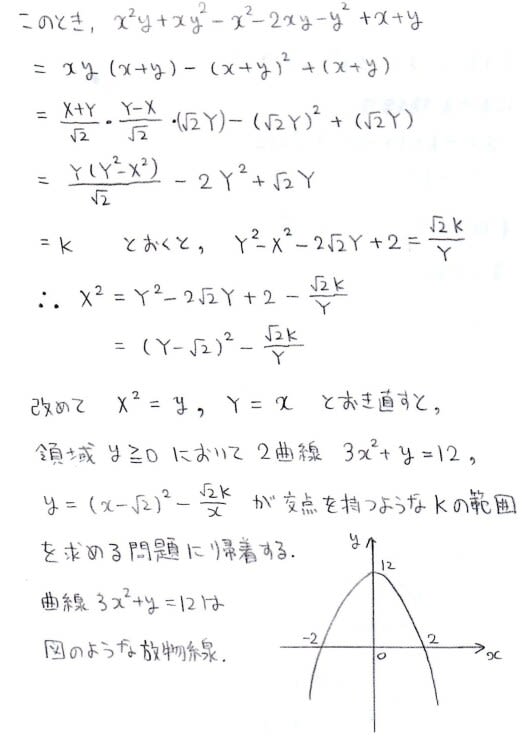



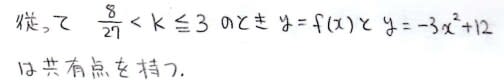



 )
)