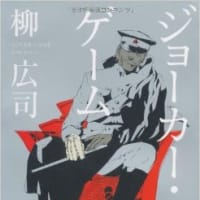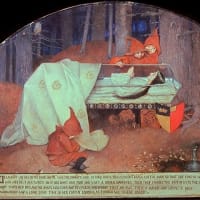経済学者にとって、ロビンソン・クルーソーは永遠のアイドルなのかもしれません。
経済学者にとって、ロビンソン・クルーソーは永遠のアイドルなのかもしれません。たとえば北海道大学経済学部のゼミをとっていたある女子大生は、「『ロビンソン漂流記』を大学に入り、経済学部の講義でたびたび耳にする機会があるとは思ってもみなかった」と、論文の冒頭で語っています。
 立命館大学産業社会学部の教授だった佐藤嘉一氏は、「社会科学における『ロビンソン・クルーソー問題』」という論文の中で、「ロビンソン・クルーソーが社会科学の中で、どのような視点でもってとらえられてきたか」を述べておられます。
立命館大学産業社会学部の教授だった佐藤嘉一氏は、「社会科学における『ロビンソン・クルーソー問題』」という論文の中で、「ロビンソン・クルーソーが社会科学の中で、どのような視点でもってとらえられてきたか」を述べておられます。佐藤氏によると「カール・マルクスは研究の関心をもっぱら『有用労働』にしぼり、『祈り』その他の生活人としてのクルーソーの関心については切り捨てている。
『孤島でのロビンソン・クルーソーの有用労働』にその関心を絞っていた」そうです。
 佐藤氏の論文からの引用。
佐藤氏の論文からの引用。「マルクスはロビンソンの孤島を『明るい島』とよぶ。…なぜロビンソン・クルーソーは『絶望の島』と呼ぶのに、マルクスは『明るい島』と呼ぶのだろうか。」
「ロビンソンの『有用労働』とは「『海に囲まれた孤島におけるたった1人の有用労働』である。たった1人の有用労働であることは『商品市場』の法廷から永遠に免責されることを意味する。
ロビンソンはもっぱら自分の<欲望>にしたがって異なる種類の有用労働に従事し、それを『労働時間の明細書』に自ら記帳し、自己管理し、自らの労働の全過程を自らのもとにおくことができる。
またその生産物も自由に処分できる。
『私の私による私ための有用労働』。
ロビンソンはまったくの『私人』である。
孤島での自らの有用労働とそれが作り出す富がすべて常に自分自身へと<戻ってくる>がゆえに、ロビンソンにとってこの島は『明るい』のである。」
 「ロビンソン・クルーソー」は少年時代からのマルクスの愛読書だったのだと、サラ☆は確信します。
「ロビンソン・クルーソー」は少年時代からのマルクスの愛読書だったのだと、サラ☆は確信します。そしてさらに、マルクスにつづくマックス・ヴェーバーもまた、ロビンソン・クルーソーをこよなく愛したのでしょう。
マルクスが「有用労働を行う人」としてロビンソンを自分の研究論文に登場させたのに対し、「同時に伝道もする孤立した経済人」として、経済学におけるあらたな「ロビンソン物語」を語りました。
ヴェーバーが注目したのは、「考えたり、工夫したり、意欲する」経済家のロビンソン・クルーソーであり、同時に「祈り、伝道もする」敬神家のロビンソン・クルーソーでもあるのです。
佐藤氏はこう続けます。
「おもうに、『社会関係』のネットワークが極端に切りつめられた孤島でのロビンソン・クルーソーの生活は、社会科学者が人間の『合理的行動』を査定する際に不可欠となる『その他の条件が等しければ』の条件設定(思考実験)──自然科学の『実験』にも等しい──のために格好の材料を提供したのである。しかし、ここに社会科学的『読解』の特質と限界がある、といわねばならない」
きっと、佐藤氏も子どもの頃、『ロビンソン漂流記』の熱烈な読者だったんでしょうね。
 さらに、ヴェーバーと同時期に活躍した、「自由貨幣の概念」を提唱した経済学者のシルビオ・ゲゼルという人も、(ミヒャエル・エンデはゲゼルの影響を受けて『モモ』を書いたのだそうです)「自由貨幣に基づく利子ならびに資本の理論」を解き明かすために、『この理論の試金石としてのロビンソン・クルーソー物語』という論文を書いています。
さらに、ヴェーバーと同時期に活躍した、「自由貨幣の概念」を提唱した経済学者のシルビオ・ゲゼルという人も、(ミヒャエル・エンデはゲゼルの影響を受けて『モモ』を書いたのだそうです)「自由貨幣に基づく利子ならびに資本の理論」を解き明かすために、『この理論の試金石としてのロビンソン・クルーソー物語』という論文を書いています。日本でも東大経済学部の教授だった大塚久雄氏が、「経済人ロビンソン・クルーソウ」というタイトルで、さまざまな著書で持論を展開しておられます。
 おお!! 要するに、みんなロビンソン・クルーソーの孤島での冒険が大好き。
おお!! 要するに、みんなロビンソン・クルーソーの孤島での冒険が大好き。そこにロマンを感じるから、「経済学と結びつけられる」糸口を見つけるや否や飛びついた。
そんな気がしてなりませんのですじゃ。