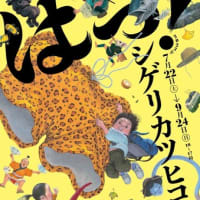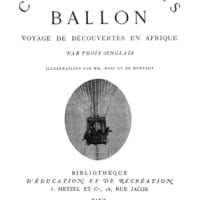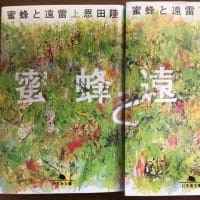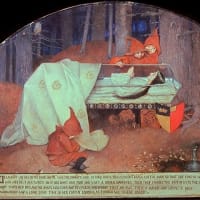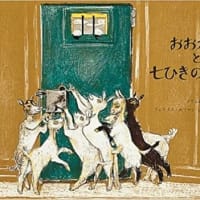朝日新聞連載の『七夜物語』は“次の夜”の章に入りました。
朝日新聞連載の『七夜物語』は“次の夜”の章に入りました。2人の子どもは、今度はどこかの館の中の応接間にいます。
2人はテーブルに突っ伏して寝ています。
館には、ほかに誰もいません。
 「だから、これから先の光景は、誰も見ることができなかった光景なのである」と作者は語りはじめます。
「だから、これから先の光景は、誰も見ることができなかった光景なのである」と作者は語りはじめます。「誰も見ることができなかった光景は、それを確かめる人がいないのだから、最初から存在しなかったものと同じなのである、というむきもあるだろう。
だからここはひとつ、この物語を読んでいるあなたに、証人になっていただきたいのだ。」
そして、応接間の花瓶にいけてある野バラが、数分の間に散り始め、枯れ、茎も霧散してしまう描写が展開します。
作者はこう続けます。
「あるはずのない光景である。
けれど、たしかにあなたは見たのである。
この物語を読むことによって。
見ていないのに。
あなたの目で見ることはできない、それは現象であるはずなのに。
けれど読むことによって、あなたは見てしまったのである。
現実に見るということによってよりも、よほどはっきりと。」
 面白い考え方をする人です。
面白い考え方をする人です。なるほど。
わかるにゃり。
目の前の現実と、イメージの中の現実。
さあ、その関係はいかに?
 作者の川上さんの論法が納得できるのなら、こういう話の展開もありかも?
作者の川上さんの論法が納得できるのなら、こういう話の展開もありかも?たとえば、誰もいない部屋の中で、あなたは1人で眠りにつきました。
真夜中、あなたは眠りこけています。
そこに、ティンカーベルのような姿の妖精がポッと出現しました。
そして、あなたの顔の斜め上の空中から、あなたの顔を覗き込みます。
妖精はふっと奇妙な笑いを浮かべると、「あなたが良い夢をみるように」と手をさっと振って、キラキラ光る粉をあなたに振りかけました。
そして、消えてしまった。
なんてことが昨夜起こったのかも知れませんね。
あなたはそのおかげで、とても幸せな夢を見たのだけど、二回目くらいのレム睡眠でその夢を見たもので、次に何回かつづいたノンレム睡眠の後では、ちっとも覚えていない。
だから、いまのあなたは、「こんなことがあったのよ」といわれても、まったく否定する。
 でも、いま話したことは、すでにイメージの中では現実になっていませんか?
でも、いま話したことは、すでにイメージの中では現実になっていませんか?あなたははっきり、ティンカーベルのような妖精が、眠っている自分の斜め上にいるのを見たのではないですか?
だから、この場合完全否定するのではなく、「へー、そうかもな」くらいの曖昧さを残しておくと、生きることが楽しくなるのではと思います。
 物語というのは、そういう作用があるのだと、作者が言っているのか、はたまたサラ☆が曲解しているのか、どちらだと思いますか?
物語というのは、そういう作用があるのだと、作者が言っているのか、はたまたサラ☆が曲解しているのか、どちらだと思いますか?