
マイミクの山が一番さんが群馬の県境の山、完登を記念して本を出版された
メールを戴いたのでさっそく購読



県境を歩くと言う事は殆どが人跡未踏でおのずとして藪漕ぎの場面が多くなる
頼みの綱はコンパスと勘
風の吹きすさぶ月明かりも無い真っ暗な中での野営
出くわしたくない熊との遭遇
「自然はいいわね」なんて戯言を言っている私には、とてもとても やりとげられない云わば戦いの日々で有った事でしょう

夢中で読み進めていく内、巻機山の項に入った時、なんとなんと私が登場
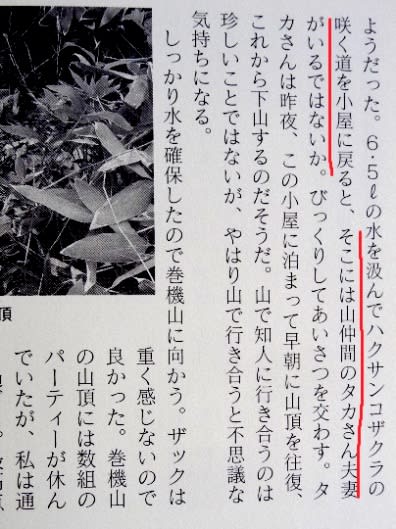
山が一番さんも文中に記しているが、山での出会いの不思議さ
確かこの稜線を制覇すれば夢の達成の日だった気がする
あの日 5分 どちらかが時間をずらしていたら・・・
本当にこういう事も有るんですね
山が一番さん、既に次の目標に向かって突き進んでいらっしゃるでしょうが先ずはお疲れ様でした
そしておめでとうございます

 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ




















偶然に出会す‥‥‥
本当に縁を感じます。
夫との出会いもそうでした。
一度会って、二度目は合うつもりもなかったのに偶然でした。
こうして、たかさんと日々コメントのやりとりをしていただいているのも何かの縁ですね。
もちろん、旅人さんとも‥‥。
ありがとうございます。
おふたりから、学ばせていただく事がいっぱいあります。
パソコンガ無かったら、ヨーロッパ旅行をしていなかったら
こうしてsisiさんとお話しする事もなかったわけですものね。
そうして、もっと不思議なのが一度もお会いした事がないのに
まるで旧知の仲の様な親しみが感じられる事・・・でしょうか。
縁は大切にしたいと、つくづく思います。
本の中にたかさん御夫婦の記事がある。
本を出版された椛澤(もみじさわ)さんも
たかさん御夫婦と相通じる心をお持ちの様子が伝わってきます。。
たかさん御夫婦は山の愛好家を通り越して、私には
山を知り尽くした山の民に思えてきます。
(私は歴史を遡り山の民に対する思い入れがあります)
私も興味をそそられ本を読み漁った時期が有りました。
定住せず山から山を移動しながら生活する民で
(一般人との接点が無かった訳では無く生活の為に蓑や笊などを売りに山を下りる事も有ったらしい)
この辺りでは秩父の山間部でも見かけた様です。
昭和に入ってからは一般人に吸収され今となっては人間界の七不思議的な存在になってしまいましたが
戸籍も持たず縄文人の様な生活をしていた人達が昭和初期まで存在していたという事に
何故かロマンを感じずにはいられません。
(私は単なる山愛好家に過ぎませんよ)
私が思い入れした山の民は、南北朝時代に、楠正成の為に河内、南紀・熊野で南朝の為に働いた山の民、おそらく
大塔の宮の為に随行して東北へ駆け抜けた山の民もあったかと思います。
武王の子が、破軍の星を見つめ、悪党の末裔たちを率いて日本の各地で40年間戦い抜いた時代を懐かしんでいます。小学生の頃は良く破軍台の丘に登りました。
眼下には、御所跡が見え、市内も一望出来ました。
室町時代初期
何時の世もそうですが特にこの頃は勢力争いで荒れた時代ですよね。
興味を持って歴史の紐を解いてみたら面白いのでしょうけど。
そして??私が知る山の民(さんか)はその末裔になるのでしょうか?
謎の「さんか」なのでルーツがわかりません。