全固体電池を搭載した電気自動車(EV)の開発が熱を帯びてきた。日産自動車は日経クロステック/日経Automotiveの取材で、2020年代後半に実用化する意向を明かした。独フォルクスワーゲン(VW)も、21年3月15日に開いた会見で「全固体電池EV」を市場投入する方針を示した。
トヨタを猛追
自動車メーカーで先行しているとされるのはトヨタ自動車。20年代前半に発売する車両に全固体電池を搭載すると発表している。トヨタよりも先の実用化を狙うのが中国のEVメーカー上海蔚来汽車(NIO)で、22年の量産を目指す。トヨタやNIOの背中を追って、日産とVWが開発のアクセルを踏む。
「27~28年には(全固体電池を搭載したEVを)世に出せるように、社内で技術ロードマップを作っている」。こう語るのは、日産でパワートレーン開発を主導する平井俊弘氏(専務執行役員)である。カーボンニュートラル(温暖化ガス排出量実質ゼロ)実現の主軸となるEVを普及させる上で、「全固体電池をいかに早く実用化し、EVがカバーできるクルマの領域を広げていくことが重要」(同氏)と説く。
日産は当面、EVと独自のシリーズハイブリッド技術「e-POWER」の2本柱で電動化を推進する。同社が「究極」と位置付けるEV一本に絞れないのは、「電池の課題を克服しなければならない」(同氏)からだ。
現行の液系リチウムイオン電池はエネルギー密度向上に限界が見え始め、電池価格はEV普及の目安とされる1キロワット時当たり100ドルから「大きくかけ離れている」(同氏)。高価な電池を大量に使えない状況では、小容量の電池で済むe-POWERを普及価格帯の車両に設定することが二酸化炭素(CO2)排出量の削減でも効果を出しやすい。
現在のリチウムイオン電池のエネルギー密度では、大型EVの航続距離を十分に確保するのが難しいという側面もある。電池を大量に積めば航続距離は長くできるが、車両価格に跳ね返ってしまう。
全固体電池で高いエネルギー密度
こうした課題を解決できる可能性を秘めるのが全固体電池という。平井氏は「全固体電池であれば(質量エネルギー密度が)1キログラム当たり500ワット時の達成が可能だ」と読む。
液系リチウムイオン電池のセルでは、質量エネルギー密度で1キログラム当たり300ワット時を超えるのは至難の業である。ニッケル(Ni)の比率を高めた「ハイNi正極」や理論容量密度が高いシリコン(Si)を使う「Si負極」などの技術を組み合わせれば可能だが、安全性や耐久性を確保するための対策が多く必要になる。
全固体電池は、液漏れや揮発など発火の原因となる電解液を固体にするため、安全性を高めやすい。その分、冷却機構などの周辺部品を簡素化しやすく、電池パックとしての低コスト化や搭載スペースの増加による電池の積み増しが可能になる。
全固体電池の実用化に向けて日産は、「材料技術だけでなく製造技術を含めて積極的に開発を進めていく」(平井氏)方針だ。詳細は明かさないが、「パートナーと共に取り組んでいく」(同氏)という。コスト目標は電池セルとして1キロワット時当たり100ドル以下を設定した。
EVシフトを鮮明にするVWも全固体電池に大きな期待を寄せる1社だ。VWグループで電池開発を主導するフランク・ブルーム氏は、「全固体電池はリチウムイオン電池の最終形態」と位置付ける。全固体電池にすることで、現行の液系電池を搭載するEVに比べて「航続距離を30%長くできる」(同氏)とする。
航続距離以上に、VWが全固体電池の特性として期待を寄せているのが急速充電との相性の良さだ。ブルーム氏は「現行のEVでは充電に25分ほどの時間が必要だが、全固体電池を搭載するEVなら半分の12分で済む」と説明する。
VWが全固体電池EVの投入時期として設定しているのは「25年以降」(同氏)で日産とほぼ同じ。実用化に向けて、米国の全固体電池開発メーカーのクアンタムスケープと共同戦線を張る。
VWはクアンタムスケープと12年から協力しており、計3億ドル以上を出資して最大の株主になっている。クアンタムスケープが開発した全固体電池として、室温での質量エネルギー密度は1キログラム当たり300超~400超ワット時、体積エネルギー密度は1リットル当たり1000ワット時前後を実現しているようだ。
VWは全固体電池の実用化と並行して、液系リチウムイオン電池の低コスト化も進める。30年までに現行比で50%のコスト低減を目標に据えた。全固体電池が量産EVに広く使われるには、圧倒的なエネルギー密度かシステムとしてのコスト優位性を誇示する必要がありそうだ。
(日経クロステック/日経Automotive 久米秀尚、日経クロステック 清水直茂)
[日経クロステック2021年3月18日付の記事を再構成]
トヨタを猛追
自動車メーカーで先行しているとされるのはトヨタ自動車。20年代前半に発売する車両に全固体電池を搭載すると発表している。トヨタよりも先の実用化を狙うのが中国のEVメーカー上海蔚来汽車(NIO)で、22年の量産を目指す。トヨタやNIOの背中を追って、日産とVWが開発のアクセルを踏む。
「27~28年には(全固体電池を搭載したEVを)世に出せるように、社内で技術ロードマップを作っている」。こう語るのは、日産でパワートレーン開発を主導する平井俊弘氏(専務執行役員)である。カーボンニュートラル(温暖化ガス排出量実質ゼロ)実現の主軸となるEVを普及させる上で、「全固体電池をいかに早く実用化し、EVがカバーできるクルマの領域を広げていくことが重要」(同氏)と説く。
日産は当面、EVと独自のシリーズハイブリッド技術「e-POWER」の2本柱で電動化を推進する。同社が「究極」と位置付けるEV一本に絞れないのは、「電池の課題を克服しなければならない」(同氏)からだ。
現行の液系リチウムイオン電池はエネルギー密度向上に限界が見え始め、電池価格はEV普及の目安とされる1キロワット時当たり100ドルから「大きくかけ離れている」(同氏)。高価な電池を大量に使えない状況では、小容量の電池で済むe-POWERを普及価格帯の車両に設定することが二酸化炭素(CO2)排出量の削減でも効果を出しやすい。
現在のリチウムイオン電池のエネルギー密度では、大型EVの航続距離を十分に確保するのが難しいという側面もある。電池を大量に積めば航続距離は長くできるが、車両価格に跳ね返ってしまう。
全固体電池で高いエネルギー密度
こうした課題を解決できる可能性を秘めるのが全固体電池という。平井氏は「全固体電池であれば(質量エネルギー密度が)1キログラム当たり500ワット時の達成が可能だ」と読む。
液系リチウムイオン電池のセルでは、質量エネルギー密度で1キログラム当たり300ワット時を超えるのは至難の業である。ニッケル(Ni)の比率を高めた「ハイNi正極」や理論容量密度が高いシリコン(Si)を使う「Si負極」などの技術を組み合わせれば可能だが、安全性や耐久性を確保するための対策が多く必要になる。
全固体電池は、液漏れや揮発など発火の原因となる電解液を固体にするため、安全性を高めやすい。その分、冷却機構などの周辺部品を簡素化しやすく、電池パックとしての低コスト化や搭載スペースの増加による電池の積み増しが可能になる。
全固体電池の実用化に向けて日産は、「材料技術だけでなく製造技術を含めて積極的に開発を進めていく」(平井氏)方針だ。詳細は明かさないが、「パートナーと共に取り組んでいく」(同氏)という。コスト目標は電池セルとして1キロワット時当たり100ドル以下を設定した。
EVシフトを鮮明にするVWも全固体電池に大きな期待を寄せる1社だ。VWグループで電池開発を主導するフランク・ブルーム氏は、「全固体電池はリチウムイオン電池の最終形態」と位置付ける。全固体電池にすることで、現行の液系電池を搭載するEVに比べて「航続距離を30%長くできる」(同氏)とする。
航続距離以上に、VWが全固体電池の特性として期待を寄せているのが急速充電との相性の良さだ。ブルーム氏は「現行のEVでは充電に25分ほどの時間が必要だが、全固体電池を搭載するEVなら半分の12分で済む」と説明する。
VWが全固体電池EVの投入時期として設定しているのは「25年以降」(同氏)で日産とほぼ同じ。実用化に向けて、米国の全固体電池開発メーカーのクアンタムスケープと共同戦線を張る。
VWはクアンタムスケープと12年から協力しており、計3億ドル以上を出資して最大の株主になっている。クアンタムスケープが開発した全固体電池として、室温での質量エネルギー密度は1キログラム当たり300超~400超ワット時、体積エネルギー密度は1リットル当たり1000ワット時前後を実現しているようだ。
VWは全固体電池の実用化と並行して、液系リチウムイオン電池の低コスト化も進める。30年までに現行比で50%のコスト低減を目標に据えた。全固体電池が量産EVに広く使われるには、圧倒的なエネルギー密度かシステムとしてのコスト優位性を誇示する必要がありそうだ。
(日経クロステック/日経Automotive 久米秀尚、日経クロステック 清水直茂)
[日経クロステック2021年3月18日付の記事を再構成]















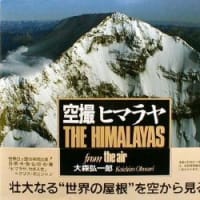




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます