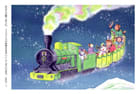エレミヤ31:16 「あなたの泣く声をとどめ、目の涙をとどめよ。あなたの労苦にはむくいがあるからだ。」
エレミヤ31:16 「あなたの泣く声をとどめ、目の涙をとどめよ。あなたの労苦にはむくいがあるからだ。」
この「報い」と言う言葉が好きです。
私たちは、蒔いた種の実を刈り取るとともに、自分では蒔かなかった昔の方々が蒔いた種の実も刈り取る時代に入りました。
いよいよ、待ちに待った、収穫の時が来たのです。




 ジョージ・ミュラーのまんがの中に、モー背の燃え尽きない芝の個所を描かなければなりません。
ジョージ・ミュラーのまんがの中に、モー背の燃え尽きない芝の個所を描かなければなりません。
今までも何回かイラストで描いたことがありますが、はたと考えました。
この芝は、どんな木なのかと言うことです。
芝と検索すると、芝生の芝しか出てきません。
芝の木があるのかと思いましたが、見つかりません。
芝生から火が出ていたのだろうかとも思いましたが、砂漠の真ん中に芝生が生えているわけがありません。
まして、岩だらけのシナイ山の近くなので、それ考えられません。 真っ赤な野苺の実に太陽が当たって燃えているように見えたと解釈される方もいるそうですが、そんなことは聖書に書いてありません。
真っ赤な野苺の実に太陽が当たって燃えているように見えたと解釈される方もいるそうですが、そんなことは聖書に書いてありません。
とげのついた木に赤い実がなるものもあるそうですが、聖書では、「燃えているように見えた。」と書いてはいません。
「火で燃えていたのに、芝は燃え尽きなかった。」とあるのです。
文語体を見ると棘と言う漢字を使って「しば」というルビがうってありました。
これは、「いばら」のことで、「とげ」とも読みます。
イエス様がかぶらされたのも、棘(いばら)の冠でした。
砂漠の写真を見ていると、枯れたような枝だけの低い木が所々生えています。
たぶんこれではないかと思いつつ、描くことにしました。








 キリスト教のラジオを聞いていたら、聖書朗読で昨日は黙示録の21~22章でした。
キリスト教のラジオを聞いていたら、聖書朗読で昨日は黙示録の21~22章でした。
この番組では、1年で聖書を通読できるようになっています。
耳で聞きながら、何度も語りかけを受けたことがあります。
自分でも毎日読んでいますが、耳で聞くのも素晴らしいです。
ところで、前に高橋是清が、宣教師フルベッキの家を出る時、聖書をもらい毎日1回読むようにと言われことを書きましたね。
晩年に書かれた高橋是清の自伝の中で、お金がないので本を売った時も、聖書だけは売らなかったと書いています。
そして、フルベッキに言われたように、毎日1回聖書を読んでいるとも書いてありました。
2・26事件で暗殺された時も、寝室の机の上にその聖書があったそうです。
聖書は、生きた神様の言葉です。






 幕末時代、日本に来た宣教師の多くは、ギュツラフ訳の聖書を読んできました。
幕末時代、日本に来た宣教師の多くは、ギュツラフ訳の聖書を読んできました。
これは、漂流した、漁師たちの助けによって翻訳されたものですが、本当に不完全な訳です。 ヨアンネスノ タヨリ ヨロコビ
ヨアンネスノ タヨリ ヨロコビ
ハジマリニ カシコイモノゴザル、コノカシコイモノ ゴクラクトモニゴザル。コノカシコイモノワゴクラク。
分かりますか? ヨハネの福音書
ヨハネの福音書
初めに、ことばがあった。 ことばは神とともにあった。 ことばは神であった。
まず、日本に真の唯一の神という概念がありませんでした。
仏教の天国は、極楽という言いかたをしますが、真の神様がおられるところなので、真の神様のことを極楽と訳しています。
それから、ヨハネはイエス・キリストのことを「ことば」と言っていますが、この地上のすべてが、神のことばによってできたので、このように表現しました。
そこで、ギュツラフは、ことばを賢いものと訳したのですが、ことばをイエス・キリストに置き換えるとこうなります。 ヨハネの良い知らせ
ヨハネの良い知らせ
初めにイエス・キリストはいた。 イエス・キリストは神とともにいた。 イエス・キリストは神であった。
ヨハネの福音書は、一番言葉の種類が少なく、日本人に理解されやすい書です。
ですから、ギュツラフは、このヨハネの福音書を翻訳したのです。
福音と言うのは、「良きおとずれ・良い知らせ・Good News」と言う意味です。
何が、「良い知らせ」かと言うと、真の神様のひとり子であるイエス・キリストが、私たちの罪の身代わりになって十字架にかかって死んでくださいました。
しかし、三日目に復活して、死を打ち破ってくださったのです。
だから、自分は罪人だと認め、その罪のために十字架にかかって死んでくださったと信じ、イエスを主(しゅ)だと告白するだけで、救われて、肉体は死んでも霊が天国に行くことができますよ。
と言うのが、良き知らせなのです。




 聖書の使徒の働きには、バルナバと言う人が出てきます。
聖書の使徒の働きには、バルナバと言う人が出てきます。
バルナバとは、「慰めの子」と言う意味です。
このバルナバは、迫害者であったパウロがイエス様に出会い、悔い改めた後に手を差し伸べた人でした。
他の人は、恐れて逃げてしまったのです。
しかし、バルナバは、パウロを受け入れたのです。
また、バルナバが、アンテオケ教会に遣わされた時、働きが大きくなったので、パウロを探しに行きます。
そして、田舎に閉じこもっていたパウロを神の大きな働きにつかせるのです。
激しい性格のパウロと、慰めの子であるバルナバの両方がいなければ、アンテオケ教会の働きは進まなかったでしょう。
信仰の良い友を持つと言うことは、本当に重要なことですね。