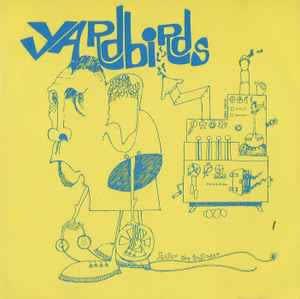2022年11月30日(水)

#381 B. B. KING「BLUES SUMMIT」(MCA MCAD-10710)
B・B・キング、93年のアルバム。
B Bはシンガー/プレイヤーとしての活動に加えて、後半生はプロデューサー、オーガナイザー的な役割を自らに課して、後進のアーティストとの共演を増やしていく。
例えば、エリック・クラプトンとの共演盤「Riding With The King」がそうだ。
この一枚も、そんなセッション企画アルバムのひとつである。リリース当時、BBは67歳。
共演者には年下のみならず、8歳上のジョン・リー・フッカーも含まれており、最若手のロバート・クレイ(28歳下)に至るまで、男女問わずさまざまな世代ブルース・ピープルが集合、さながらブルース界の「頂上会議」の様相を呈している。
【個人的ベストファイブ・5位】
「Playin’ With My Friends」
シンガー/ギタリスト、ロバート・クレイとの共演。曲はクレイのオリジナル。
クレイは当時39歳。人気も出て来て、中堅シンガーへの仲間入りをした頃ではあるが、ブルースマンとしては、まだまだ若手、ひょっこ。
そんな彼をBBは我が子のように慈愛深くリードしている。ギターも率先して弾きまくり、それがいかにも気持ち良さげである。
ふたりのギターや歌のスタイルの違いがはっきり出ていて、面白い。
【個人的ベストファイブ・4位】
「Call It Stormy Monday」
テキサス・ブルースマン、アルバート・コリンズ(当時60歳)との共演。
曲はブルース・スタンダード中のスタンダード、T・ボーン・ウォーカーの作品。
ギターのプレイ・スタイルはまったく違うふたりであるが、掛け合いにより、見事な緊張感が生まれている。
リラックスした中にも、火花の散るような展開。
これぞベテラン同士の、ガチンコバトルの醍醐味だ。
【個人的ベストファイブ・3位】
「I Pity The Fool」
バディ・ガイとの共演(当時56歳)。曲は、ディアドリック・マローン(ドン・ロビー)作、ボビー・ブルー・ブランドでお馴染みのナンバーだ。
ほぼひとまわり下の後輩との共演は、迫力に満ちたシャウター・バトルになった。
ふたりのハイテンションな歌いぶりに太刀打ち出来る若いブルースマンは、多分いないだろうね(笑)。
【個人的ベストファイブ・2位】
「You Shook Me」
キング・オブ・ブギことジョン・リー・フッカー(当時75歳)との共演。
曲はウィリー・ディクスン作、マディ・ウォーターズの歌やツェッペリンのカバーで知られるナンバー。
当時のブルース界の最長老ジョン・リーとの「対決」は、実にスリリングで、妖しさ抜群である。
歌うというよりは、呪詛をつぶやくように、唸るスタイル。
B Bを挑発するように合いの手を入れる、ジョン・リーがカッコよすぎる。
【個人的ベストファイブ・1位】
「We’re Gonna Make It」
ニューオリンズ出身の女性シンガー、アーマ・トーマス(当時52歳)との共演。
曲はリトル・ミルトンのヒットで知られるソウル・ナンバー。
本アルバムではアーマ以外にもココ・テイラー、エッタ・ジェイムズ、ケイティ・ウェブスター、ルース・ブラウンといった綺羅星の如きベテラン・ディーバと共演しているが、その中では若いこともあってか、アーマの歌声が一番みずみずしい。
なんというか、聴いていて、とても前向きな気分になれる歌なんだな。明日に希望が持てるのだ。
B Bも、軽快なギター・ソロと歌で、アーマの快唱を盛り立てている。
他にもベテラン・ブルースマン、ローウェル・フルスンとの「Little By Little」、シンガー/ギタリスト、ジョー・ルイス・ウォーカーとの「Everybody’s Had The Blues」でのギター・バトルなど聴きどころは多い。
B Bの残した膨大な遺産のひとつ。今から聴いても、十分楽しめまっせ。
<独断評価>★★★★
B・B・キング、93年のアルバム。
B Bはシンガー/プレイヤーとしての活動に加えて、後半生はプロデューサー、オーガナイザー的な役割を自らに課して、後進のアーティストとの共演を増やしていく。
例えば、エリック・クラプトンとの共演盤「Riding With The King」がそうだ。
この一枚も、そんなセッション企画アルバムのひとつである。リリース当時、BBは67歳。
共演者には年下のみならず、8歳上のジョン・リー・フッカーも含まれており、最若手のロバート・クレイ(28歳下)に至るまで、男女問わずさまざまな世代ブルース・ピープルが集合、さながらブルース界の「頂上会議」の様相を呈している。
【個人的ベストファイブ・5位】
「Playin’ With My Friends」
シンガー/ギタリスト、ロバート・クレイとの共演。曲はクレイのオリジナル。
クレイは当時39歳。人気も出て来て、中堅シンガーへの仲間入りをした頃ではあるが、ブルースマンとしては、まだまだ若手、ひょっこ。
そんな彼をBBは我が子のように慈愛深くリードしている。ギターも率先して弾きまくり、それがいかにも気持ち良さげである。
ふたりのギターや歌のスタイルの違いがはっきり出ていて、面白い。
【個人的ベストファイブ・4位】
「Call It Stormy Monday」
テキサス・ブルースマン、アルバート・コリンズ(当時60歳)との共演。
曲はブルース・スタンダード中のスタンダード、T・ボーン・ウォーカーの作品。
ギターのプレイ・スタイルはまったく違うふたりであるが、掛け合いにより、見事な緊張感が生まれている。
リラックスした中にも、火花の散るような展開。
これぞベテラン同士の、ガチンコバトルの醍醐味だ。
【個人的ベストファイブ・3位】
「I Pity The Fool」
バディ・ガイとの共演(当時56歳)。曲は、ディアドリック・マローン(ドン・ロビー)作、ボビー・ブルー・ブランドでお馴染みのナンバーだ。
ほぼひとまわり下の後輩との共演は、迫力に満ちたシャウター・バトルになった。
ふたりのハイテンションな歌いぶりに太刀打ち出来る若いブルースマンは、多分いないだろうね(笑)。
【個人的ベストファイブ・2位】
「You Shook Me」
キング・オブ・ブギことジョン・リー・フッカー(当時75歳)との共演。
曲はウィリー・ディクスン作、マディ・ウォーターズの歌やツェッペリンのカバーで知られるナンバー。
当時のブルース界の最長老ジョン・リーとの「対決」は、実にスリリングで、妖しさ抜群である。
歌うというよりは、呪詛をつぶやくように、唸るスタイル。
B Bを挑発するように合いの手を入れる、ジョン・リーがカッコよすぎる。
【個人的ベストファイブ・1位】
「We’re Gonna Make It」
ニューオリンズ出身の女性シンガー、アーマ・トーマス(当時52歳)との共演。
曲はリトル・ミルトンのヒットで知られるソウル・ナンバー。
本アルバムではアーマ以外にもココ・テイラー、エッタ・ジェイムズ、ケイティ・ウェブスター、ルース・ブラウンといった綺羅星の如きベテラン・ディーバと共演しているが、その中では若いこともあってか、アーマの歌声が一番みずみずしい。
なんというか、聴いていて、とても前向きな気分になれる歌なんだな。明日に希望が持てるのだ。
B Bも、軽快なギター・ソロと歌で、アーマの快唱を盛り立てている。
他にもベテラン・ブルースマン、ローウェル・フルスンとの「Little By Little」、シンガー/ギタリスト、ジョー・ルイス・ウォーカーとの「Everybody’s Had The Blues」でのギター・バトルなど聴きどころは多い。
B Bの残した膨大な遺産のひとつ。今から聴いても、十分楽しめまっせ。
<独断評価>★★★★