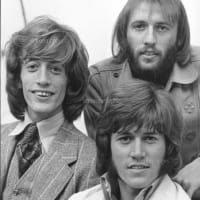2004年3月7日(日)

#208 ヨーヨー・マ「SOLO」(SONY SK 64114)
フランス生まれの中国系チェロ奏者、ヨーヨー・マの無伴奏ソロ・アルバム。99年リリース。
チェロという弦楽器は、アンサンブル用だけでなく独奏にも比較的適していて、それ用に書かれた楽曲も多いのだが、独奏曲だけで、しかも最も著名なバッハの「無伴奏ソナタ」抜きでまるまる一枚作ってしまうというのは、商売的にはかなりの「冒険」である。
当代随一の人気チェリストならではの企画と言えよう。
<筆者の私的ベスト2>
2位「SEVEN TUNES HEARD IN CHINA(中国で聞いた七つの歌)」
本アルバムに収められている曲は、大半が「現代音楽」の範疇に入る。その作曲者の名も大半が、われわれには馴染みのないものであろう。
この組曲風の七章を書いたブライト・シェンもそんなひとり。代表作は「CHINA DREAMS」。そう、ヨーヨー・マと同じく、中国人の音楽家、盛中亮なのである。
55年、上海生まれ。多感な思春期に文革を体験し、バルトーク、ストラヴィンスキーといった民族楽派に影響を受けた彼は、現在の中国を代表する中堅作曲家といえるだろう。
彼の紡ぎ出す音楽は、あくまでも西洋音楽をベースにしながらも、そこはやはりアジア人、非常に瞑想的な雰囲気を持ち、その一方で清新な躍動感も感じさせるものだ。
同胞で、しかもタメ年でもあるヨーヨー・マ(馬友友)は、シェンの音楽の本質をもっとも理解する演奏者といえるだろう。
もっとも望ましい弾き手を得ることで、この作品はベストといえる仕上がりを見せている。
ときには胡弓のように流麗で官能的な響き、ときには筝のようなダイナミックなプレイ(実際にコンサートを観に行ったひとのレポでは、ボウだけでなくバチまで使っていたそうだ)を聴かせてくれる。
技術、響き、そして情感の表現、すべてにおいて、文句なしの出来である。
1位「SONATA FOR SOLO CELLO Op.8(無伴奏チェロ・ソナタ 作品8)」
何を隠そう、筆者がこのCDを買ったのは、この曲を聴くがためであった。
ベラ・バルトークと並んでハンガリーを代表する作曲家、ゾルターン・コダーイ(1882-1967)の作品。
筆者は約20年前、堤剛の演奏で初めてこの曲を知ったのだが、西洋音楽とも東洋音楽とも言い切れぬ、独自の音世界に思わず引きずりこまれてしまったものだ。
ハンガリーの民俗音楽を匂わせる、土臭い旋律。広大な草原の中で、一台のチェロを弾いているさま、そんな風景が思い浮かんでくる一曲なのだ。
曲は三章の構成となっており、通しで弾くと30分近い長尺である。
その中でも、第一章冒頭のフレーズは、何度聴いてもインパクトがある。ベートーベンの「運命」のそれにも匹敵する、そんな感じ。
まさに、「つかみ」の一撃というべきか。
この曲は、西洋のいわゆる教会音階とは異なる、独特の音階を使用しているのだが、楽器の調弦もそれに合わせて、C弦やG弦をチューン・ダウンした変則チューニングを採用している。
そのため、通常のチェロ以上に中低音に異様なまでの迫力が感じられる。
ボウの動きにより発せられる音が、あたかも馬に打つ鞭のようにも聴こえるのだ。
さて、この曲のベスト・テイクは、作者同様ハンガリー出身のヤーノシュ・シュタルケルによる演奏であると多くの評者により言われて来た。
筆者もシュタルケルの演奏は愛聴しており、同じ意見である。それは今でも変わらないのだが、ヨーヨー・マのこのヴァージョンも、なかなか捨てがたいものがある。
シュタルケルの音色の重厚さ、ワイルドさに比べると、こちらのほうがもう少し軽くてジェントルかなという印象はあるが、技術的には互角。
30分近く、聴く者の神経を最後まで一瞬たりとも弛緩させることなく引っ張っていく。この演奏力はやはり、ただものではない。
素顔の温厚なキャラクターとは裏腹に、"紙一重"の狂気をも感じさせるヨーヨー・マの演奏。まぎれもなく、「天才」の業だと思うね。
<独断評価>★★★★