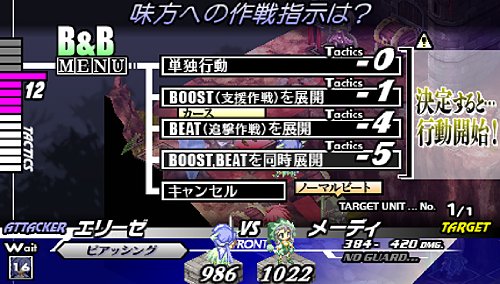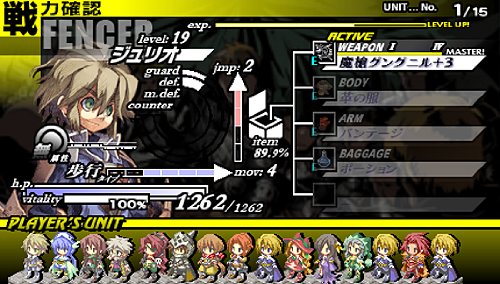パッケージ画像全体が公開されれば理由もわかってくるのだが、現在取り扱えるネタはこれぐらいしかないのである。
CEROになるにもいろいろ理由があるが、今作では種族差別が取り扱われるから「言葉・その他」はあるだろう。他に妥当なものとしては「犯罪」「暴力」だろうか。沐浴が入れば「セクシャル」も入ってくるだろうが、無理やりねじ込まれても…。
CEROに抑止力があるわけではないし、ターゲット層も中高生以上だろうからCでも構わないだろうが、セクシャル抜きでCERO CをSRPGで表現しているというのはかなりえぐいストーリーでもないと無理だろうな。
CEROになるにもいろいろ理由があるが、今作では種族差別が取り扱われるから「言葉・その他」はあるだろう。他に妥当なものとしては「犯罪」「暴力」だろうか。沐浴が入れば「セクシャル」も入ってくるだろうが、無理やりねじ込まれても…。
CEROに抑止力があるわけではないし、ターゲット層も中高生以上だろうからCでも構わないだろうが、セクシャル抜きでCERO CをSRPGで表現しているというのはかなりえぐいストーリーでもないと無理だろうな。