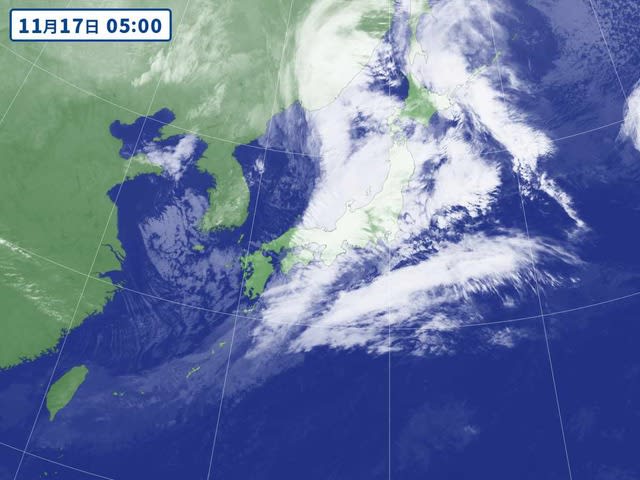11月19日 (日曜日) 晴れ
素晴らしい天気になった。
〇杓子菜を収穫して漬物つくりを始めた。初回なので小ぶりの樽にした。

〇青梗菜も大きくなってきたのでひとつづつ獲ってきては炒め物にしている。

~~~~~~~~~~~
〇菜園のかたずけ途中でKさんが作ったという干し柿をもってきてくれた。

良く出来ているので甘い。
〇ほうれん草も畑で観ていると小さいので、ほっとくと大きくなってしまう

〇落花生が夏の暑さで土が硬かったのか土にうまく落下しなかったせいか実が出来ていない。
大失敗であった。根の張りも悪く残念だ!全部抜いて小さい実はカラスへの御馳走だなあ~!
=================================
毎日新聞 余録19日
作家、筒井康隆さんの小説「毟(むし)りあい」は、
不毛な報復をエスカレートさせる人間心理の闇を描いた短編だ。
~~~~~~~~~~~~~~
要約「要約
主人公の井戸が会社から帰ってくるとマスコミや警官が自宅を取り囲んでいる、
というところから始まります。
警察官からの説明によれば、凶悪犯が脱獄し彼の妻子を人質にたてこもっているといいます。
犯人は娑婆に残してきた妻が別の男を作っていると
聞きつけて愛する妻と子に会うべく脱獄したものの、
~~~~~~~~~~~~
潜伏している警察官たちに気づいて近場の家に侵入して人質を盾にとって、
自分の妻子に会わせろと要求している状況です。
犯人である小古呂(おごろ)の妻は怯えてしまい説得に赴くつもりはなく、
警察も打つ手なしという段で、井戸は警官の案内によって小古呂の妻のもとに行き、
説得するよう説得することになります。
~~~~~~~~~~~~~
ところが、小古呂の家に着くや否や井戸は一変して
案内してくれた警官を殴って昏倒させ、拳銃を奪ってから放り出し、
自分も小古呂の妻子を人質にとります。
警官に取り次いでもらって小古呂へと電話をつないで先に妻子を解放するように要求し、
小古呂の子供を殴って泣かせ小古呂を追い込みます。
小古呂は泣き叫ぶ妻子の声に動揺しつつ、自分も井戸の子供を泣かせて反発しますが、
同時に井戸は小古呂の子供の指をへし折り、さらに圧力をかけます。
テレビをつけて翌日になっても小古呂が出てきていないことを確認すると、
井戸は小古呂の子供の指を切断し警官に運ばせ、
意趣返しのように小古呂は井戸の子供の指を切断し運ばせ、
井戸はもう一本指を切断し運ばせ、小古呂も同様にし、
二人は子供が失血死した後も死体から指を調達し、
もはや切断する指がなくなると今度は根比べとばかりに互いの妻の指を切断し運ばせます。
小古呂の妻もとうに死に、いよいよ切断する指もなくなるまで井戸と小古呂の応酬が続き、
井戸が「さあ。次はおれの小指を切るからな」と宣言し、小説は終わります。
====================================
▲悪夢のような、現実のこれは、むしりあいではないか。
イスラエルのハマス攻撃で、ガザ地区の子どもたち4500人以上がすでに犠牲となった。
軍はガザ最大の医療機関であるシファ病院に突入、病院が戦闘に巻き込まれた。
~~~~~~~~~
▲発電機の燃料が尽き、すでに新生児ら多くの患者が亡くなった病院である。
多くの遺体が腐敗したことで衛生上の危機に陥り、敷地で墓地が設営されているという。
日々悪化する状況に胸が痛む・
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▲病院突入にあたり、イスラエルはハマスの地下司令部があると説明していた。
地下トンネルを発見したと映像を公開したが、ハマス側と言い分は激しく対立する。
いずれにせよ、病院にいる市民の命を奪うことは正当化できない。
▲後手に回っていた国連安全保障理事会もやっと、戦闘休止を求める決議にこぎつけた。
米国などの思惑で機能不全を露呈したが、
子どもを含む民間人を救うためという、誰も否定できぬ倫理が細い糸をつないだ
▲筒井さんの作品には、事態を傍観し続ける警察やメディアも登場する。
憎悪と報復の連鎖や拡大を食い止めることができるのか。
国際社会と世論の力が試されている、
ガザの人道危機だ。
===========================
私の感じること・・
★報道で観る限りでは”人道”などという場面は何処にも映らない。
唯々、どす黒い血にまみれた惨状が伝わってくるだけである。
先日書いたが藤原先生の白黒つけるとすれば
そんなものはなく・・・限りなく灰色から真っ黒な世界に変わっていく事態である。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
メモ
WEB上にあったので借用する。
〇「毟(むし)りあい」
要約
主人公の井戸が会社から帰ってくるとマスコミや警官が自宅を取り囲んでいる、というところから始まります。警察官からの説明によれば、凶悪犯が脱獄し彼の妻子を人質にたてこもっているといいます。犯人は娑婆に残してきた妻が別の男を作っていると聞きつけて愛する妻と子に会うべく脱獄したものの、潜伏している警察官たちに気づいて近場の家に侵入して人質を盾にとって、自分の妻子に会わせろと要求している状況です。犯人である小古呂(おごろ)の妻は怯えてしまい説得に赴くつもりはなく、警察も打つ手なしという段で、井戸は警官の案内によって小古呂の妻のもとに行き、説得するよう説得することになります。
ところが、小古呂の家に着くや否や井戸は一変して、案内してくれた警官を殴って昏倒させ、拳銃を奪ってから放り出し、自分も小古呂の妻子を人質にとります。警官に取り次いでもらって小古呂へと電話をつないで先に妻子を解放するように要求し、小古呂の子供を殴って泣かせ小古呂を追い込みます。小古呂は泣き叫ぶ妻子の声に動揺しつつ、自分も井戸の子供を泣かせて反発しますが、同時に井戸は小古呂の子供の指をへし折り、さらに圧力をかけます。テレビをつけて翌日になっても小古呂が出てきていないことを確認すると、井戸は小古呂の子供の指を切断し警官に運ばせ、意趣返しのように小古呂は井戸の子供の指を切断し運ばせ、井戸はもう一本指を切断し運ばせ、小古呂も同様にし、二人は子供が失血死した後も死体から指を調達し、もはや切断する指がなくなると今度は根比べとばかりに互いの妻の指を切断し運ばせます。小古呂の妻もとうに死に、いよいよ切断する指もなくなるまで井戸と小古呂の応酬が続き、井戸が「さあ。次はおれの小指を切るからな」と宣言し、小説は終わります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
感想
なかなかすごい話です。
おどろおどろしいという意味での強烈さもありますが、それだけではない中身を感じさせます。
実際、いくつかの賞を得ていて、日本だけでなく海外でもたびたび舞台化される作品と聞きます。
舞台の感想を読み漁ると「狂気」という単語が目立ち、
なるほど人がかように常軌を逸している姿の演技はたいそう見応えがありそうで、
とても観てみたいです。小説を読んだのみなので演技の凄みに触れられていないのが少々残念です。
要約では割愛しましたが、前半では警察官や記者や被害者といった登場人物たちが自分の役割をまっとうしようとする姿が戯画的に強調されている印象があります。記者は事件を報道するべく井戸にインタビューをしますが、井戸がまだ事件に気づいていないと知ると、十分に現状を把握するための時間をおいて改めて「どういった心境ですか?」と聞いていました。言い換えれば、井戸が十分に被害者になるのを待ってから被害者として発言することを記者の立場から要求していると読めるわけです。記者たちの中でも立場はバラバラで7時のニュースに間に合わせたい人もいれば長尺のインタビューを取りたい人もいて、各々の思惑に応じた理想的な被害者の振る舞いを井戸に要求しており、その場における井戸の役割を定めようとする他者たちの勢力図が見て取れます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
井戸が妻子に会いたいという気持ちについて小古呂への同情を示すと、ある記者が
「あなた。それ、本気で言ってるんですか」「嘘にきまってるじゃないか」と
決めつけるように言います。記者の言い分としては放送されて犯人に聞かれた時のことを
考えて発言しているんだというものですが、それはむしろ頭ごなしに
否定したことの辻褄合わせという側面が強く、記者が求める被害者像にそぐわない
発言への反発が実態でしょう。この応酬を経て、井戸は記者を「加害者」とみなしています。
この場面を、井戸が他者からの要求に応えるのではなく自分の意思で発言をして、
拒絶されていると読み換えることができます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
妻子が人質にとられた善良な市民ならば、普通は取り乱したり涙ながらに妻子の無事を願ったりということが普通です。しかし、必ず取り乱さないといけないということはありません。現実においてはコードから外れた感情を抱くことはとても一般的です。たとえば卒業式の日、これまでの思い出深い日々をしみじみ振り返ったり別れに感極まったりするのが普通と思いきや、実際には「この靴箱を使うことってもうないんだなー」とか、なんなら「今日やけに鼻の頭がかゆい」というようなことを、よりによって考えたりするものです。そう思うからといって別に異常者というわけではありません。しかし、そういうことを大々的に言うのはなんか違うわけで、そう感じさせる理由として外部から要求される振る舞いのコードとそぐわないから、ということを挙げられると思います。
このコードを絶対視してみて、言い換えればコードに合わない応答をされるのが誰にとっても耐え難いかのような極端な設定にしたのが「毟りあい」であると理解しました。犯人に同情を示すというのは、妻子を人質にとられたかわいそうな被害者の反応としては0点で、井戸は記者たちが望む回答をするよう迫られているわけです。しかし井戸はコードに従いたがらず、他者から規定される役割ではなく自分の意思で動こうとする人間です。他者から要求される役割と自分の意思で動くことの闘争、これが前半で描かれているように感じます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
役割という言葉をここまで随分と否定的に論じてきましたが。それがポジティブな意味を持つことは普通にあり得ます。子供の頃の憧れを現実にして電車の運転手になった人や努力の成果で弁護士になった人が、自分の職業を誇りに思うならば、いかにも運転手や弁護士らしい振る舞いをする自分に酔いしれるのは不思議ではありません。その場合、自分の役割を全うするために他の人たちにも自分の相手役としてふさわしい振る舞いを暗に要求することもあるかもしれません。「毟りあい」に出てくる警察官の百百山は警察官という職業に誇りを持ち、井戸が自分の領分に踏み込んでくることを許しません。
自我が崩壊しそうになっているおれの様子を見て、百百山の眼には、きら、と優越感がひらめいた。小気味よげに唇の端を吊りあげ、彼は喜色を満面に浮かべてうなずいた。「警察にまかせておきなさい」
本文より
これを受けて井戸は「百百山もおそらく、おれに対して一瞬加害者の快感を覚えたに違いなかった」と感じています。そして小古呂の妻子を人質にとった後で百百山と電話するとき、「これ以上被害者であり続けるよりは、むしろ小古呂同様の加害者たらんとする道を選んだのだ」「自分は被害者としての適性のない人間だ」と述べます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ここでの被害者や加害者という言葉遣いは特殊で面白いものがあります。被害者とは文字通りには妻子を人質に取られ、かわいそうで善良な市民という役を指していると思われます。これは記者たちが井戸に望んだ役です。それが自分の望むものではないと井戸が感じているのは先に確認した通りです。他方で、百百山が「警察にまかせておきなさい」と言って自分の役割を全うすべく井戸を制限するときに百百山を加害者とみなしていました。これに対するものとしての被害者を考えるならば、誰かの役を引き立てるための犠牲として、他人にあてがわれた役を演じざるを得ない、受動的で主体性のない人間と言うことができそうです。これも割愛していた話ですが井戸は話のなかでエリートの側にいて、積極的に自分を作り上げてきた人間と示されています。であるとすれば、他人に求められるがままに動くことは望まず「被害者としての適性のない人間」であるという言い分もわかります。要するに井戸の言う「被害者」とは二重になっていて、妻子を人質にとられて泣きわめくといった被害者を意味するのみならず、他人の役のために自分の役やセリフを譲り渡すような被害者をも意味すると理解できます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ところで、自然にセリフや役という言い回しを使ってきてしまいました。これは自分としては小説から直接的に引き出してきたもののつもりで、だからこそこの作品が舞台化されやすいということに納得感があります。他人に求められる役や自分の望む役といったことが問題となっている以上、舞台の上でこのテーマが取り上げられるのも必然のように感じます。
踏み込んだ話をする余裕も用意もないのですが、舞台というのは役者がある程度主体的に演じると言えど誰かにあてがわれた役であるという点で、現実世界とは違います。われわれの人生を舞台に見立てることがありますが、われわれは誰かに筋書きを用意してもらうことはありません。だからと言って、舞台においても登場人物の主体性を強調してもその舞台が現実に似るわけではありません。むしろ「それだけではない」舞台の特殊さが際立つかもしれません。「毟りあい」は当然脚本がある話ではありますが、登場人物たちが誰かの思惑に乗ることなく自分の役を演じ、他人を従属させようと闘争しています。そのように各々が自分の意思に基づいている点では実際のわれわれの姿に寄っているはずなのに大胆に現実から離れていく、というこのことに何か舞台の特殊性が抉り出されているように感じます。だからこそ舞台関係者の注目を集めるのかも、と考えたのでした。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ここまでの読み筋ですが、井戸が被害者であることを選ばず加害者でいることを選択したと理解しています。自分で自分の役割を掴み取ることを目指しているわけで、好意的な印象すら覚えます。が、どう考えても井戸を好意的に捉えてはいけないというのが面白いところです。井戸は結局のところ二人を殺害し妻子を見殺しにしていますから、文字通りの意味でも加害者になっています。そして最後には根比べという勢いで自分の指を切り放そうというところまで達しており、どうしようもなく盲目的です。事実、井戸が小指を切り離す直前から最後まで、数ページにわたって一度たりとも段落替えをしておらず、いわば冷静になる瞬間がないような書き方がされています。ですが、自分の役を自分で掴もうということまでは乗れる話であったはずです。どこでおかしくなったのでしょう。正しく見えたはずの決意が即座に狂気に裏返るというこの状況は一体なんなのでしょう。強烈な問いです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ひとつ思いつくのは、役を演じるために他人の役を食いつぶす必要があるという前提に乗っかるのがマズイということです。井戸は切り落とした指を警察官に運ばせることで、警察官を郵便屋の役に貶めてやったと悦に浸っていますが、自分の主張を通すこととは他人との闘争に他ならない(協調する余地がまったくない)というのは単純すぎる見方でしょう。そして興味深いことに、井戸の立てこもりが続くとあれだけ囲ってきた記者たちは引いていき、放送もほとんどされなくなります。舞台の比喩にたよって言い換えてみれば、自分のやりたい役にこだわるあまり、観客がいなくなっているという状況でしょうか。自分のやりたい役ができているのだからいいじゃないか、という見方もできるかもしれませんが、果たしてそれは本当に魅力的な舞台になっているのでしょうか。客観的に魅力がないのならば、自分の役を観客として見たときに満足できるかどうかは微妙です。また、自分の役を演じるために他人に特定の言動を強いていたように、役とはある程度以上は他人を要求するものであるはずです。にもかかわらず自分の都合だけ通そうというのは、視野が狭いと言わざるを得ないでしょう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
自分の演じたいように各々が演じようとするこの状況は、ホッブズの想定した自然状態に似ています。本来人間は利己的であるから、社会的な制約がない自然状態では自分の利益だけを考えるもの同士の闘争となるだろうというものです。このような理解は安直で不完全ですが、ありふれた見解でもあります。限られた客層を企業同士が奪い合うと言われたとして、そのときにイメージされるのは自分の利益を拡大し、食いつぶし合う利己的なもの同士の闘争です。
以上を整理してみると、井戸は自分の価値観がどのような土台のうえに成り立っているのかを自覚せぬままに、自分の役を自分で掴み取ることに固執しており、土台を疑わないままに直進する姿勢が彼の盲目に対するひとつの説明となりそうです。そして他方、井戸やこの舞台の人物たちが前提している世界観がわれわれにも浸透している以上、自分がその狂気からまぬがれていて安全である保証はありません。井戸が狂ってるからと冷静にみることができたとて、事情は変わりません。井戸の狂気が人ごとならざるものだと受け取ったとしても、他人の指を切断するなんてことはまず思わないでしょう。あれが我々にとっても身につまされるものであるのは、彼と同じ種類の盲目に陥る可能性があり、あるいは現にそのように盲目であるかもしれないからであると考えます。もともと記者の振る舞いなんかも戯画的で、現実を部分的に強調したという面がありますから、井戸の異常行動もかなり極端にしただけの我々と考える余地は十分にあるわけです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
と、いうのを一旦の結論としつつ、やはりそれだけの話と考えるわけにはいかないでしょう。たとえば、指を切るまでいくのを極端な強調として片付けるのは単純化がすぎる感じがします。
有限な資源を食いつぶしながら自分の役を全うしようという消耗が表現されていると考えることもできるかもしれません。
独りよがりな生き方は外部からの供給もなければ、
(記者という観客がいなくなったように)自分自身が需要になることもありません。
他人との関係のうちで我を通すことだけを考えるならば、
かえって身を削ってしか再現できないというのが、自分の読みとして言えそうなことです。
が、やはりどこか単純化しているように思われます。
===================================

素晴らしい天気になった。
〇杓子菜を収穫して漬物つくりを始めた。初回なので小ぶりの樽にした。

〇青梗菜も大きくなってきたのでひとつづつ獲ってきては炒め物にしている。

~~~~~~~~~~~
〇菜園のかたずけ途中でKさんが作ったという干し柿をもってきてくれた。

良く出来ているので甘い。
〇ほうれん草も畑で観ていると小さいので、ほっとくと大きくなってしまう

〇落花生が夏の暑さで土が硬かったのか土にうまく落下しなかったせいか実が出来ていない。
大失敗であった。根の張りも悪く残念だ!全部抜いて小さい実はカラスへの御馳走だなあ~!
=================================
毎日新聞 余録19日

作家、筒井康隆さんの小説「毟(むし)りあい」は、
不毛な報復をエスカレートさせる人間心理の闇を描いた短編だ。
~~~~~~~~~~~~~~
要約「要約
主人公の井戸が会社から帰ってくるとマスコミや警官が自宅を取り囲んでいる、
というところから始まります。
警察官からの説明によれば、凶悪犯が脱獄し彼の妻子を人質にたてこもっているといいます。
犯人は娑婆に残してきた妻が別の男を作っていると
聞きつけて愛する妻と子に会うべく脱獄したものの、
~~~~~~~~~~~~
潜伏している警察官たちに気づいて近場の家に侵入して人質を盾にとって、
自分の妻子に会わせろと要求している状況です。
犯人である小古呂(おごろ)の妻は怯えてしまい説得に赴くつもりはなく、
警察も打つ手なしという段で、井戸は警官の案内によって小古呂の妻のもとに行き、
説得するよう説得することになります。
~~~~~~~~~~~~~
ところが、小古呂の家に着くや否や井戸は一変して
案内してくれた警官を殴って昏倒させ、拳銃を奪ってから放り出し、
自分も小古呂の妻子を人質にとります。
警官に取り次いでもらって小古呂へと電話をつないで先に妻子を解放するように要求し、
小古呂の子供を殴って泣かせ小古呂を追い込みます。
小古呂は泣き叫ぶ妻子の声に動揺しつつ、自分も井戸の子供を泣かせて反発しますが、
同時に井戸は小古呂の子供の指をへし折り、さらに圧力をかけます。
テレビをつけて翌日になっても小古呂が出てきていないことを確認すると、
井戸は小古呂の子供の指を切断し警官に運ばせ、
意趣返しのように小古呂は井戸の子供の指を切断し運ばせ、
井戸はもう一本指を切断し運ばせ、小古呂も同様にし、
二人は子供が失血死した後も死体から指を調達し、
もはや切断する指がなくなると今度は根比べとばかりに互いの妻の指を切断し運ばせます。
小古呂の妻もとうに死に、いよいよ切断する指もなくなるまで井戸と小古呂の応酬が続き、
井戸が「さあ。次はおれの小指を切るからな」と宣言し、小説は終わります。
====================================
▲悪夢のような、現実のこれは、むしりあいではないか。
イスラエルのハマス攻撃で、ガザ地区の子どもたち4500人以上がすでに犠牲となった。
軍はガザ最大の医療機関であるシファ病院に突入、病院が戦闘に巻き込まれた。
~~~~~~~~~
▲発電機の燃料が尽き、すでに新生児ら多くの患者が亡くなった病院である。
多くの遺体が腐敗したことで衛生上の危機に陥り、敷地で墓地が設営されているという。
日々悪化する状況に胸が痛む・
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▲病院突入にあたり、イスラエルはハマスの地下司令部があると説明していた。
地下トンネルを発見したと映像を公開したが、ハマス側と言い分は激しく対立する。
いずれにせよ、病院にいる市民の命を奪うことは正当化できない。
▲後手に回っていた国連安全保障理事会もやっと、戦闘休止を求める決議にこぎつけた。
米国などの思惑で機能不全を露呈したが、
子どもを含む民間人を救うためという、誰も否定できぬ倫理が細い糸をつないだ
▲筒井さんの作品には、事態を傍観し続ける警察やメディアも登場する。
憎悪と報復の連鎖や拡大を食い止めることができるのか。
国際社会と世論の力が試されている、
ガザの人道危機だ。
===========================
私の感じること・・

★報道で観る限りでは”人道”などという場面は何処にも映らない。
唯々、どす黒い血にまみれた惨状が伝わってくるだけである。
先日書いたが藤原先生の白黒つけるとすれば
そんなものはなく・・・限りなく灰色から真っ黒な世界に変わっていく事態である。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
メモ

WEB上にあったので借用する。
〇「毟(むし)りあい」
要約
主人公の井戸が会社から帰ってくるとマスコミや警官が自宅を取り囲んでいる、というところから始まります。警察官からの説明によれば、凶悪犯が脱獄し彼の妻子を人質にたてこもっているといいます。犯人は娑婆に残してきた妻が別の男を作っていると聞きつけて愛する妻と子に会うべく脱獄したものの、潜伏している警察官たちに気づいて近場の家に侵入して人質を盾にとって、自分の妻子に会わせろと要求している状況です。犯人である小古呂(おごろ)の妻は怯えてしまい説得に赴くつもりはなく、警察も打つ手なしという段で、井戸は警官の案内によって小古呂の妻のもとに行き、説得するよう説得することになります。
ところが、小古呂の家に着くや否や井戸は一変して、案内してくれた警官を殴って昏倒させ、拳銃を奪ってから放り出し、自分も小古呂の妻子を人質にとります。警官に取り次いでもらって小古呂へと電話をつないで先に妻子を解放するように要求し、小古呂の子供を殴って泣かせ小古呂を追い込みます。小古呂は泣き叫ぶ妻子の声に動揺しつつ、自分も井戸の子供を泣かせて反発しますが、同時に井戸は小古呂の子供の指をへし折り、さらに圧力をかけます。テレビをつけて翌日になっても小古呂が出てきていないことを確認すると、井戸は小古呂の子供の指を切断し警官に運ばせ、意趣返しのように小古呂は井戸の子供の指を切断し運ばせ、井戸はもう一本指を切断し運ばせ、小古呂も同様にし、二人は子供が失血死した後も死体から指を調達し、もはや切断する指がなくなると今度は根比べとばかりに互いの妻の指を切断し運ばせます。小古呂の妻もとうに死に、いよいよ切断する指もなくなるまで井戸と小古呂の応酬が続き、井戸が「さあ。次はおれの小指を切るからな」と宣言し、小説は終わります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
感想
なかなかすごい話です。
おどろおどろしいという意味での強烈さもありますが、それだけではない中身を感じさせます。
実際、いくつかの賞を得ていて、日本だけでなく海外でもたびたび舞台化される作品と聞きます。
舞台の感想を読み漁ると「狂気」という単語が目立ち、
なるほど人がかように常軌を逸している姿の演技はたいそう見応えがありそうで、
とても観てみたいです。小説を読んだのみなので演技の凄みに触れられていないのが少々残念です。
要約では割愛しましたが、前半では警察官や記者や被害者といった登場人物たちが自分の役割をまっとうしようとする姿が戯画的に強調されている印象があります。記者は事件を報道するべく井戸にインタビューをしますが、井戸がまだ事件に気づいていないと知ると、十分に現状を把握するための時間をおいて改めて「どういった心境ですか?」と聞いていました。言い換えれば、井戸が十分に被害者になるのを待ってから被害者として発言することを記者の立場から要求していると読めるわけです。記者たちの中でも立場はバラバラで7時のニュースに間に合わせたい人もいれば長尺のインタビューを取りたい人もいて、各々の思惑に応じた理想的な被害者の振る舞いを井戸に要求しており、その場における井戸の役割を定めようとする他者たちの勢力図が見て取れます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
井戸が妻子に会いたいという気持ちについて小古呂への同情を示すと、ある記者が
「あなた。それ、本気で言ってるんですか」「嘘にきまってるじゃないか」と
決めつけるように言います。記者の言い分としては放送されて犯人に聞かれた時のことを
考えて発言しているんだというものですが、それはむしろ頭ごなしに
否定したことの辻褄合わせという側面が強く、記者が求める被害者像にそぐわない
発言への反発が実態でしょう。この応酬を経て、井戸は記者を「加害者」とみなしています。
この場面を、井戸が他者からの要求に応えるのではなく自分の意思で発言をして、
拒絶されていると読み換えることができます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
妻子が人質にとられた善良な市民ならば、普通は取り乱したり涙ながらに妻子の無事を願ったりということが普通です。しかし、必ず取り乱さないといけないということはありません。現実においてはコードから外れた感情を抱くことはとても一般的です。たとえば卒業式の日、これまでの思い出深い日々をしみじみ振り返ったり別れに感極まったりするのが普通と思いきや、実際には「この靴箱を使うことってもうないんだなー」とか、なんなら「今日やけに鼻の頭がかゆい」というようなことを、よりによって考えたりするものです。そう思うからといって別に異常者というわけではありません。しかし、そういうことを大々的に言うのはなんか違うわけで、そう感じさせる理由として外部から要求される振る舞いのコードとそぐわないから、ということを挙げられると思います。
このコードを絶対視してみて、言い換えればコードに合わない応答をされるのが誰にとっても耐え難いかのような極端な設定にしたのが「毟りあい」であると理解しました。犯人に同情を示すというのは、妻子を人質にとられたかわいそうな被害者の反応としては0点で、井戸は記者たちが望む回答をするよう迫られているわけです。しかし井戸はコードに従いたがらず、他者から規定される役割ではなく自分の意思で動こうとする人間です。他者から要求される役割と自分の意思で動くことの闘争、これが前半で描かれているように感じます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
役割という言葉をここまで随分と否定的に論じてきましたが。それがポジティブな意味を持つことは普通にあり得ます。子供の頃の憧れを現実にして電車の運転手になった人や努力の成果で弁護士になった人が、自分の職業を誇りに思うならば、いかにも運転手や弁護士らしい振る舞いをする自分に酔いしれるのは不思議ではありません。その場合、自分の役割を全うするために他の人たちにも自分の相手役としてふさわしい振る舞いを暗に要求することもあるかもしれません。「毟りあい」に出てくる警察官の百百山は警察官という職業に誇りを持ち、井戸が自分の領分に踏み込んでくることを許しません。
自我が崩壊しそうになっているおれの様子を見て、百百山の眼には、きら、と優越感がひらめいた。小気味よげに唇の端を吊りあげ、彼は喜色を満面に浮かべてうなずいた。「警察にまかせておきなさい」
本文より
これを受けて井戸は「百百山もおそらく、おれに対して一瞬加害者の快感を覚えたに違いなかった」と感じています。そして小古呂の妻子を人質にとった後で百百山と電話するとき、「これ以上被害者であり続けるよりは、むしろ小古呂同様の加害者たらんとする道を選んだのだ」「自分は被害者としての適性のない人間だ」と述べます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ここでの被害者や加害者という言葉遣いは特殊で面白いものがあります。被害者とは文字通りには妻子を人質に取られ、かわいそうで善良な市民という役を指していると思われます。これは記者たちが井戸に望んだ役です。それが自分の望むものではないと井戸が感じているのは先に確認した通りです。他方で、百百山が「警察にまかせておきなさい」と言って自分の役割を全うすべく井戸を制限するときに百百山を加害者とみなしていました。これに対するものとしての被害者を考えるならば、誰かの役を引き立てるための犠牲として、他人にあてがわれた役を演じざるを得ない、受動的で主体性のない人間と言うことができそうです。これも割愛していた話ですが井戸は話のなかでエリートの側にいて、積極的に自分を作り上げてきた人間と示されています。であるとすれば、他人に求められるがままに動くことは望まず「被害者としての適性のない人間」であるという言い分もわかります。要するに井戸の言う「被害者」とは二重になっていて、妻子を人質にとられて泣きわめくといった被害者を意味するのみならず、他人の役のために自分の役やセリフを譲り渡すような被害者をも意味すると理解できます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ところで、自然にセリフや役という言い回しを使ってきてしまいました。これは自分としては小説から直接的に引き出してきたもののつもりで、だからこそこの作品が舞台化されやすいということに納得感があります。他人に求められる役や自分の望む役といったことが問題となっている以上、舞台の上でこのテーマが取り上げられるのも必然のように感じます。
踏み込んだ話をする余裕も用意もないのですが、舞台というのは役者がある程度主体的に演じると言えど誰かにあてがわれた役であるという点で、現実世界とは違います。われわれの人生を舞台に見立てることがありますが、われわれは誰かに筋書きを用意してもらうことはありません。だからと言って、舞台においても登場人物の主体性を強調してもその舞台が現実に似るわけではありません。むしろ「それだけではない」舞台の特殊さが際立つかもしれません。「毟りあい」は当然脚本がある話ではありますが、登場人物たちが誰かの思惑に乗ることなく自分の役を演じ、他人を従属させようと闘争しています。そのように各々が自分の意思に基づいている点では実際のわれわれの姿に寄っているはずなのに大胆に現実から離れていく、というこのことに何か舞台の特殊性が抉り出されているように感じます。だからこそ舞台関係者の注目を集めるのかも、と考えたのでした。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ここまでの読み筋ですが、井戸が被害者であることを選ばず加害者でいることを選択したと理解しています。自分で自分の役割を掴み取ることを目指しているわけで、好意的な印象すら覚えます。が、どう考えても井戸を好意的に捉えてはいけないというのが面白いところです。井戸は結局のところ二人を殺害し妻子を見殺しにしていますから、文字通りの意味でも加害者になっています。そして最後には根比べという勢いで自分の指を切り放そうというところまで達しており、どうしようもなく盲目的です。事実、井戸が小指を切り離す直前から最後まで、数ページにわたって一度たりとも段落替えをしておらず、いわば冷静になる瞬間がないような書き方がされています。ですが、自分の役を自分で掴もうということまでは乗れる話であったはずです。どこでおかしくなったのでしょう。正しく見えたはずの決意が即座に狂気に裏返るというこの状況は一体なんなのでしょう。強烈な問いです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ひとつ思いつくのは、役を演じるために他人の役を食いつぶす必要があるという前提に乗っかるのがマズイということです。井戸は切り落とした指を警察官に運ばせることで、警察官を郵便屋の役に貶めてやったと悦に浸っていますが、自分の主張を通すこととは他人との闘争に他ならない(協調する余地がまったくない)というのは単純すぎる見方でしょう。そして興味深いことに、井戸の立てこもりが続くとあれだけ囲ってきた記者たちは引いていき、放送もほとんどされなくなります。舞台の比喩にたよって言い換えてみれば、自分のやりたい役にこだわるあまり、観客がいなくなっているという状況でしょうか。自分のやりたい役ができているのだからいいじゃないか、という見方もできるかもしれませんが、果たしてそれは本当に魅力的な舞台になっているのでしょうか。客観的に魅力がないのならば、自分の役を観客として見たときに満足できるかどうかは微妙です。また、自分の役を演じるために他人に特定の言動を強いていたように、役とはある程度以上は他人を要求するものであるはずです。にもかかわらず自分の都合だけ通そうというのは、視野が狭いと言わざるを得ないでしょう。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
自分の演じたいように各々が演じようとするこの状況は、ホッブズの想定した自然状態に似ています。本来人間は利己的であるから、社会的な制約がない自然状態では自分の利益だけを考えるもの同士の闘争となるだろうというものです。このような理解は安直で不完全ですが、ありふれた見解でもあります。限られた客層を企業同士が奪い合うと言われたとして、そのときにイメージされるのは自分の利益を拡大し、食いつぶし合う利己的なもの同士の闘争です。
以上を整理してみると、井戸は自分の価値観がどのような土台のうえに成り立っているのかを自覚せぬままに、自分の役を自分で掴み取ることに固執しており、土台を疑わないままに直進する姿勢が彼の盲目に対するひとつの説明となりそうです。そして他方、井戸やこの舞台の人物たちが前提している世界観がわれわれにも浸透している以上、自分がその狂気からまぬがれていて安全である保証はありません。井戸が狂ってるからと冷静にみることができたとて、事情は変わりません。井戸の狂気が人ごとならざるものだと受け取ったとしても、他人の指を切断するなんてことはまず思わないでしょう。あれが我々にとっても身につまされるものであるのは、彼と同じ種類の盲目に陥る可能性があり、あるいは現にそのように盲目であるかもしれないからであると考えます。もともと記者の振る舞いなんかも戯画的で、現実を部分的に強調したという面がありますから、井戸の異常行動もかなり極端にしただけの我々と考える余地は十分にあるわけです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
と、いうのを一旦の結論としつつ、やはりそれだけの話と考えるわけにはいかないでしょう。たとえば、指を切るまでいくのを極端な強調として片付けるのは単純化がすぎる感じがします。
有限な資源を食いつぶしながら自分の役を全うしようという消耗が表現されていると考えることもできるかもしれません。
独りよがりな生き方は外部からの供給もなければ、
(記者という観客がいなくなったように)自分自身が需要になることもありません。
他人との関係のうちで我を通すことだけを考えるならば、
かえって身を削ってしか再現できないというのが、自分の読みとして言えそうなことです。
が、やはりどこか単純化しているように思われます。
===================================