特に国立大学では、職員の3年定期異動というのは標準となっている、ないし思われているのではないでしょうか。
大阪大学では、職員採用のサイトに、その旨を書いています。
こんな風に考えられないでしょうか。
3年で異動≒ある程度定型化された仕事
≒誰でも同じような仕事ができる期待
(改善指向の弱さも関係?)
≒専門性の否定
ではないかということです。
一方で、ルーティン業務や、成熟した業務やサービスだったら、3年異動で回せないと(維持できないと)、何か間違っているでしょう。
また、組織風土や、人材、異動の運用によっては、3年異動でも新規事業を動かせるでしょう。
大学図書館業界(国立大学かもしれませんが)で、専門性と言うと、
自分達の世界を自分達で区切って、
その世界を専門性と呼び、
研修で専門性を高めて、
という印象があります。
ICT、学修支援、研究評価などなど、新しい課題(新規事業)も出てるのだから(出続けるでしょうし)、自分達のフィールドは柔軟に考えて、周囲とは人的にも流動性を増やし、その中で適性を見つつ専門性を高めることって大事と思います。
なお、明治大学では事務職員の異動頻度は「5年」が基本(?)と明文化されているそうです。
3年定期異動が、誰でも5点満点で3点の仕事を期待される、ゼネラリスト?を前提にしているように感じます。
そういう組織を目指すのも間違いとは言いませんが、新しい仕事や専門性という切り口で考えると、そこを問い直すのも意味があることでは?
ちょっと雑なメモですが、これもまずは文字にしてみました。
大阪大学では、職員採用のサイトに、その旨を書いています。
こんな風に考えられないでしょうか。
3年で異動≒ある程度定型化された仕事
≒誰でも同じような仕事ができる期待
(改善指向の弱さも関係?)
≒専門性の否定
ではないかということです。
一方で、ルーティン業務や、成熟した業務やサービスだったら、3年異動で回せないと(維持できないと)、何か間違っているでしょう。
また、組織風土や、人材、異動の運用によっては、3年異動でも新規事業を動かせるでしょう。
大学図書館業界(国立大学かもしれませんが)で、専門性と言うと、
自分達の世界を自分達で区切って、
その世界を専門性と呼び、
研修で専門性を高めて、
という印象があります。
ICT、学修支援、研究評価などなど、新しい課題(新規事業)も出てるのだから(出続けるでしょうし)、自分達のフィールドは柔軟に考えて、周囲とは人的にも流動性を増やし、その中で適性を見つつ専門性を高めることって大事と思います。
なお、明治大学では事務職員の異動頻度は「5年」が基本(?)と明文化されているそうです。
3年定期異動が、誰でも5点満点で3点の仕事を期待される、ゼネラリスト?を前提にしているように感じます。
そういう組織を目指すのも間違いとは言いませんが、新しい仕事や専門性という切り口で考えると、そこを問い直すのも意味があることでは?
ちょっと雑なメモですが、これもまずは文字にしてみました。

















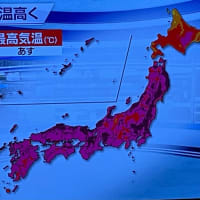
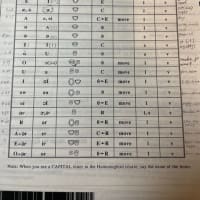

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます