
 琵琶湖博物館の地下収蔵庫で標本整理中にたまたま来訪された吉安裕博士と、巣と繭と蛹の進化について雑談しました。するとその話は面白いから2015年1月25日に大阪市で開かれる日本蛾類学会で特別講演して下さいと頼まれました。その話を忘れかけていた頃、また依頼があり、特別講演は先に一人決まっているが、その人と30分ずつ話してほしいとのことで引き受けました。私は山に籠り、長い間学会講演をしていないので、草津市に移ってから長崎大学熱帯医学研究所で講演した時は、1時間の講演を吹き込んだICレコーダーを持って行き、それをスピカ―で流しました。事前に100回ぐらい吹き込んで一番良いのを使ったので、わかりやすく大変評判が良かったのです。そこで学会でもその積りだったのですが、もちろん万一に備えて原稿を持って行きました。ところがICレコーダーは使えず、また講演台に明かりがなく暗くて原稿が読めないので困りました。
琵琶湖博物館の地下収蔵庫で標本整理中にたまたま来訪された吉安裕博士と、巣と繭と蛹の進化について雑談しました。するとその話は面白いから2015年1月25日に大阪市で開かれる日本蛾類学会で特別講演して下さいと頼まれました。その話を忘れかけていた頃、また依頼があり、特別講演は先に一人決まっているが、その人と30分ずつ話してほしいとのことで引き受けました。私は山に籠り、長い間学会講演をしていないので、草津市に移ってから長崎大学熱帯医学研究所で講演した時は、1時間の講演を吹き込んだICレコーダーを持って行き、それをスピカ―で流しました。事前に100回ぐらい吹き込んで一番良いのを使ったので、わかりやすく大変評判が良かったのです。そこで学会でもその積りだったのですが、もちろん万一に備えて原稿を持って行きました。ところがICレコーダーは使えず、また講演台に明かりがなく暗くて原稿が読めないので困りました。私の講演の目的は鱗翅目の巣と繭と蛹の進化について話すことです(図1)。つまり完全変態群の進化です。そこでまず最近描かれた昆虫の系統図をスライド(省略)で示しました。なお3対、6本脚の節足動物をすべて一緒にして六脚綱Hexapodaと呼ぶ学者がいます。また私のようにそれらをひっくるめて昆虫綱Insectaと呼ぶ人もいます。しかし、昆虫は普通名詞であり、しかも綱の名称ですから、昆虫学会、昆虫学者、昆虫図鑑などすでに世界中で定着していますから、譲るべきは六脚綱を使うことにこだわる人々です。私は九重昆虫記10巻でラマルクのことを詳しく紹介しました。彼は分類の綱、目、科、属、種などの段階に命名がともなうのは、専門家のためではなく、日常生活でそれらを何らかの名前で呼ぶ必要がある一般人の利便性のためであると喝破しています。
目の数はその系統図では無変態群が6目、不完全変態群が16目、完全変態群が11目あります。つまり33目のうち完全変態群はちょうど三分の一を占めています。
まず無変態群、不完全変態群、完全変態群を私なりに定義してみましょう。無変態群は複数回脱皮し、そのたびに体が大きくなるけれど、一生の間に顕著な形態的な変化が起こらない、つまり他の2群に特徴的な翅を持つことがありません。
不完全変態群も成長過程で複数回脱皮します。外骨格を持つ節足動物は餌を食べて体の実質が増えても、外側を覆っている殻が硬いので体の大きさは変わりません。そこで、時々、殻を脱ぎもっと大きな殻に変えねばなりません。
しかし、複数回脱皮して成長することが、実は節足動物の進化を可能したのです。内部で少しずつ変更したことを、脱皮のたびに具体化し、まず翅を生やしました。不完全変態群の誕生です。
昆虫の先祖は湿った場所や水中で進化したのではないかと私は考えています。そういう環境では小さな昆虫なら水分に含まれている栄養分を吸収する⇒さらに植物の柔らかい組織から汁を吸収する方向、つまり昆虫が祖先から受け継いできた噛む形の口を少しずつ作り変え、幼虫時代から吸収型口器を採用する半翅目のような虫が出現しました(図2、アワフキムシの不完全変態)。また幼虫も成虫も祖先から受け継いだ噛む形の口器を持つ不完全変態するアシグロツユムシの変態を図3に示しました。残念ながらこの虫の卵や初齢幼虫の写真はありません。この型は半翅目型の不完全変態よりも古いと考えられています。翅を生やすだけなら脱皮のたびに少しずつ改造できるから、キリギリス型もアワフキムシ型(半翅目型)もわざわざ餌を食べないで“作り変え”をする蛹の時期を設ける必要はありません。
完全変態群と不完全変態群の最も違う点は、幼虫と成虫の食物の違いによる口器の違いの変化が見られることです。つまり変態の第一段階は翅を生やすこと、第二段階では鱗翅目のように幼虫の口器を噛む形のまま残し、成虫の口器を別の形つまり吸収型などに変更することです(図3)。幼虫と成虫が食物をまったく変えるには、一時的に摂食をやめ口器や消化管を改造してから、成虫として再スタートしなければなりません。その食物を摂取しない時期は一種の休眠状態だから、その時期だけをすごす特殊な形態を蛹と呼びます。多くの完全変態群昆虫はできるだけ呼吸によって失われるエネルギーを節約するため、体表面積を小さくした形、つまり脚や触角を縮め体にぴったりくっつけた特別な形を採用しています。
現在、完全変態群に分類される群は、幼虫時代の口器と成虫の口器が同じ噛む形を採用している目もありますが、鱗翅目、膜翅目、双翅目などは口器・脚・消化器官・体型などを根本的に変更したため、どうしても活動を停止する蛹の時期が必要です。
完全変態と不完全変態という用語から受けるイメージは、明らかに後者の方が劣っており、完全な域に達していないと思われがちです。しかしどの虫もそれぞれの生きている環境に十分に適応しているから、どちらが完全か判定することはできません。ただ言えることは動物の進化は食うことから始まったので、どの動物群を研究する時も口を見ればある程度かれらの暮らしがわかります。おしゃべりの人を口から先に生まれた人と形容しますが、すべての動物は口から先に生まれたと断言できます。なぜなら無脊椎動物から脊椎動物までほとんどの動物が口の近くに主要感覚器官である目、耳、鼻と司令塔である脳、運動器官である前足を配置し、食い物の情報をいち早く感知し、それに向かって突進しやすい体型に作られています。
脊椎動物も変態します。彼らと昆虫群は様々の点で似ています。カエルのオタマジャクシは、脚がなく鰭で泳ぎます。解剖すると細く長い消化管を持っており内部に植物の破片が詰まっています。成体つまりカエルは虫を食べます。解剖すると消化管は食道・胃・小腸・大腸に分かれ、立派な肺も持っています。脊椎動物は外骨格ではなく内骨格、つまり体内に骨があり、そのため内部から少しずつ成長すればよいので脱皮することはありません。哺乳動物である人は変態しませんが、その代わりその時期を子宮内で過ごします。赤ん坊は乳つまり液状物をとり、成長するにつれ固形物を食べるようになります。
繭とは動けない蛹を天敵から守るために発達したシェルターあるいはカプセルです。繭は絹糸を使ってしっかりと作るカイコやヤママユガの繭から、糸量を節約するため木の葉を綴るマイマイガまで様々あり、蛹も繭の形も千差万別です。ガ類では一般的傾向として、食樹上で葉や糸を綴って繭を綴る種は、糸や葉を節約する方向に進化しやすく、結果的に繭内の蛹が外から見えそうになります。繭内の蛹の色はもともと茶色や茶褐色系が主流ですが、葉や糸を節約するにつれ蛹の色が緑色になり、ついにドクガ科やシャクガ科で、繭に包まれていない緑色の裸蛹が見られます。繭については後でもう少しお話しします。










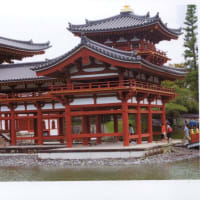
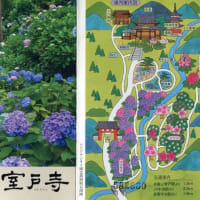








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます