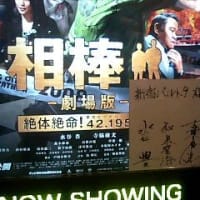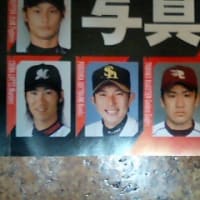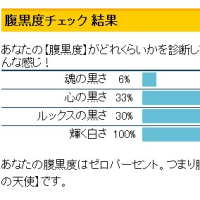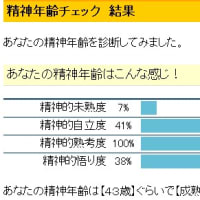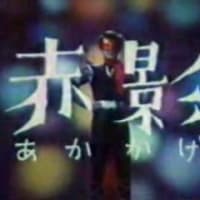これまたちょっと前の話になるのですが、6月末を迎えると、会社案内をリニューアルするところも多いのではないかと。
株主総会で役員の顔ぶれが変わると、会社案内には役員の紹介欄があったりしますから(別シートにしてるところもあるでしょうが)、これを機に、ということで。
株主総会で役員の顔ぶれが変わると、会社案内には役員の紹介欄があったりしますから(別シートにしてるところもあるでしょうが)、これを機に、ということで。
で、今年に関しては、組織図も変えようかという話が出ました。
組織体系そのものは変わっていないんだけども、図の表現の仕方を変えようと。いわゆる逆ピラミッド型にです。
通常
株主総会――取締役会-社長-○○本部×n-・・・
|
組織体系そのものは変わっていないんだけども、図の表現の仕方を変えようと。いわゆる逆ピラミッド型にです。
通常
株主総会――取締役会-社長-○○本部×n-・・・
|
監査役、監査役会
逆ピラ型
お客様-○○支店×n-○○本部×n-社長-取締役会
縦書きにしないとニュアンスが伝えにくいのですが、顧客を一番上に持ってきて、その次が直に顧客に接する部署、ついでその部署を管轄する部署...ときて、最後が社長(取締役会)という図になります。で、ボリューム的には顧客のゾーンが一番大きく、社長は通常一人だから小さくなる、よって逆ピラミッド型に描かれるというわけです。
顧客満足の姿勢を表す概念ということではあるんですが、微妙に付加すべきポイントがあったりします。
すべての階層に顧客を設定するということで、例えば社長にとっての「顧客」は専務か常務、常務にとっての顧客は部長・課長、ついで顧客に近い一般社員となる。これらの「顧客」の概念を「内部顧客」といって、いわゆる顧客満足を達成するためには、本当の顧客に接する一般社員への支援と貢献にかかってくる、そしてその支援と貢献はその上司のバックアップにかかってくる・・・という考え方です。
顧客満足の姿勢を表す概念ということではあるんですが、微妙に付加すべきポイントがあったりします。
すべての階層に顧客を設定するということで、例えば社長にとっての「顧客」は専務か常務、常務にとっての顧客は部長・課長、ついで顧客に近い一般社員となる。これらの「顧客」の概念を「内部顧客」といって、いわゆる顧客満足を達成するためには、本当の顧客に接する一般社員への支援と貢献にかかってくる、そしてその支援と貢献はその上司のバックアップにかかってくる・・・という考え方です。
これは海外生まれの概念ですが、既にいくつかの国内でも正式な組織図として取り入れている会社が見受けられます。で、当社もそれにならおうという話があったということなんですね。
結局、今回はお流れになったのですが、従来の一般的な図と比べてお気づきの点があるかと思います。
結局、今回はお流れになったのですが、従来の一般的な図と比べてお気づきの点があるかと思います。
株主(総会)の存在をどこに持ってくるか。
この逆ピラ志向は、内部顧客の概念を取り入れることによって、ノーム(規範)をアップさせる効果があるとされ、実際に利益を上げた事例が報告されており、会社にはプラスの話。
一方、会社は株主のものというトレンドからすると、欄外というのはいかがなものかと。<o:p></o:p>
一方、会社は株主のものというトレンドからすると、欄外というのはいかがなものかと。<o:p></o:p>
組織図ひとつとっても、会社をどういう風に捉えるかの考え方が問われるというシチュエーションなんでありますね。
さて。
今週の『日経ビジネス』には、格差社会の話が特集されてまして、その中で「日本の資本主義は資本原理主義になりつつある」みたいな記述がありました。
その過程で、正社員と非正社員の格差が広がっていると(シャープ亀山工場の例)。一方、株式を非公開化したワールドさんでは、非正社員を正社員化する動きが見られると。
自分らはバランスとってるつもりなのかもしれませんが、どうも日経グループは中国進出とか、構造改革路線とか、ある流れを煽っておいて、後にひっくり返すパターンが多いように思うのですが、最近彼らが推す流れは、人材を大事にする会社こそ伸びるという路線ですね。
さてさて。
組織図で株主を一番上に持ってきたところで、あるいは株主重視経営を唱えたところで、業績が上がらなければ株主は損するという当然の理屈があるわけで、そしてそれを達成するための手段は何かという、これまた当然の理屈があるわけで。
組織図の表記くらいどっちでもいいという話はあれど、この辺は経営者の姿勢、出てると思いますよ。
表記をチェックして、両者の業績を中期的にヲチできればいいかなと思うのですが、当方に出来るわけも無く。。
今の昭和経営陣が去ったときに提案してみようかなと思う次第。そのときまで覚えていれば、ですが。