
全国の大学経営者にキャンパス改革の方向性をコンサルティングしている、桜美林大学大学院教授の諸星裕さんが説いた、本格的な淘汰の時代に入った日本の大学が、生き残るために求められているものは一体何かという一冊という書き方をすれば格好がつくでしょうか。新書というのは罪なタイトルをつけます。どの新書も似たり寄ったりのデザインですから裏腹にタイトルが過激になるのでしょうか。車内の週刊誌の広告かと思うほどです。ちょっとびっくりして手に取ってしまいますね。
ともあれ、こういうタイトルを見かけるとまず心配になるのは自分の母校はどうなんだろう、大丈夫かということ。読み手によっては、「我が息子が通っている大学はどうなんだろう」と心配になるかも知れません。なにしろ2010年時点で日本には778校の大学があるそうえですから、もしかしたら駅弁の数よりも 多いかも知れません(なんぼなんでも駅弁の数のほうが多いやろ!)。
現在の日本での大学の生き残りの時代よりも前、アメリカでは1970年代後半に「大学のユニバーサル化」(大学全入)がやってきたそうです。その時代に改革できた大学は生き残り、そうでない大学は生き残れなかった。すでに彼の国では経験済なのですね。
筆者が大切だというものに「ミッション」があります。学生に提供できる「大学の価値」を各大学が独自に定義したもの、それを「ミッション」と呼ぶのだそうです。最も大切なことは、大学に入学してくる者、学生が大学教育の中でいかに成長できるか、どういった人間になって社会に出て行けるかということであり、 そのために大学は何ができるかを明言できなければならない。
筆者はこれからの日本に必要な大学として三つのパターンに分類してい ます。一つ目は世界レベルの研究大学。二つ目は本当の意味での教養人を養成する大学、そして、三つ目は一生懸命学生を鍛えて社会に役立つ人材を育てることを意識した大学であり、それこそが大学全入時代を意識した大学だというわけです。それに関連して、大学教員が研究者ばかりである必要はない、むしろ博士号よりも教育者としての教員も必要だといい、このあたりの論点は実にすっきりしています。
これから大学を選ぼうとする高校生に、また、その保護者にも、大学とは何かを考える上の参考書にしていただきたい一冊。さらに、この時代に、生き残る大学とはどんな大学かという観点から、大人にはビジネス指南書としても読んでみてほしい一冊です。
はじめに-日本の大学の致命的欠陥
第一章 崩れ始めた日本の「大学ビジネス」
第二章 教育力は再生するか?-脱「旧帝大モデル」という活路
第三章 タイプ別・日本の大学それぞれの「いま」
第四章 受験生はなぜ「大学選び」を誤るのか?
第五章 大学から日本がよみがえる
おわりに-EU「ボローニャ宣言」が示した大学の未来










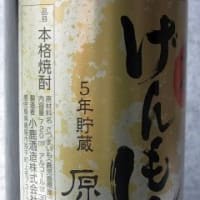


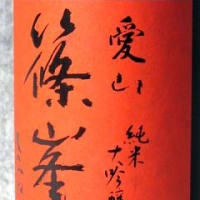
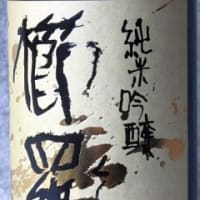





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます