◆朝日新聞記事「私が私であるために―ベルギーの精神医療改革―」(2.26~2.28付)と言う記事が掲載されました。
ベルギーは日本と同様、精神医療を多くの民間病院が支えており、本人中心の理念をもとに地域医療へと軸足を移し、長期の入院を減らそうと取組みを強化しています。
その取り組みについて掲載されていましたのでまとめてみました。
**前号より*************************************
3.ベルギーの精神医療改革を日本でも生かせるか?専門家は・・
◯医療、福祉、就労など支援の要素が機能する仕組みつくりを!・・・
・精神科医療、障害福祉、就労支援、住宅紹介など様々な領域の要素を最適に組合せ、機能させる「仕組み」があることがベルギーの優れた点だ。
日本にも各要素は既にあるが、精神疾患を有する本人を中心に据えて、連携して一体的に機能する仕組みが追いついていない。
ベルギーのネットワークに近いものとして、国が進める「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」が考えられる。精神疾患を有する本人が地域で自分らしく暮らせるように、医療、福祉、就労など様々な領域を統合して支援しようとするものだが、ただ、連携していても、紹介先に全てを任せてしまいがちで、継続的な取組が乏しく、協議の場が位置づけられているが、責任者の位置づけも不明瞭だ。日本でも責任者を明確にして圏域内で統合した支援が完結する仕組みに改善することが必要だ。
・そして、生活全般を支えるには、診療報酬に基づく医療と、障害者総合支援法に基づく福祉の連携が必要。入院と同程度に、地域に出向く訪問型に手厚い診療報酬つけるなど報酬のあり方も仕組作りの大事な要素だ。ベルギーでは予算化をして取組んでいる。
精神病床の規模に依存せず、地域で暮らすための本人のニーズに基づいた支援を提供する地域ケア、これが世界の潮流であり、あるべき姿といえる。みんな頭では分かっている。
必要なのは、近未来のニーズに合わせた仕組作りを再構築することだ。
ベルギーは精神科病院の規模を縮小し、本人中心の仕組により入院期間を可能な限り短縮し「たまに入院ほぼ在宅」を実現してきた。日本でもできないことはない。あと一歩踏み込めるかどうか、それが問われている最終局面が今である。
****次号に続く*******************************

ベルギーは日本と同様、精神医療を多くの民間病院が支えており、本人中心の理念をもとに地域医療へと軸足を移し、長期の入院を減らそうと取組みを強化しています。
その取り組みについて掲載されていましたのでまとめてみました。
**前号より*************************************
3.ベルギーの精神医療改革を日本でも生かせるか?専門家は・・
◯医療、福祉、就労など支援の要素が機能する仕組みつくりを!・・・
・精神科医療、障害福祉、就労支援、住宅紹介など様々な領域の要素を最適に組合せ、機能させる「仕組み」があることがベルギーの優れた点だ。
日本にも各要素は既にあるが、精神疾患を有する本人を中心に据えて、連携して一体的に機能する仕組みが追いついていない。
ベルギーのネットワークに近いものとして、国が進める「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」が考えられる。精神疾患を有する本人が地域で自分らしく暮らせるように、医療、福祉、就労など様々な領域を統合して支援しようとするものだが、ただ、連携していても、紹介先に全てを任せてしまいがちで、継続的な取組が乏しく、協議の場が位置づけられているが、責任者の位置づけも不明瞭だ。日本でも責任者を明確にして圏域内で統合した支援が完結する仕組みに改善することが必要だ。
・そして、生活全般を支えるには、診療報酬に基づく医療と、障害者総合支援法に基づく福祉の連携が必要。入院と同程度に、地域に出向く訪問型に手厚い診療報酬つけるなど報酬のあり方も仕組作りの大事な要素だ。ベルギーでは予算化をして取組んでいる。
精神病床の規模に依存せず、地域で暮らすための本人のニーズに基づいた支援を提供する地域ケア、これが世界の潮流であり、あるべき姿といえる。みんな頭では分かっている。
必要なのは、近未来のニーズに合わせた仕組作りを再構築することだ。
ベルギーは精神科病院の規模を縮小し、本人中心の仕組により入院期間を可能な限り短縮し「たまに入院ほぼ在宅」を実現してきた。日本でもできないことはない。あと一歩踏み込めるかどうか、それが問われている最終局面が今である。
****次号に続く*******************************
















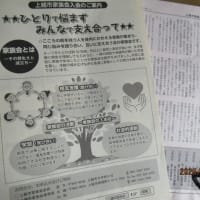


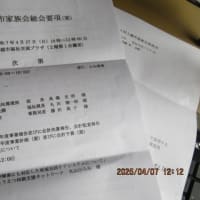

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます