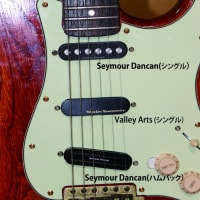金田式No_218と比較してみると、どうも、中高域が伸びていない感じがする。
WE球を使ったSRPPのプリアンプというのはあまり聞かないので、向いてないのかも
しれない。または、供給電圧を120Vとやや低めにしているので、プレート電流が
1mAほどしか流れていないせいかも知れない。
そこで、急遽、SRPPでは定番の6DJ8に替えてみることにした。WE407はヒーター電圧が20V
なので、ちょっと定電圧回路をいじらなくてはならない。LM317Tを使っていたが、面倒なので
12Vの三端子REGを使うことにした。6DJ8とはソケットのピンの配列が違うので、結局
ソケット周りは全てやり直しになるので、午後の時間いっぱいかかってしまった。
10年くらい前にさんざんSRPPは試したので、10本くらいはまだ手元に残っていた。
Sovtek製の6922を10本近く持っていたが、残っていなかった。「手づくりの会」のときに
提供したのかも知れない。
残っていたのは、
・シルバニア製が2本。(うち1本はノイズが出て使えず)
・東芝製(通測用)が5本
・ムラード製が3本
・ヒューレット・パッカード製が 1本 (1本は、空気が入ってしまってダメになった)
聴き比べてみた感じでは、ヒューレット・パッカード製は東芝製とペアで聴いてみたが、
音の雰囲気が違い、左右の音が違ってしまった。どちらがいいのか判断がつかず。
クリアな感じは ムラード製。
東芝は、昔はいいように感じていたが、中庸といったところか。
やっぱり、金田式No_218と比べると 中高域の切れでは負けるか。
ただし、ピアノ音などは、鍵盤をころがる音が コロコロとしていて気持ちがいい。
Fusion系のJAZZのベースとバスドラムは、やっぱり音が膨らむようだ。
ここを締めるには、B電源を安定化する必要があるのかも。それか
後段にカソード・フォロアー的な回路を追加するのも関係があるかも知れない。
ちなみにB電圧は202Vで、プレート電流は、設計値に近く 約5mA。
B電源を安定化するための 高圧用の石を持ってないので、安定化電源の構想は
しばらくお預けだ。