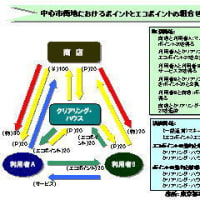「日本企業は何を目指すべきか」について、拙著『安心革命』(2003)は以下のように続けています。
業績の成長著しい企業には、共通する2つの本質的なカギがあります。ひとつは「経営者の能力や資質」、もうひとつは「市場創造」です。このことについては、経済産業研究所の新原浩朗上席研究員が「優秀企業ベスト経営者の能力」(文芸春秋2002年9月号)で正鵠を射た分析を行っています。新原上席研究員は、過去15年にわたる企業の収益性(総資本経常利益率)、安全性(自己資本比率)、成長性(経常利益額の推移)を分析し、そのうちの30~40社について経営トップにヒアリングを行いました。その対象は、ざっと挙げるだけも、トヨタ自動車の張富士夫社長、キャノンの御手洗冨士夫社長、花王の後藤卓也社長、マブチモーターの馬渕隆一社長、信越化学の金川千尋社長、ヤマト運輸の小倉昌男元会長、シマノの島野容三社長と錚々たる顔ぶれの経営者たちです。
すると、企業のせ経営トップの能力が非常に重要なファクターであることがはっきりしてきました。その能力とは、次のようなものです。
①自分たちが取り組む事業の範囲を明確に把握している。
②経営トップが論理的に考えに考え抜いている。
③トップの多くは、そのキャリアのなかに“傍流”であった時代がある。
④危機をチャンスに転化する能力を有している。
⑤身の丈にあった成長を図り、事業リスクを直視している。
⑥持続性のある規律の文化を企業に埋め込んでいる。
一言でまとめると、自らが考えた事業を、手を広げすぎずに、愚直にまじめに考え抜き、事業に情熱を持って取り組んでいる経営トップということができるでしょう。これは、まさにジェームズ・コリンズとジェリー・ポラスの著書『ビジョナリー・カンパニー』で挙げた四つの特性と符合しています。『ビジョナリー・カンパニー』は、日本でもベストセラーになった本であり、いまでも多くの日本の経営者の座右の銘になっています。
「ビジョンを有する企業」の特性を、コリンズとポラスは次のようにまとめています。
①組織の卓抜性――通常想定されているように、新製品を案出することに長けた才能、戦略的洞察力、個性の力に傾注するよりも、卓抜した組織をつくり、それを維持し、そして更新することに注力している。
②コアとなるイデオロギー――イデオロギーとしては、顧客サービスへの献身、技術の最先端であることのコミットメント、個々の社員への尊敬、イノベーションの創造などがある。重要なのはイデオロギーの正しさではなく、むしろ企業信念の強さである。
③進歩に対するあくなき意欲――現状に満足しないことが重要であり、新たな技術、戦略、製品の改善に絶えず取り組み、実験をしていること、さらにより良くしようとする意欲が大きな役割を果たしている。
④連携する組織――従業員、ナレッジワーカー、そしてサプライヤーや提携企業とつねに連携しながら価値を創造する。
これらの4つの「ビジョナリー・カンパニー」になるための特性は、いわば普遍的なものであると考えることができます。不確実性が増大する二一世紀の環境の下では、これらの特性の妥当性がますます増しているといっても過言ではありません。なぜなら、企業はあたかも生命のように「進化」しなければならず、4つの特性はそのための必要十分条件になっているといえるからです。
「進化」する生命の本質は、安定しているが変化し、変化するが安定しているという矛盾に満ちたダイナミズムを抱えているところにあります。この本質を言い当てているのが、いわゆる「赤の女王」仮説です。
「赤の女王」はルイス・キャロルの童話『不思議の国のアリス』のなかに登場するキャラクターです。女王は次のようにいいます。「ここではのう、同じ場所にいようと思ったら、あらう限りの速さで走ることが必要なのじゃ」と。つまり、同じ場所にとどまるために全力で走らなければならない、というのです。「赤の女王」仮説は、「進化」していくための戦略とは、それに参加しているすべてのプレーヤーが全速力で自らを変化させている、という意味です。この仮説は、不確実性が増大する企業においても通用するのです。
かつてハーバード大学のマイケル・ポーター教授は「日本企業にはオペレーションがあるだけで、戦略がない」と酷評しましたが、ポーターのいう「戦略」とは、つねに競争相手に対して“相対的な優位”を保ち続けることを念頭においたものでした。しかし、不確実性が増大する二一世紀の経済環境では、競争相手に対してつねに相対的優位を保つことなど不可能です。競争相手に対するアドバンテージは、相手の裏をかく方法では勝ちとれないからです。したがって、ポーターのいう「戦略」そのものの内容が見直されなければならなくなっているといえます。
業績の成長著しい企業には、共通する2つの本質的なカギがあります。ひとつは「経営者の能力や資質」、もうひとつは「市場創造」です。このことについては、経済産業研究所の新原浩朗上席研究員が「優秀企業ベスト経営者の能力」(文芸春秋2002年9月号)で正鵠を射た分析を行っています。新原上席研究員は、過去15年にわたる企業の収益性(総資本経常利益率)、安全性(自己資本比率)、成長性(経常利益額の推移)を分析し、そのうちの30~40社について経営トップにヒアリングを行いました。その対象は、ざっと挙げるだけも、トヨタ自動車の張富士夫社長、キャノンの御手洗冨士夫社長、花王の後藤卓也社長、マブチモーターの馬渕隆一社長、信越化学の金川千尋社長、ヤマト運輸の小倉昌男元会長、シマノの島野容三社長と錚々たる顔ぶれの経営者たちです。
すると、企業のせ経営トップの能力が非常に重要なファクターであることがはっきりしてきました。その能力とは、次のようなものです。
①自分たちが取り組む事業の範囲を明確に把握している。
②経営トップが論理的に考えに考え抜いている。
③トップの多くは、そのキャリアのなかに“傍流”であった時代がある。
④危機をチャンスに転化する能力を有している。
⑤身の丈にあった成長を図り、事業リスクを直視している。
⑥持続性のある規律の文化を企業に埋め込んでいる。
一言でまとめると、自らが考えた事業を、手を広げすぎずに、愚直にまじめに考え抜き、事業に情熱を持って取り組んでいる経営トップということができるでしょう。これは、まさにジェームズ・コリンズとジェリー・ポラスの著書『ビジョナリー・カンパニー』で挙げた四つの特性と符合しています。『ビジョナリー・カンパニー』は、日本でもベストセラーになった本であり、いまでも多くの日本の経営者の座右の銘になっています。
「ビジョンを有する企業」の特性を、コリンズとポラスは次のようにまとめています。
①組織の卓抜性――通常想定されているように、新製品を案出することに長けた才能、戦略的洞察力、個性の力に傾注するよりも、卓抜した組織をつくり、それを維持し、そして更新することに注力している。
②コアとなるイデオロギー――イデオロギーとしては、顧客サービスへの献身、技術の最先端であることのコミットメント、個々の社員への尊敬、イノベーションの創造などがある。重要なのはイデオロギーの正しさではなく、むしろ企業信念の強さである。
③進歩に対するあくなき意欲――現状に満足しないことが重要であり、新たな技術、戦略、製品の改善に絶えず取り組み、実験をしていること、さらにより良くしようとする意欲が大きな役割を果たしている。
④連携する組織――従業員、ナレッジワーカー、そしてサプライヤーや提携企業とつねに連携しながら価値を創造する。
これらの4つの「ビジョナリー・カンパニー」になるための特性は、いわば普遍的なものであると考えることができます。不確実性が増大する二一世紀の環境の下では、これらの特性の妥当性がますます増しているといっても過言ではありません。なぜなら、企業はあたかも生命のように「進化」しなければならず、4つの特性はそのための必要十分条件になっているといえるからです。
「進化」する生命の本質は、安定しているが変化し、変化するが安定しているという矛盾に満ちたダイナミズムを抱えているところにあります。この本質を言い当てているのが、いわゆる「赤の女王」仮説です。
「赤の女王」はルイス・キャロルの童話『不思議の国のアリス』のなかに登場するキャラクターです。女王は次のようにいいます。「ここではのう、同じ場所にいようと思ったら、あらう限りの速さで走ることが必要なのじゃ」と。つまり、同じ場所にとどまるために全力で走らなければならない、というのです。「赤の女王」仮説は、「進化」していくための戦略とは、それに参加しているすべてのプレーヤーが全速力で自らを変化させている、という意味です。この仮説は、不確実性が増大する企業においても通用するのです。
かつてハーバード大学のマイケル・ポーター教授は「日本企業にはオペレーションがあるだけで、戦略がない」と酷評しましたが、ポーターのいう「戦略」とは、つねに競争相手に対して“相対的な優位”を保ち続けることを念頭においたものでした。しかし、不確実性が増大する二一世紀の経済環境では、競争相手に対してつねに相対的優位を保つことなど不可能です。競争相手に対するアドバンテージは、相手の裏をかく方法では勝ちとれないからです。したがって、ポーターのいう「戦略」そのものの内容が見直されなければならなくなっているといえます。