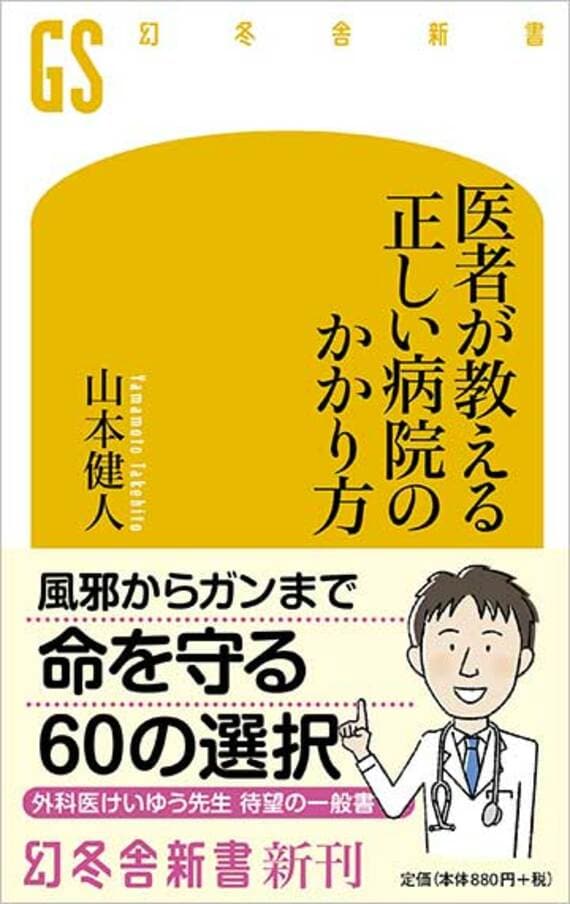近赤外線を照射する臨床現場でのアルミノックス治療の様子。提供:楽天メディカル
近赤外線を照射する臨床現場でのアルミノックス治療の様子。提供:楽天メディカル
頭頸部がん「アルミノックス治療(光免疫療法)」臨床現場で実際の治療にあたる医師にその効果を聞く
米国の国立衛生研究所(NIH)の日本人研究者、小林久隆氏によって開発されたアルミノックス治療(光免疫療法)は、
従来にはなかった全く新しいがん治療技術だ。
現状、治療対象は限定されているが、実際に臨床現場で頭頸部アルミノックス治療を行っている医師にその効果を聞いた。
アルミノックス治療とは
がんの治療法には大きく外科的な手術、抗がん剤、放射線、免疫療法などがあるが、いずれもがんだけでなく
健康な細胞や臓器にも悪影響をおよぼすなどの副作用が出ることが多い。
アルミノックス治療が、最初に学術誌に発表されたのは2011年のことだ。
すると、翌年にはオバマ米元大統領が一般教書演説で言及するなど、新たながん治療法として注目を集め始め、
健康な細胞をほとんど傷つけることなく、がん細胞だけを破壊することができる治療効果の高い治療法として期待されている。
アルミノックス治療では、特定の細胞に選択的に結合し、光に反応する薬剤の投与と、
特定の波長の光照射の組み合わせによって、がんの腫瘍細胞を選択的に死滅させる。
がん細胞の表面には、他の正常な細胞には少ない抗原(がん抗原タンパク質)があり、がん抗原と結合する抗体にIR700という光感受性物質をくっつけ、
それを点滴で患者へ静脈投与する。すると、抗体とIR700の結合体が、がん細胞に結合し、そこに光ファイバーで近赤外線を数分間、照射する。
光感受性物質が光に反応して結合している抗体の形を変え、それによってがん細胞の表面に物理的に穴を開ける。
こうした現象が、がん細胞の表面で無数に起き、がん細胞がみるみるうちに破壊されていくのだという。
アルミノックス治療では、2020年9月に使用薬剤(アキャルックス点滴静注250ミリグラム)の製造販売とレーザー光照射装置による
頭頸部がんへの治療法が承認され、2021年1月から耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域で保険診療が始まっている。
また、2023年11月からは歯科口腔外科領域でも治療が開始された。
先日、都内で頭頸部アルミノックス治療の提供開始3周年を記念した講演会が開かれた。国内外から300人以上の臨床医や研究者が集まり、
同治療法の成果について発表が相次いだ。
頭頸部がんの限定した治療が対象
では、実際の臨床現場で、頭頸部アルミノックス治療はどのような効果があるのだろうか。
広島大学大学院医学系科学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科の上田勉氏に話をうかがった。
──上田先生が最初にアルミノックス治療について知ったのはいつでしたか。
上田「小林久隆先生が2019年11月26日に、広島大学でご講演されたんです。
そのとき、初めて知りましたが、それまでは全く知りませんでした」
──小林先生のご講演を聴いてどのように思われましたか。
上田「光を組み合わせるアイディアは確かに理にかなっていますし、これはいい治療法だなと思いました。
ただ、その頃はまだ臨床試験の段階でしたから、うちの大学でもできるようになったらぜひやってみたいと思いました」
──いつ頃から治療を始められましたか。
上田「うちは日本で最初に手を上げた20施設に入っています。2021年から始めました」
──実際に治療を始めてみてどうでしたか。
上田「始めた頃には全国からたくさんのお問い合わせがありました。現状の頭頸部アルミノックス治療は、頭頸部がんで切除ができない局所進行性、
または局所再発の場合に限って使用が認められています。
手術で完全切除ができず、標準治療として放射線治療などをすでに受けている患者さんが対象になります。
頭頸部がんでは肺へ遠隔転移することがありますが、遠隔転移があり、全身療法が必要な患者さんには原則使えません」
──頭頸部がんに限定されているというわけですね。
上田「頭頸部がんは、口、鼻、副鼻腔、咽頭・喉頭、唾液腺、甲状腺など、首(鎖骨)から上で、脳と眼を除く臓器に発生するがんです。
現在、この治療のターゲットは、あくまで頭頸部がんであり、頭頸部の局所にできた切除不能ながん、あるいは頭頸部に再発したがんが治療対象になります」
──頭頸部がんのステージ(病期)は関係ありますか。
上田「がんのステージというのは診断がついた最初の評価で、がんが進行してステージが上がるわけではありません。
頭頸部アルミノックス治療は、どのステージの頭頸部がんでも切除不能の局所、あるいは頭頸部に再発したがんで治療対象になります」
──頭頸部に再発した場合、すぐにアルミノックス治療を受けられるんでしょうか。
上田「再発した場合、普通は切除手術ができないかを検討します。切除できない場合は薬物療法を試してみます。
化学療法や免疫チェックポイント阻害剤、分子標的薬など、いろんな治療法がありますから、それらを単独あるいは組み合わせて試してみて、
それでもダメな場合、頭頸部アルミノックス治療を始めます」
──再発してもすぐに受けられるわけではないということでしょうか。
上田「頭頸部で切除手術をした場合、大切な部位を取ってしまい、たとえ治療できても患者さんのQOLを下げてしまう危険性があります。
なので、できるだけ切除手術で広い範囲の部位を取ってしまいたくはありません。
ただ、先ほど言ったように、現状では、標準治療を差し置いてはできません」
次第に広げられつつある適用範囲
──光免疫療法が最後の手段ということになりますか。
上田「放射線は1回しかできませんから、一度使ったらもう次は使えません。
お薬での治療は、先ほど述べた通り、何種類もあるのでそれを使っていきますが、効かなくなったら変えていくとだんだん手数が減っていきます。
最終的には治療法がなくなってしまい、今後は緩和治療を中心にという話になっていました。頭頸部アルミノックス治療は、こ
の緩和治療の前に入ってきたというわけで、どんな治療法もなかった患者さんにとってはまさに希望の光のような存在なのかもしれません」
──アルミノックス治療は、魔法の杖ではないということでしょうか。
上田「私自身の実感としては、アルミノックス治療の効果はかなりあると思っています。
しかし、対象群と比較して治療効果はどれくらいというような医学的な研究は倫理的にもできないでしょう。
なので今後、実臨床の現場で少しずつ治療の成果を積み上げていくことが重要と考えています。
ただ、これまで全国で知見が蓄積されてきたことから、頭頸部アルミノックス治療の適用を少しずつ広げる方向へ向かっているのも事実です」
──適用を広げる方向というのはどういう意味でしょうか。
上田「対象となる患者さんは多くはないと思いますが、頭頸部がんの患者さんのQOLを重視した上でのケースです。
例えば、舌がんで口の中がもう腫瘍でいっぱいになるくらい大きくなって切除手術もできず、
長くかかる化学療法では患者さんのQOLに大きなダメージがおよぶ場合、化学療法の前にアルミノックス治療をやってもいいのでは、
というような適用の拡大もあり得るのではないかということです」
治療実績とその効果
──これまで何例くらい頭頸部アルミノックス治療の実績がありますか。
上田「うちではこれまで14例です(2024年4月現在)。頭頸部がんの種類としては、口腔がん、咽頭がん、喉頭がん、舌がん、副鼻腔がんなどです。
これらのがんに対して、手術などした後再発し、それらに対してさらに手術や化学療法をした後再発された患者さんです」
──14例の内訳はどのようになりますか。
上田「男性が10例、女性4例です。CR(Complete response、完全寛解)7症例、PR(Partial response、部分寛解)3症例、
SD(Stable disease、安定)2例、PD(Progressive Disease、進行)2例です」
──この治療の効果をどのように評価されますか。
上田「アルミノックス治療をすれば、がんの腫瘍は確かに小さくなります。消えてしまう患者さんもいます。
当科の傾向としては、小さながんは消えやすく、大きながんは小さくはなるが消えるまではいかないようです」
──かなり劇的な効果があるというわけですね。
上田「もちろん、中には、期待する結果にならなかった患者さんもいらっしゃいます。ただ、頭頸部アルミノックス治療をすることで、
生存期間を延ばすことはできているのだと思います。
逆に、腫瘍が小さくなったり、消失することによる弊害もあって、例えば頬に腫瘍がある場合、光免疫療法で腫瘍がなくなると頬にぽっかり穴が開いてしまい、
患者さんのQOLを下げてしまうわけです。この治療を始めた当初は一気にやってしまおうという考え方でしたけれど、
4回までアルミノックス治療を繰り返せますから、一気にやって腫瘍のサイズが小さくなったり消失したりしてQOLを下げないように、
1回ずつ様子をみながら段階的に治療をし、頬の肉がなくならないようにやるといったことも始めています」
──4回しかできないんですか。
上田「頭頸部アルミノックス治療の今の適用ですと4回までです。
3回やって腫瘍がなくなったので、残りの1回を取っておいて治療を中断している患者さんもいらっしゃいます。
ただ、5回目以上についていくつかの施設で臨床試験をやっていまして、広島大学もその一つです。ですから、臨床試験の結果、効果があるとわかり、
何か新たな有害事象がなければ、5回目以上の治療についても今後、可能になっていくと思います。
また、何回でもできるということになれば、他の治療法と組み合わせながら、少しずつアルミノックス治療をやっていくというように治療戦略も変わっていくでしょう」
痛み、浮腫などの副作用が
──副作用などについてはどうでしょうか。
上田「治療中や治療後、治療当日と翌日に痛みをうったえる患者さんが多いです。
全身麻酔をかけて治療するんですが、麻酔をかけていても身体は痛みに反応しますから血圧が上がったりします。
光に反応して腫瘍がなくなっていく段階で、こうした痛みが出るのだと思います」
──痛みというのはわかりにくい訴えですよね。
上田「あまりに痛いので、もうやりたくないという患者さんもいます。
ただ今では局所鎮痛剤の投与など、痛みをあまり感じないように工夫もしています」
──痛み以外の副作用はどうでしょうか。
上田「治療部位にもよりますが、喉頭や咽頭に浮腫を生じ、気道をふさいでしまうことがよくあります。
そのため、あらかじめ呼吸ができるように気管切開をすることもあります。
頭頸部アルミノックス治療による治療が始まって3年ほどが経ち、治療戦略、副作用対策などが次第にはっきりしてきたと思います」
──光感受性物質による影響はどうでしょうか。
上田「最初の頃は、光曝露対策をしっかりやらなければということで、患者さんに常時、光が当たらないように細心の注意を払っていましたが、
今ではそこまでしなくてもいいことがわかってきました。
光に対する感受性テストをして、それで大丈夫なら退院となるのですが、入院中でも室内で読書する程度の明るさなら全く問題ありません。
ただし、屋外で紫外線を浴びたり、室内でも赤外線ストーブにあたるなどは危険です」
──上田先生のところでは、頭頸部がんの患者さんはどのような方が多いんですか。
上田「男女比でいうと男性が多いです。喫煙と飲酒の影響だと思います。年代は50代から80代までが多いです。
また最近になって、ヒトパピローマウイルスの感染による中咽頭がんの患者さんが増えています。HPVワクチンは男性も女性もうったほうがいいと思います」
臨床の現場で頭頸部がんの治療にアルミアルミノックス治療を使ってきた上田氏は、その高い治療効果についてこう実感を持って話してくれた。
使われ始めて3年ほどが経ち、次第に効果的な治療法が模索され、副作用対策などが講じられてきたことでアルミノックス治療の可能性が広がりつつある。
現在、全国の多くの医療機関で、頭頸部アルミノックス治療による治療が受けられるようになってきている。
そして、この治療法に対する期待の高まりとともに、治療できる医療機関は増えていくだろう。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
上田勉(うえだ・つとむ)
1994年、広島大学医学部医学科卒業後、広島大学病院耳鼻咽喉科から国立呉病院耳鼻咽喉科を経て、
広島大学大学院医学系研究科博士課程外科系専攻へ進み、2003年に修了。
2010年に広島大学医学部附属病院耳鼻咽喉科・頭頸部外科助教から同講師、2018年より同准教授。
また、2018年に英国のUniversity of Birminghamへ留学。医学博士。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
※ Yahooニュース・エキスパート 2024年7月12日 配信記事より記事より記事より記事より転載
著者:石田雅彦(科学ジャーナリスト)
 胃がんの周囲にICGを注射すると、このようにリンパ節への流れを観察できます。
胃がんの周囲にICGを注射すると、このようにリンパ節への流れを観察できます。