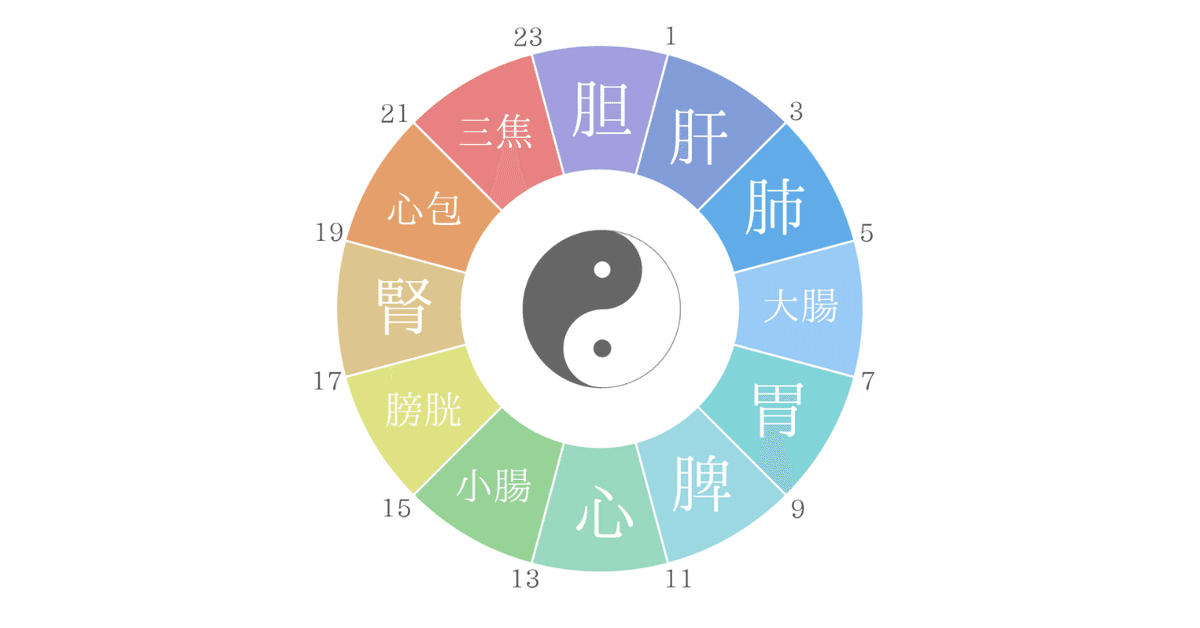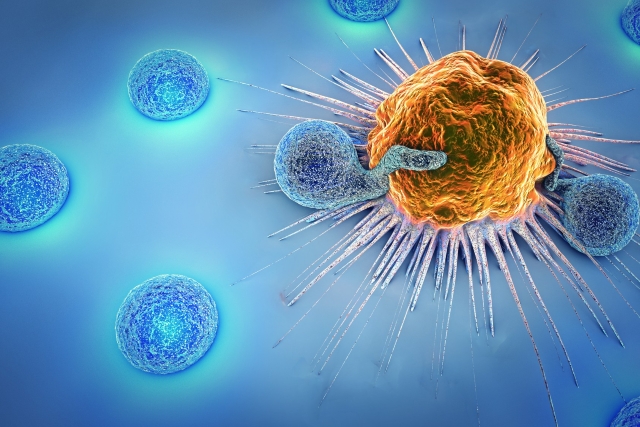 「Medical DOC」より転用
「Medical DOC」より転用
「免疫力を高めてがんを予防」という言葉を耳にすることはありますが、じつはこれは大きな誤解をまねく表現です。
がん患者の免疫は普通に働いているのに、なぜがんは倒せないのか? その理由は、がん細胞が免疫に「賄賂」を渡して逃げているからであるとのことです。
ノーベル賞受賞で注目された免疫チェックポイント阻害薬から、最新のがん免疫療法について、
米国アラバマ大学バーミンガム校脳神経外科助教授の大須賀覚先生にわかりやすく解説していただきました。
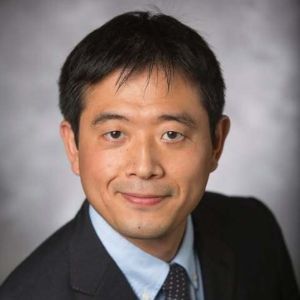 </picture>
</picture>監修医師:
大須賀 覚(米国アラバマ大学バーミンガム校 脳神経外科助教授)
風邪予防の「免疫」と「がん免疫」との違い
〔編集部〕
免疫という言葉がヨーグルトや風邪予防など、幅広く使われています。医療現場での免疫療法とはどう違うのでしょうか?
〔大須賀先生〕
一般の方が考える免疫とがんの免疫療法は、じつはかなり違います。
多くの人は「免疫細胞を強くすれば、がん細胞を倒せる」と考えがちですが、実際はそんな単純な話ではありません。
がんは体の中で発生するもので、もともと自分の細胞がおかしくなってできたものです。
私はよく「グレていくギャング」に例えるのですが、青年(普通の細胞)がだんだんグレて、最終的にギャングのようになっていくのががんの発生過程です。
免疫はそのギャングを捕まえる“警察”にあたるものです。
〔編集部〕
では、警察である免疫の力が下がるとがんになりやすいということでしょうか?
〔大須賀先生〕
一般の方が考える免疫とがんの免疫療法は、じつはかなり違います。
多くの人は「免疫細胞を強くすれば、がん細胞を倒せる」と考えがちですが、実際はそんな単純な話ではありません。
がんは体の中で発生するもので、もともと自分の細胞がおかしくなってできたものです。
私はよく「グレていくギャング」に例えるのですが、青年(普通の細胞)がだんだんグレて、最終的にギャングのようになっていくのががんの発生過程です。
免疫はそのギャングを捕まえる“警察”にあたるものです。
〔編集部〕
では、警察である免疫の力が下がるとがんになりやすいということでしょうか?
〔大須賀先生〕
マウスの実験で免疫をなくすとがんの発生率が上がることは確認されています。つまり、免疫は日常的に異常な細胞を排除してくれていて、がんができるのを防いでいます。
ただ、がんができてからの治療ということだと、話は変わってきます。最終的にがんになるのは、がん細胞が免疫から逃れる術を獲得したからです。
警察の取り締まりを防ぐ「賄賂」を渡す能力を獲得できた者だけが、最終的にギャングになれる。賄賂を渡せなかった者は途中で捕まってしまうわけです。
〔編集部〕
がん患者さんの免疫は弱っているわけではないのですか?
〔大須賀先生〕
そこが重要なポイントです。がん患者さんも風邪をひけば治りますし、インフルエンザになっても回復します。
がんがあることで弱くなることはありますが、基本的には細菌やウイルスへの免疫自体はちゃんと機能しているのです。
免疫がなくなったわけではなく、がん細胞が逃れる術を獲得しているから倒せない。そこが一般の人の考える免疫とがん免疫療法の大きな違いです。
ノーベル賞が証明した「免疫チェックポイント阻害薬」の実力
〔編集部〕
本庶佑(ほんじょ たすく)先生がノーベル賞を受賞したチェックポイント阻害薬とは、どのような薬なのでしょうか?
〔大須賀先生〕
まさに、がん細胞が出している「賄賂」を遮断する治療です。がん細胞は、免疫細胞を攻撃しないようにさせるシグナル、つまり賄賂を出しているのです。
本庶先生たちは、このシグナルを抑える薬を開発しました。「賄賂を遮断したら、びっくりするほどがんを殺せるようになった」。
これが免疫チェックポイント阻害薬です。
〔編集部〕
でも、すべての患者さんに効くわけではないのですよね?
〔大須賀先生〕
その通りです。効かないがんもじつはたくさんあります。がんの中には、免疫細胞を抑える力がとてつもなく強いものがあるのです。
賄賂を多少阻害する薬を入れても、十分に抑えきれないことがあります。また、がんの集団はとても複雑です。
8割のがんで賄賂を防ぐ薬であっても、残り2割は違う方法を使っていたり、一つのがん細胞が複数の逃げ道を持っていたりする場合もあります。
〔編集部〕
先生が研究されている脳腫瘍では、とくに効きにくいそうですね。
〔大須賀先生〕
脳腫瘍は、チェックポイント阻害薬が効きにくいがんの代表例です。理由は主に二つあります。
一つは、薬が脳の中にうまく届かないこと。脳は重要な臓器なので、外から異物が入らないようにする特別なバリアがあります。これが薬の侵入も防いでしまうのです。
もう一つは、脳腫瘍独特の免疫抑制です。
脳腫瘍は免疫から逃れる技がとてつもなく多彩で、先ほどの賄賂にとどまらず、見つからないように隠れるなど多種な方法で免疫から逃れます。
膵がんなども同様ですが、現時点で予後が悪いがんの多くは、免疫療法がうまくいっていないことが背景にあります。
※「Medical DOC」2025/08/04記事より 転載










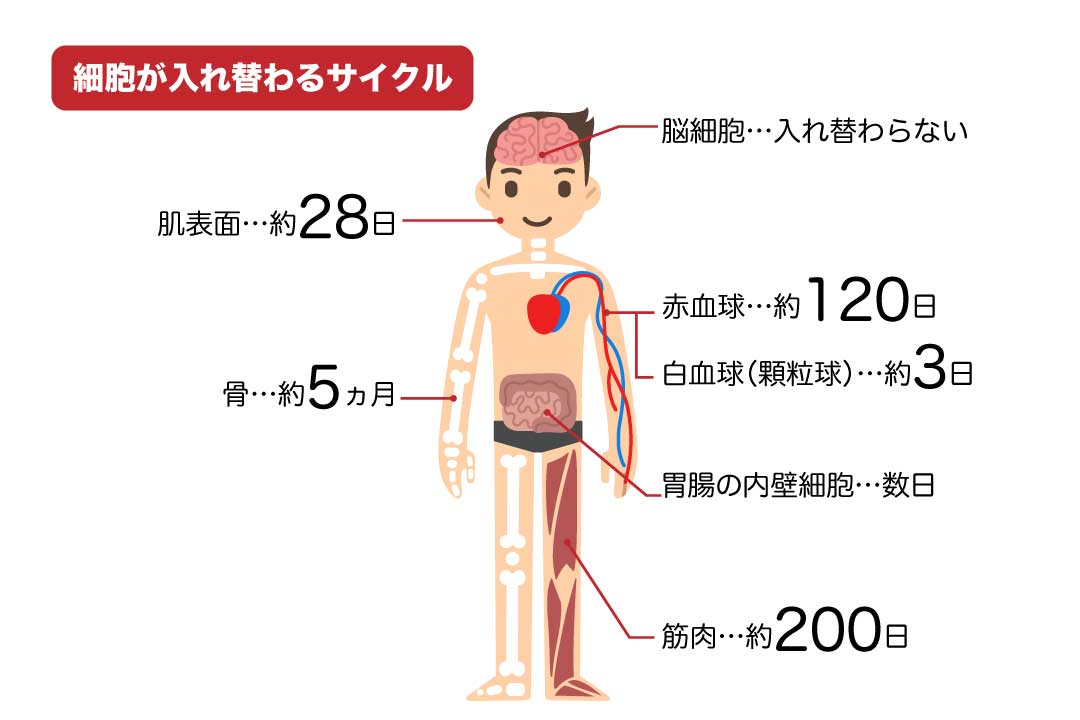
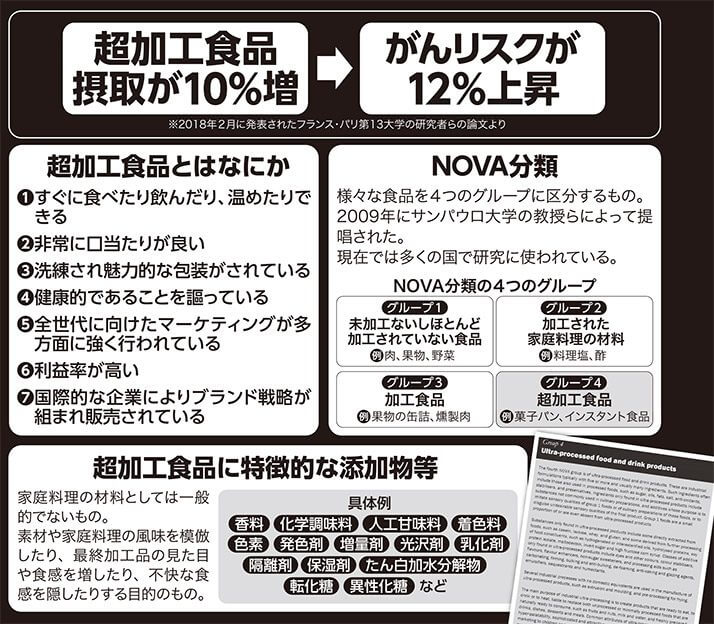
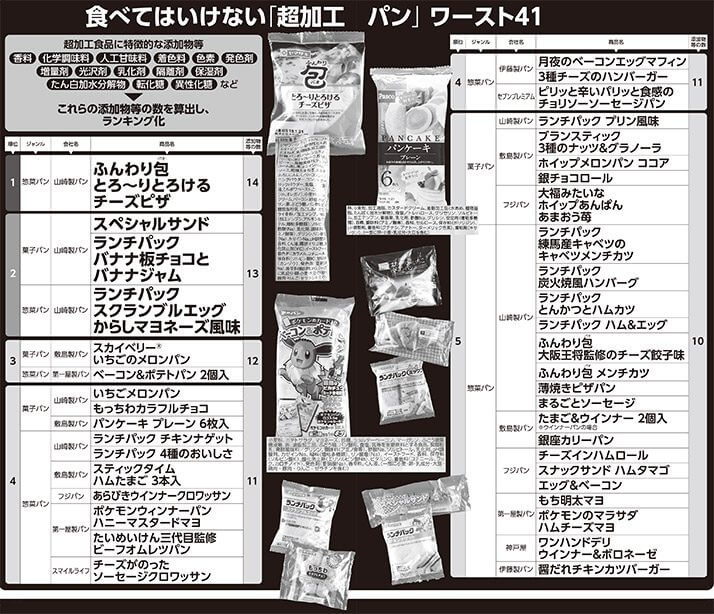


 姜を食べ
姜を食べ