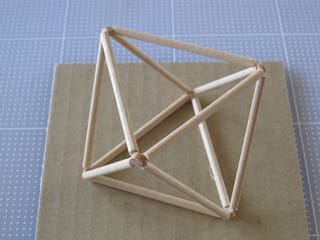「コミュニティデザイン」山崎亮著を読んだ。
情熱大陸に山崎氏が出演しているのを見て気になっていた。番組の中でパーマカルチャーデザイナーの四井さんが関わっている五島列島半泊集落のプロジェクトも紹介されていたので、ますます興味がわいたのだ。
本の中では山崎氏がこれまでに関わってきたプロジェクトが順に紹介され、彼の発想、プレゼンテーションの方法、社会のニーズ、今後のひろがりなどを感じることができた。
カミオプロジェクトを進める上でも大いに参考となります。
以下、山崎語録。いいこと書いてあります。
*ハードをデザインするだけでなく、ソフトをマネジメントするという視点
*思い立ったらすぐに企画書を書く
*社会の課題に取り組むこと
*里から採れる材料をつかって遊び場をつくり続けることで、持続的に良好な里山環境を担保することができないか
*オープンスペースのデザインは、単に美しく樹木や花を植えられているだけでは十分とはいえない。その場所でどんな仲間とどんな体験ができるのかをデザインしなければならないのだ。
*自分たちで少しずつお金を出し合ってでも楽しみたいと思えるような活動
*屋外を使いこなす人、生活者がどんどん関わることのできるような空間をデザインすべきではないか
*学ぶ場でもある
*プログラムのデザインとカタチのデザインを重ね合わせる、美しい風景として成立するようなデザインへと修正
*優れたダイアグラムをつくることができれば、デザインは方向性を決めやすくなる
*島外の人が島を使って楽しませてもらうプロジェクトなのだから、参加者が自ら費用を負担すべきだと考えた
*テーマ型のコミュニティ
*コミュニティデザインにおいて「ゆっくりであること」は大切なことだ
*楽しいプロジェクトと信頼できる仲間
*10年後の島をイメージしながら、そのために今後何をしていくべきか
*まだまだ状況は好転させられる
*荒れた里山に入り込んで、園路をつくったり遊び場をつくったり劇場をつくったりするのがパークレンジャーである
*時代の転換期には大都市から新しいことなんて生まれないのかもしれない
*あせらず、ゆっくりとプロジェクトを進める。そうすれば、至らない点がいろいろ見えてくる。それを修正しながらプロジェクトのスキームを固めてゆく。
*おしゃれに飾りたてることがデザインなのではなく、課題の本質を掴み、それを美しく解決することこそがデザインなのである
*デザインは社会の課題を解決するためのツールである
*課題を解決するデザイン、ソーシャルなデザイン
以上、そのままカミオプロジェクトにも当てはまる言葉たちです。