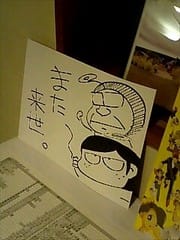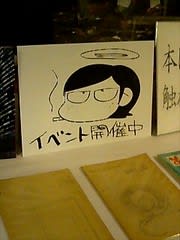「はてな」の方に接続できないから、こっちに投稿しておく。
「セイントフォー」に匹敵する「大人気」の安倍晋三
**1 「安倍晋三人気」と視聴率
>>
http://news.www.infoseek.co.jp/gendainet/society/story/16gendainet02028365/
「総裁選への視聴者の反応は薄い。3候補の顔がブラウン管に映れば映るほど、視聴率は下がる一方で、数字が取れなければ取り上げる回数も減るという悪循環です。安倍サンは数字を持っていないことが分かりました」(あるワイドショースタッフ)
思わぬ不人気ぶりにしょげかえっているのが、安倍応援団の連中だ。来る衆院補選、統一地方選、参院選と続く選挙ラッシュに向け、「安倍首相」を大々的に売り出すチャンスともくろんだが、期待外れもいいところ。安倍本人も焦っているのか、最近はあの手、この手を繰り出し、自分の売り込みに余念がない。
<<
ゲンダイネットだと小沢一郎子飼い記者あたりが書いていそうだからイマイチアレだけど、「安倍サンは数字を持っていないことが分かりました」というのは以前から言われていることで今更「わかった」もなにもねえだろ、と思うが。
>>
http://www.222.co.jp/president/topics/new/picup_db.php?mode=oneday&id=907
22:20 2004/07/12
1年待たずに辞任…。早くも賞味期限切れた“選挙の顔”。悪あがきすれば次期総裁の目もパー。
北朝鮮とマスコミ圧力だけでは票集まらず。
<<
「安倍応援団」は「安倍人気」なんて存在しない、捏造されたものだということすら知らなかったのか。真性のバカぞろいか? そのうち「私は悪い官房長官に騙されていました」とでも言うんだろうか。中国と戦争になってボロボロになった後あたりで。そんなバカどもが国政に携わるなボケ。また失政のケツ拭いを国民にさせるつもりだろ、「一億総懺悔」とか言って。ところで「一億総懺悔」って皇族首相の言葉だったな、まあどうでもいいけど。
**2 「次期総理は靖国参拝すべきだ」と「キゼンと」言っていた安倍晋三
>>
*** 855 名前:名無しさん@3周年 投稿日:2006/09/16(土) 08:38:21 KzqM89WU
次期総理は靖国参拝すべきだと言って来た安倍壷三。最近になって靖国に行く行かないはノーコメントと言い出したけど、結局、アメリカからハッキリ非難されたから行くと言えなくなったんだな。外国から言われて参拝しないというもんではないなんて散々言って。憲法違反を違反じゃないと言ってきたくせに。
>>
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=intl&NWID=2006091501001131
次期首相に参拝中止要請 米大物議員の抗議相次ぐ
【ワシントン14日共同】米下院外交委員会の重鎮、ラントス議員(民主党)は14日の公聴会で、小泉純一郎首相の靖国神社参拝を非難し、次期首相に参拝中止を要請した。さらに、太平洋戦争中の南京大虐殺の実態を否定する教科書を「日本政府が認めている」と指摘。「歴史を否定する者は(同じことを)繰り返す」と、歴史問題に対する日本政府の態度を厳しく批判した。
同委員会のハイド委員長(共和党)も同神社内の展示施設「遊就館」の太平洋戦争に関する説明内容を修正すべきだと主張しており、米議会の大物が日本側の歴史認識に相次ぎ抗議した格好だ。
11月の中間選挙で野党民主党が下院を奪回した場合、ラントス議員は同委員会の委員長に就任する予定。同議員は第2次大戦中のホロコースト(ユダヤ人大量虐殺)の生存者でもある。
<<
*** 861 名前:名無しさん@3周年 投稿日:2006/09/16(土) 13:40:38 kKDpiTTN
確かに安倍は、どうしようもないマヌケだな。w
>860
>>
「靖国神社に参拝するからといって首脳会談をしない姿勢がよいのか」 とアジア諸国にケンカを売っているのだから、どういうつもりなのか。
<<
アメリカからも総理の靖国参拝批判を受けた。安倍はもちろん毅然とした参拝するんだろ。散々、外国に言われて参拝しないのはおかしいだの。次期総理(自分〔安倍晋三〕だが)も靖国に参拝するべきだとか言ってきたんだ。まさかアメリカ様に土下座外交はしないだろ。
*** 862 名前:名無しさん@3周年 投稿日:2006/09/16(土) 14:00:17 395cX1W7
北朝鮮しか知らない安倍が総理になってどーするの? この緊急時に美しい国とか能天気な事を言ってる安倍が総理になってどーするの?
<<
**3 安倍政権で「教育改革国民会議」復活
>>
http://www.sankei.co.jp/news/060830/sei034.htm
首相主導で教育改革 安倍氏当選なら「推進会議」設置へ
下村博文自民党副幹事長は29日、9月の自民党総裁選で安倍晋三官房長官が当選し、首相に就任した場合、首相直属の「教育改革推進会議」(仮称)が設置されるとの見通しを明らかにした。東京都内で開かれた教育基本法改正シンポジウムで語った。〔略〕
安倍氏に近い下村氏は「文科省だけに任せずに、かつての教育改革国民会議のような首相主導で教育改革を行う組織を、新政権が発足したらすぐに設置しなければならない」と述べた上で「新政権発足から半年以内に結論を出すくらいのことが必要だ」とスピーディーな審議を訴えた。〔略〕
同じく安倍氏に近い山谷えり子内閣府政務官は来賓あいさつで、「推進会議と国民運動の連携が望ましい」と述べ、教育再生に向けたネットワークが必要との認識を示した。
【2006/08/30 東京朝刊から】(08/30 10:08)
<<
>>
*** 664 名前:名無しさん@3周年 投稿日:2006/09/16(土) 23:05:08 h3KQQLN0
教育改革国民会議の迷言集w ソース:首相官邸公式サイト
>>
http://www.kantei.go.jp/jp/kyouiku/1bunkakai/dai4/1-4siryou1.html
・子どもを厳しく「飼い馴らす」必要があることを国民にアピールして覚悟してもらう
・家庭教育について対話できる土壌をつくるため、企業やテレビと協力して古来の諺などを呼びかける
・「ここで時代が変わった」「変わらないと日本が滅びる」というようなことをアナウンスし、ショック療法を行う
・名刺に信念を書くなど、大人一人一人が座右の銘、信念を明示する
・遠足でバスを使わせない、お寺で3~5時間座らせる等の「我慢の教育」をする
・ 地域の偉人の副読本を作成・配布する
・ 学校に畳の部屋を作る
・学校に教育機関としてのシンボルを設ける
・有害情報、玩具等へのNPOなどによるチェック、法令による規制
・バーチャル・リアリティは悪であるということをハッキリと言う
・団地、マンション等に「床の間」を作る
・警察OBを学校に常駐させる
・文部省、マスコミが1、2週間程度学校で過ごす
・教育基本法を改正を提起し、従来の惰性的気風を打ち破るための社会的ショック療法とする
<小学生>簡素な宿舎で約2週間共同生活を行い肉体労働をする
<中学生>簡素な宿舎で約2週間共同生活を行い肉体労働をする
<高校生>満18歳で全ての国民に1年ないし2年間の奉仕活動を義務づける
<<
カルトの見本市ですなw
<<
関連
**4 「セイントフォー」に匹敵する「大人気」の安倍晋三
「セイントフォー」って覚えている? 宣伝費40億円かけたということだけが話題で全くヒットしなかったアイドルグループだけど。(今にして思うと、いったい、宣伝費はどこに消えたんだろ?)安倍晋三と「セイントフォー」がかぶって見えるこの頃。…あ。検索したら、「セイントフォー」って途中でメンバーチェンジがあって岩男潤子が入っていたのか…。岩男潤子、苦労したんだなあ…。失敬、言い直します。安倍晋三の「大人気」は、かつてのアイドルグループ「少女隊」に匹敵する。
 このブログの存在に気づいた有志は、
このブログの存在に気づいた有志は、 をクリック下さい。
をクリック下さい。
「セイントフォー」に匹敵する「大人気」の安倍晋三
**1 「安倍晋三人気」と視聴率
>>
http://news.www.infoseek.co.jp/gendainet/society/story/16gendainet02028365/
「総裁選への視聴者の反応は薄い。3候補の顔がブラウン管に映れば映るほど、視聴率は下がる一方で、数字が取れなければ取り上げる回数も減るという悪循環です。安倍サンは数字を持っていないことが分かりました」(あるワイドショースタッフ)
思わぬ不人気ぶりにしょげかえっているのが、安倍応援団の連中だ。来る衆院補選、統一地方選、参院選と続く選挙ラッシュに向け、「安倍首相」を大々的に売り出すチャンスともくろんだが、期待外れもいいところ。安倍本人も焦っているのか、最近はあの手、この手を繰り出し、自分の売り込みに余念がない。
<<
ゲンダイネットだと小沢一郎子飼い記者あたりが書いていそうだからイマイチアレだけど、「安倍サンは数字を持っていないことが分かりました」というのは以前から言われていることで今更「わかった」もなにもねえだろ、と思うが。
>>
http://www.222.co.jp/president/topics/new/picup_db.php?mode=oneday&id=907
22:20 2004/07/12
1年待たずに辞任…。早くも賞味期限切れた“選挙の顔”。悪あがきすれば次期総裁の目もパー。
北朝鮮とマスコミ圧力だけでは票集まらず。
<<
「安倍応援団」は「安倍人気」なんて存在しない、捏造されたものだということすら知らなかったのか。真性のバカぞろいか? そのうち「私は悪い官房長官に騙されていました」とでも言うんだろうか。中国と戦争になってボロボロになった後あたりで。そんなバカどもが国政に携わるなボケ。また失政のケツ拭いを国民にさせるつもりだろ、「一億総懺悔」とか言って。ところで「一億総懺悔」って皇族首相の言葉だったな、まあどうでもいいけど。
**2 「次期総理は靖国参拝すべきだ」と「キゼンと」言っていた安倍晋三
>>
*** 855 名前:名無しさん@3周年 投稿日:2006/09/16(土) 08:38:21 KzqM89WU
次期総理は靖国参拝すべきだと言って来た安倍壷三。最近になって靖国に行く行かないはノーコメントと言い出したけど、結局、アメリカからハッキリ非難されたから行くと言えなくなったんだな。外国から言われて参拝しないというもんではないなんて散々言って。憲法違反を違反じゃないと言ってきたくせに。
>>
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=intl&NWID=2006091501001131
次期首相に参拝中止要請 米大物議員の抗議相次ぐ
【ワシントン14日共同】米下院外交委員会の重鎮、ラントス議員(民主党)は14日の公聴会で、小泉純一郎首相の靖国神社参拝を非難し、次期首相に参拝中止を要請した。さらに、太平洋戦争中の南京大虐殺の実態を否定する教科書を「日本政府が認めている」と指摘。「歴史を否定する者は(同じことを)繰り返す」と、歴史問題に対する日本政府の態度を厳しく批判した。
同委員会のハイド委員長(共和党)も同神社内の展示施設「遊就館」の太平洋戦争に関する説明内容を修正すべきだと主張しており、米議会の大物が日本側の歴史認識に相次ぎ抗議した格好だ。
11月の中間選挙で野党民主党が下院を奪回した場合、ラントス議員は同委員会の委員長に就任する予定。同議員は第2次大戦中のホロコースト(ユダヤ人大量虐殺)の生存者でもある。
<<
*** 861 名前:名無しさん@3周年 投稿日:2006/09/16(土) 13:40:38 kKDpiTTN
確かに安倍は、どうしようもないマヌケだな。w
>860
>>
「靖国神社に参拝するからといって首脳会談をしない姿勢がよいのか」 とアジア諸国にケンカを売っているのだから、どういうつもりなのか。
<<
アメリカからも総理の靖国参拝批判を受けた。安倍はもちろん毅然とした参拝するんだろ。散々、外国に言われて参拝しないのはおかしいだの。次期総理(自分〔安倍晋三〕だが)も靖国に参拝するべきだとか言ってきたんだ。まさかアメリカ様に土下座外交はしないだろ。
*** 862 名前:名無しさん@3周年 投稿日:2006/09/16(土) 14:00:17 395cX1W7
北朝鮮しか知らない安倍が総理になってどーするの? この緊急時に美しい国とか能天気な事を言ってる安倍が総理になってどーするの?
<<
**3 安倍政権で「教育改革国民会議」復活
>>
http://www.sankei.co.jp/news/060830/sei034.htm
首相主導で教育改革 安倍氏当選なら「推進会議」設置へ
下村博文自民党副幹事長は29日、9月の自民党総裁選で安倍晋三官房長官が当選し、首相に就任した場合、首相直属の「教育改革推進会議」(仮称)が設置されるとの見通しを明らかにした。東京都内で開かれた教育基本法改正シンポジウムで語った。〔略〕
安倍氏に近い下村氏は「文科省だけに任せずに、かつての教育改革国民会議のような首相主導で教育改革を行う組織を、新政権が発足したらすぐに設置しなければならない」と述べた上で「新政権発足から半年以内に結論を出すくらいのことが必要だ」とスピーディーな審議を訴えた。〔略〕
同じく安倍氏に近い山谷えり子内閣府政務官は来賓あいさつで、「推進会議と国民運動の連携が望ましい」と述べ、教育再生に向けたネットワークが必要との認識を示した。
【2006/08/30 東京朝刊から】(08/30 10:08)
<<
>>
*** 664 名前:名無しさん@3周年 投稿日:2006/09/16(土) 23:05:08 h3KQQLN0
教育改革国民会議の迷言集w ソース:首相官邸公式サイト
>>
http://www.kantei.go.jp/jp/kyouiku/1bunkakai/dai4/1-4siryou1.html
・子どもを厳しく「飼い馴らす」必要があることを国民にアピールして覚悟してもらう
・家庭教育について対話できる土壌をつくるため、企業やテレビと協力して古来の諺などを呼びかける
・「ここで時代が変わった」「変わらないと日本が滅びる」というようなことをアナウンスし、ショック療法を行う
・名刺に信念を書くなど、大人一人一人が座右の銘、信念を明示する
・遠足でバスを使わせない、お寺で3~5時間座らせる等の「我慢の教育」をする
・ 地域の偉人の副読本を作成・配布する
・ 学校に畳の部屋を作る
・学校に教育機関としてのシンボルを設ける
・有害情報、玩具等へのNPOなどによるチェック、法令による規制
・バーチャル・リアリティは悪であるということをハッキリと言う
・団地、マンション等に「床の間」を作る
・警察OBを学校に常駐させる
・文部省、マスコミが1、2週間程度学校で過ごす
・教育基本法を改正を提起し、従来の惰性的気風を打ち破るための社会的ショック療法とする
<小学生>簡素な宿舎で約2週間共同生活を行い肉体労働をする
<中学生>簡素な宿舎で約2週間共同生活を行い肉体労働をする
<高校生>満18歳で全ての国民に1年ないし2年間の奉仕活動を義務づける
<<
カルトの見本市ですなw
<<
関連
**4 「セイントフォー」に匹敵する「大人気」の安倍晋三
「セイントフォー」って覚えている? 宣伝費40億円かけたということだけが話題で全くヒットしなかったアイドルグループだけど。(今にして思うと、いったい、宣伝費はどこに消えたんだろ?)安倍晋三と「セイントフォー」がかぶって見えるこの頃。…あ。検索したら、「セイントフォー」って途中でメンバーチェンジがあって岩男潤子が入っていたのか…。岩男潤子、苦労したんだなあ…。失敬、言い直します。安倍晋三の「大人気」は、かつてのアイドルグループ「少女隊」に匹敵する。
 このブログの存在に気づいた有志は、
このブログの存在に気づいた有志は、
- 38
第9 海外からの情報発信について
1 海外のサーバに蔵置された情報へのプロバイダ等の技術的対応可能性の限界について
プロバイダ等は、海外に設置されたサーバに対する管理可能性を有さないので、当該サーバに蔵置された情報に対するアクセスを遮断する以外の対応をとることはできない。さらに、アクセスの遮断については、当該サーバに割り振られたIPアドレスへのアクセスを遮断する形で行われるものの、サーバに割り振られたIPアドレスの変更は容易であり、プロバイダ等によるアクセスの遮断を発信者は容易に回避できる。また、日本から海外へのアクセスについては別のサーバを経由して違法・有害情報が掲載されたサーバにアクセスすることによっても、アクセス遮断を回避することが可能である。
これらの技術的限界が存在するため、我が国のプロバイダが、海外に設置されたサーバに蔵置された情報に対して直接有効な対応を行うことは困難である。
2 法執行機関・ホットラインの国際連携による取組
サーバの設置国で合法な情報については、我が国の法律で違法とされていても、設置国の法執行機関による捜査等が困難であるため、我が国の法執行機関、ホットラインと設置国の法執行機関、ホットラインとの間で国際的な連携を行うことができない。
しかしながら、サーバの設置国でも違法とされている情報については、法執行機関の国際連携による対応が可能である。具体的には、日本の警察に通報された情報について、インターポールを経由してサーバの設置国の法執行機関に捜査協力を要請する方法が考えられる。一方で、一般利用者からの通報を受付ける、「ホットライン」の間での国際連携も、各国のホットライン機関によって構成される国際団体であるINHOPEを経由して行われており、特に児童ポルノ等国際的に広く違法とされている情報について、一定の有効な対応が行われている。
我が国においても、平成18年6月から「インターネット・ホットライン
- 39
センター」が活動を開始している。現時点では同機関の対応する違法・有害情報の範囲は日本国内のサーバに蔵置された情報に限られているが、将来的にはINHOPEを通じて、国際的な連携の枠組に参加することも検討されており、同機関を通じた取組が推進されることが期待される。
- 40
第10 まとめ
インターネット上の違法・有害情報の流通が大きな社会問題になっている状況にかんがみ、本研究会においては、インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討課題を整理した上で、プロバイダや電子掲示板の管理者等による自主的対応及びこれを効果的に支援する方策について検討してきた。
インターネット上の違法・有害情報について、アクセスプロバイダの立場で送信防止措置等を行うことは、技術的理由等により困難であることが多いことから、本研究会では、電子掲示板の管理者やサーバの管理者等といったデータファイルやサーバの管理権限を有する者による送信防止措置を念頭に検討を行った。
その上で、(1)電子掲示板の管理者等による自主的対応に関する法的責任、(2)電子掲示板の管理者等による違法・有害情報への自主的対応を支援する方策、(3)プロバイダ責任制限法における発信者情報開示の運用、(4)インターネットにおける匿名性、(5)海外からの情報発信等について検討を行った。
検討の結果、電子掲示板の管理者等による自主的対応に関する法的責任については、単に違法な情報を放置したとの理由のみで、刑事上、民事上の責任を問われることは通常は考えられず、また、電子掲示板の管理者等が、違法・有害な情報について送信防止措置を行った場合についても、通常は刑事上、民事上の責任を負うことは考えられない、との整理がなされた。
研究会では、このような法的な整理を踏まえて議論をとりまとめ、電子掲示板の管理者等による違法・有害情報への対応に関して、電子掲示板の管理者等による情報の違法性・有害性の判断を支援する方策や、フィルタリングの利用促進に向けた取組等についての提言を行うものである。
今後、この研究会での提言等を踏まえ、インターネット上の違法・有害情報に対して、行政の支援のもと、電気通信事業者及び利用者による自主的な対応が促進され、表現の自由に配慮しつつ各人がインターネットの利便性を享受できるような環境の整備が望まれる。
- 41
第9 海外からの情報発信について
1 海外のサーバに蔵置された情報へのプロバイダ等の技術的対応可能性の限界について
プロバイダ等は、海外に設置されたサーバに対する管理可能性を有さないので、当該サーバに蔵置された情報に対するアクセスを遮断する以外の対応をとることはできない。さらに、アクセスの遮断については、当該サーバに割り振られたIPアドレスへのアクセスを遮断する形で行われるものの、サーバに割り振られたIPアドレスの変更は容易であり、プロバイダ等によるアクセスの遮断を発信者は容易に回避できる。また、日本から海外へのアクセスについては別のサーバを経由して違法・有害情報が掲載されたサーバにアクセスすることによっても、アクセス遮断を回避することが可能である。
これらの技術的限界が存在するため、我が国のプロバイダが、海外に設置されたサーバに蔵置された情報に対して直接有効な対応を行うことは困難である。
2 法執行機関・ホットラインの国際連携による取組
サーバの設置国で合法な情報については、我が国の法律で違法とされていても、設置国の法執行機関による捜査等が困難であるため、我が国の法執行機関、ホットラインと設置国の法執行機関、ホットラインとの間で国際的な連携を行うことができない。
しかしながら、サーバの設置国でも違法とされている情報については、法執行機関の国際連携による対応が可能である。具体的には、日本の警察に通報された情報について、インターポールを経由してサーバの設置国の法執行機関に捜査協力を要請する方法が考えられる。一方で、一般利用者からの通報を受付ける、「ホットライン」の間での国際連携も、各国のホットライン機関によって構成される国際団体であるINHOPEを経由して行われており、特に児童ポルノ等国際的に広く違法とされている情報について、一定の有効な対応が行われている。
我が国においても、平成18年6月から「インターネット・ホットライン
- 39
センター」が活動を開始している。現時点では同機関の対応する違法・有害情報の範囲は日本国内のサーバに蔵置された情報に限られているが、将来的にはINHOPEを通じて、国際的な連携の枠組に参加することも検討されており、同機関を通じた取組が推進されることが期待される。
- 40
第10 まとめ
インターネット上の違法・有害情報の流通が大きな社会問題になっている状況にかんがみ、本研究会においては、インターネット上の違法・有害情報への対応に関する検討課題を整理した上で、プロバイダや電子掲示板の管理者等による自主的対応及びこれを効果的に支援する方策について検討してきた。
インターネット上の違法・有害情報について、アクセスプロバイダの立場で送信防止措置等を行うことは、技術的理由等により困難であることが多いことから、本研究会では、電子掲示板の管理者やサーバの管理者等といったデータファイルやサーバの管理権限を有する者による送信防止措置を念頭に検討を行った。
その上で、(1)電子掲示板の管理者等による自主的対応に関する法的責任、(2)電子掲示板の管理者等による違法・有害情報への自主的対応を支援する方策、(3)プロバイダ責任制限法における発信者情報開示の運用、(4)インターネットにおける匿名性、(5)海外からの情報発信等について検討を行った。
検討の結果、電子掲示板の管理者等による自主的対応に関する法的責任については、単に違法な情報を放置したとの理由のみで、刑事上、民事上の責任を問われることは通常は考えられず、また、電子掲示板の管理者等が、違法・有害な情報について送信防止措置を行った場合についても、通常は刑事上、民事上の責任を負うことは考えられない、との整理がなされた。
研究会では、このような法的な整理を踏まえて議論をとりまとめ、電子掲示板の管理者等による違法・有害情報への対応に関して、電子掲示板の管理者等による情報の違法性・有害性の判断を支援する方策や、フィルタリングの利用促進に向けた取組等についての提言を行うものである。
今後、この研究会での提言等を踏まえ、インターネット上の違法・有害情報に対して、行政の支援のもと、電気通信事業者及び利用者による自主的な対応が促進され、表現の自由に配慮しつつ各人がインターネットの利便性を享受できるような環境の整備が望まれる。
- 41
- 31
(2)諸外国の発信者情報開示制度
ア アメリカ
他人の権利を侵害する情報については、身元不詳の発信者を相手方とする仮名訴訟を提起した上で、審理(trial)の前に行われる証拠開示(discovery)の手続において、裁判所からsubpoena32(文書提出命令)を取得することで、訴訟外の第三者である電子掲示板の管理者等に対して発信者情報の開示を請求することができる。また、著作権侵害情報に関しては、デジタルミレニアム著作権法(DMCA)第512条(h)33の規定に基づき、権利保有者において同法の定める書類を裁判所書記官に提出すれば、権利保有者は電子掲示板の管理者等に対して権利侵害情報の発信者情報の開示を請求するための命令を裁判所から取得することができる。
イ イギリス
情報の流通により権利を侵害された者は、Norwich Pharmacal Order と呼ばれる第三者情報開示命令を裁判所から取得することで、審理前の段階で、プロバイダに対して発信者情報の開示を請求することができる34。
また、当該情報が掲載された電子掲示板の管理者等を訴えた場合に、被告である電子掲示板の管理者等は、民事訴訟規則第20条の5に基づく訴えを当該情報の発信者等に対して提起することができる。これは、ある訴訟について、被告が第三者に対して提起できる訴えであり、この訴えを提起することが裁判所に認められれば、当該者を訴訟に参加させることができる。ただし、この訴えを起こすかどうかは被告の任意である。(イギリスでは、アメリカと異なり、証拠開示の手続においてsubpoena(文書提出命令)の対象となるのは、訴訟当事者だけである。)
ウ フランス
情報の流通により権利を侵害された者は、レフェレという仮の地位を定める仮処分に類似した制度により、裁判所からレフェレ命令を受けることで発信者情報の開示を受けることができる。レフェレは、通常は相手方を呼び出した上、1回の口頭弁論で審理を終え、無保証で命令が出
〔脚注〕
32 subpoena の発行は裁判所名で行われるが、裁判所書記官が形式審査のみで発令している。(米国民訴規則第45条)
33 デジタルミレニアム著作権法第512条(h)の条文については、http://www.cric.or.jp/gaikoku/america/america.html 参照。
34 長谷部由起子「提訴に必要な情報を得るための仮処分:暫定的実体権再論」『権利実現過程の基本構造 竹下守夫先生古稀祝賀』(有斐閣,2002)所収参照。
- 32
される。
(3)まとめ
これまで調査した範囲内においては、海外では、裁判所を介さずに発信者情報の開示を受けられる制度は存在せず、任意での発信者情報の開示は認められていない。なお、アメリカでは、発信者情報の開示を得るために裁判所を介するといっても、イギリスやフランスと異なり、裁判所書記官の形式審査によって開示命令が発令されるなど、比較的容易に発信者情報の開示を受けることが可能であるが、特にDMCAについては開示が容易すぎるとの批判もあるところである。
我が国では任意での発信者情報の開示が制度上可能になっているが、開示請求の目的が権利侵害情報によって蒙った損害に対する賠償請求権の行使等にあることを考えると、どのような場合に裁判所を介さずに発信者情報の開示を行うことができるかについては、権利侵害を受けた者の救済の必要性と通信の秘密や表現の自由の利益を総合的に考慮した上で、慎重に検討する必要があると考えられる。
2 プロバイダ等による発信者情報の開示の状況
570社のプロバイダに対して実施した調査によれば35、プロバイダ責任制限法第4条の運用状況は次のとおりである。
(1)発信者情報開示の件数等
回答のあった63社のうち、半数を超える33社が発信者情報開示請求を受けており、33社のうち12社が発信者情報を開示したことがある。開示に応じた理由としては、「発信者に対して意見照会をして同意を得た」が最も多く、次いで裁判での開示命令の取得が続いている。一方、不開示とした理由としては、「侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」という、「プロバイダ責任制限法第4条第1項第1号の要件を満たしていると判断できない」が群を抜いて多い。
(2)発信者情報開示訴訟の件数等
〔脚注〕
35 (社)電気通信事業者協会、(社)テレコムサービス協会、(社)日本インターネットプロバイダー協会の3団体に加盟するプロバイダを対象に、(財)マルチメディア振興センターが調査を行った。調査報告書の全文については、http://www.fmmc.or.jp/report/054.pdf にて入手可能。
- 33
発信者情報開示請求訴訟の件数は、平成15年は7件、平成16年は10件、平成17年度は24件となっており、年々増加しつつある。侵害された権利の内容としては名誉毀損が19件と大半を占めている。また、確定判決が出される前に、裁判所から発信者情報の開示を命じる仮処分命令が出された事例も3件ある。
3 発信者情報の開示を巡る課題の整理
(1)発信者情報開示手続に関する誤解
プロバイダにおいて、発信者情報開示手続を巡り様々な誤解が生じていることが、発信者情報の円滑な開示を妨げの一因となっていると考えられる。主な誤解としては、①プロバイダ責任制限法第4条第2項の発信者に対する意見聴取を行うためには、第4条第1項の要件を満たしていることが必要である、②第4条第1項の要件は、開示請求を受けた時点において満たされていることが必要である、③発信者情報開示には、第4条第1項の要件を満たしていても、第4条第2項の意見聴取を行い発信者から回答が得られることが必要である、等が挙げられる。
(2)要件判断の困難性
プロバイダ責任制限法第4条第1項第1号の要件である「権利が侵害されたことが明らかであるとき」とは、開示請求者の権利が侵害され、不法行為等の成立を阻却する事由の存在をうかがわせるような事情が存在しないことまでを意味すると解されており、プロバイダが発信者情報開示の請求を受けた場合に、当該請求が同号の要件を満たしているかどうかを判断するためには法律の専門的知識が必要となる。特に法律の専門家がいない小規模なプロバイダにおいては、このような判断は困難であるため、仮に請求が要件を満たしているとしても、判断が難しいことを理由に開示を行わないことが、発信者情報開示手続の円滑な運用の妨げの一因となっていることが考えられる。
(3)民事保全制度の未活用
発信者情報開示請求権については、仮処分によってその実現を図ることも考えられる。特に、電子掲示板における書き込みについて発信者情報開示請求を行う場合のように、発信者情報開示請求が、「①電子掲示板の管理者に対するIPアドレスとタイムスタンプの開示請求」、「②経由プロバイダに対する契約者情報の開示請求」の二段構成になる場合には、「①電子掲
- 34
示板の管理者に対するIPアドレスとタイムスタンプの開示請求」についての保全の必要性は比較的高いと考えられる36。実際にも、前述のとおり件数は少ないものの、裁判所から発信者情報開示の仮処分命令が出されている事例37が既にいくつか出てきており、権利を侵害された者を救済する上で迅速な対応が可能になっている。
しかしながら、このような仮処分を得られることが法曹関係者の間で必ずしも広く知られておらず、民事保全制度が活用されているとは言いがたい状況にある。
(4)発信者情報開示請求の対象となる事業者の特定の困難性
権利侵害情報が掲載されている電子掲示板やウェブページを特定できたとしても、当該電子掲示板や、ウェブページのアドレス等から管理者を特定するためには一定の知識が必要であり、知識がないために管理者を特定できず、結果として発信者情報開示請求を行うことができないことがある。
4 発信者情報開示制度に関する提言
発信者情報の開示に関する課題のうち、開示手続に関する誤解及び要件判断の困難性に関する点については、プロバイダ責任制限法施行後の発信者情報を巡る判例や、各社の対応事例、諸外国の状況等を参考に、発信者情報開示請求があった場合の電子掲示板の管理者等の行動指針を策定することが、発信者の法的利益に配慮しつつ、権利侵害の被害者に対する迅速な救済を可能にするための有効な方策であると考えられる。
この点、プロバイダ責任制限法第3条に関しては、典型的な権利侵害の類型である名誉毀損・プライバシー侵害、著作権侵害、商標権侵害について、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会において、判断指針となる関係ガイドラインが策定され、法解釈及び法適用(事実認定)の両面において、電子掲示板の管理者等の行動指針として活用されている。これに対して、プロバイダ責任制限法第4条に関しては、同様のガイドラインが整備されておらず、(社)テレコムサービス協会において発信者情報開示請求の対応手順を公表しているに留まっている。
そこで、今後の方策として、電気通信事業者団体等において、権利を侵害された者が発信者情報の開示を受けるためのわかりやすい手続及び電子
〔脚注〕
36 発信者情報開示の仮処分については、鬼澤友直・目黒大輔「発信者情報の開示を命じる仮処分の可否」
(判例タイムズ1164号4頁)も参照。
37 東京地裁平成17年1月21日決定(判例時報1894号35頁)等。
- 35
掲示板の管理者等が任意に発信者情報を開示できる場合を類型化した事例等を盛り込んだ、発信者情報開示に関するガイドラインを策定することにより、プロバイダ責任制限法第4条の用意している制度についての正しい理解を促進するとともに、電子掲示板の管理者等の法解釈、法適用に関する指針を提供することが考えられる。
また、課題のうち民事保全制度の未活用及び発信者情報開示請求の対象となる事業者の特定の困難性については、これらに関する知識の不足を解消することにより解決が可能となりうる問題であり、関連する情報について、広く周知するような方策を検討していくことが考えられる。
- 36
第8 インターネットにおける匿名性について
1 匿名性をめぐる諸問題の現状について
インターネットは本来、誰もが自由に情報を発信し、表現行為を行う場であり、表現の自由を確保するためには、発信者を誰であるか明かさないことが必要な場合もあると考えられる。また、物理的空間の制約にとらわれず、いつでも、誰でも、どこからでもネットワークに接続することができる、中央管理者が存在しない、といった技術的特性の上でも、容易に「匿名での」情報発信が可能である。
しかし一方で、インターネットを利用した詐欺、麻薬売買等の犯罪や誹謗中傷等様々な問題が起こっており、これらの問題が解決困難な理由の一つとして、「インターネットの匿名性」、つまり発信者の追跡が不可能であるという点が挙げられる。
インターネットの匿名性には、さまざまな種類のものがあるが、次のように分類可能と考えられる。
インターネット上で匿名で通信を行うためのアプリケーションファイル交換ソフト
匿名メーラー
インターネット上で匿名性を得るためのサービス
匿名プロキシ
無料メール、ブログ、ホスティング
匿名ドメイン
匿名掲示板 インターネットアクセスにおける匿名性
無料ホットスポット ネットカフェ
2 対応の限界
以上のように、インターネットでは様々なレベルで匿名性を確保するための方法があるが、例えば電子メールについては、匿名メーラーを利用し、さ
- 37
らに匿名リメーラーサーバ38を複数経由してメールを送信することで、真の発信者を突き止めることが非常に困難な形で送信することが可能である。また、Winny に代表されるP2P型ファイル交換ソフトを利用することで、容易には真の発信者を突き止められない形で、情報のやり取りを行うことが可能である。さらに、ユーザ認証を行わない無料ホットスポットや、利用者の身分確認を行わないネットカフェ等を利用することで、仮に発信者のIPアドレスを追跡することができたとしても、最終的にIPアドレスを利用していた個人を特定することが不可能な場合があり、匿名性を完全に排除することは非常に困難である。
加えて、インターネットの匿名性は、プライバシーの保護に活用されていることも事実であり、また、匿名で表現する自由や通信の秘密にも留意する必要がある。
3 今後の方向性
本研究会においては、インターネット上の違法・有害情報への対応として、電子掲示板の管理者等による、送信防止措置(削除等)の自主的対応を支援する方策(違法情報への対応ガイドラインの策定)、フィルタリングサービスの利用等受信者側での対応や、プロバイダ責任制限法第4条の発信者情報開示制度の課題等を検討したところであり、今後はこれらによってインターネット上の違法・有害情報に対し、効果的な対応がなされることが期待される。
また、利用者の選択により、匿名性をある程度排除しうるようなサービスの提供のあり方も参考となるところである。
その上で、なおインターネット上の違法・有害情報への対応が十分になされていないと評価され、その原因が匿名性の存在にあると考えられる状況があるのであれば、様々なレベルでの匿名性が存在する中で、どのようなレベルでの匿名性が真に問題となっているのかを把握し、技術的、経済的な対応可能性や実効性、匿名での表現の自由、通信の秘密との関係等を十分に考慮に入れつつ、必要に応じて可能な対応を検討することが考えられる。
〔脚注〕
38 メール本文中に数行の命令を記載して当該サーバ宛に電子メールを送信することで、電子メールのヘッダ情報を書き換えて真の発信者がわからないようにした上で、発信者が送信先に指定したアドレスに電子メールを送信する機能を持つメールサーバのことをいう。
(2)諸外国の発信者情報開示制度
ア アメリカ
他人の権利を侵害する情報については、身元不詳の発信者を相手方とする仮名訴訟を提起した上で、審理(trial)の前に行われる証拠開示(discovery)の手続において、裁判所からsubpoena32(文書提出命令)を取得することで、訴訟外の第三者である電子掲示板の管理者等に対して発信者情報の開示を請求することができる。また、著作権侵害情報に関しては、デジタルミレニアム著作権法(DMCA)第512条(h)33の規定に基づき、権利保有者において同法の定める書類を裁判所書記官に提出すれば、権利保有者は電子掲示板の管理者等に対して権利侵害情報の発信者情報の開示を請求するための命令を裁判所から取得することができる。
イ イギリス
情報の流通により権利を侵害された者は、Norwich Pharmacal Order と呼ばれる第三者情報開示命令を裁判所から取得することで、審理前の段階で、プロバイダに対して発信者情報の開示を請求することができる34。
また、当該情報が掲載された電子掲示板の管理者等を訴えた場合に、被告である電子掲示板の管理者等は、民事訴訟規則第20条の5に基づく訴えを当該情報の発信者等に対して提起することができる。これは、ある訴訟について、被告が第三者に対して提起できる訴えであり、この訴えを提起することが裁判所に認められれば、当該者を訴訟に参加させることができる。ただし、この訴えを起こすかどうかは被告の任意である。(イギリスでは、アメリカと異なり、証拠開示の手続においてsubpoena(文書提出命令)の対象となるのは、訴訟当事者だけである。)
ウ フランス
情報の流通により権利を侵害された者は、レフェレという仮の地位を定める仮処分に類似した制度により、裁判所からレフェレ命令を受けることで発信者情報の開示を受けることができる。レフェレは、通常は相手方を呼び出した上、1回の口頭弁論で審理を終え、無保証で命令が出
〔脚注〕
32 subpoena の発行は裁判所名で行われるが、裁判所書記官が形式審査のみで発令している。(米国民訴規則第45条)
33 デジタルミレニアム著作権法第512条(h)の条文については、http://www.cric.or.jp/gaikoku/america/america.html 参照。
34 長谷部由起子「提訴に必要な情報を得るための仮処分:暫定的実体権再論」『権利実現過程の基本構造 竹下守夫先生古稀祝賀』(有斐閣,2002)所収参照。
- 32
される。
(3)まとめ
これまで調査した範囲内においては、海外では、裁判所を介さずに発信者情報の開示を受けられる制度は存在せず、任意での発信者情報の開示は認められていない。なお、アメリカでは、発信者情報の開示を得るために裁判所を介するといっても、イギリスやフランスと異なり、裁判所書記官の形式審査によって開示命令が発令されるなど、比較的容易に発信者情報の開示を受けることが可能であるが、特にDMCAについては開示が容易すぎるとの批判もあるところである。
我が国では任意での発信者情報の開示が制度上可能になっているが、開示請求の目的が権利侵害情報によって蒙った損害に対する賠償請求権の行使等にあることを考えると、どのような場合に裁判所を介さずに発信者情報の開示を行うことができるかについては、権利侵害を受けた者の救済の必要性と通信の秘密や表現の自由の利益を総合的に考慮した上で、慎重に検討する必要があると考えられる。
2 プロバイダ等による発信者情報の開示の状況
570社のプロバイダに対して実施した調査によれば35、プロバイダ責任制限法第4条の運用状況は次のとおりである。
(1)発信者情報開示の件数等
回答のあった63社のうち、半数を超える33社が発信者情報開示請求を受けており、33社のうち12社が発信者情報を開示したことがある。開示に応じた理由としては、「発信者に対して意見照会をして同意を得た」が最も多く、次いで裁判での開示命令の取得が続いている。一方、不開示とした理由としては、「侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき」という、「プロバイダ責任制限法第4条第1項第1号の要件を満たしていると判断できない」が群を抜いて多い。
(2)発信者情報開示訴訟の件数等
〔脚注〕
35 (社)電気通信事業者協会、(社)テレコムサービス協会、(社)日本インターネットプロバイダー協会の3団体に加盟するプロバイダを対象に、(財)マルチメディア振興センターが調査を行った。調査報告書の全文については、http://www.fmmc.or.jp/report/054.pdf にて入手可能。
- 33
発信者情報開示請求訴訟の件数は、平成15年は7件、平成16年は10件、平成17年度は24件となっており、年々増加しつつある。侵害された権利の内容としては名誉毀損が19件と大半を占めている。また、確定判決が出される前に、裁判所から発信者情報の開示を命じる仮処分命令が出された事例も3件ある。
3 発信者情報の開示を巡る課題の整理
(1)発信者情報開示手続に関する誤解
プロバイダにおいて、発信者情報開示手続を巡り様々な誤解が生じていることが、発信者情報の円滑な開示を妨げの一因となっていると考えられる。主な誤解としては、①プロバイダ責任制限法第4条第2項の発信者に対する意見聴取を行うためには、第4条第1項の要件を満たしていることが必要である、②第4条第1項の要件は、開示請求を受けた時点において満たされていることが必要である、③発信者情報開示には、第4条第1項の要件を満たしていても、第4条第2項の意見聴取を行い発信者から回答が得られることが必要である、等が挙げられる。
(2)要件判断の困難性
プロバイダ責任制限法第4条第1項第1号の要件である「権利が侵害されたことが明らかであるとき」とは、開示請求者の権利が侵害され、不法行為等の成立を阻却する事由の存在をうかがわせるような事情が存在しないことまでを意味すると解されており、プロバイダが発信者情報開示の請求を受けた場合に、当該請求が同号の要件を満たしているかどうかを判断するためには法律の専門的知識が必要となる。特に法律の専門家がいない小規模なプロバイダにおいては、このような判断は困難であるため、仮に請求が要件を満たしているとしても、判断が難しいことを理由に開示を行わないことが、発信者情報開示手続の円滑な運用の妨げの一因となっていることが考えられる。
(3)民事保全制度の未活用
発信者情報開示請求権については、仮処分によってその実現を図ることも考えられる。特に、電子掲示板における書き込みについて発信者情報開示請求を行う場合のように、発信者情報開示請求が、「①電子掲示板の管理者に対するIPアドレスとタイムスタンプの開示請求」、「②経由プロバイダに対する契約者情報の開示請求」の二段構成になる場合には、「①電子掲
- 34
示板の管理者に対するIPアドレスとタイムスタンプの開示請求」についての保全の必要性は比較的高いと考えられる36。実際にも、前述のとおり件数は少ないものの、裁判所から発信者情報開示の仮処分命令が出されている事例37が既にいくつか出てきており、権利を侵害された者を救済する上で迅速な対応が可能になっている。
しかしながら、このような仮処分を得られることが法曹関係者の間で必ずしも広く知られておらず、民事保全制度が活用されているとは言いがたい状況にある。
(4)発信者情報開示請求の対象となる事業者の特定の困難性
権利侵害情報が掲載されている電子掲示板やウェブページを特定できたとしても、当該電子掲示板や、ウェブページのアドレス等から管理者を特定するためには一定の知識が必要であり、知識がないために管理者を特定できず、結果として発信者情報開示請求を行うことができないことがある。
4 発信者情報開示制度に関する提言
発信者情報の開示に関する課題のうち、開示手続に関する誤解及び要件判断の困難性に関する点については、プロバイダ責任制限法施行後の発信者情報を巡る判例や、各社の対応事例、諸外国の状況等を参考に、発信者情報開示請求があった場合の電子掲示板の管理者等の行動指針を策定することが、発信者の法的利益に配慮しつつ、権利侵害の被害者に対する迅速な救済を可能にするための有効な方策であると考えられる。
この点、プロバイダ責任制限法第3条に関しては、典型的な権利侵害の類型である名誉毀損・プライバシー侵害、著作権侵害、商標権侵害について、プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会において、判断指針となる関係ガイドラインが策定され、法解釈及び法適用(事実認定)の両面において、電子掲示板の管理者等の行動指針として活用されている。これに対して、プロバイダ責任制限法第4条に関しては、同様のガイドラインが整備されておらず、(社)テレコムサービス協会において発信者情報開示請求の対応手順を公表しているに留まっている。
そこで、今後の方策として、電気通信事業者団体等において、権利を侵害された者が発信者情報の開示を受けるためのわかりやすい手続及び電子
〔脚注〕
36 発信者情報開示の仮処分については、鬼澤友直・目黒大輔「発信者情報の開示を命じる仮処分の可否」
(判例タイムズ1164号4頁)も参照。
37 東京地裁平成17年1月21日決定(判例時報1894号35頁)等。
- 35
掲示板の管理者等が任意に発信者情報を開示できる場合を類型化した事例等を盛り込んだ、発信者情報開示に関するガイドラインを策定することにより、プロバイダ責任制限法第4条の用意している制度についての正しい理解を促進するとともに、電子掲示板の管理者等の法解釈、法適用に関する指針を提供することが考えられる。
また、課題のうち民事保全制度の未活用及び発信者情報開示請求の対象となる事業者の特定の困難性については、これらに関する知識の不足を解消することにより解決が可能となりうる問題であり、関連する情報について、広く周知するような方策を検討していくことが考えられる。
- 36
第8 インターネットにおける匿名性について
1 匿名性をめぐる諸問題の現状について
インターネットは本来、誰もが自由に情報を発信し、表現行為を行う場であり、表現の自由を確保するためには、発信者を誰であるか明かさないことが必要な場合もあると考えられる。また、物理的空間の制約にとらわれず、いつでも、誰でも、どこからでもネットワークに接続することができる、中央管理者が存在しない、といった技術的特性の上でも、容易に「匿名での」情報発信が可能である。
しかし一方で、インターネットを利用した詐欺、麻薬売買等の犯罪や誹謗中傷等様々な問題が起こっており、これらの問題が解決困難な理由の一つとして、「インターネットの匿名性」、つまり発信者の追跡が不可能であるという点が挙げられる。
インターネットの匿名性には、さまざまな種類のものがあるが、次のように分類可能と考えられる。
インターネット上で匿名で通信を行うためのアプリケーションファイル交換ソフト
匿名メーラー
インターネット上で匿名性を得るためのサービス
匿名プロキシ
無料メール、ブログ、ホスティング
匿名ドメイン
匿名掲示板 インターネットアクセスにおける匿名性
無料ホットスポット ネットカフェ
2 対応の限界
以上のように、インターネットでは様々なレベルで匿名性を確保するための方法があるが、例えば電子メールについては、匿名メーラーを利用し、さ
- 37
らに匿名リメーラーサーバ38を複数経由してメールを送信することで、真の発信者を突き止めることが非常に困難な形で送信することが可能である。また、Winny に代表されるP2P型ファイル交換ソフトを利用することで、容易には真の発信者を突き止められない形で、情報のやり取りを行うことが可能である。さらに、ユーザ認証を行わない無料ホットスポットや、利用者の身分確認を行わないネットカフェ等を利用することで、仮に発信者のIPアドレスを追跡することができたとしても、最終的にIPアドレスを利用していた個人を特定することが不可能な場合があり、匿名性を完全に排除することは非常に困難である。
加えて、インターネットの匿名性は、プライバシーの保護に活用されていることも事実であり、また、匿名で表現する自由や通信の秘密にも留意する必要がある。
3 今後の方向性
本研究会においては、インターネット上の違法・有害情報への対応として、電子掲示板の管理者等による、送信防止措置(削除等)の自主的対応を支援する方策(違法情報への対応ガイドラインの策定)、フィルタリングサービスの利用等受信者側での対応や、プロバイダ責任制限法第4条の発信者情報開示制度の課題等を検討したところであり、今後はこれらによってインターネット上の違法・有害情報に対し、効果的な対応がなされることが期待される。
また、利用者の選択により、匿名性をある程度排除しうるようなサービスの提供のあり方も参考となるところである。
その上で、なおインターネット上の違法・有害情報への対応が十分になされていないと評価され、その原因が匿名性の存在にあると考えられる状況があるのであれば、様々なレベルでの匿名性が存在する中で、どのようなレベルでの匿名性が真に問題となっているのかを把握し、技術的、経済的な対応可能性や実効性、匿名での表現の自由、通信の秘密との関係等を十分に考慮に入れつつ、必要に応じて可能な対応を検討することが考えられる。
〔脚注〕
38 メール本文中に数行の命令を記載して当該サーバ宛に電子メールを送信することで、電子メールのヘッダ情報を書き換えて真の発信者がわからないようにした上で、発信者が送信先に指定したアドレスに電子メールを送信する機能を持つメールサーバのことをいう。