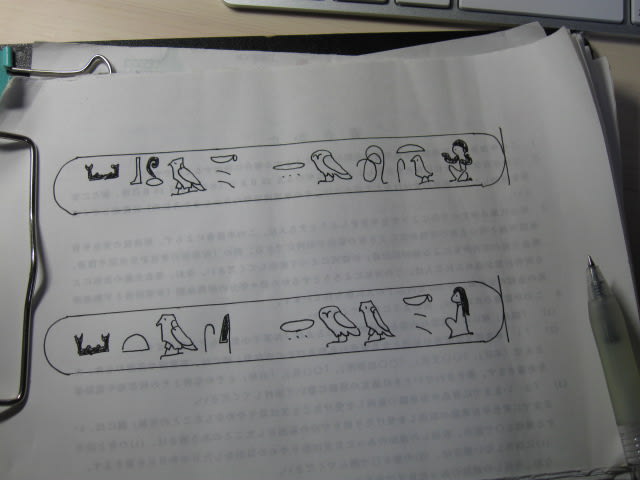僕は幕末の歴史がニガテなんだけれど、それでもまぁ少しくらいは知っている。
まずなにより勝海舟と西郷隆盛による、世界史にすら残るといわれている「江戸城無血開城」でしょ。
それに坂本龍馬が大政奉還の提案をするために新しい国家の形を示した「船中八策」。京都への放火計画を阻止するために池田屋に乗り込んだ新選組たちの激闘の中、隊員・沖田総司が結核の吐血をしたのはあまりにも有名な話。あと新選組といえば隊士は戦闘のプロになるためにそれぞれ剣術のひとつの型のみを徹底的に習熟したんだっけ。三番隊隊長・斉藤一の一撃必殺の突き「牙突」とかね。
たとえば龍馬。
龍馬の事績の数々は1883年に坂崎紫瀾《さかざきしらん》が書いた伝記風小説『天下無双人傑海南第一伝奇 汗血千里駒』が初出らしい。 』を執筆。現在に至る。
』を執筆。現在に至る。
というわけ。
(amazonでは『天下無双人傑海南第一伝奇 汗血千里駒』は、東方出版からの現代語訳『坂本龍馬伝 明治のベストセラー「汗血千里の駒」 』がある)
』がある)
たしかに龍馬に関しては、いくらなんでもひとりでいろんなことをやりすぎだろうとは思ってたけどさ、そうか、プロパガンダだったのか……。
実際の龍馬はどうだったかというと、
それなりに重要なポストにいたことは確かだけれど、スーパーヒーローすぎる活躍は後世の創作である可能性が高いというわけだ。
紹介した龍馬以外にも、本書には幕末の「じつは」なエピソードが合計40個紹介されている。どんな内容なのかは後述のもくじを見ていただくとして、それぞれのエピソードはいくつかの小分類に分けてまとめられていて、とても読みやすくてわかりやすい。
装丁もソフトカバーでお値段お手頃。気軽に読めて「へー」となる本だ。
あと。
値段の割に巻末の「参考文献」の多さに僕は驚いた。
なぜならこの系の「あれってじつはこうなんですよ」と暴露する本って、けっこう考証がいい加減な本が多くて、なかには都市伝説としか思えないようなことまで収録されていることがあるんだ。そういう本ってのはたいてい参考文献は伏せてる。だってネタ元に直に当たられたらバレるから。
つまり、これだけきちんと参考文献を出せるということはきちんと調べたうえの内容なんだろうね。
それにしてもこの龍馬にはちょっとショックだよなぁ……あと西郷さんのイメージが180度変わったかも。
→『教科書には載っていない! 幕末の大誤解 』熊谷充晃・彩図社
』熊谷充晃・彩図社
もくじ
→『竜馬がゆく 』司馬遼太郎・文藝春秋
』司馬遼太郎・文藝春秋
→『坂本龍馬伝 明治のベストセラー「汗血千里の駒」 』坂崎紫瀾・東方出版
』坂崎紫瀾・東方出版
→【本がもらえる】レビュープラス
↓いろんな書評が読めます


まずなにより勝海舟と西郷隆盛による、世界史にすら残るといわれている「江戸城無血開城」でしょ。
それに坂本龍馬が大政奉還の提案をするために新しい国家の形を示した「船中八策」。京都への放火計画を阻止するために池田屋に乗り込んだ新選組たちの激闘の中、隊員・沖田総司が結核の吐血をしたのはあまりにも有名な話。あと新選組といえば隊士は戦闘のプロになるためにそれぞれ剣術のひとつの型のみを徹底的に習熟したんだっけ。三番隊隊長・斉藤一の一撃必殺の突き「牙突」とかね。
 | 教科書には載っていない! 幕末の大誤解 価格:¥ 1,260(税込) 発売日:2013-01-29 |
誰もが知る幕末維新にはまずオビのことばに驚いた。そして読んでみたらいろいろ驚いた。なんちゅうかまぁ、僕の記憶は全部間違いだったってこと?
仰天の裏面史があった!
・ペリーに抱きついた日本人とは
・実在した「ラスト・サムライ」
・明治維新は無血開城ではない
・坂本龍馬は無名のスパイだった
たとえば龍馬。
龍馬の事績の数々は1883年に坂崎紫瀾《さかざきしらん》が書いた伝記風小説『天下無双人傑海南第一伝奇 汗血千里駒』が初出らしい。
実はこの時まで坂本龍馬なんて名前は、明治政府の関係者たちの心の中にあるだけで、歴史的な英雄とは認識されていなかった。それから10年ごとくらいに龍馬ブームが起こり、坂崎紫瀾の小説を参考にして司馬遼太郎が『竜馬がゆく
(略)
連載小説がスタートした当時は、自由民権運動が盛んな時期。龍馬と同郷で運動の旗手・板垣退助は、忘れられた郷土の英雄を運動のプロパガンダに活用することを思いつく。
(略)
それまで龍馬について言及することなどなかったのに、だ。
というわけ。
(amazonでは『天下無双人傑海南第一伝奇 汗血千里駒』は、東方出版からの現代語訳『坂本龍馬伝 明治のベストセラー「汗血千里の駒」
たしかに龍馬に関しては、いくらなんでもひとりでいろんなことをやりすぎだろうとは思ってたけどさ、そうか、プロパガンダだったのか……。
実際の龍馬はどうだったかというと、
フットワークの軽い龍馬は、遠隔地にいる者同士を取り持つ「連絡係」、いわばスパイの役目を請け負っていたという側面がある。とまあこんな感じ。
Aという人物に聞いた話をBに、Bの意見をCに、というように、歩く情報ネットワークの役割をこなしていたのは確かだ。やがて龍馬が語る誰かのアイディアは、聞く側にとっては龍馬のものと受け取られることも多くなる。こうして「龍馬の手柄」が急増して言ったと考えられる。
それなりに重要なポストにいたことは確かだけれど、スーパーヒーローすぎる活躍は後世の創作である可能性が高いというわけだ。
紹介した龍馬以外にも、本書には幕末の「じつは」なエピソードが合計40個紹介されている。どんな内容なのかは後述のもくじを見ていただくとして、それぞれのエピソードはいくつかの小分類に分けてまとめられていて、とても読みやすくてわかりやすい。
装丁もソフトカバーでお値段お手頃。気軽に読めて「へー」となる本だ。
あと。
値段の割に巻末の「参考文献」の多さに僕は驚いた。
なぜならこの系の「あれってじつはこうなんですよ」と暴露する本って、けっこう考証がいい加減な本が多くて、なかには都市伝説としか思えないようなことまで収録されていることがあるんだ。そういう本ってのはたいてい参考文献は伏せてる。だってネタ元に直に当たられたらバレるから。
つまり、これだけきちんと参考文献を出せるということはきちんと調べたうえの内容なんだろうね。
それにしてもこの龍馬にはちょっとショックだよなぁ……あと西郷さんのイメージが180度変わったかも。
英雄視されている人間に対しては特に、厳しい表現が多かったかもしれないし、そのことで気分を害したファンもいることと思う。うん。歴史って面白い。そしてこの本も面白かった。
だけど、それもひっくるめて歴史の面白さがあるんだ、ということ。一面しか見ずにひたすら賛美を送るのでは、カルト宗教の信徒と教祖の関係みたいなものだ。ダークサイドも知ってこそ、深みある人間としてさらに好きになる。その方が、精神衛生上は好ましいように思う。
 | 教科書には載っていない! 幕末の大誤解 価格:¥ 1,260(税込) 発売日:2013-01-29 |
→『教科書には載っていない! 幕末の大誤解
もくじ
はじめに
第一章 あの英雄たちの意外な素顔
1 龍馬の正体は無名のスパイ?
2 意外にヘタレだった勝海舟
3 仰天! ペリーの沖縄戦両計画
4 金に汚い福沢諭吉大先生
5 実は差別主義者だった高杉晋作
6 その正体は策略家? 西郷隆盛
7 徳川慶喜が考えた姑息な作戦
8 なぜ大村益次郎は死んだのか?
9 意外に進んでいた新選組
第二章 歴史を変えた大事件の舞台裏
10 桜田門外の変の真実
11 生麦事件の犠牲になった英国婦人
12 池田屋事件は維新を遅らせた?
13 幕末におはぎが大流行したワケ
14 薩長同盟の目的は倒幕じゃない?
15 江戸城無血開城の舞台裏
16 上の戦争で皇室に弓引いた?
第三章 こんなに凄かった! 江戸幕府
17 幕末日本の実力は?
18 各藩が挑んだ改革の数々
19 実は充実していた幕府の人材
20 幕府も立憲国家を目指していた
21 明治期の言論界は幕臣だらけ
22 幕府外交が起こしたウルトラC
23 すでに存在していた日の丸!
第四章 仰天! 幕末の裏エピソード
24 仰天の黒船撃退計画とは
25 市井の生活はどんなだった?
26 あの時代劇の主人公はどうなった?
27 阿鼻叫喚の地獄を見た秘湯の地
28 日本のラストフロンティア・北海道
29 旧幕軍は一切いない靖国神社
30 日本人は維新を歓迎したのか?
第五章 維新史に埋もれた偉人たち
31 ラスト・サムライは実在した!
32 おんな砲兵隊長・新島八重
33 開国を導いた傑物・岩瀬忠震
34 米国でアイドルになった日本人
35 ヘタレな最後を迎えた岡田以蔵
36 数奇な人生を歩んだ斉藤一
37 フレデリック・ヘンドリック
38 龍馬暗殺のカギを握る二枚舌男
39 日本海軍を作った小栗忠順
40 脱藩して官軍と戦った林忠崇
おわりに
参考文献
 | 教科書には載っていない! 幕末の大誤解 価格:¥ 1,260(税込) 発売日:2013-01-29 |
→『竜馬がゆく
→『坂本龍馬伝 明治のベストセラー「汗血千里の駒」
幕末維新いろいろ |
↓いろんな書評が読めます













![歴史魂 2011年 04月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/612a4frX5iL._SL160_.jpg)