18歳以下の子どもは、親の付き添いが必要ですこれはアメリカの公園に実際にある立て札の文言だ。
18歳以下ということは当然、高校生も含まれている。日本人からしたらちょっと「?」と思ってしまう。だけどこれ、アメリカではよくある光景なのだそうな。
 | 子どもがひとりで遊べない国、アメリカ—安全・安心パニック時代のアメリカ子育て事情価格:¥ 1,575(税込)発売日:2011-11 |
著者は谷口輝世子氏。
1998年に大リーグの取材のために渡米し、フリーランスのライターとなってアメリカに住み子育てをしている。
日本人の感覚を持った母親からみたアメリカの子育て事情は、かなり「?」が多いものだった。
もちろん日米の文化の違いもあるだろう。
だけれど、「日本人のママさん」目線で見るアメリカの「子どもを守る」ことへの徹底さはなんだかちょっと行きすぎて不思議に思える点が多いのだ。
本書の前半ではその不思議さを紹介する。
私は市の警察に「小学生の子どもを子どもだけで公園で遊ばせたいのですが」と電話で問い合わせたことがある。返事はこうだった。「どの公園ですか? あ、あの公園ね。安全だと思えるあの公園でも、子どもだけで遊ばせるのはやめたほうがいいです」。私はいったい何歳ならいいのだろうかと思って、ちょっとカマをかけた。「一〇歳や一一歳でもでしょうか」ともう一度尋ねた。「そうです」との返事だった。話はこれだけでは終わらない。小学校低学年の子どもに一人で買い物に行かせると「ボク、お母さんは?」と必ず聞かれる。
このあと、日本ならば「一人でお使いに来れて偉いわね」となりそうなものだけれど、アメリカではそうはならない。「一人で買い物? 母親は育児放棄じゃないの?」と思われて子どもは『保護』され、親は『通報』される。
同じように、
子どもが公園で遊ぶときでも親が絶対に付き添っていなければならない。
もし付き添っていないと、他の子どもに付き添っているママさんに「ケガしたらどうするの? 誘拐されたらどうするの? これって育児放棄では?」と思われて通報されてしまうのだ。このあたり、日本の感覚ではちょっと想像できない徹底さだ。
親同士が顔見知り等で通報までは至らないとしても、「あそこのお母さんは子どものことを見てくれないから、もう一緒に遊んではいけませんよ」と子どもに教えることになる。
結果、自分の子どもが友達をなくすことにもなりかねない。
それはそれでまた違う意味で怖いし、そしてなにより息が詰まる。
なかには著者と同じように「これってちょっとヘンよね?」と思っているお母さんもいるのだけれど、「正しいこと」がなにより重視される文化のアメリカでは、大きな声を出せないまま、まわりの「正しいこと」に合わせるしかない現実もある。
もちろん、最初からこうではなかったはず。
『トム・ソーヤ』や『ハックルベリー・フィンの冒険』では、子どもだけで魚釣りをしたり森のなかにログハウスの秘密基地を作っていた。まあ現実はお話と同じようにはいかなくとも、古き良きアメリカは古き日本と同じように近所のいろいろな年齢の子どもが自由に遊び回っていたはずだ。
では、なぜこうなったのだろう?
本書の後半は「なぜこうなったか?」を考えていく。
一因にはアメリカの犯罪の多さもあるだろう。
だが、本当にそんなに多いのだろうか? と著者は問う。
もちろん自分のかけがえのない子どもが事件に巻き込まれるのは痛ましいことだ。だが、冷静に統計としての数字を見るなら、現在のアメリカは親の生活の時間や子どもの自由な遊びを犠牲にしてまで防衛しなければいけないほどの緊急事態だろうか?
スラム街などではたしかに防衛は必要かもしれないし、政府もそういうアナウンスをしている。でもそのアナウンスに反応できるのは残念ながらスラム街の住人ではないのだ。危険だからといってスラム街の住人にベビーシッターを雇ったりする経済的余裕はない。そして、安全な郊外に居を構えて経済的にも時間的にも余裕のある中流階級の人々が政府のアナウンスに次々に過剰反応していく。そのあたりの歪《いびつ》さが「子どもへの過剰な防衛」の一因にあるのかもしれない、本書は考えていくのだが……。
結局。
答えはどこにあるのだろうか。
本書の最終章で著者は述べる。
子どもを守るための安全対策は、大人が監視することや危ない遊びを避けること、危ないものに近づけないことで終わりではないはずだ。そのだめに子供が失ったもの、遊び時間の減少や子どもだけで行動する楽しさを、大人は補うことを考えなければいけないのかもしれない。親子で閉じてしまうことも避けたい。親だけでなく、社会で考えてもらえれば、有難い。ただ、「子どもたちによい環境を」と。
私は日本の公園に「一八歳以下の子どもは、大人の付き添いが必要です」という立て札が現れないように願っている。日本人の感覚をもったお母さんが、子どもを想いアメリカの事情を訴える。
日本もこうなってしまわないために。
この意見、聞いてみる価値は有るんじゃなかろうか。
 | 子どもがひとりで遊べない国、アメリカ?安全・安心パニック時代のアメリカ子育て事情価格:¥ 1,575(税込)発売日:2011-11 |
(※『[書評]のメルマガ』に掲載されました)
→『子どもがひとりで遊べない国、アメリカ
もくじ
はじめに僕の個人的な感想では、
Part.1 子どもとの暮らし
Part.2 本当に危ないのか
Part.3 いつからこんな時代になったのか
Part.4 責任者出てこい
Part.5 車社会
Part.6 育児放棄か?
Part.7 格差社会アメリカ
Part.8 子どもを持つ家庭への影響
Part.9 ミシェル・オバマ「レッツ・ムーブ」
Part.10 似たような考え方の人を見つけた
Part.11 代替案を探す
さいごに
本書を読む限りのアメリカの子育て事情って一種の集団ヒステリーではないかな、と思った。
集団ヒステリーの怖いところは、その中にいる人には自分の状態が理解できないってこと。本人は「ヒステリー? はっ、バカ言うなよ」と思いながら、冷静に考えたら明らかに無理な要求を掲げてデモをしたりする。
日本でも震災と原発事故でヒステリーに陥ってる団体や個人をよく見るのだけれど、そりゃ大切なのはわかるけどさ、必死になりすぎてもっと大切なものを捨てることになっちゃダメじゃないの? と思うのだ。
本書を対岸の火事として読むのではなく、「こういうこともあるんだ」「自分はどうだろう?」と一歩立ち止まって考えてみてはどうだろうか。
神戸の震災から17年で、
東日本大震災からは一年ちょっとの春。
僕はこんなふうに本書を読んだ。
本書の内容からは少し離れた読み方をしてしまって申し訳ないのだけれどもね。
 | 子どもがひとりで遊べない国、アメリカ—安全・安心パニック時代のアメリカ子育て事情価格:¥ 1,575(税込)発売日:2011-11 |
→【本がもらえる】レビュープラス










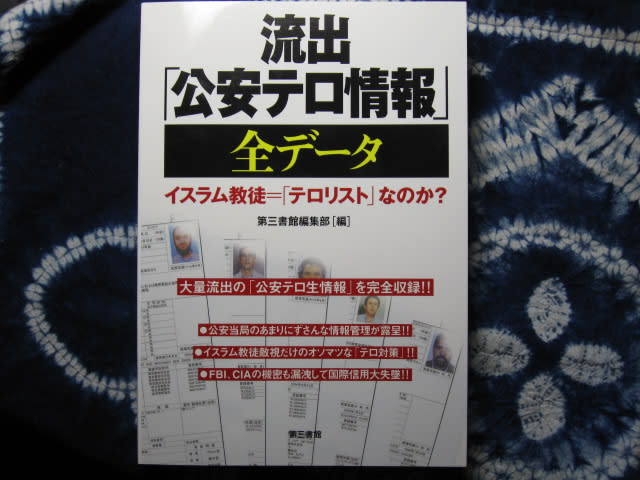
![森田さんのなぞりがき 天気図で推理する[昭和・平成]の事件簿](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51NRuUzViXL._SL160_.jpg)