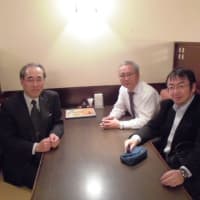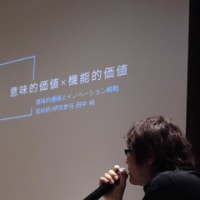※あらゆる業務はサービスであり、その価値を計るとき「成果の受益者」の視点を忘れてはならない...
● ● ●
連日蒸し暑いですね。数回着ただけでスーツをクリーニングに出さなければなりません。最近は洗えるものが出回っているようですがどんな感じなんでしょう?ちゃんときれいになって、シワとかも出ないんですかね?お持ちの方はぜひ教えてください---
---さて、突然ですが、私はもともと生産システム畑の出身で、VA/VE(バリュー・エンジニアリング/バリュー・アナリシス)やIE(インダストリアル・エンジニアリング)などの手法を用いて生産工程や生産管理システム、FA(ファクトリー・オートメーション)の設計・改善を行うといった仕事をしていました。
なので、今日は、これらのむかし(?)の手法について、思いつくままに述べてみたいと思います。
VA/VEやIEというと、一般的には、自社製品と他社製品を並べてバラバラに分解し、細かいムダやオーバーデザイン、プロセスの隘路などを発見し、材料費の削減や手間ヒマの簡略化など、主に内部の事情からくるコストダウンにつなげるという目的で使われている例が多いようです。
つまり、(限りなく)「閉じられた世界」で用いられてきたということです。
しかし、実は、VA/VEやIEといった手法は、このような絶対基準(閉鎖空間)でのコストダウンに用いるだけではなく、「受益者からの視点」すなわち「提供先にどういった経済的なインパクトやリスク低減などのメリットをもたらすか」といった外からの評価指標を加えて使ってみると、サービス業務をはじめとするさまざまなワークを設計・改善するためにも活用できるのです。
つまり、業務を行っている当事者だけではなく、その業務の受益者の視点が入るので、そうした人たちも巻き込んで、より多角的な視点から、「その製品や業務はほんとうに役に立っているのか」「コストや工数に見合う効能が得られているのか」といった議論ができるようになるのです。
そして、この考え方を反映し体系的にまとめた数少ない手法があります。マッキンゼー社が間接業務の削減のために開発したOVA(オーバーヘッド・バリュー・アナリシス)です。
このOVAはかなり実用的な手法で、コストダウン・プロジェクトにありがちな「10%一律削減」や「トップダウンによる一方的なコスト削減」と違って、まず当該業務に対し、当事者や業務の受益者によって定量・定性的な評価を施したうえで削減や改善の可否を決定します。
ゆえに、改善案がファクトとコンセンサスに基づいて決定されるので受け入れられやすく、また、真に無駄な業務が削減されるので、バグを除去したプログラムのように業務プロセスが滑らかになり、結果として定着しやすくなるというメリットが認められています。
大胆な戦略立案コンサルティングのイメージが強い同社ですが、実はVA/VEのような地味(?)で伝統的な手法もしっかりと取りこんで、自社の視点を加味しながら活用しているんですね~。
ものごとを鵜呑みにせず、理論や手法・技法の本質をみきわめ、さらに自分たちの問題意識や創意工夫をぶつけてみる、といった姿勢には、われわれも学ぶべきところがあるのではないかと思います。
ちなみに、かつて一世を風靡しながら古くなってしまったと思われている手法とか、適用範囲が狭いなどと思われる手法にも、新たな視点を加えたり、ちょっとした改良を施したりするだけで、複雑な現代の企業経営や、その他の(特にソフトサービスなどの)領域に応用できるものがいくつもあります。
VA/VEにかぎらず、皆さんも、むかし学んだり使ったりした手法・技法を別な角度から見直してみると良いと思います。
自分の創意工夫を注入することによってその手法がさらに手になじんだツールとなるし、さらには大きなコストもかからない。何よりも成果を獲得できる可能性がグンと高まると思うのですがいかがでしょう?
■ジェイ・ティー・マネジメント田中事務所■
http://www.jtm-tanaka.com/
〒105-0003
東京都港区西新橋1-2-9日比谷セントラルビル14階
TEL:03-3975-8171 FAX:03-3975-8171
この記事の一部またはすべての無断転載を固くお断りします。
Copyright (C) 2010 Kiyoshi Tanaka All Rights Reserved
◆◆◆
● ● ●
連日蒸し暑いですね。数回着ただけでスーツをクリーニングに出さなければなりません。最近は洗えるものが出回っているようですがどんな感じなんでしょう?ちゃんときれいになって、シワとかも出ないんですかね?お持ちの方はぜひ教えてください---
---さて、突然ですが、私はもともと生産システム畑の出身で、VA/VE(バリュー・エンジニアリング/バリュー・アナリシス)やIE(インダストリアル・エンジニアリング)などの手法を用いて生産工程や生産管理システム、FA(ファクトリー・オートメーション)の設計・改善を行うといった仕事をしていました。
なので、今日は、これらのむかし(?)の手法について、思いつくままに述べてみたいと思います。
VA/VEやIEというと、一般的には、自社製品と他社製品を並べてバラバラに分解し、細かいムダやオーバーデザイン、プロセスの隘路などを発見し、材料費の削減や手間ヒマの簡略化など、主に内部の事情からくるコストダウンにつなげるという目的で使われている例が多いようです。
つまり、(限りなく)「閉じられた世界」で用いられてきたということです。
しかし、実は、VA/VEやIEといった手法は、このような絶対基準(閉鎖空間)でのコストダウンに用いるだけではなく、「受益者からの視点」すなわち「提供先にどういった経済的なインパクトやリスク低減などのメリットをもたらすか」といった外からの評価指標を加えて使ってみると、サービス業務をはじめとするさまざまなワークを設計・改善するためにも活用できるのです。
つまり、業務を行っている当事者だけではなく、その業務の受益者の視点が入るので、そうした人たちも巻き込んで、より多角的な視点から、「その製品や業務はほんとうに役に立っているのか」「コストや工数に見合う効能が得られているのか」といった議論ができるようになるのです。
そして、この考え方を反映し体系的にまとめた数少ない手法があります。マッキンゼー社が間接業務の削減のために開発したOVA(オーバーヘッド・バリュー・アナリシス)です。
このOVAはかなり実用的な手法で、コストダウン・プロジェクトにありがちな「10%一律削減」や「トップダウンによる一方的なコスト削減」と違って、まず当該業務に対し、当事者や業務の受益者によって定量・定性的な評価を施したうえで削減や改善の可否を決定します。
ゆえに、改善案がファクトとコンセンサスに基づいて決定されるので受け入れられやすく、また、真に無駄な業務が削減されるので、バグを除去したプログラムのように業務プロセスが滑らかになり、結果として定着しやすくなるというメリットが認められています。
大胆な戦略立案コンサルティングのイメージが強い同社ですが、実はVA/VEのような地味(?)で伝統的な手法もしっかりと取りこんで、自社の視点を加味しながら活用しているんですね~。
ものごとを鵜呑みにせず、理論や手法・技法の本質をみきわめ、さらに自分たちの問題意識や創意工夫をぶつけてみる、といった姿勢には、われわれも学ぶべきところがあるのではないかと思います。
ちなみに、かつて一世を風靡しながら古くなってしまったと思われている手法とか、適用範囲が狭いなどと思われる手法にも、新たな視点を加えたり、ちょっとした改良を施したりするだけで、複雑な現代の企業経営や、その他の(特にソフトサービスなどの)領域に応用できるものがいくつもあります。
VA/VEにかぎらず、皆さんも、むかし学んだり使ったりした手法・技法を別な角度から見直してみると良いと思います。
自分の創意工夫を注入することによってその手法がさらに手になじんだツールとなるし、さらには大きなコストもかからない。何よりも成果を獲得できる可能性がグンと高まると思うのですがいかがでしょう?
■ジェイ・ティー・マネジメント田中事務所■
http://www.jtm-tanaka.com/
〒105-0003
東京都港区西新橋1-2-9日比谷セントラルビル14階
TEL:03-3975-8171 FAX:03-3975-8171
この記事の一部またはすべての無断転載を固くお断りします。
Copyright (C) 2010 Kiyoshi Tanaka All Rights Reserved
◆◆◆