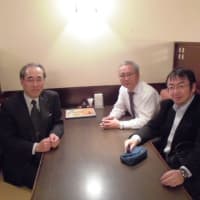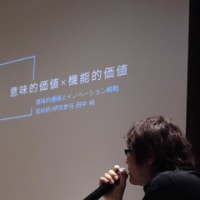※これからの企業は、ITの駆使により、5つの発展段階を最も効率的かつ効果的に乗り切れる可能性がある...
◆気になるひとこと◆
---日本企業にとっての国際化、多国籍化が困難な理由は、体質に国際的普遍性がなく、世界的に特異な均質集団だからである。国際化に近道はなく、的確なフェーズを踏むことによってのみ、成功が着実なものとなる---
~大前研一 『日本企業生き残り戦略』
◆コメント◆
大前研一氏が、マッキンゼー日本支社長時代の1987年に提唱した「真の企業国際化のための5つのフェーズ」の説明で語られている言葉です。
大前氏によると、日本企業の真の国際化に近道はなく、次の5つのステップを踏み、しかも常に現在から数ステップ先のための人材や経営システムの開発に先行投資することによってのみ、成功を収めることができる、ということです。
その5つのフェーズを概観してみましょう。
-----------------------------------------------------------------------
◆国際化の5つのフェーズ(要約)◆ ※あわせて上図をご参照ください
-----------------------------------------------------------------------
■第1フェーズ: 現地の提携代理店を通しての輸出・販売
国内で事業が充実してくると、商社などを使い、現地で輸入代理店(ディストリビューター)を使って、自社製品を輸出し始める。
↓ ↓ ↓
■第2フェーズ: 自前の販売店の展開による市場への接近
代理店では把握できない顧客ニーズや市場動向を得るために、直轄販売店を自前で設立する。権限委譲を的確に行わない場合、現地の顧客や競合よりも、日本の本社の方をむいて仕事をするので注意が必要。
↓ ↓ ↓
■第3フェーズ: 現地生産の開始
※多くの日本企業が国際化を達成したとカン違いするフェーズ(当時)
現地で生産を開始する。日本企業の多くはこのフェーズを国際化と考えている。しかし、現地生産で失敗したり、為替が円安になれば再び国内に引き揚げればよい、といった姿勢で生産を続ける企業も多いため、真の国際化が果たされないままのケースが多い。
↓ ↓ ↓
■第4フェーズ: 研究開発、財務、人事などワンセット・ビジネス機能を現地に移植
生産、販売だけではなく、財務、研究開発、設計、人事、購買などの機能をワンセットで現地に持っていく。こうしてようやく現地の主要企業と戦うための体制が整う。日本企業でこの段階に入っているところはない(当時)が、IBM、コカコーラなどはここに進んでいる。
↓ ↓ ↓
■第5フェーズ: 全体最適機能と部分最適機能の調和・棲み分けによる真のグローバル化
グローバル・インテグレーションの段階。世界企業はあくまで戦いの場である現地に創意工夫が生まれるような組織運営形態をとることが望ましい。その結果生まれてくる機能や努力の重複を避け、かつ同じ屋号のもとで事業展開するための価値観、連帯感といったものを共有する方向で再統合すべき。
-------------------------------------------
注意点として、大前氏も強調されていますが、第2~4フェーズを飛ばして、最初から第5フェーズを達成することはあり得ないということです。
なぜなら、各フェーズを端折って諸機能の作り込みや調整を最初からやり過ぎると、本社への依存体質が強まり、均質化がむしろ進んでしまいます。つまり、真の国際化に必要となる、多様性を糧とする懐の深い企業カルチャや、紆余曲折の経験を経営資源(ナレッジ)として生かす企業システムなどが育たなくなってしまうからなのです。
ゆえに、大前氏は、着実にこれらのフェーズを、焦らず、しかし効率的に消化していく必要性を強調されているのです。
前述したように、このモデルは20年以上も前のものです。しかし、いまだに、現地と業務提携したり、採用した現地人に日本の教育を受けさせたり、役職者の外国人比率を上げたりすることが「国際化」とカン違いをしている企業が多いのが現状です。
重要な権限を事実上、日本人が独占し、トラブル対応が遅れたことで批判を受けた自動車会社の例が示唆するように、いまだに彼の地の文化や価値観を心からうやまい、心身ともにその国に溶け込んでいる日本企業はほとんどないといっていいでしょう。
一方で、P&G、ジョンソン&ジョンソン、IBM、コカ・コーラ、アップル、アマゾンなどの企業は、日本企業に比較して、人事政策や商品展開など一歩も二歩も現地化が進んでいる感があるのは否めません。
(アップルやアマゾンには、最初から「国境」という概念がないように見えますよね♪)
日本企業が国際化で後れをとる大きな原因の一つに、最初から「分母」に世界をすえているのか、国内市場を置いているのかといったことがあります。
その昔、海外と情報やマインドを共有する手段を持たなかった多くの日本企業は、いったん国内向けの体質を作り込んでから、改めて国際的な多様性へと組織体質を転換していかねばならなかったため、最初から10年くらいのハンディキャップがあったのです。
しかし今は違います。ヨハネスブルグで「いまランチをしている人」の“つぶやき”をフォローし、iPADを駆使して、地球の裏側にいる仲間と同時に仕事を進めることができる時代です。
こうした時代を生きる現代の企業(もちろん中小、ベンチャー企業も含みますよ)は、最先端のITと大前モデルとを融和させたうえで、臆することなく、最初からアジアやアフリカなどの市場を「分母」に置いたビジネスモデルをめざしてほしいと思います。
■ジェイ・ティー・マネジメント田中事務所■
http://www.jtm-tanaka.com/
〒105-0003
東京都港区西新橋1-2-9日比谷セントラルビル14階
TEL:03-3975-8171 FAX:03-3975-8171
この記事の一部またはすべての転載を固くお断りいたします。
Copyright (C) 2010 Kiyoshi Tanaka All Rights Reserved
◆◆◆
◆気になるひとこと◆
---日本企業にとっての国際化、多国籍化が困難な理由は、体質に国際的普遍性がなく、世界的に特異な均質集団だからである。国際化に近道はなく、的確なフェーズを踏むことによってのみ、成功が着実なものとなる---
~大前研一 『日本企業生き残り戦略』
◆コメント◆
大前研一氏が、マッキンゼー日本支社長時代の1987年に提唱した「真の企業国際化のための5つのフェーズ」の説明で語られている言葉です。
大前氏によると、日本企業の真の国際化に近道はなく、次の5つのステップを踏み、しかも常に現在から数ステップ先のための人材や経営システムの開発に先行投資することによってのみ、成功を収めることができる、ということです。
その5つのフェーズを概観してみましょう。
-----------------------------------------------------------------------
◆国際化の5つのフェーズ(要約)◆ ※あわせて上図をご参照ください
-----------------------------------------------------------------------
■第1フェーズ: 現地の提携代理店を通しての輸出・販売
国内で事業が充実してくると、商社などを使い、現地で輸入代理店(ディストリビューター)を使って、自社製品を輸出し始める。
↓ ↓ ↓
■第2フェーズ: 自前の販売店の展開による市場への接近
代理店では把握できない顧客ニーズや市場動向を得るために、直轄販売店を自前で設立する。権限委譲を的確に行わない場合、現地の顧客や競合よりも、日本の本社の方をむいて仕事をするので注意が必要。
↓ ↓ ↓
■第3フェーズ: 現地生産の開始
※多くの日本企業が国際化を達成したとカン違いするフェーズ(当時)
現地で生産を開始する。日本企業の多くはこのフェーズを国際化と考えている。しかし、現地生産で失敗したり、為替が円安になれば再び国内に引き揚げればよい、といった姿勢で生産を続ける企業も多いため、真の国際化が果たされないままのケースが多い。
↓ ↓ ↓
■第4フェーズ: 研究開発、財務、人事などワンセット・ビジネス機能を現地に移植
生産、販売だけではなく、財務、研究開発、設計、人事、購買などの機能をワンセットで現地に持っていく。こうしてようやく現地の主要企業と戦うための体制が整う。日本企業でこの段階に入っているところはない(当時)が、IBM、コカコーラなどはここに進んでいる。
↓ ↓ ↓
■第5フェーズ: 全体最適機能と部分最適機能の調和・棲み分けによる真のグローバル化
グローバル・インテグレーションの段階。世界企業はあくまで戦いの場である現地に創意工夫が生まれるような組織運営形態をとることが望ましい。その結果生まれてくる機能や努力の重複を避け、かつ同じ屋号のもとで事業展開するための価値観、連帯感といったものを共有する方向で再統合すべき。
-------------------------------------------
注意点として、大前氏も強調されていますが、第2~4フェーズを飛ばして、最初から第5フェーズを達成することはあり得ないということです。
なぜなら、各フェーズを端折って諸機能の作り込みや調整を最初からやり過ぎると、本社への依存体質が強まり、均質化がむしろ進んでしまいます。つまり、真の国際化に必要となる、多様性を糧とする懐の深い企業カルチャや、紆余曲折の経験を経営資源(ナレッジ)として生かす企業システムなどが育たなくなってしまうからなのです。
ゆえに、大前氏は、着実にこれらのフェーズを、焦らず、しかし効率的に消化していく必要性を強調されているのです。
前述したように、このモデルは20年以上も前のものです。しかし、いまだに、現地と業務提携したり、採用した現地人に日本の教育を受けさせたり、役職者の外国人比率を上げたりすることが「国際化」とカン違いをしている企業が多いのが現状です。
重要な権限を事実上、日本人が独占し、トラブル対応が遅れたことで批判を受けた自動車会社の例が示唆するように、いまだに彼の地の文化や価値観を心からうやまい、心身ともにその国に溶け込んでいる日本企業はほとんどないといっていいでしょう。
一方で、P&G、ジョンソン&ジョンソン、IBM、コカ・コーラ、アップル、アマゾンなどの企業は、日本企業に比較して、人事政策や商品展開など一歩も二歩も現地化が進んでいる感があるのは否めません。
(アップルやアマゾンには、最初から「国境」という概念がないように見えますよね♪)
日本企業が国際化で後れをとる大きな原因の一つに、最初から「分母」に世界をすえているのか、国内市場を置いているのかといったことがあります。
その昔、海外と情報やマインドを共有する手段を持たなかった多くの日本企業は、いったん国内向けの体質を作り込んでから、改めて国際的な多様性へと組織体質を転換していかねばならなかったため、最初から10年くらいのハンディキャップがあったのです。
しかし今は違います。ヨハネスブルグで「いまランチをしている人」の“つぶやき”をフォローし、iPADを駆使して、地球の裏側にいる仲間と同時に仕事を進めることができる時代です。
こうした時代を生きる現代の企業(もちろん中小、ベンチャー企業も含みますよ)は、最先端のITと大前モデルとを融和させたうえで、臆することなく、最初からアジアやアフリカなどの市場を「分母」に置いたビジネスモデルをめざしてほしいと思います。
■ジェイ・ティー・マネジメント田中事務所■
http://www.jtm-tanaka.com/
〒105-0003
東京都港区西新橋1-2-9日比谷セントラルビル14階
TEL:03-3975-8171 FAX:03-3975-8171
この記事の一部またはすべての転載を固くお断りいたします。
Copyright (C) 2010 Kiyoshi Tanaka All Rights Reserved
◆◆◆