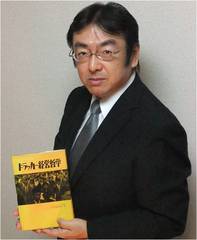リアルな経営の場における学習とは、他人が著したものについての知識量を増やすことではありません。知識の学習は、ひとつの過程であり方法にすぎません。
. . . 本文を読む
先日、久しぶりに映画『大脱走』を観ました。3時間近い大作ですが、いつもあっという間に時間が過ぎてしまいます。われわれ企業戦略に携わる実務者としては、組織やマネジメントの視点から鑑賞すると、改めて別の面白さや新しさが見つかるかもしれません。
. . . 本文を読む
伊藤雅俊さんのこの名著は、ともすれば企業再生の現場において、技術と力に頼りがちなマネジメントになってしまう私にとって、常に「自分が誰によって生かされているか、誰によって支えられているか」「真の顧客志向とはどういうことか」を思い起こさせてくれます。
. . . 本文を読む
ともすれば経営者や事業家は、自分の夢やいまの自分の事業を、自分だけのものとして考え、語りがちです。だけど、周りをよく見てみると、口には出さないけれども、誰に言われるでもなくその夢を自分のものとして感じてくれて、その実現に向かって、力を貸してくれる人が必ずいるものです。
. . . 本文を読む
この本には多数の著名な事業家、経営者が登場しますが、著者の一橋大学院教授の楠木健さんによって、もっとも面白い戦略ストーリーを語る事業家として取り上げられているのが、創薬ベンチャーの雄、アリジェン製薬の所 源亮(ところげんすけ)社長です
. . . 本文を読む
今年はハーバード大学の政治哲学者マイケル・サンデル教授の講義(ハーバード白熱教室/NHK教育テレビにて放送)が話題となりました。彼の投げかける設問にはどのような意図があるのでしょうか?
. . . 本文を読む
志とか理念、社会貢献など、美麗字句を発するのはたやすいことです。しかし、大成功をおさめた後、以前にもまして気を引き締め、さらにドライブをかけて自社のミッションを追求していこうとする経営者やリーダーはごく僅かだと思います。
. . . 本文を読む
たった1人の強い意志が周囲を動かし、状況を大きく変えつつある。「ごみだらけで風景画が描けない」。そんな子供たちの声を聞き、4年ほど前、市内に住む男性が浦安市の旧江戸川護岸で、1人黙々とごみを拾い始めた。 . . . 本文を読む
ブロークン・ウインドウズ(割れ窓)理論という、環境改善のための考え方があります。成功例に、ニューヨーク市の、地下鉄などの都市環境や犯罪率の劇的な改善例があることはよく知られています。会社再建の名人である、日本電産の永守会長も、同様の考えかたを実践して成果をあげています。
. . . 本文を読む
「ドラッカーのマネジメント理論」というとGMやIBMなどの企業名がよく出てくるので、大企業の経営者向けの理論、というイメージが強いと思います。
しかし、実は、その内容は、本質を突いたものでありながらシンプルで、方向性と真に重要なポイントのみ、簡潔に示されている部分が多く、日々の活動にも取り入れやすいものとなっています。 . . . 本文を読む
意外に知られていませんが、責任を持って「本当に」戦略を立案し運用するという実務に携わっている人間は、いわゆる戦略理論やフレームワークを中心的に使って戦略を立案しているわけでは決してありません。
. . . 本文を読む
写真で私が持っている本は、1959年に刊行された「ドラッカー経営哲学」(当時の定価で230円!)です。つい先日、父から譲り受けました。40数年間、大切に保管してきたということです。
. . . 本文を読む
どんなに厳しい状況にある企業にも、当人たちも自覚していない、または過小評価しているケイパビリティやインタンジブルな資産が埋もれています。その最小単位は、個人の中に留まっているスキルやノウハウなどですが、大きな単位になると、ある一定方向からのアプローチしかできていないゆえに、せっかく特権的なアクセス権があるにもかかわらず、「大きなプロフィット・ポテンシャルを持つ顧客セグメントを丸ごと埋没させてしまっている例」などがあります。 . . . 本文を読む
ものごとを構造的にとらえる、というときの思考法の基本は、マッキンゼー社を嚆矢とするMECE(ミッシー)でしょう。なかでも5W3H思考は、ある事象・現象を構造化するための、最も汎用的かつベーシックなMECEであるといえます。 . . . 本文を読む