日本中、冷えていますね~
そんな日は部屋の中で暖まりながら1クリック!
2月も順調に1位を維持しています。
いつも本当にありがとうございます。
なんでこんなに寒いんでしょうねぇ
立春なんて本当に名ばかりで 2月は寒さの底です。
足元がジンジン冷えています。
今年は本当に春が待ち遠しいです。
絹が今 どんどん値上がりしていて
今年は胴裏や八掛、白生地が一気に値上がりするか
いっそ生産中止になってしまうのでは、と思います。
要因はいくつかあるようですが
輸入の8割ほどを占めている中国で桑の生育が悪くて蚕の餌が不足したことや
中国で真綿の布団が人気で中国国内での絹の需要が増えて輸出に回せないなど。
絹糸が値上がりすると 糸も値上がりしますから
縫い糸や刺繍糸も値上がりして 結果仕立て代にも響くのでは・・と思えます。
そんな貴重な絹糸をたっぷり触れるのが今週末のずり出し体験です。
繭から糸を取る方法はいくつかありますが
人間が手で糸にするのは 大きく3つに分けられます。
まずは 結城紬でお馴染みの「手紡ぎ」
繭を解して綿にして そこから糸を引き出します。
煮た繭を引きのばして7枚ほど重ね、つくし、と呼ばれる棒に巻き付けて、
そこから糸を引き出します。
結城の場合は 細くまっすぐに、撚りをかけずに引き出します。
膝の前にある筒状の入れ物が おぼけ。これ一杯に7つ分で1枚の着物の糸の量です。
繭を真綿に解さずに糸口を見つけて1本の糸として引き出すのが座繰り。
牛首紬などにも使われている方法です。
ここでは芝崎さん独自の70個一気引き。


普通は7個ほどの繭から一緒に糸を引き出してその糸を4本寄り合わせますが
芝崎さんの方法は70個ほどから一気に1本の糸を引き出します。
とても力のいる方法です。
引き出された糸は真綿ではないので 毛羽がなく艶やかに光っています。
現在 この紡ぐ、と 座ぐる、が紬糸の主流です。
そして登喜蔵さんの ずり出し。
これは 先に繭のまま草木染にして 染めた繭から糸を摘まみだす方法です。
繭は染めた後、一度は乾燥させ ずり出す前に水に浸けます。
繭を摘まんで そのまま糸を引っ張り出していきます。
手の感覚だけで細くも太くも引きずり出します。
結城は出来るだけ細く均一に紡ぎ出すのが大切ですが
登喜蔵さんは あえて強弱をつけた節のある糸を布の味わいにしています。
糸によって織り上がりの風合い、表情も変わってきます。
じざいやには 結城も芝崎さんも登喜蔵さんも一度に比べて頂けますので
ぜひ この機会に 糸の作り方による布の違いを感じてください。
下の「着物・和装・業者」というバナーか、「にほんブログ村」という文字をクリックして下さい。










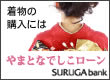 やまとなでしこローン
やまとなでしこローン
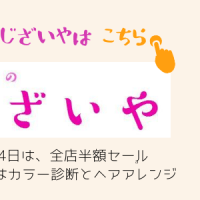











※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます