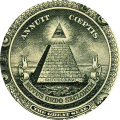創価学会や日蓮正宗関係では、いわゆる「退転者」には不幸が襲い地獄の様な生活がその先に待っているという。だから組織を離れる人を憐憫の眼差しで見る人が、会員や活動家幹部の中には多く見受けられる。私も壮年部となり、組織活動になかなか付けない時期、支部長からは「親の信心は子供に如実に出てくるもの」と言われた。当時は次女を嫁が妊娠している時だったので「それは生れてくる子供に現証として出てくるという事なんですか?」と聞くと、支部長はニヤつきながら「さあね、でも駿馬は鞭(ムチ)を入れられる前に走ると言う諺があるから、よく考えた方が良い」と言われた事があった。
なんとも無神経な言葉ではないだろうか。
私は現在、創価学会の組織活動を離れて既に十五年以上経過しているが、よく言われる「仏罰」というのを経験した事が無い。それは人生であるから、苦しい事や悲しい事は沢山あった。でもそれを「仏罰」だとは感じた事もないし、それよりも学会活動から離れ、そこで知り合った多くの人たち、これは主に創価学会以外の人達の事を指すが、そういう人たちに励まされ支えられ、また様々な触発を受けてこれまで生きてこれて来た事は実感している。
法華経の話に久しぶりに少し戻るが、大乗仏教には諸法実相という教理がある。これは諸法(社会の様々な事象や自分自身の周囲に起きる事象)は実相(心の本質)から起きるという事だ。そして諸法として一念三千は解き明かされ、実相として久遠実成の釈尊という事が説かれている。そしてこの二つこそが法華経の肝心だと日蓮も御書の中では書き残している。
久遠実成によれば、人はこの世界で巡り合う出来事の意味について、心の奥底の本質的な心では理解をしてつつ、その上でこの世界に生を受け、一つひとつの出来事に巡り合い、そこで苦悩を感じたり、また幸福感を感じたりしているというのだ。「仏の智慧は甚深無量」というのは、その事を指しているのだろう。しかしそれは深層心理の奥深く、過去世から現在に続く記憶の海である阿頼耶識の遥か奥底での認識であって、「自我(末那識)」により「自分自身は他者や環境から独立した存在だ」という、簡単に言えば阿頼耶識を元にした末那識より表層的な意識での「誤認識」や「自我への執着」から、日常生活の意識(六識)では容易にその事を感知する事が出来ない。だから人は目の前に起きた出来事で一喜一憂し、簡単に言えばそこで苦悩に打ちひしがれたりもしているのだろう。
この構造を簡単にイラストにしたのが今回の扉絵である。
以前に高須クリニック院長の高須克弥氏の言葉で以下のものがあった。
「この世界では乗り越えられない事は無い。だからいくら苦しくても生きていれば、どんな問題であっても必ず乗り越える事が出来る。だからけして死んではいけない、生きなければいけない。(要旨)」
これは実に名言だと私は感じたので、ここで紹介をさせていただいた。
私が思うに法華経の上で久遠実成の理屈(理-ことわり)としてはそうなのだが、そうは言っても人は容易にこれを信じる事なんて出来やしない。例えば事業に失敗し莫大な借金を抱え込んだ人に対して「その苦しみには意味があり、貴方はその意味を本当は理解しているのだ」と言った処で「その前にこの借金の苦しみを何とかしてくれ!」と言われるだろう。それは当たり前のことだ。しかし法華経の教理を元に考えたら、その苦悩している事には、しっかりとした意味があり、なおかつ自分自身も心の奥底ではそれを理解しているというのである。
これはどうしても信じられる事ではない。だからこそ法華経は「難信難解」と言われるのだろう。
ここで少し私の信仰体験ではないが、私が五十歳頃にふと気づいた事があるので少し書かせて頂く。
私は創価学会の活動を止めたのち、当時在籍していた会社で新規事業を立ち上げる業務に従事した。詳細は割愛するが全くの徒手空拳で必死に働いた。しかしちょうどサブプライムローンの問題がアメリカで発生し、その煽りを受けて営業活動もままならない状態になってしまった。その時は深夜まで御題目を唱えた事もあったが、何も事態は一向に打開しない。結果、社会でもかなり大赤字を出してしまい、毎日の出社は針の筵だった。人というのはとことん追いつめられると思考力も低下する。打開すべき問題が山積みなのだが思考が働かない。恐らく今から考えたら鬱病の一歩手前まで行っていたと思う。そこで一旦、新規事業は畳み、社内の他の業務に携わる事になった。しかしこのプロジェクトにしても短期なプロジェクトで、仕事が終わった時には体のいい社内失業状態となってしまった。
しかし私は、何故か心の奥底には「大丈夫だ、この状態は必ず打開できる」という確信に近いものがあった。その確信はどこから来るのか、私自身にも全くわからない。この時には既に勤行唱題も時間の無駄だと考えて止めてしまっていたが、それでも心の奥底からふつふつと確信が湧いてくる。日々出社をすると「お前は次、何の仕事をやるんだ?」と経営層からは言わていたが、明確な反論は出来なかった。でももう少しの辛抱だと耐えていた。
そんなある時、会社に一本の電話が来た。その時は私がその電話を取ったのだが、それは以前に派遣先で働いていた会社の課長だった。「おー斎藤さん。久しぶり」。思わず懐かしい声にかられながら世間話をしていると「斎藤さんの会社でまた派遣要員を一名出してくれないか?」との電話だった。なんでも新規業務を行うのに、その要員を探しているとの事だった。私は即「斎藤が行きましょうか?」と言うと「来てくれるのはありがたいけど、大丈夫なの?」との事だった。そこで私が自分自身の派遣関連の見積もりや手続きを行い、その会社に派遣として仕事をする事になったのである。(ちなみに単価はかなり高めに設定し、自分自身で交渉した)
それが今でも務めている会社である。その後、当時いた会社は事業縮小したりリストラがあったりしたそうだが、私は今の職場で派遣元の会社は幾つか変わりはしたが、十五年以上、この職場で無事に仕事を続けてきて、子供たち二人、高校から大学まで送り出すだけの収入を得てきた。
この事でふと思ったのは、人生とは実は「一つの道」の様なものがあるのでは無いかと言う事だ。私が社会人になったのは19歳の時だった。それから様々な人と巡り合い、様々な仕事の場を与えられ、そこで一生懸命仕事はやってきて多くの経験を得て来れた。今から振り返ると、必要な時期に必要な人と出会い、そこで仕事を共にしてきたが、それがすべて先々の仕事などに関係してきたという事だ。つまり今の自分があるのは、過去に生きてきた人生の中で、そこで様々な人に出会う事によって結果今があるという事だ。楽しい事もあったが苦しい事も沢山あった。しかしそれが五十代になって感じたのは、これまでの出来事や出会いには無駄がなく、その一つひとつの経験の上に今の自分があるという事だった。
そう考えると、人生というのは実に興味深いものだと感じている。法華経にある「久遠実成の釈尊」では無いか、実は人生に起きる問題というのは、そこに一切無駄な事というのは存在せず、実は自分自身の心の奥底ではそれら出来事の事を理解しているのかもしれない。ただし心の奥底にある「声」はとてもわずかな音量でしかない。もし私が心の中にかすかに聞こえる声を聞き逃してしまったのであれば、今の自分は存在しなかっただろう。
創価学会では「信心」という言葉をよく使う。これは「創価学会という組織を信じる心」であったり「池田先生を信じる心」であったり、「御本尊様(文字曼荼羅)を信じる心」だと教えている。
しかし今の私はもし「信心」という言葉を言うのであれば「自分自身を信じる心」こそが一番大事な事だと言いたい。いまこの時代に生きる自分という存在を信じる心、これこそが一番大事なのではないだろうか。良く「自信を持つ」というが、これは自分自身を信じる心を持つという事だろう。
日蓮の言葉で「心の師とはなるとも心を師とせざれ」という言葉があるが、これを自己否定の御文だと私は創価学会の先輩から教わった。要は今の自分を肯定してはいけない。まだ駄目だ!まだ駄目だ!と今の自分を否定し叱咤するのが、この御文の意味だというのだ。しかしこれは違うだろう。この御文の「心の師とはなるとも」とは感情に流され紛動するような心を統率する事を言っていて、感情に任せて紛動する心に従ってはいけないという意味ではないだろうか。私も事業縮小され、その時の苦衷の感情に惑わされてしまっていたら、おそらく今の私というのは存在しなかった。その様な感情に惑わされる事なく、自分の心の奥底から聞こえる確信の感情を信じて、今ある自分という存在を信じて来れたからこそ今の私があるのだ。
自分自身を信じれない者が、果たして他者を信じる事が出来るのか。
自分自身を、自分が信じないで、一体だれが自分を信じると言うのか。
ここから書くことは我見と言われても否定はしない。しかし自分が考えている事なので書かせてもらう。法華経とは全て読んでみると、要は自分自身の心の奥底には「久遠実成の釈尊」が存在するという事を解き明かしている。そこから考えてみると「南無妙法蓮華経」とは、その法華経に書かれている事に帰依するという意味だろう。要は自分自身の心の奥底には「久遠実成の釈尊」がいるのだ。だからそれを解き明かした法華経に帰依する。帰依とは色心にわたって信じ帰服するという事で、心でも信じ、言動でも信じる行動をとるという事だろう。
そして「南無妙法蓮華経」と題目を唱えるのは、それを自分自身に言い聞かせる言葉であって、けして「呪文(マントラ)」などではないのだ。
本来であれば、内観という修行を通して、この心の奥底にある「久遠実成の釈尊」という存在を覚知出来れば良いのかもしれないが、それは極めて敷居が高い。日蓮も唱法華題目抄において「愚者多き世となれば一念三千の観を先とせず其の志あらん人は必ず習学して之を観ずべし。」と述べている様に、一念三千の観心を必ずしも優先する必要はないと言っている。その代わりに南無妙法蓮華経と日々の生活の中で口に言い聞かせ、自分自身の中にある久遠の仏を信じて行けば、結果として得られるものは内観同等のものである。日蓮はそれを言いたかったのかもしれない。
以上が今の私が理解している「事と理」についてである。前にも書いたが自分自身が理解している事を文字に書き起こすのは極めて難しい。ただ今の私にとって「事(の一念三千)と理(の一念三千)」を考えた時、この様な内容となっている。少しでも参考になったら幸いである。