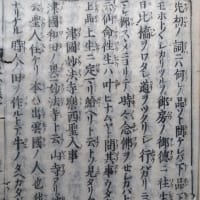正治二年後鳥羽院御初度百首歌 80首
1200年23名に百首歌を命じた。
第一 春歌上
3 春 式子内親王
山ふかみ春とも知らぬ松の戸にたえだえかかる雪の玉水
17 春 藤原家隆朝臣
谷河のうち出づる波も聲たてつうぐひすさそへ春の山かぜ
31 春 惟明親王
鶯のなみだのつららうちとけてふる巣ながらや春を知るらむ
44 春 藤原定家朝臣
梅の花にほひをうつす袖のうへに軒漏る月のかげぞあらそふ
45 春 藤原家隆朝臣
梅が香にむかしをとへば春の月こたへぬかげぞ袖にうつれる
52 春 式子内親王
ながめつる今日は昔になりぬとも軒端の梅はわれを忘るな
62 春 攝政太政大臣
歸る雁いまはのこころありあけに月と花との名こそ惜しけれ
66 春 攝政太政大臣
ときはなる山の岩根にむす苔の染めぬみどりに春雨ぞ降る
83 春 式子内親王
いま桜咲きぬと見えてうすぐもり春に霞める世のけしきかな
91 春 藤原定家朝臣
白雲の春はかさねてたつた山をぐらのみねに花にほふらし
第二 春歌下
130 春 二條院讃岐
山たかみ峯の嵐に散る花の月にあまぎるあけがたのそら
149 春 式子内親王
花は散りその色となくながむればむなしき空にはるさめぞ降る
157 春 攝政太政大臣
初瀬山うつろう花に春暮れてまがひし雲ぞ峯にのこれる
158 春 藤原家隆朝臣
吉野川岸のやまぶき咲きにけり嶺のさくらは散りはてぬらむ
174 春 攝政太政大臣
明日よりは志賀の花園まれにだに誰かは訪はむ春のふるさと
第三 夏歌
207 夏 民部卿範光
郭公なほひとこゑはおもひ出でよ老曾の森の夜半のむかしを
215 夏 式子内親王
聲はして雲路にむせぶほととぎす涙やそそぐ宵のむらさめ
240 夏 式子内親王
かへり來ぬむかしを今とおもひ寝の夢の枕に匂ふたちばな
241 夏 前大納言忠良
たちばなの花散る軒のしのぶ草むかしをかけて露ぞこぼるる
255 夏 攝政太政大臣
いさり火の昔の光ほの見えてあしやの里に飛ぶほたるかな
270 夏 攝政太政大臣
秋近きけしきの森に鳴く蝉のなみだの露や下葉染むらむ
271 夏 二條院讃岐
鳴く蝉のこゑも涼しきゆふぐれに秋をかけたる森のした露
第四 秋歌上
291 秋 皇太后宮大夫俊成
伏見山松のかげよりみわたせばあくるたのもに秋風ぞ吹く
308 秋 式子内親王
うたたねの朝けの袖にかはるなりならすあふぎの秋の初風
349 秋 式子内親王
花薄まだ露ふかし穂に出でばながめじとおもふ秋のさかりを
356 秋 攝政太政大臣
荻の葉に吹けば嵐の秋なるを待ちける夜半のさをしかの聲
357 秋 攝政太政大臣
おしなべて思ひしことのかずかずになほ色まさる秋の夕暮
380 秋 式子内親王
ながめわびぬ秋より外の宿もがな野にも山にも月やすむらむ
432 秋 式子内親王
秋の色はまがきにうとくなりゆけど手枕馴るるねやの月かげ
第五 秋歌下
438 秋 入道左大臣
山おろしに鹿の音高く聞ゆなり尾上の月にさ夜や更けぬる
439 秋 寂蓮法師
野分せし小野の草ぶし荒れはててみ山に深きさをしかの聲
442 秋 惟明親王
み山べの松のこずゑをわたるなり嵐にやどすさをしかの聲
469 秋 寂蓮法師
物思ふそでより露やならひけむ秋風吹けば堪へぬものとは
474 秋 式子内親王
跡もなき庭の淺茅にむすぼほれ露のそこなる松蟲のこゑ
485 秋 式子内親王
ふけにけり山の端ちかく月さえてとをちの里に衣うつこゑ
512 秋 前大僧正慈圓
秋を經てあはれも露もふかくさの里とふものは鶉なりけり
518 秋 攝政太政大臣
きりぎりす鳴くや霜夜のさむしろに衣かたしきひとりかも寝む
534 秋 式子内親王
桐の葉もふみ分けがたくなりにけり必ず人を待つとならねど
540 秋 二條院讃岐
散りかかる紅葉の色は深けれど渡ればにごるやまがはの水
第六 冬歌
584 冬 二條院讃岐
折こそあれながめにかかる浮雲の袖も一つにうちしぐれつつ
589 冬 入道左大臣
まきの屋に時雨の音のかはるかな紅葉や深く散り積るらむ
593 冬 宜秋門院丹後
吹きはらふ嵐の後の高峰より木の葉くもらで月や出づらむ
615 冬 攝政太政大臣
笹の葉はみ山もさやにうちそよぎ氷れる霜を吹くあらしかな
629 冬 守覺法親王
むかし思ふさ夜の寝覺の床さえて涙もこほるそでのうへかな
630 冬 守覺法親王
立ちぬるる山のしづくも音絶えてまきの下葉に垂氷しにけり
635 冬 攝政太政大臣
かたしきの袖の氷もむすぼほれとけて寝ぬ夜の夢ぞみじかき
638 冬 式子内親王
見るままに冬は來にけり鴨のゐる入江のみぎは薄氷りつつ
662 冬 式子内親王
さむしろの夜半のころも手さえさえて初雪しろし岡のべの松
671 冬 藤原定家朝臣
駒とめて袖うち拂ふかげもなし佐野のわたりの雪のゆふぐれ
690 冬 式子内親王
日數ふる雪げにまさる炭竈のけぶりもさびしおほはらの里
701 冬 入道左大臣
いそがれぬ年の暮こそあはれなれ昔はよそに聞きし春かは
第七 賀歌
734 祝 式子内親王
天の下めぐむ草木のめもはるにかぎりも知らぬ御世の末々
736 祝 攝政太政大臣
敷島ややまとしまねも神代より君がためとやかため置きけむ
第十 羇旅歌
944 旅 宜秋門院丹後
知らざりし八十瀬の波を分け過ぎてかたしくものは伊勢の濱荻
947 旅 式子内親王
行末は今いく夜とかいはしろの岡のかや根にまくら結ばむ
948 旅 式子内親王
松が根のをじまが磯のさ夜枕いたくな濡れそあまの袖かは
969 旅 藤原家隆朝臣
契らねど一夜は過ぎぬ清見がた波にわかるるあかつきの空
977 鳥 宜秋門院丹後
おぼつかな都にすまぬ都鳥こととふ人にいかがこたへし
985 旅 前大僧正慈圓
さとりゆくまことの道に入りぬれば戀しかるべき故郷もなし
第十一 戀歌一
1030 恋 前大僧正慈圓
わが戀は松を時雨の染めかねて眞葛が原に風さわぐなり
1036 忍戀 式子内親王
わが戀は知る人もなしせく床のなみだもらすな黄楊の小まくら
1073 恋 攝政太政大臣
かぢをたえ由良の湊による舟のたよりも知らぬ沖つしほ風
1074 恋 式子内親王
しるべせよ跡なきなみに漕ぐ舟の行方も知らぬ八重のしほ風
第十二 戀歌二
1083 恋 攝政太政大臣
戀をのみすまの浦人藻鹽垂れほしあへぬ袖のはてを知らばや
1120 恋 二條院讃岐
なみだ川たぎつ心のはやき瀬をしがらみかけてせく袖ぞなき
1124 恋 式子内親王
夢にても見ゆらむものを歎きつつうちぬる宵の袖のけしきは
1134 恋 惟明親王
逢ふことのむなしき空の浮雲は身を知る雨のたよりなりけり
第十三 戀歌三
1153 恋 式子内親王
逢ふことを今日まつが枝の手向草いく世しをるる袖とかは知る
第十四 戀歌四
1293 恋 攝政太政大臣
いはざりき今來むまでの空の雲月日へだててもの思へとは
第十五 戀歌五
1386 恋 藤原家隆朝臣
逢ふと見てことぞともなく明けぬなりはかなの夢の忘れ形見や
第十六 雜歌上
1510 秋 二條院讃岐
むかし見し雲居をめぐる秋の月いまいくとせかそでにやどさむ
1517 秋 攝政太政大臣
月見ばといひしばかりの人は來でまきの戸たたく庭のまつ風
1538 秋 藤原隆信朝臣
ながめても六十ぢの秋は過ぎにけりおもへばかなし山の端の月
1576 土御門内大臣
朝ごとにみぎはの氷ふみわけて君につかふる道ぞかしこき
第十七 雜歌中
1622 山家 藤原家隆朝臣
瀧の音松のひびきも馴れぬればうちぬるほどの夢は見せけり
1663 山家 式子内親王
今はわれ松のはしらの杉の庵に閉づべきものを苔ふかき袖
1664 山家 小侍從
しきみ摘む山路の露にぬれにけりあかつきおきの墨染の袖
1665 山家 攝政太政大臣
忘れじの人だに訪はぬ山路かな櫻は雪に降りかはれども
第十八 雜歌下
1810 鳥 式子内親王
曉のゆふつけ鳥ぞあはれなる長きねぶりを思ふまくらに
1835 山家 前大僧正慈圓
いつかわれみ山の里の寂しきにあるじとなりて人に問はれむ